評論|西村朗 考・覚書(31)光とは何か|丘山万里子
西村朗 考・覚書(31)光とは何か
Notes on Akira Nishimura(31) Light
Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)
西村を筆者は光フェチと言ったが、これについては第2回ですでに触れている。
「光」がタイトルに含まれる作品リストはここでは割愛するが、1990年から10年間は毎年、2000年以降は07年まで6作に「光」を産出している。そこに強く生理的なものを感じていたのだが、西村の音楽との最初の出会いがシューベルトの『軍隊行進曲』であったことに立ち戻ろう。すなわち、
あるときレコードをかけながら、校庭をぼんやり眺めていると、だれもいなくて、いい天気で、光がきらめいている。で、中間部のところを聴いていると、何か不思議な気持ちになってきたんですよ。何かがやってくるような感じというか、こう吸い寄せられるというか、胸がきゅーんとなるような息苦しさみたいな感覚ですね。この箇所へ差しかかると、いつもそう感じる。音楽というのは不思議な力を持っているんだな、と朧気ながら思った。それは、僕にとっての一種の神秘体験と言ってもいいようなもので、音楽というものに全身で震えるように引き寄せられた瞬間でした。(『光の雅歌』p.014)
ここにある「光のきらめき」と中間部に感じる「胸がきゅーんとなる息苦しさ」を、彼は一種の神秘体験と言っている。筆者はシューベルトの音楽を「執拗な楽句の繰り返し、光と翳の不可思議な交錯、その隙間に魂の深淵をのぞかせるそら恐ろしい魔界音楽」とし、さらにそこに忍び込むロマ的妖しさが含む異国への誘惑を述べ、この「光と翳」の感触こそが、西村の音楽の出立点と見た。
ここで、西村の『光のマントラ』までの光の道筋を振り返ってみる。
処女作はオーケストラのための『耿(こう)』(1970)。
耿は明らか、ひかりを意味するが、『字統』1によれば耳は聖・聡を表し、火をもってその聖聡を清める儀礼をいう字とある。留意したいのは、耳が聖なるものの意であることだ。あらゆる宗教の成り立ちにまず置かれるのは「聞こえる」(聞く、でなく受動態)という現象だ。いわゆる天の声、神の声を人は聞き取るのであり、それを仲介する人間をインドでは聖仙(リシ)、キリスト教、イスラーム教では預言者と呼び、天啓を授かり伝える存在として位置付けられる。なお、この耿は『楚辞』の《離騒》に「耿として吾既にこの中正を得たり」(神巫がその清明の心をえたとすること)という句があるところから、合唱処女作『汨羅の淵より』(1978)を思い起こさせる言葉でもある。
 西村17歳(2013年改訂)のこの作品は杉山寧の絵画『耿』を見て書かれており、「自然界を照らす一瞬の美しく神秘的な光。その風景画の具象と抽象の中間域での夢幻的表現に強く魅せられた」とし、さらに武満徹『地平線のドーリア』(1966)からの影響、「非常に魅惑されたのは『地平線のドーリア』で、抽象的な点と線が無重力で浮遊して、夢幻的な光のような響きを生んでゆくのは驚きだった」と述べている。(第10回より再録)。
西村17歳(2013年改訂)のこの作品は杉山寧の絵画『耿』を見て書かれており、「自然界を照らす一瞬の美しく神秘的な光。その風景画の具象と抽象の中間域での夢幻的表現に強く魅せられた」とし、さらに武満徹『地平線のドーリア』(1966)からの影響、「非常に魅惑されたのは『地平線のドーリア』で、抽象的な点と線が無重力で浮遊して、夢幻的な光のような響きを生んでゆくのは驚きだった」と述べている。(第10回より再録)。
『耿』については既に詳細に触れた。シューベルトの光と翳、さらに生と死の臨界域、トワイライト・ゾーン、そして寂光院からの帰路の黄昏時、古知谷阿弥陀堂への道で踵を返したこと(足を踏み入れたら戻れない)。その異様な感触を「冥界への道」と語る西村に筆者はいささか辟易したが、今こうして振り返ると、八瀬手前での停車が生んだ「無音」、さらに「冥界への道」にあるこれも一種の神秘体験を、あ、そう、と素通りできない気持ちになるのだ。光の感知は常に闇を伴い、それは生と死の往還・循環に他ならないことを少年西村はこのとき、漠然と察知した。それは少年らしい本能的な死への反応であったのではないか、と。
この作品での彼のテーマは「春光」だが、3部構成に「Reflexion(Hansha)」「 Lueur (Bikō)」「 Ombre (Kage)」とあるように、すでに西村の光宇宙が映じており、グリッサンド、トレモロ、帯状の響きの動かし方など、のちの西村ヘテロフォニーへ収斂する全ての要素が明瞭に見てとれる。
が、筆者がここで確認したいのは、本作制作の動機が絵画『耿』を見て、であることだ。『慧可断臂』(1976)は雪舟(絵とストーリーが先で谷川雁の詩にはのちに出会った)、そしてヘテロフォニー4部作『雅歌Ⅰ〜Ⅳ』1987-88)の契機は1985年秋、東京都美術館《日本戦後美術の40年展》の看板で見た高松次郎の『扉の影』(1968/彫刻)の写真に誘われて、だ。60年代前衛回顧中心の展示に自分の創作の目がパキッと覚めたとのことだが、高松の『扉の影』(オブジェ)は「影」ばかりを描いたシリーズの一つ。さらに『太陽の臍』(1989)は杉浦康平のアジアの図像世界から。第19回で述べたように、西村の創作の節目には、それを後押しする視覚的刺激があるように思う。可視化された形象からの「呼びかけ」が彼の音像の明瞭化を促すのだろうか。
そう考えると西村には「母胎音響」だけでなく「母胎図像」とでもいうものがその基底にあるのではないか、と思えてくる。すなわち、西村宇宙の基底音と基底像。
仏教には「見仏聞法」という言葉がある。見仏とは、仏身を見ること、仏の姿を目の当たりに見て礼拝すること、あるいは自己の仏性を悟ること(見性)。一方、聞法とは仏の教えを聞くこと。
先述したように、古今東西どの宗教においても「聞こえる」が先行し、「見える(視える・観える)」は後に続く行為として現れる。赤子はすでに母胎内で聴覚を持つが、視覚すなわち光を認識するのは、外界に触れてのちで、遅れてやってくる(開眼というように)。おぼろ世界がだんだんはっきりしてくるのは生後2ヶ月ぐらい。西村は前衛作品群の展示に覚醒、「ヘテロフォニー」という言葉が浮き上がり、響きのフォルムすなわちヘテロフォニーの形姿が見えた。
『耿』からヘテロフォニー4部作、さらに『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』を経て『太陽の臍』までをヘテロフォニー確立の路程とするなら、そこでの作業は響きの「聞き取り(聴聞・傾聴)」すなわち聞法であったと言えようか。
一方、『太陽の臍』から『光のマントラ』に至る一連の作品は、インドのヴィシュヌ神から密教の大日如来に至る西村の「光宇宙」への路程。密教の「身口意(しんくい)」とは、身体的活動(身)と言語活動(口)と精神活動(意)だが、器としてのヘテロフォニーを「意」とするなら、そこに光を満たすべくマントラの呪力「口」(光明真言)とマンダラ儀礼「身」の採用は「光に見(まみ)える」見仏とも言えよう。
となれば、彼の基底像とは、形象ではなく「光」そのものなのではないか。
「見仏聞法」とは瞑想にあって、それぞれのスタイルをとるものの、目指すのは梵我一如、密教では即身成仏。敷衍すれば宇宙の真理。かつ、いずれも分別を離れた直覚による境地である。
例えば東大寺の修二会での練行衆の凄まじい行中に彼らが仏を見る、出会う、声が聞こえる、確かにそこにいらっしゃる、ありがたいありがたい、と語るのを聞く時、それはそうであろう、と頷ける、それが信心というものではないか。
マントラを唱えマンダラの中に入る行を重ね、ついに自分が仏になりきるのが即身成仏だが、そうした信心における神秘体験はおそらく光の遍在、あまねく光が満ち満ちている世界の「開かれ」なのであろう。それはどこまでも開かれゆくものであり、境界なき無限の光エネルギーの遍在といっても良い。その光のマンダラの中心に座すのが大日如来。「一即多」もおそらくここにある。
信心も神秘体験もなく、かつそれらを胡散臭く思う筆者にそのイメージを描出することはできないが、おそらくそういうものであろうと思う。(「見仏聞法」や「身口意」など、筆者は何も無理やり仏教的思考に引き寄せようとしているわけではなく、西村を語るにあたってその方が馴染むと思うからで、これを西欧の思考言語に置き換えるのは難しい。)
 西村は、こうして『耿』から『光のマントラ』への道筋に、「光を聞き」(聞法)ヘテロフォニーを生み出し、「光に見(まみ)え」(見仏)音響による光のマンダラを設営した。それはまた、彼の光宇宙の基底音と基底像を見出す一種の「行」でもあったと言えるのではないか。
西村は、こうして『耿』から『光のマントラ』への道筋に、「光を聞き」(聞法)ヘテロフォニーを生み出し、「光に見(まみ)え」(見仏)音響による光のマンダラを設営した。それはまた、彼の光宇宙の基底音と基底像を見出す一種の「行」でもあったと言えるのではないか。
ところで筆者はふと、以前読んだギヨーム・アポリネールの「光の声」という言葉を思い出した。アポリネールはキュビズムを擁護したフランスの詩人、美術評論家だがその『動物詩集』の冒頭、《獣類―オルフェの言葉》にあった一句2。
ほめよ、たたえよ
線の気高さと 力強さを
これだ エルメース・トリメジストが
『ピマンドル』3の中で歌っている
光の声というあれは
後続のノートには、こうある。
『ピマンドル』のなかにはこう書いてある「やがて闇の中からなんとも言いようのない叫びが聞こえたが、どうやらそれは光の声であるような気がした」云々と。
この光の声こそは、デッサン、すなわち線ではないだろうか? それにまた、光がその全表情を発揮する場合、万物に色彩がうまれでる。だから絵画はしょせん光の言葉にほかならないというわけだ。4
そこで筆者は、こう思った。
西村の『耿』における春光からヴィシュヌ世界『太陽の臍』までの歩みは、「光の声を聞き」それをヘテロフォニーという形式に抽出し(デッサン)、可聴化する聞法。
アポリネールはまた『美的省察――キュビズムの画家たち』(1933)で、「すべての物体は光の前では平等である。その変化は、光が勝手に作る、光の力の結果である。われわれはすべての色を知らない。各人が新しい色を発明する。」5と述べている。すなわち、光という単一のものが物質世界に当たって出現させる色彩の多数性、多様性を指摘しており、そこに「一即多」としての光をイメージするのはそれほど突飛ではなかろう。
すなわち、『太陽の臍』から『光のマントラ』までは、光の十全の表出、すなわち「光の色彩を見取り」可聴化する「見仏」。西村はそれを内宇宙、と表現したが、それは『耿』での「Reflexion 」までたどることのできる鏡面世界丸ごとの内外なき全一宇宙の光そのものの希求であり、『光のマントラ』での光明真言とマンダラは、響きによる光の全一的可聴化の試みであった、と言えようか。
ここで、古代世界における宇宙と光の現れ、を見ておきたい。
まず『リグ・ヴェーダ』では。
《宇宙開闢の歌》
そのとき(太古において)無もなかりき、有もなかりき。空界もなかりき、その上の天もなかりき。何ものか発動せし、いずこに、誰の庇護の下に。深くして測るべからざる水は存在せりや。
太古において、暗黒は暗黒に蔽われたりき。この一切は標識なき水波なりき。空虚に蔽われ発現しつつあるもの、かの唯一物は、熱(tapas)の力によって出生せり。6
《タパスの歌》
創造者は太陽と月とを、順序に従って形づくれり、天と地と空間とを、次に光明を。7
《スーリアの歌》
彼の輝く標識、光線は遠く人間のあいだに現れつ、火のごとく燃えさかりつつ 弛まず進み、一切に見らるる汝は、光明の創造者なり、スーリアよ。汝は光明世界を輝かす。
われらは暗黒より(出でて)、高空の光明を(仰ぎ)見つつ、神々のあいだなる神スーリアに向いて行けり、最高の光明に向いて。8
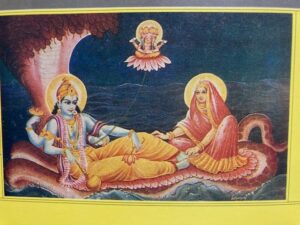 つまり、宇宙の暗黒原水から熱(摩擦)によって創造主(唯一なるもの)が現れ、太陽(昼)と月(夜)をつくった、その太陽が光明の創造者だ、と言っているわけだ。太陽の持つ万物を明らめる・現す作用としてのこの光明は、密教における大日如来と考えてよかろう。大日如来とは梵語Mahāvairocanaマハーヴァイローチャナ、摩訶毘盧遮那(まかびるしゃな)で、大遍照、大光明遍とも呼ばれ、輝かしいもの、という意。万物の究極の根底にある仏、宇宙の中心仏、マンダラの中心仏であるのも宜なるかな。
つまり、宇宙の暗黒原水から熱(摩擦)によって創造主(唯一なるもの)が現れ、太陽(昼)と月(夜)をつくった、その太陽が光明の創造者だ、と言っているわけだ。太陽の持つ万物を明らめる・現す作用としてのこの光明は、密教における大日如来と考えてよかろう。大日如来とは梵語Mahāvairocanaマハーヴァイローチャナ、摩訶毘盧遮那(まかびるしゃな)で、大遍照、大光明遍とも呼ばれ、輝かしいもの、という意。万物の究極の根底にある仏、宇宙の中心仏、マンダラの中心仏であるのも宜なるかな。
ついでに言うと、ヴェーダで最も人気の高い武勇の最強神インドラは金剛杖をかざし悪魔を退治する神で、こちらは帝釈天となり、マンダラの金剛界へと繋がる。一方、ヴィシュヌ神の胎内から伸びた蓮華の中からさまざまな神々が出現、それが宇宙全体を産んだというヴェーダ神話もまた、そのまま胎蔵界へと繋がるわけで、インド古代世界はこのように時空を経ての変化(へんげ)を遂げ、脈々と今日まで生き続けていると言えよう。9
なお、西村の『タパス』(1990)は『チェロ協奏曲』『永遠なる混沌の光の中へ』と同年作であり、原水・混沌・熱・光をそのまま音で模索する姿がそこに見えるように思う。
スーリアから大日如来、つまり古代インドから日本密教の道の間にはむろん中国がある。
では古代中国の世界起源の一つ、盤古神話(『三五歴記』『述異記』など3世紀頃の古文献に記録・採録されたもの)での光は?
『三五歴記』の一文を引くと、
天地混沌如雞子盤古生其中萬八千歲天地開闢陽清為天隂濁為地盤古在其中
これに、民間伝承として伝わるいくつかの神話を光の出現(太陽)を中心に筆者が大雑把に一つにまとめると、こんな感じだ。
天地混沌の中の鶏卵から巨人盤古が生まれ、一万八千年を経て天地が分かれ陽と清が天となり,陰と濁が地となる。盤古の成長につれ、天地の間はどんどん広がり、一万八千年を経て天地は九万里にまで達する。盤古が死ぬとその息は風に、左目は太陽、右目は月となった。そうして万物が生成された。10
こちらは『リグ・ヴェーダ』のもう一つの宇宙開闢讃歌《黄金の胎児讃歌》11、創造神は「黄金の胎児」として太初の原水の中に孕まれて現れる、というストーリーに連なる。万有の胚子「黄金の卵」すなわち「宇宙卵」というイメージだ。
混沌が明(天)暗(地)に分かれるのは盤古が天を持ち上げ、地を沈めたからという話もあるが、どの伝承でも一致するのは彼の屍から生まれるのが太陽、月ということ。さらにその身体部分から風、河川、草木、山岳などが生まれるという伝承は『リグ・ヴェーダ』の原人(プルシャ)に重なろう。
では、我らが『古事記』(712年)はどうか。序にはこうある(現代文のみ)。
臣安萬侶(やすまろ)が申し上げます。
そもそも宇宙の初めに、混沌とした根元がすでに固まって、まだ生成力も形も現れなかったころのことは、名づけようもなく動きもなく、誰もその形状を知るものはなかった。
しかしながら、天と地が初めて分かれると、三柱の神が万物の創造主となりました。
そして陰と陽の二気に分かれると、その二神の霊が万物を生み出す祖先となりました(伊邪那岐命いざなぎのみこと・伊邪那美命いざなみのみこと)。
そして、黄泉の国を訪れて現世に帰り、目を洗ったことにより日の神(あまてらすおおみかみ/天照大神)と月の神(つくよみ/月読)が現れ、海に浮き沈みして身を洗ったことにより天津神(あまつかみ/天の神)と国津神(くにつかみ/地の神)が現れました。12
混沌が天地に分かれると神が出現、神が万有を生み、日の神月の神を生む《宇宙開闢讃歌》系である。なお、やや遅れて編纂された『日本書紀』は宇宙卵系となっている。
いずれにせよ共通するのは混沌から天地が分たれ、創造主が現れ、ついで太陽、月が生まれることだ。混沌はインドでは暗黒原水とされるが、どの神話でも創造神がまず太陽を生むのであれば、古代人がいかに「光」を渇望したかも伝わってくるのではないか。
ついでに言えば、筆者は西村の声楽作品に「我の井戸から汲む声」を聴いたが、その井戸の底に流れるのはこの原水であろうと思う。
暗黒原水〜熱〜創造主は、むろん生命(ヒト)の誕生のなぞりに近い。男女の交合から生まれる生命(母胎内宇宙・宇宙卵)もそれだし、出生も同様。母胎内の羊水に浮かぶ眼を閉じた胎児は闇と水に包まれており、産道を通って生まれ出で、大気を吸い眼裏に光を感じる。誰もが等しく経験し忘れる(記憶している人も居るようだが)この闇から光への誕生のプロセスが、そのまま宇宙論になるのは自然だろう。太陽の巡行、夜から昼、闇から光、冥界からこの世、その円環に輪廻の概念が生まれるのもまた宜なるかな。そうして、ここに示される思考・傾向は光の「受け止め」としての「光、来たれり」のように思う。
その意味で、旧約聖書の『創世記』は特異だ。
旧約聖書の『創世記』は以下。
はじめに、神は天と地を造られた。
地はむなしくなにもなかった。やみは深淵の上にあり、神の霊が水の上をおおい動いていた。
神が、「光あれ」と言われると、光があった。
神はその光を見て、よいとされた。神は光とやみとを分けて、光を「昼」と名づけ、やみを「夜」と名づけられた。そして夕となり朝となって1日が過ぎた。13
暗黒原水の認識は共通するが、全権は神にある。
だがいずれにせよ、まず「光、あれ」であるのはやはり光が人類普遍の初発の渇望であることを示していよう。それは人間の生存本能そのものである、と言ってもいい。
筆者はインドの片田舎のボロいホテルでシャワーを浴びようとしていた時、突如停電し、それこそ真っ暗、漆黒の闇に包まれたことがある。立っているその感覚が足裏にあっても、自分という存在がかき消えたような強烈な不安に襲われた。
闇は存在消失の恐怖、さらには死の恐怖でもあろう。
前稿で光が人間にとっての宗教の根源・始原にあるものだと筆者は述べたが、「光、あれ」にせよ「光、来たれり」にせよ、それは人間の発する最初の、そして最も切実な願い、すなわち「祈り」に他なるまい。したがってどの文化圏でも光は唯一無二の聖性を宿し、唯一者、絶対者ともみなされるのだ。アートマンも様々な神も、光として語られるように。
『人間はなぜ歌うのか』をめぐり、歌は呼びかけである、と筆者は結論したが、それを光への呼びかけ(招来)、とすればそこにありありと宗教儀礼が立ち現れる。
であれば、西村の『耿』から『光のマントラ』まで、彼の光の希求は音響における「光の儀礼」の創出への道のりであったのではないか。マンダラが梵我一如の行の一つであったように、ここでの儀礼とは音楽による光の招来であり、その意味で古代のそれと変わりない。一気に言えば、やはり西村は宗教音楽家なのだ。
ちなみに、彼の管楽器作品は『巫楽』2作(1990&1994版/管楽と打楽器のためのヘテロフォニー)に続き、吹奏楽『秘儀Ⅰ〜Ⅸ』シリーズ9作となっている。タイトルを列挙する。
 秘儀Ⅰ(2008)
秘儀Ⅰ(2008)
秘儀Ⅱ(2013)
秘儀Ⅲ 旋回舞踊のためのヘテロフォニー (2014)
秘儀Ⅳ 行進(2016)
秘儀Ⅴ エクリプス(2019)
秘儀Ⅵ ヘキサグラム(2020)
秘儀Ⅶ 不死鳥(2018)14
秘儀Ⅷ 地響天籟(2021)
秘儀Ⅸ アスラ(2023)
思うに、吹奏楽という形(気息の楽)にこの「秘儀」というタイトルをあてたのは、まさにそれが天への儀礼であることを意味するからだろう。筆者はここに彼の創作の「素」のままのありようを見る気がする。
先日、この『秘儀シリーズ』全曲演奏会に出向き15、そのプログラムに「秘儀」とはシャーマニズムに類するもので、「『秘儀』のシリーズは、宗教や内容を特定しない秘教的な祈祷の儀式をイメージして作曲されている。」とあるのを読み、さらにステージで「吹奏楽(曲によっては弦打も入るが)が色彩的にもスケール的にもアジアの精神世界を描くのに向いており、自分にとっては直接的に表現できる領域」と語るのを聞き、やはりそうか、と思った。全9曲(最後のⅨは委嘱作世界初演)は舞踊であったり行進であったり、さまざまなスタイルをとるものの、ヘテロフォニーからケチャまでこれでもかとばかり盛り込んだ、いわばはちゃめちゃ自己解放のような作品群で、そのように猛烈な熱量を噴出する「自分が怖い」との本人の言は、つまりは西村自身がシャーマンだ、と言うことであり、全曲演奏の若きメンバーたちの獅子奮迅・快刀乱麻ぶりはまさに「降臨」そのものであった。何が降臨かといえば、太陽の光輝とおどろおどろしい闇(の神々)との交差で、第9曲『アスラ』のアスラと神々の戦闘など、メンバーが血沸き肉躍らせ完全にその音楽に没入しているのを見聞、つまりはインド古代神話世界は今日のゲーム世界の戦いと全く同じなのだ、とつくづく感じたのであった。ある意味、幻想・仮想世界とは人間にとって必須のものなのかも知れない。
光は闇とのセットであり、それは生と死に他ならない。そうして宗教とは常に死(生老病死)の凝視から導かれる生への問いから発する光への祈りである、と言うこともできよう。かつ、祈りとは自己の非力(この世の抗いようのない不条理への無力)を知ってこそ生まれる最も人間的な行為であろう。
遍在する光の眩い輝きを西村はいつ、どこで感知したか。
そんなことはわからない。ただ、幼い頃から仏教のある宗派の熱烈な信徒であり、神社神道を敬ういかにも日本的な信心深い祖父に「お釈迦さま」の漫画本をもらい、おそろしい地獄絵図も見、「雲の上には仏様のいる極楽、地面の底深くには地獄があると素直に信じた」16子供であれば、天地のイメージは完璧に刷り込まれていたろう。さらにこちらも信心深い母ともなれば結婚して長く子供に恵まれず霊験あらたかな「金光教」(金の光だ)に入信、その甲斐あって17年目にようやく授かった子供であれば、妊娠を告げられる朝に目を開くと「まばゆい光の輪が広かり、霊妙な鈴の音が聞こえた、だからお前は神様に授けられた子」と繰り返し繰り返し言って聞かせたのだから、そうして「あきら」と命名したのだから、その種のセンサーは間違いなく幼児期から発達したに違いない。
筆者のいう宗教、あるいは宗教性とは、哲学思想の次元ではなく、日々の生活の中に溶け込み根付く神仏への畏敬・畏怖の心のことであり、むしろそれこそが「信心」の本来の姿と思う。その意味で、西村はあくまで衆生の海に浮かぶ人であった。
「光が聞こえ、光が見える」あるいは「光を聞き、光を見る」。
西村は光について、沼野との対談でこう語っている(『光の雅歌』p.199)。
僕の初期に、ひかりという言葉の意味は、生命体そのものの象徴であって、光の波動が生命体であり、自分を突き刺すように迫ってくるような光のあり方だった。まさしく、生命が光っているという感覚ですね。
『光のマントラ』(1993)以降、産出される「光」タイトルは管弦楽作品で『光の鳥』(94)『メロスの光背』『光の雅歌』(96)『残光』(98)『光と影の旋律』(2000)『秘密〜マニの光』(01)『内なる光』(03)の7作。室内楽は『蓮華の光』(96)『静寂と光』(97)『ヘイロウス(光輪)』『オパール光のソナタ』(98)『夜光』(99)『瑠璃光の庭』(2005)『光の雫』(07)の7作。邦楽器は『耿』(2000)『夢幻の光』(2004)2作。
『光のマントラ』以降の光シリーズは虹のヘテロフォニーと言えば良いか。『太陽の臍』の生命エネルギーとは異なる静けさと輝きを広げているのは、次なる影世界への歩みと言えよう。
さて繰り返すが、光と闇は常に表裏だ。それは生死でもある。その深淵に立つのが宗教、音楽というものだ。
光の希求とともに見えてくるのは影・闇だが、1994年インドの聖地ベナレスで日没と日昇を眼前にした西村は、むろんそこで生死の実相を知ることになる。
『黄昏の幻影』(1995)がまず管弦楽に現れる。ピアノ独奏『三つの幻影』(1994)、室内楽『黄昏』(1995/ソプラノ、トランペットとオルガンのための)で彼は光から闇への狭間にある「黄昏」を描く。そうして管弦楽『流れ〜闇の訪れた後に』『蓮華化生』(いずれも1997年)で、黄昏から闇へと入ってゆくのである。
その闇に足を踏み入れる前に、人類が手にした擬似陽光たる文明の火、炎がうら若い女人を焼く芥川龍之介『地獄変』のオペラ化『絵師』(1999)を次回は取り上げたい。筆者としては、やっとオペラに辿り着いた、ここまでが長かった、とつらつら思う次第。
脚注
- 『字統』 白川静 平凡社 p.303
- 『アポリネール詩集』 堀口大學訳 新潮文庫 p.13, p.40
- エルメス・トリメジストス:古代ギリシアの神秘思想・錬金術の神人。
- 『ピマンドルポイマンドレース』:グノーシス神話
- 『アポリネール詩集』 堀口大學訳 新潮文庫 p.40
- 『アポリネールと立体派の画家たち』 中込純次著 p.21
- 『リグ・ヴェーダ』 辻直四郎訳 岩波文庫 p.322-323
- 同上 p.309
- 同上 p.30
- 『密教経典・他』 中村元著 現代語訳 大乗仏典6 東京書籍 p.126-128
『藝文類聚』『太平御覽』にある『三五歴記』からの引用文
徐整三五歴紀曰
天地混沌如雞子盤古生其中萬八千歲天地開闢陽清為天隂濁為地盤古在其中一日九變神於天聖於地天日髙一丈地日厚一丈盤古日長一丈如此萬八千歲天數極髙地數極深盤古極長後乃有三皇數起於一立於三成於五盛於七處於九故天去地九萬里 - 『リグ・ヴェーダ』 p.317
- 『古事記 (上)』 全訳注 次田真幸 講談社学術文庫 p.17
- 『創世記』 聖書 原文校訂による口語訳 フランシスコ会 聖書研究所訳注 p.30
- 年代順になっていないが、シリーズの順番に合わせた
- 「Wind Orchestra Spark 特別演奏会“秘儀”」 2023年5月27日@武蔵野市民文化会館大ホール
- 『曲がった家を作るわけ』 西村朗著 春秋社 p.64
参考資料)
◆書籍
『字統』白川静著 平凡社 1984
『古代思想』 中村元選集「決定版」別巻1 春秋社 1998
『アポリネール詩集』 堀口大學訳 新潮文庫 2007
『アポリネール全集』 堀口大學著 青土社 1979
『アポリネールと立体派の画家たち』 中込純次著 青樹社 1993
『リグ・ヴェーダ』 辻直四郎訳 岩波文庫 1984
『光の解読』 宗教への問い2 坂口ふみ・小林康夫・西谷修・中沢新一編集 岩波書店 2000
『リグ・ヴェーダ』 辻直四郎訳 岩波文庫 1984
『密教経典・他』 中村元著 現代語訳 大乗仏典6 東京書籍 2004
『アジアの宇宙観 図像カタログ』 構成:杉浦康平 監修:岩田慶治 講談社 1982
『古事記 (上)』 全訳注 次田真幸 講談社学術文庫 1977
『創世記』 聖書 原文校訂による口語訳 フランシスコ会 聖書研究所訳注 1996
『曲がった家を作るわけ』 西村朗著 春秋社 2013
(2023/6/15)


