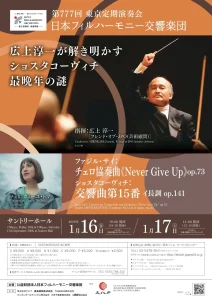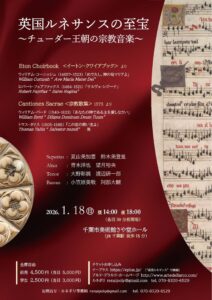オペラシアターこんにゃく座公演「明日のオペラへの誘い」|齋藤俊夫
 オペラシアターこんにゃく座公演「明日のオペラへの誘い」
オペラシアターこんにゃく座公演「明日のオペラへの誘い」
Opera Theatre Konnyakuza “Invitation to Tomorrow’s Opera”
2025年3月6日 俳優座劇場
2025/3/6 Haiyuzagekijou
宮澤賢治歌劇場VI
オペラ『タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった』
オペラ『鹿踊りのはじまり』
2025年3月12日 俳優座劇場
2025/3/12 Haiyuzagekijou
宮澤賢治歌劇場VII
オペラ『なめとこ山の熊』
コミックオペレット『饑餓陣営』
賢治詩歌集
Reviewed by 齋藤俊夫 (Toshio Saito)
Photos by 長澤直子/写真提供:こんにゃく座
<スタッフ・キャスト> →foreign language
原作:宮澤賢治
演出:加藤直
作曲:林光(オペラ『鹿踊りのはじまり』、コミックオペレット『饑餓陣営』)
萩京子(オペラ『なめとこ山の熊』)
中野健一(オペラ『タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった』)
美術:池田ともゆき
衣裳:生田志織
照明:齋藤茂男
振付:山田うん
演出助手:城田美樹
舞台監督:八木清市
舞台監督助手:山貫理恵
音楽監督:萩京子
宣伝美術:小田義久(デザイン)、竹上妙(木版画)
オペラ『タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった』(新作初演)
タネリ:小林ゆず子
風1:齊藤路都
風2、お母さん:岡原真弓
風3:髙野うるお
風4:泉篤史
風5:富山直人
クラリネット:橋爪恵一、ヴァイオリン:山田百子、打楽器:石崎陽子、アコーディオン:佐藤芳明
オペラ『鹿踊りのはじまり』(新演出)
わたくし:金村慎太郎
嘉十:島田大翼
鹿:西田玲子
鹿:北野雄一郎
鹿:沢井栄次
鹿:熊谷みさと
鹿:小田藍乃
鹿:冬木理森
クラリネット:橋爪恵一、ヴァイオリン:山田百子、打楽器:石崎陽子、アコーディオン:佐藤芳明
オペラ『なめとこ山の熊』(オペラ版初演)
熊1、小十郎の孫:青木美佐子
熊2、小十郎の孫:鈴木裕加
熊3:梅村博美
熊4、おきの(荒物屋の女中):彦坂仁美
熊5、子熊、小十郎の孫:石窪朋
熊6、犬:沖まどか
熊7:鈴木あかね
熊8、婆さま:相原智枝
熊9、母熊:花島春枝
熊10、平助(荒物屋の使用人):中村響
熊11、荒物屋の主人:壹岐隆邦
熊12、熊:佐藤敏之
熊13、熊:吉田進也
熊14:松田祐慈郎
小十郎:大石哲史
打楽器:髙良久美子、ピアノ:吉村安見子
コミックオペレット『饑餓陣営』(新演出)
バナナン大将:武田茂
特務曹長:沖まどか
曹長:松田祐慈郎
兵卒1:花島春枝
兵卒2:石窪朋
兵卒3:佐藤敏之
兵卒4:豊島理恵
兵卒5:壹岐隆邦
兵卒6:鈴木裕加
兵卒7:鈴木あかね
兵卒8:入江茉奈
兵卒9:中村響
兵卒10:吉田進也
兵卒11:彦坂仁美
ピアノ:吉村安見子
賢治詩歌集
詩:宮澤賢治
『月夜のでんしんばしら』(曲:宮澤賢治、編曲:林光)
『岩手軽便鉄道の一月』(曲:林光、編曲:萩京子)
『電車』(曲:萩京子)
『祈り』(曲:林光)
『海だべがど』(曲:林光)
『五がつははこだてこうえんち(「函館港春夜光景」より)』(曲:萩京子)
『風がおもてで呼んでゐる』(曲:萩京子)
『ポラーノの広場のうた』(曲:林光)
『星めぐりの歌』(曲:宮澤賢治、編曲:林光)
大石哲史、梅村博美、相原智枝、岡原真弓、青木美佐子、佐藤敏之、富山直人、花島春枝、髙野うるお、石窪朋、鈴木裕加、豊島理恵、彦坂仁美、島田大翼、西田玲子、北野雄一郎、沢井栄次、沖まどか、熊谷みさと、齊藤路都、壹岐隆邦、金村慎太郎、武田茂、小田藍乃、小林ゆず子、鈴木あかね、冬木理森、泉篤史、吉田進也、入江茉奈、中村響、松田祐慈郎
ピアノ:萩京子、吉村安見子、打楽器:髙良久美子
宮澤賢治作品に内在する「ほんたうのこと」は、大上段に構えた「この世の真理」なんてもののイメージからは程遠い、小さく、いとけなく、手にしたらすぐにホロホロと崩れ消え去っていき、それでも私たちの心に確かに残り続ける、そんなものではないだろうか。
 『タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった』の原作は筆者の蔵書には収録されておらず、青空文庫で初めて読んだ。そしてその〈非劇的な劇〉ぶりに大いに驚かされた。
『タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった』の原作は筆者の蔵書には収録されておらず、青空文庫で初めて読んだ。そしてその〈非劇的な劇〉ぶりに大いに驚かされた。
あらすじはこうだ。タネリ(男の子か女の子かはわからない)が藤蔓を噛みながら1)「山のうえから、青い藤蔓とってきた…西風ゴスケに北風カスケ…」等々歌いつつ家を出て、自然の中で風や柏の木や蟇(ひきがえる)や栗の木や鴇(とき)たちと会話しつつ散策し、家に帰る、ただそれだけ。
中野健一がこの〈非劇の劇〉のために書いた音楽は日本伝統音階、もしくはそれに近い音階で、器楽はアコーディオンのソロを主軸とし、そこにタネリと心を交わす自然界の諸々の音楽としてヴァイオリンとクラリネットが闖入してくる。ミニマルな、単純簡素な音楽だったと言えるだろう。
「風」役5人が語りと歌で劇を進行し、タネリを包む自然を現す。あたかもネオリアリズモのように〈自然〉描写と〈幻想〉描写が交錯し、それに合わせて「風」たちもうねうねと腕をくねらせたり、タネリを中心にグルグルと駆け回ったりする、そのコレオグラフィーも幻想的。
本当に何も出来事らしき出来事が起きないこのオペラ、観ている最中の楽しさと観終わったときの得も言われぬ感慨、共に類を見ない。人間が人間としてあるがままの姿で、人間が自然の中の一部としてあるがままの姿で自然と交流する。その人間と自然の「ほんたうのこと」の温かさ、それが都会の民たる筆者の胸を打った。
 『鹿(しし)踊りのはじまり』、これもいわゆる〈劇的〉な物語ではない。農家の嘉十が手拭いと栃の実の団子をつい置き忘れてしまった所、鹿6匹が栃団子とその手拭いを怪しんで順繰りにこれは何であろうかと探り合う。鹿たちは手拭いは蝸牛(なめくずら)の干からびたものであろうと結論し、祝いの合唱をし、栃団子を少しずつ分けて食べ、さらに鹿が自然の美しさを称えるアリアを順に歌い、手拭いを中心に「鹿踊り」を輪舞する。それを見ていて感極まった嘉十が声を上げてしまい、鹿は逃げ隠れてしまう、ただそれだけ。
『鹿(しし)踊りのはじまり』、これもいわゆる〈劇的〉な物語ではない。農家の嘉十が手拭いと栃の実の団子をつい置き忘れてしまった所、鹿6匹が栃団子とその手拭いを怪しんで順繰りにこれは何であろうかと探り合う。鹿たちは手拭いは蝸牛(なめくずら)の干からびたものであろうと結論し、祝いの合唱をし、栃団子を少しずつ分けて食べ、さらに鹿が自然の美しさを称えるアリアを順に歌い、手拭いを中心に「鹿踊り」を輪舞する。それを見ていて感極まった嘉十が声を上げてしまい、鹿は逃げ隠れてしまう、ただそれだけ。
鹿たちが手拭いを探り探りするシーンと手拭いの正体を見破ったシーンのユーモア、祝いの合唱のおおらかなスケールの大きさ、銘々のアリアの美しさ、鹿踊りのたった4人のアンサンブルと6人の合唱が大編成のように響く林光の音楽のダイナミズム、さらに演出、コレオグラフィーの見事さ、なんと愉快な観劇体験であったことか。
鹿たちの他愛もないが邪気もない純真な心、自然の「ほんたうのこと」が舞台上に現れていた。おそらく、筆者はこんなふうには生きられないだろう、と思いつつも憧れる「ほんたうのこと」であった。
 『なめとこ山の熊』、主人公・淵沢小十郎は熊捕りの名手。ある日出くわした熊に「もう2年ばかり待ってくれ。2年目にはおれもお前の家の前でちゃんと死んでやるから」と言われ、見逃してやるとその2年後、小十郎の家の軒先で熊がそっと死んでいた。そんな小十郎は町で熊の皮と胆を旦那に売るときは頭を低く低くせざるを得ない。そしてある日、小十郎は熊を撃ち損じて熊に殺される。その3日目の晩、小十郎の死骸をぐるりと熊たちが囲んでいつまでも動かないでいるのであった。
『なめとこ山の熊』、主人公・淵沢小十郎は熊捕りの名手。ある日出くわした熊に「もう2年ばかり待ってくれ。2年目にはおれもお前の家の前でちゃんと死んでやるから」と言われ、見逃してやるとその2年後、小十郎の家の軒先で熊がそっと死んでいた。そんな小十郎は町で熊の皮と胆を旦那に売るときは頭を低く低くせざるを得ない。そしてある日、小十郎は熊を撃ち損じて熊に殺される。その3日目の晩、小十郎の死骸をぐるりと熊たちが囲んでいつまでも動かないでいるのであった。
「熊。おれはてまえを憎くて殺したのでねえんだぞ。おれも商売ならてめえも射たなけぁならねえ。(中略)てめえも熊に生れたが因果ならおれもこんな商売が因果だ。やい、この次には熊なんぞに生れなよ。」2)の言葉に端的に現れているように、自然も人間も、優しいけれど、厳しく、残酷ですらある。それも「ほんたうのこと」の一側面。熊は憎くないけれど、捕らなければ生きていけない。熊を捕ることに失敗すれば、自分が殺される。捕られる熊も小十郎を憎く思っていない。熊が「おお小十郎おまえを殺すつもりはなかった。」と言えば、小十郎は死ぬ際に「熊ども、ゆるせよ。」と言う3)。全ては自然の道理で、因果で、「ほんたうのこと」だ。だがなんと寂しく切ない「ほんたうのこと」であろうか。
人形紙芝居風の演出と、総勢14名の熊たちによる合唱オペラの形式を取った本作、最後のシーンで暗闇の中で熊たちが燐光のように光るものを持って小十郎を囲み、その小十郎の顔が微笑みを浮かべているように見えたのが特に印象に残った。
 浅草オペラを範にとったと言われる「コミックオペレット」『饑餓陣営』、タイトルが「饑餓」「陣営」と不穏極まりない二語からなるが、内容は宮澤賢治の作品でも指折りの喜劇。
浅草オペラを範にとったと言われる「コミックオペレット」『饑餓陣営』、タイトルが「饑餓」「陣営」と不穏極まりない二語からなるが、内容は宮澤賢治の作品でも指折りの喜劇。
マルトン原と呼ばれる地で、バナナン軍団が臨時幕営を張っている。バナナン大将不在であるが、軍団は皆空腹を抱えて「ストマックウォッチも、もうめちゃくちゃだ。」4)とやけっぱちになっている。そこにバナナン大将が菓子でできた勲章とバナナ(当時は高嶺の花の果物である)でできたエボレット(礼装用軍服等の肩飾り)で身を固めて帰営する。特務曹長と曹長以下兵卒たちは、銃殺されても構わんとばかりにバナナン大将の勲章とエボレットを褒め称えてはそれを食べてしまう。全て食べ終わった後に、特務曹長と曹長が自決の覚悟を決めると、バナナン大将はそれを制止し、果樹整技法に基づく生産体操を皆に教授する。皆が生産体操を習得すると、全員バナナン軍団を称える歌を唄いつつ行進し、幕が降りる。
軍隊という集団が生来的に持つ凄惨さは語るも愚かであるが、宮澤賢治は本作品でそれを反転させて実に牧歌的で温かい集団に変えてしまっている。現実の軍隊は殺し、奪い、破壊する集団であるが、本作品のバナナン軍団は果樹整技法生産体操で果物類を育て、皆でバナナを食べ、歌を唄う集団である。この宮澤の反転のラディカリズムは、世界で戦争が続いており、日々廃墟・瓦礫・死傷者の映像を見ざるをえないまさに現在こそ実感できるものだ。農村に楽園を見ようとした宮澤が今の世界の戦地を見たならばどんなにか嘆くであろうか。銃を捨てよ、鍬をとれ、歌を唱え、もっと「ほんたうのこと」を見つめろ、そう宮澤賢治なら訴えたであろう。
腹が減って仕方がない軍団の行進、本当に腹が減って仕方がない兵卒の歌、腹が膨れたところで特務曹長と曹長が決死の覚悟で唄う「饑餓陣営のたそがれの中~」の神妙なアリア、そして全員での果樹整技法生産体操の振り付けと最後の行進の大合唱、楽しからざる所なき、まさに小さな喜歌劇、「コミックオペレット」にふさわしい佳品であった。
 宮澤賢治歌劇場の最後を飾った「賢治詩歌集」、時にダイナミックであったり(岩手軽便鉄道の一月)、自分の死さえ厭わずに平和を祈る敬虔な心が現れていたり(祈り)、日本伝統音階をベースにしつつも対位法のテクスチュアが美しく織りなされたり(海だべがど)、「栄えある世界を共に作らん」と理想への強い意志を見せたり(ポラーノの広場のうた)など多彩だがどれもこれもリリカル、しかしどうしても宮澤賢治となると今回最後に歌われた『星めぐりの歌』にやられてしまう。何故こんなに純真無垢な歌があり得るのだろうか……?
宮澤賢治歌劇場の最後を飾った「賢治詩歌集」、時にダイナミックであったり(岩手軽便鉄道の一月)、自分の死さえ厭わずに平和を祈る敬虔な心が現れていたり(祈り)、日本伝統音階をベースにしつつも対位法のテクスチュアが美しく織りなされたり(海だべがど)、「栄えある世界を共に作らん」と理想への強い意志を見せたり(ポラーノの広場のうた)など多彩だがどれもこれもリリカル、しかしどうしても宮澤賢治となると今回最後に歌われた『星めぐりの歌』にやられてしまう。何故こんなに純真無垢な歌があり得るのだろうか……?
歌劇の楽しさを存分に楽しみつつも、宮澤賢治が短い生涯で追い求めたその小さいけど真実な「ほんたうのこと」をこの世界でどうやって守り続けることができるのだろうか、などと考えさせられる「明日のオペラ」であった。
(2025/4/15)
1) 藤蔓を噛んで柔らかくして繊維を取り出して織物に使うのである。
2) 「なめとこ山の熊」『注文の多い料理店』新潮文庫、平成9年、293頁。
3) 前掲書、302頁。
4) 「饑餓陣営」『銀河鉄道の夜』新潮文庫、昭和54年、243頁。
—————————————
<Staff>
Author: Miyazawa Kenji
Director: Kato Tadashi
Composers: Hayashi Hikaru, Hagi Kyoko, Nakano Kenichi
Art Director: Ikeda Tomoyuki
Costume: Ikuta Shiori
Lighting: Saito Shigeo
Choreography: Yamada Un
Assistant Director: Shirota Miki
Stage Manager: Yagi Seiichi
Assistant Stage Manager: Yamanuki Rie
Music Director: Hagi Kyoko
Advertisement: Oda Yoshihisa, Takegami Tae
<Players>
Miyazawa Kenji Opera Theatre VI
Taneri certainly seemed to be biting every day.
Composer: Nakano Kenichi
Kobayashi Yuzuko, Saito Rutsu, Okahara Mayumi, Takano Uruo, Izumi Atsushi, Tomiyama Naoto
Cl: Hashizume Keiichi, Vn: Yamada Momoko, Perc: Ishizaki Yoko, Accordion: Sato Yoshiaki
The Origin of the Deer Dance
Composer: Hayashi Hikaru
Kanemura Shintaro, Shimada Daisuke, Nishida Reiko, Kitano Yuichiro, Sawai Eiji, Kumagai Misato, Oda Aino, Fuyuki Yoshimori
Cl: Hashizume Keiichi, Vn: Yamada Momoko, Perc: Ishizaki Yoko, Accordion: Sato Yoshiaki
Miyazawa Kenji Opera Theatre VII
The bears of Mt.Nametoko
Composer: Hagi Kyoko
Aoki Misako, Suzuki Hiroka, Umemura Hiromi, Hikosaka Hitomi, Ishikubo Tomo, Oki Madoka, Suzuki Akane, Aihara Tomoe, Hanashima Harue, Nakamura Hibiki, Iki Takakuni, Sato Toshiyuki, Yoshida Shinya, Matsuda Yujiro, Oishi Satoshi
Perc: Takara Kumiko, Piano: Yoshimura Amiko
Hunger Camp
Composer: Hayashi Hikaru
Takeda Shigeru, Oki Madoka, Matsuda Yujiro, Hanashima Harue, Ishikubo Tomo, Sato Toshiyuki, Toyoshima Rie, Iki Takakuni, Suzuki Hiroka, Suzuki Akane, Irie Mana, Nakamura Hibiki, Yoshida Shinya, Hikosaka Hitomi
Piano: Yoshimura Amiko
Kenji Song Concert
Oishi Satoshi, Umemura Hiromi, Aihara Tomoe, Okahara Mayumi,
Aoki Misako, Sato Toshiyuki, Tomiyama Naoto, Hanashima Harue,
Takano Uruo, Ishikubo Tomo, Suzuki Hiroka, Toyoshima Rie,
Hikosaka Hitomi, Shimada Daisuke, Nishida Reiko, Kitano Yuichiro,
Sawai Eiji, Oki Madoka, Kumagai Misato, Saito Rutsu, Iki Takakuni,
Kanemura Shintaro, Takeda Shigeru, Oda Aino, Kobayashi Yuzuko,
Suzuki Akane, Fuyuki Yoshimori, Izumi Atsushi, Yoshida Shinya,
Irie Mana, Nakamura Hibiki, Matsuda Yujiro