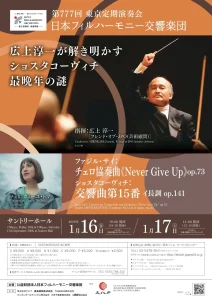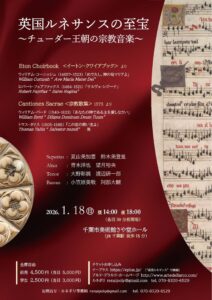日本フィルハーモニー交響楽団 第409回名曲コンサート|齋藤俊夫
 日本フィルハーモニー交響楽団 第409回名曲コンサート
日本フィルハーモニー交響楽団 第409回名曲コンサート
Japan Philharmonic Orchestra 409th Popular Concert
2025年3月1日 サントリーホール
2025/3/1 Suntory Hall
Reviewed by 齋藤俊夫 (Toshio Saito)
写真提供:日本フィルハーモニー交響楽団
<演奏> →foreign language
指揮:カーチュン・ウォン
ヴァイオリン:小林美樹(*)
<曲目>
伊福部昭:管絃楽のための『日本組曲』
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35(*)
(ソリスト・アンコール)
J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番より「ラルゴ」(*)
ムソルグスキー(ラヴェル編曲):組曲『展覧会の絵』
(オーケストラアンコール)
リムスキー=コルサコフ:『熊蜂の飛行』
ここのところ本誌でも集中して取り上げているが、現在のカーチュン・ウォン&日フィルの輝きは誰もが首肯するところだろう。筆者も稀に見る伊福部振りとして、かつその采配の鋭さをもって今の在京オケの指揮者として特級の逸材と評価している。そんなカーチュンが伊福部の『日本組曲』、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲、ムソルグスキー&ラヴェルの『展覧会の絵』という筆者の大好物を一度に振ってくれるというのだから垂涎の体で会場に赴いた。
最初に伊福部昭の『日本組曲』である。筆者の持っている録音音源でのマスターピースは1994年の小林研一郎指揮・新交響楽団の演奏1)。重厚で、野太く、筋骨たくましき伊福部解釈である。しかして今回のカーチュン・日フィルはあまり重くなく、太くもなく、筋骨たくましいわけでもない。だが恐ろしく斬れ味があり、1つ1つの音の音楽的位置が正確にはまっており、かつダイナミクスやテンポを大胆不敵に動かす。小林・新響がボクシングで言えばインファイターだとすれば、カーチュン・日フィルはアウトボクサーである。
第1楽章「盆踊」の時点でカーチュンは泥道を裸足で歩くような伊福部解釈ではなく、ペーブメントを革靴で歩くような解釈を聴かせてきた。
第2楽章「七夕」は透き通った寂しさの中の哀しさと美しさをゆっくりと味わう。木管楽器と弦楽器が呼び交わすような箇所でカーチュンの耳の鋭さがよくわかる。
第3楽章「演伶(ながし)」、この曲もまた寂しさを味わう。しかして弦楽器やホルンが雄大で、アッチェレランドはシャープに。カーチュンは自分の音楽を躊躇わずに確信を持って伊福部作品にぶつけてきて、その結果として最良の伊福部を再現している。
第4楽章「侫武多(ねぶた)」、随分と荒ぶると思っていたら、どんどんスピードが加速、音量が増大して、今までこんな伊福部音楽は聴いたことがないというほどのレベルにまで達する。だが一糸乱れぬ大乱舞で、ねぶた祭りが最高潮、有頂天に至って最後の和音が鳴り響き、会場一斉にブラボーの声が!
プ ログラム第2曲はチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲。
第1楽章、機械的な尺度でテンポやダイナミクスを測ったら異常にフラつきの大きい不安定な演奏と判定されるかもしれない小林美樹のソロだが、我 々人間が受け止めると、テンポルバートもダイナミクスの加減も実に自然で、人間的な「うた」として聴こえる。ソリストとオーケストラが、泣くように笑い、笑うように泣き、さらには、怒るように、嗚咽を上げるように唄う。これがチャイコフスキー、北国の音楽だ。
第2楽章の寂寥は先の伊福部の「七夕」を想起させる。寒い。凍える空気に、木管楽器の音が暖炉のように実に温かい。
そこから一転しての第3楽章、一気に雄渾にかつ俊敏にそして音楽的に正鵠を射た、ソリストとオーケストラによる、チャイコフスキー音楽の真骨頂。所々ゆっくりとしたテンポになる所で木管楽器の温もりを味わいつつ、高速で全員が一丸となって駆け抜ける!見事!
ムソルグスキー&ラヴェル『展覧会の絵』、あまりにもメジャー過ぎてかえって個性を発揮しづらい作品かもしれないが、この作品でもカーチュン・日フィルはやってくれた。
今回何度も言及したが、まず木管楽器群が素晴らしい。「古城」冒頭からのファゴット→アルトサックス→コール・アングレ→アルトサックスとソロが受け継がれていく場面の音の豊かさに目が覚める心地がした。他にも「テュイルリー宮殿の前庭」での鳥の囀りのような木管楽器の細かな無窮動にも非凡な技量が感じられた。日フィル、輝いている。
してみると「ビドロ」でのチューバソロの堂々たる横綱相撲も注記すべきかもしれない。さらには同曲でのオーケストラ全体がクレッシェンド→デクレッシェンドする場面ののしかかってくるような迫力も。
あるいは「殻をつけた雛の踊り」の的確極まりないリズムも記しておきたいところだ。リズムを外から押し付けられるものでなく、体の内から湧き出して揃っていくものとして体得したからこそできる芸当だ。
各パート、各楽器が自己主張するのだが、カーチュンの鋭い耳に基づく正確無比な采配によってお互いがお互いを高め合う、そんなオーケストラとしての最高の水準に達していたのが今回の『展覧会の絵』であった。最後の「キエフ(キーウ)の大門」の豊かすぎる音響に興奮冷めやらず、拍手鳴り止まず、アンコールとして冗談交じりの『熊蜂の飛行』が演奏されてやっと帰路につくことができた。何度でも言おう。今、カーチュン・ウォンと日フィルはかつて無い高みに達しようとしている。
1) 小林研一郎指揮、新交響楽団「管弦楽のための「日本組曲」」、CD『新交響楽団 伊福部昭 傘寿記念シリーズ』東芝EMI、TYCY-5424,25、1995年
(2025/4/15)
—————————————
<Players>
Conductor: Kahchun WONG
Violin: KOBAYASHI Miki(*)
<Pieces>
IFUKUBE Akira: Japanese Suite for Orchestra
Pyotr TCHAIKOVSKY: Concerto for Violin and Orchesra in D-major, Op.35(*)
(Soloist Encore)
J.S. Bach: Largo from Sonata No. 3 for Solo Violin BWV 1005
Modest MUSSORGSKY (Arr. By Maurice RAVEL): Suite “Pictures at an Exhibition”
(Orchestra Encore)
Rimsky-Korsakov : “Flight of the Bumblebee”