西村朗 考・覚書(20)邦楽器領域の作品(Ⅰ)篳篥と箏|丘山万里子
西村朗 考・覚書(20)邦楽器領域の作品(Ⅰ)篳篥と箏
Notes on Akira Nishimura (20) Japanese Instrumental Works
Text & Photos by 丘山万里子(Mariko Okayama)
『太陽の臍』(1989)で使用された篳篥の威力を「一人勝ち」と言ったが、細川俊夫が武満徹『ノヴェンバー・ステップス』(1967)での「尺八のあのすごい響き」に衝撃を受けたように、ここでの篳篥は西洋楽器を睥睨するところがある。
だが、武満と西村の邦楽器の響きへの向き合い方は、ずいぶん異なる。
『ノヴェンバー・ステップス』はニューヨーク・フィルからの委嘱であったが、武満は前年に琵琶・尺八『エクリプス』を書いており、協奏のアイデアはその折の演奏者鶴田錦史、横山勝也によって得た音の領土の拡大と深化の自覚から生まれている。また60年に NHK教育テレビ『日本の美』シリーズにおける『日本の紋様』のための音楽で筑前琵琶、琴などの邦楽器を初めて取り上げ、ミュージック・コンクレートの手法で作曲した。TV制作担当は杉浦康平と粟津潔で、1962年には杉浦との協働によるグラフィック記譜法作品『ピアニストのためのコロナ』(1962)が生まれている。1)この時期の杉浦はグラフィックデザインの旗手として音楽会カタログデザインなどでも活躍(雑誌『音楽芸術』1960~63も手掛ける)、72年に初のアジア訪問(タイ、インド、インドネシアなど)により一気にアジア宇宙観へとぶっとんでゆくのである。西村が彼と出会ったのはそうした軌跡上での精華が次々に花開いた時期であった。
いずれにせよ、武満の邦楽器領域開眼については宮内庁で聴いた雅楽(1962)、6o年の TV音楽、さらに映画『切腹』(1963)での琵琶使用を経ての6o年代前半。実験工房結成が1951年で、当時のメンバーが鈴木大拙を「発見」し夢中になっていたことを思えば、この時期の前衛における日本文化、あるいは邦楽(邦楽器)への接近が鎌倉仏教における禅宗の影響下、「間(ま)」「幽玄」「侘び」「寂び」といった能美学(観阿弥・世阿弥)に傾いていたことが知れよう。尺八のひと吹きに凝縮された美「一音成仏」はその典型と言え、武満の『ノヴェンバー・ステップス』もその路線上にある。
武満が作曲にあたり記したコメントを抜粋しよう。2)
「オーケストラに対して、日本の伝統楽器をいかにも自然にブレンドするというようなことが、作曲家のメチエであってはならない。むしろ、琵琶と尺八が指し示す異質の音の領土を、オーケストラに対置することで際立たせるべきなのである。」p.191
「数多くの異なる聴覚的焦点を設定すること、これは作曲という行為の(客観的な)側面であり、また、無数の音たちのなかに一つの声を聴こうとするのは、そのもうひとつの側面である。」同上
「洋楽の音は水平に歩行する。だが、尺八の音は完全に垂直に樹のように起こる。」p.192
「尺八の名人が、その演奏の上で望む至上の音は、風が古びた竹藪を吹きぬけていくときに鳴らす音であることを、あなたは知っていますか?」同上
「特別の旋律的主題をもたない11のステップ。能楽のようにたえず揺れ動く拍。」p.193
初演ゲネプロ時、オーケストラは序奏部でざわつき、反感をあらわにする様子もあったが、鶴田、横山両氏は目を閉じたまま端然としている。そうして、二者の演奏に入ると徐々に雰囲気が変化、独奏部ではじっと聞き入り、コーダ後の沈黙ののち、楽員たちの「ブラボー」と拍手が起こった、と武満の回想にある。p.195
東洋の未知と好奇心以上に、二人の演奏家の演奏が彼らを惹きつけた、という武満の実感は、けれどもやはり東西の対置・照応にあったと言えよう。
だが、西村の篳篥にそんな意識はない。もっとトータルな生命世界観とでも言えようか。
そもそも、篳篥は7世紀末〜8世紀初頭に雅楽の楽器として入ってきた西アジア起源のもの。篳(ヒツ)は柴竹を意味し、篥(リキ)もまた竹を意味するが栗(リツ)から「悲しくて身震いするような」3)の意がある。悲哀の音(ね)、とでも言え、古くは『源氏物語』若紫の巻に、源氏を迎えにきた頭中将の随行楽人が吹く場面「例の、ひちりき吹く随身、笙の笛持たせたるすきものなどあり」もその情感を伝えていよう。一方、異国で土龍などを脅すもの、4)ともされ、こちらは『枕草子』石清水臨時祭御前の儀での歌笛に続いての演奏を「ただいみじう、うるはし髪持たらむ人も、皆立ちあがりぬべきここちすれ」とあるように、祝祭的な力強さをもつ。
雅楽での使用はその後者を汲んだものであろう。龍笛の高音尖鋭に比べるとオーボエのような豊かな鳴りが特徴的だが、鳴らすには頬を膨らませる強い息が必要とされる。基礎音階はGから1オクターブ弱と狭いが、大きなポルタメントが可能で、まさに西村が好む中低音域(さらに母胎音響 G)そのもの。雅楽合奏の中でも常に旋律の中心を吹き、ヘテロフォニーを誘導する存在で、その響きの強さ、生命力にこそ、西村は賭けたのだ。そこに「哀の音」はない。
「篳篥の一本の力がオーボエ十七本分の力があるという仮説に立って、木管楽器群と対峙させた。で、篳篥が勝つ。どれぐらい勝つかというのが、次の瞬間から始まって、ここではむしろある意味では人間が地球上の生命世界を蝕んでいくわけです。オーケストラはそれを生命体で覆い尽くすんだけど、その中で篳篥は譲らない。」5)
武満は「対置」したが、西村は「対峙」させた。
ここには、篳篥に限らず、邦楽器の持つ精神的非合理性への強い共感が示されている。いわく「合理主義と精神的非合理主義との対峙」。p.100
邦楽器は、他地域では進化変容を遂げているのに対し、むしろ退行の道を辿る。古い形を墨守、あるいは退化させ、扱いは極めて不自由だが、それによって音色のキャラクターが強まり、「ものすごい音の力、表現力」を得ることになったと西村は言う。その退化・退行志向にあるのは、人間の文化文明世界の合理に対する原始的な非合理世界の「抵抗」と言ってよかろう。同時に、西洋哲学的思惟の生む自然界の世界秩序(合理)に抵抗しうる宗教的生命観が抱く不分明な混沌(非合理)を篳篥によって代弁させた、とも。
「あんな十八センチしかない、あの小さく原始的で不自由な楽器が大管弦楽と対峙する姿を示したかったんです。」6)
西村にとって、対峙とは、抵抗であった。
雅楽演奏の中で聴く篳篥の音圧には、両腕・摺り足でぐいぐい何かを押してゆくような力感がある。まさにそれが篳篥という楽器の持つ力のベクトルの一つで、「抵抗」としての篳篥を際立たせている。ヴィシュヌたる生命がそこに横溢しているのは言うまでもない。
西村が、なぜ篳篥を選んだか。
そこには、彼の強い生命欲求と非合理世界への傾斜が現れていると思える。
ところで、『太陽の臍』後半には笙の合竹のような響き(弦楽ノン・ヴィブラート和音とハーモニクス和音による)が聴かれ非常に印象的だが、この楽器は雅楽の途切れぬ平明な流れにあって常に背景音として響くもので、その奥ゆかしさと奥行きの広さ深さが、本作でも見事に生かされている。
さて、ここで、西村の邦楽器使用作品をざっと眺めておこう。
まず、箏。
箏関連はアラビア風旋法を用いた自由な即興音楽『タクシーム』(独奏二十絃箏のための/1982)を始点に、『時の虹彩』(箏群のためのヘテロフォニー/1987)、『七重』(独奏二十絃箏のための/1988)、『十七絃の書』(独奏十七絃箏のための/1988)、『彩歌』(箏独奏のための/1988)、『炎の幻声』(独奏二十絃箏と弦楽合奏のための協奏曲/1988)、『覡(KAMUNAGI)』(十七絃箏と打楽器のための/1992)、『瑠璃琴』(独奏二十絃箏のための/1999)、『樹海』(二十絃箏とオーケストラのための協奏曲/2002)、『偲琴』(二十五絃箏と低音二十五絃箏のための/2009)、『五面の箏のためのシャコンヌ』(2011)、『波の入り日』(箏と十七絃箏のための/2019)と全12曲。
箏もまた7、8世紀に唐楽の楽器(十三絃)として輸入され雅楽で使われたが、やがて寺院や民間に流れたものが、16世紀の「筑箏」を経て17世紀に八橋検校による「俗箏」となり、生田流・山田流に分派し現在に至る。宮城道雄が開発した合奏低音用の十七絃以降、1960年代末に器楽独奏楽器として脚光を浴び、また野坂恵子が三木稔と開発した二十絃(絃数は21に定着)でさらにレパートリーが広がり、現代箏曲の活気を生むこととなった。
したがって、西村らが用いるのは、表現範囲の広い十七絃や二十絃が多い。
 『タクシーム』に続く箏群のためのヘテロフォニー『時の虹彩』は国立劇場の委嘱作品(国立劇場がこの時期に果たした現代邦楽領域での役割は次回に述べる)。ソロ1を含む七面の箏とソロ1を含む三面の十七絃のための、となっており、初演は沢井忠夫、沢井一恵、沢井忠雄合奏団8名で壮大かつやや風変わりな音響世界を創出している。
『タクシーム』に続く箏群のためのヘテロフォニー『時の虹彩』は国立劇場の委嘱作品(国立劇場がこの時期に果たした現代邦楽領域での役割は次回に述べる)。ソロ1を含む七面の箏とソロ1を含む三面の十七絃のための、となっており、初演は沢井忠夫、沢井一恵、沢井忠雄合奏団8名で壮大かつやや風変わりな音響世界を創出している。
全2部でスコアに付記のコメントは以下。7)
大宇宙が無数の光のヴァイブレーションで満たされているように、大宇宙にはまた無数の時の流れの相が存在する。作曲者はこの作品で、それら時の相を象徴的かつ抽象的に描き出そうとしている。
<Ⅰ―時の層>では、近接する時どうしの“ゆらぎ”を表現することが望まれ、
<Ⅱ―時の河>では、解き放たれた10種の時の流れが独自の音空間を形成しつつ彷徨するような表現が望まれている。
単音ソロ低音Eから Gへと余韻を伴いゆったり上昇、三面が加わり、やがてこずえが細かく揺れるような下降音形が光の瞬きとともに次々とふってくる。低音十七絃が入り俄然、音響の幅が拡大され、低弦fffでの同音連打や高音域での下行上行グリッサンドなど、音の渦が出現。ゆらぎ、というより筆者には大小の渦の旋回に聴こえ、かつトレモロなど忙しなくかき鳴らされると箏であるだけにこっちの皮膚が爪で引っかかれるような感じがして、かなりおどろおどろしい。西洋の弦楽器の比ではない、というかやはり異質。景色は変わり、ぽつんと水滴が落ちるような風情...と思いきや、あっという間の騒乱状態。10小節で静寂が...と思いきや、収縮と膨張を繰り返し、如何せん「余韻」というものが良くも悪くもただならぬ尾を引くので、気分はくるくる変わってしまう。美しくもあれば残酷でもあるのだ。コーダの攻めに至っては、アッチェレランドでぐんぐん加速、最後のfff無調音グリッサンドがグサっとひと刺し。


スコアに付記された作曲者ノートを一部引いておく。
ゆらぎは個々の時間流の中にも見られる。マイクロ・ポリリズムと私が呼ぶ、細かいリズムのズレが幾層にも重なって奏出される。調弦は、冒頭に箏ソロが提示する完全5度の積み重ねを全楽器の骨格モードとし、そのすきまを各楽器にふり分けられた7種の部分モードがうめるように定められている。
が、第2部は、全く異なる世界。
奏者別々のスコアを持ち、演奏方法として7つの項目が記載されている。箏と十七絃ソロはプリペアドでPA使用。前衛なのだ!余情とか情感とかを剥奪された音たちはぴこぴこ踊り、これを時の河と聴くのは、いかに河のイメージはそれぞれと言ってもかなり無理があるのではないか。冒頭こそもの思わせぶりに静かだが、鹿威しの如き単音が落ちる背後はなにやら近未来的宇宙音が広がる。が、やがてリズミックなケチャに盛り上がり、時々人魂が浮遊するような気配が掠めるものの、どこかアニメチックに思えるのはやはりPA音響のせいだろう。ほとんど打楽器世界といって良い。
7項目を列挙しておく。
1. ここでは各奏者は別々の楽譜を持つ
2. 箏1の開始からCodaに入る前の休止までの時間は9分間とする。
3. 各奏者は自分のパートを9分間に時間的に構成する。
4. 楽譜中のフェルマータの長さは全く任意で、なるべく不規則な長さとする。
5. 箏ソロは箏1の開始から9分間が経過した時に(箏ソロのみ時計によってそのタイミングを知る)左手をあげて全奏者に知らせる。この時まだ演奏を終えていない奏者は、その時点で演奏中のフレーズを奏し、それが終わった時次のフレーズに入ることなく休止する。
6. そして箏ソロは全員の休止を確認したのち、Codaのテンポ♩=42を示し、Codaの入のアインザッツを全奏者に与える。
7. この曲では各奏者は自分固有の時間の流れの中に身を置き、他奏者との間でのアンサンブルは全く考えない。



というわけだが、各奏者が自由に、というか自分勝手な時間でやっているどころか、見事なケチャのノリで、これはどうしたところで人間の本源であろう。筆者はむしろそれが愉快であった。
こちらも作曲者ノートから一部。
近接する時の流れではなく、より遠く離れあって始まり、互いに干渉しつつ集まってゆき、ついには太い1本の時間流、すなわち時の河の主流を現出させることになる。箏ソロと十七絃ソロはクリップ、フィンガー・シンバル、ワリバシ等でプリペアードされ、他の8人の奏者は弦楽器の弓で箏を摩擦する。
初演時、会場はこの異形の響きにざわめいたそうだ。
この作品はスコアに CD付きの豪華本で入手は難しいと思われ、編成を見れば再演は無理にしても、お蔵に入ったまま、は残念な貴重品である。
西村自身もこの作品への言及はスコア以外、どこを探しても無いので、思うところがあるのかも知れぬが、筆者はこの時期の彼の創作の珍しい一面を見たようで、ここで長々と紹介した次第である。
なお、彼はこの後、このコンセプトをさらに引き締めラディカルにしたという『時の陽炎』(尺八、箏群と打楽器のための/1997)を書いているが、次回、尺八の項目で触れることにする。
さて、翌年の作品、演奏者吉村七重の名をタイトルとした『七重』(1988)が収録されている CD『七重』には、西村に杉浦康平を出会わせた友、佐藤聡明『神招琴』(1989)、湯浅譲二『内触覚的宇宙第3番 虚空』(1990)、南聡『彩色計画Ⅲ』(1989)、吉松隆『もゆらの五ッ』(1990)の作品が並ぶ。
佐藤、吉松が楽器の特性、情感・間など伝統を生かしたものであれば、西村はやはり己が世界に引っ張り込み、高低音域も自在に使用、トレモロ、ポルタメントそのほか彼の嗜好をぐいぐい押し出し、リズムパターン反復やたたみかけなどで盛り上げ、楽器の情感・余韻などに神妙に沿う気配はない。
一方、湯浅はすでに尺八2本での『対話五題』(1972)に引用の本曲『虚空』をここでも使用、彼らしい音響設計で聴かせる。「鈴木大拙師の説くコズミック・アンコンシャスネス<宇宙的無意識>への音楽的参加」(CD解説より)とのことで、改めて大拙の影響を思うものの、それが音響設計とどう繋がるのかは筆者には不明だが、印象的だ。
南作品は「響きの情感に委ねることを拒否」し「彩色計画」というタイトル通り、リズミックなミニマルアートを見るような軽快がある。
ほぼ同年代に作られたこれらの作品は、当時、作曲家が邦楽器の伝統にどう向かい合ったかが知れ、なかなか興味深い。
やはり二十絃と弦楽合奏のための『炎の幻声』は『七重』と同年だが、不気味な弦楽器低音に音滴がぽぽん、ぽぽんとしたたり落ち、細いグリッサンド上昇形が昆虫の羽音のように螺旋旋回を描き、下で低音が蠢く中、箏がビヨーンと入る。繊細でもあれば、美しくもあり、凄まじくもあり、のいわゆる西村ワールド全開で、やはり箏を「掻き鳴らす」という行為がもたらす音響の千変万化がそら恐ろしくもある。その背後での弦たちの動きも、迫り出したり、背景を埋めたりと自在。勘所に入る箏打撃音(打楽器的奏法)も心得たものだ。終盤に吉村のカデンツァが入り、最後は弦の静寂な持続音がクレッシェンド、箏の荒々しい上行アルペッジョが空に跳ね上がる。
解説によれば、炎は自宅近くの密教寺院で毎月見る、とあるから、目黒不動の護摩であろう。筆者もまたその炎に妖艶と悽愴を見たゆえ、実によくわかる。「時としてその炎に声のようなものを感ずることがある」(CD解説)。なお、弦楽合奏と箏の協奏は、「相違を保ったままの共存」が生む新たな緊張が描きだす心象の像で、むろんヘテロフォニーの手法をとった、とのこと。聴けば一聴瞭然である。
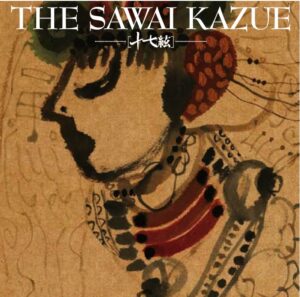 『覡(KAMUNAGI)』(1992)は、打楽器との協奏ゆえ、さらに強烈。韓国シャーマン一族が村々を巡って行う儀式「クツ」(人への悼み、豊漁・豊穣への祈りなど)の「世にもものすごい音楽」「そのリズムの多様さと心をえぐる音のうねり、“恨”をうちに秘めつつ、圧倒的なエネルギーを放ちつづけるその音楽は、私にとってほとんど麻薬でした。」(CD解説)と西村は語る。通底する韓国のリズム「クッコリ」は韓国音楽を血肉とするベーシスト齋藤徹に依頼しての録音となっているが、沢井一恵とのうねり具合はまさに麻薬だ。
『覡(KAMUNAGI)』(1992)は、打楽器との協奏ゆえ、さらに強烈。韓国シャーマン一族が村々を巡って行う儀式「クツ」(人への悼み、豊漁・豊穣への祈りなど)の「世にもものすごい音楽」「そのリズムの多様さと心をえぐる音のうねり、“恨”をうちに秘めつつ、圧倒的なエネルギーを放ちつづけるその音楽は、私にとってほとんど麻薬でした。」(CD解説)と西村は語る。通底する韓国のリズム「クッコリ」は韓国音楽を血肉とするベーシスト齋藤徹に依頼しての録音となっているが、沢井一恵とのうねり具合はまさに麻薬だ。
筆者は先般、喪礼にあり、多くの御門徒衆による読経中、唱えつつ足で拍子をとる人を数人見かけ、やはりラップだ、と、その声の集合念力のようなものを実感した。それは音波となって天空、あるいは彼岸へ届けという力の実体で、この『覡』はそれに満ち満ちている。日本情緒や侘び寂び観念とは全く異なるアジアのエネルギーの奔出を体感でき、海外での演奏に絶大な効果を発揮すると思われる作品。ちなみに覡とは神事、神楽、神おろしなどを行う人のこと。
以上、西村の現代箏曲作品群を見渡すなら、むろん『雅歌』シリーズにおけるヘテロフォニーの基本パターンの展開形であり、その分枝であることが知れる。さらに伝統を生かすというより、純粋音響としての響きへの鋭い嗅覚と、強い好奇に駆られる彼の生理情動をここでも見た気がする。とりわけ『時の虹彩』での冒険ぶりを、そういうこともあったのか、と新鮮に聴いたのは収穫であった。
また『炎の幻声』や『覡』に満ちる声や響きに、やはり「衆生の海」に浮沈する西村を思わずにいられない。
「一音成仏」というより「一即多」のわやわや衆生ヘテロ音響世界。
邦楽器の背後に響くご利益願いの素朴な信心の雑声混声を、西村は我がものと聴いたのではなかろうか。
他の邦楽器では、この他、18声と16の邦楽器のためのシアターピース『アワの歌』(1989)、『時の蜜』(独奏三弦のための/1990)、『巫幻楽』(1990)、『蛍』(篠笛独奏のための/1996)、『秘水変幻』(横笛と二十弦箏のための/2004)、『夢幻の光』(雅楽合奏のための/2004)、『邦楽合奏のためのヘテロフォニー』(2010)がある。
中ではとりわけ、横笛の赤尾三千子らの名を挙げることができよう。
いずれにせよ、西村の邦楽器への関心は、挑戦する演奏家と作曲家の協働の機運が高まる時期に重なっている。
次回は、尺八に触れたのち、国立劇場の木戸敏郎との出会いからの創作を見ることとする。
1.『音、沈黙とはかり合えるほどに』年譜他 武満徹著 新潮社 1971
2. 同上、p.191,192
3.『大字源』p.1336 角川書店 1992
4.『日本国語大辞典9』p.2 小学館 1981
5.『光の雅歌』p.96
6.同上p.100
7.『現代の日本音楽10 西村朗』春秋社 2003
参考資料)
◆CD
『TAQSIM』 カメラータ・トウキョウ 25 CM-258
『 NANAE/吉村七重』 カメラータ・トウキョウ 25CM-189
『炎の幻声/吉村七重』 カメラータ・トウキョウ CMCD-25026
『 THE SAWAI KAZUE 十七』『覡(KAMUNAGI)』 邦楽ジャーナル
『覡(KAMUNAGI) 菊地悌子・十七絃箏の世界』 カメラータ・トウキョウ 30CM-267
『魂の内なる存在/西村 朗 協奏曲集【西村 朗 作品集 7】』『樹海』 カメラータ・トウキョウ CMCD-28058
◆楽譜
『西村 朗:オーケストラと篳篥のための音楽「太陽の臍」』全音楽譜出版社 1990
『現代の日本音楽 西村朗』春秋社 2003
◆書籍
『音、沈黙とはかり合えるほどに』 武満徹 新潮社 1971
『日本戦後音楽史 下』平凡社 2007
『光の雅歌』西村朗+沼野雄司 春秋社 2005
『日本楽器法』CD付 三木稔 音楽之友社 1996
『大字源』角川書店 1992
『日本国語大辞典9』小学館 1981
◆Youtube
『Taqsim』
『七重』
『炎の幻声』
『覡』Nanae Yoshimura – Kamunagi (“Shaman”)
(2022/6/15)


