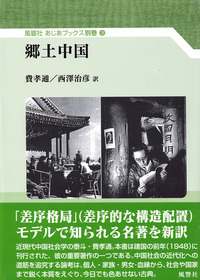漢語文献学夜話|Mencius escapes|橋本秀美
Mencius escapes
Text by 橋本秀美(Hidemi Hashimoto)
一
数年前から「忖度」という言葉をよく目にするが、中国語では現在殆ど使われていない。同様の場面で、中国語なら「揣摩(上意)」などと言われる。「忖度」が日本語として広く使われ始めたのは何時頃だろうか。出所は『詩経』に違いないが、『孟子』に引用されていることが、日本でこの言葉が普及する上で大きな意味を持ったのではないかと疑っている。
『孟子』は旧時代の封建思想の代表として近代以降否定されがちだったし、空疎な理屈を展開する学派の始祖のようなイメージも有って、少なくとも私個人はずっと敬遠してきた。しかし、現在の漢語世界の思想の背後には、宋元から近代に及ぶ儒家の思想が根強く影響を及ぼしているし、日本においても徳川時代から近代にかけて、『孟子』は必読教科書の一つだったから、自らの属する社会を理解する上でも、『孟子』はやはり無視する訳にはいかないと思うようになった。
二
実は、「君子は庖廚を遠ざける」という言葉がずっと気になっていた。昔は、男性が家事をしない口実として冗談で使われることも有ったが、『孟子』本来の文脈で言えば、牛や羊を屠殺するのは残虐で、見るに忍びないものであるから、貴族たるものはそういう場面からは距離を置く、という意味だ。気持ちは分かるが、これでは「豚は夜運べ」(by藤原新也)そのもので、レストランで肉料理は食うけれど畜育や屠殺の場面は想像もしたくない、では「臭い物に蓋」や「Not in My Backyard」と同じことだから、倫理的に問題だろう。だから、『孟子』の話も、後ろの方のどこかに何かこの話題を回収するオチが有るのではないかと思っていた。しかし、そんなものは無かった。むしろ、この「偽善的」自己矛盾こそが、『孟子』の思想の基調だった。
孔子の継承者を以て自任する孟子は、自己を中心とした人間関係の倫理を説く。この点は、前にも紹介した『郷土中国』で費孝通が『論語』と共に『孟子』を引用して説明していた。例えば、聖人天子である舜には、素行の悪い父親が居た。父親が仮に殺人の罪を犯したとしたら、舜はどうしただろうか?という仮定の問いに、孟子は、天子の地位を捨てて、父を連れて法治の及ばない辺境に逃げて暮らしただろう、と答える。父親である以上、特別扱いして大事にしない訳にはいかないからだ。似たような話は沢山有り、どのように行動すべきかは、自分と相手との遠近関係によって変わってくる。同室で喧嘩が有れば、直ぐに仲裁に入るべきだが、隣村の喧嘩であれば、戸締りをして構わないでおく。他国の賊に襲われた際、曽子は弟子たちを連れて逃げ、子思は逃げずに止まったが、それは立場が違うからで、逆の立場なら二人ともそれぞれ逆のことをした、等々。
結局の所、家族を中心とする人間の自然な感情を基本として、現実社会の秩序を穏健に護っていこうという考えだから、論理的類推による極端な議論は拒否する。例えば、自ら生産したのではないものを所有するのは盗みに等しい、と言って君主が民衆から搾り取った税から報酬を貰うことを潔しとしないような議論は否定する。そして、孟子の倫理基準は常に現実的に揺れ動く。極端はいけないが、中道主義に固執するのも誤りで、そこは柔軟でなければならない。
客観的規範が無いということから推測できるとおり、これは明らかに「恥の文化」であって、『孟子』には「人として羞恥心が無いというのは駄目」「恥というのは人にとっては重大事」といった言葉が有る。後世「四端」として有名な言い方の一つは、「羞悪の心は義の端である」で、何が正しいのかは、論理的に考えるのではなく、悪を恥じることを通して知っていく。周りを見て、文化伝統を学ぶことを通して、社会人としての倫理を身に付けていく。同調が必須とされている。
三
こうして見ると、『菊と刀』で日本について論じられたことと重なる部分が多い。残念ながら、『菊と刀』の作者は中国文化については研究していなかったので、その中で試みられた日中文化の比較は殆ど失敗している。一方、『郷土中国』の作者費孝通は、近代中国学者の例に漏れず、中国以外の社会・文化に根本的関心を寄せることが無かったから、日本との比較は一切していない。日本・中国の社会文化論として最も影響力の大きいこの二著において日中の比較が空白だったことは、我々に宿題が与えられたようなものだ。
さて、最近改めて『孟子』を通読して、最も印象深かったのは、その元気の良さ、精神的な自立と健康さだ。上の紹介からも分かるように、孟子は人間の矛盾を丸ごと受け容れ、伝統文化の秩序維持を主張し、遠近感の有る自然な人間関係を強調した。そして、権力者に対しても自らの尊厳を貫き、媚びおもねるような所が全く無い。あっけらかんとして羨ましいほどで、こういう人なら鬱病になったりする心配は全く無いと思われる。こんな能天気な人がよくやっていけたなあ、とさえ思われるが、当時の条件は後世とは大きく違う。孔子の生きた春秋時代から孟子の生きた戦国時代まで、建前上は周王朝の下に多くの諸侯国が並存する本来の意味の「封建」体制が続いていた。諸侯の同族大臣(卿)は、君主に大過有れば諫言を行い、繰り返し諫言しても容れられなければ君主を交代させるべきだが、同族ではない大臣の場合、繰り返し諫言して受け容れられない場合、その国を離れて別の国に行く、という説明が『孟子』に有る。君主と意見が合わなければ、別の国に行く、というのは、『儀礼』『礼記』にも見られる。実際、孔子も孟子も、諸国を浪々している。これは、ある意味で彼らの精神の独立性を護る上で必要な逃げ道であったと思う。自分の意見を殺す必要はない。それどころか、自分の意見を曲げるような人間に、他人を正しく導くことなど出来ない、というのが『孟子』の主張だ。
秦漢と統一帝国が続き、唐代中期以降は科挙合格が立身出世の唯一の道となる。科挙は、全国統一の試験であり、最終的には皇帝の裁可を得なければならない。こうなると、もう逃げ場は無い。中央朝廷の政策には嫌でも従わざるを得ない。諫言が受け容れられないからといって、他に行ける国は無い。皇帝と朝廷の権威に挑戦することは、全く不可能となった。興味深いことに、正にそのような逃げ道の無い時代に、『孟子』が経典として重要視されるようになった。それは何故か?
積極的な面を見るなら、集権体制であるからこそ、官僚士大夫が精神の独立性を失わない為の栄養剤が必要だった、ということかもしれない。そうでなければ、朝廷は体制翼賛のイエスマンばかりとなり、政治は破綻してしまう。宋代以降の実際の政治は、皇帝・朝廷の絶対権威の下、文人官僚が派閥闘争を繰り広げる形で政策の調整が行われた。消極的な面を見るなら、宋代以降の知識人は、『孟子』の精神を良く身に付け、建前と現実の矛盾を当然のこととして受け容れるようになっていたとも言えよう。逃げる外国を失った彼らは、心の中に逃げ道を作ったのだ。
四
『孟子』には、皇帝・朝廷の絶対的権威と相容れない内容も有る。例えば、「君主が臣下を自分の手足のように扱うなら、臣下は君主を自分の心臓のように大事に思うだろう。君主が臣下を犬や馬のように扱うなら、臣下は君主を一般国民と同様にしか思わないだろう。君主が臣下をゴミのように扱うなら、臣下は君主を敵のように思うだろう。」極く自然な心理であるが、臣下の無条件絶対服従を当然と考える明の太祖はこうした内容に不満で、気に入らない内容を削除した修訂版『孟子』を作り、科挙出題範囲をそれに限った。しかし、このような過剰な反応は一時的なもので、『孟子』は直ぐに復権を遂げている。気骨の有る知識人が『孟子』の独立精神を護った、という評価がされがちであるが、大半の知識人にとって『孟子』の建前と絶対服従の現実との間の矛盾はとっくに織り込み済みだった、と見る方が私には自然に思われる。乞食から皇帝に成り上がった明の太祖は、知識人の伝統的智慧を甘く見すぎて、取り越し苦労をした、という所だろう。
『郷土中国』で費孝通は、伝統が権威であるような中国社会において、偽善は不可避だ、と論じていた。伝統的家庭においてよく見られる光景は、誰もが家長である年寄りの意見に表面的に従いながら、実際にはその意見とは異なる処理をするというものだ。家長は絶対に尊重されなければならないが、現実問題には現実的対応が必要とされるからだ。そういう伝統的智慧の流れの中に、阿Qの精神勝利法も位置するが、その源流に位置するのが『孟子』だとは言えないだろうか。
五
現在の私の感想として、『孟子』の最大の問題は、個人対個人の関係だけで社会問題を考え、目に見えない矛盾を簡単に無視してしまうこと。もう一つ別のレベルで最大の問題は、漢文化中心主義で、漢文化以外の世界を無視してしまうことだ。逆に魅力は、その精神の健全さだ。『礼記』に、殺人にも礼が有る、という話が有る。戦争なんだから、どうせ殺すんだから、何をやっても一緒だろう、とケツを捲るのではなく、人を殺すことに恐れや悲しみを持つ気持ちを大事にすることを説く。それは、偽善ではなくて、矛盾の中で人間性を護る方法なのだと思う。肉を食うなら屠殺に平気になれ、そうでないなら肉食を止めろ、というのは確かに論理的だが、肉を食っても屠殺される牛羊を可哀そうと思う気持ちは大事にしたい。そういう気持ちを割り切ってあきらめてしまうことを、孟子は「自暴自棄」だと言った。これまた、日本語として馴染み深い言葉である。
(2020/11/15)
ーーーーーーーーー
橋本秀美(Hidemi Hashimoto)
1966年福島県生まれ。東京大学中国哲学専攻卒、北京大学古典文献専攻博士。東京大学東洋文化研究所助教授、北京大学歴史学系副教授、教授を経て、現在青山学院大学国際政治経済学部教授。著書は『学術史読書記』『文献学読書記』(三聯書店)、編書は『影印越刊八行本礼記正義』(北京大出版社)、訳書は『正史宋元版之研究』(中華書局)など。