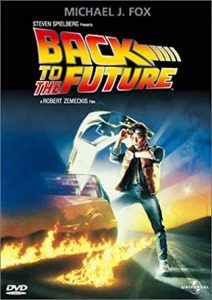小人閑居為不善日記|懐かしい「コロナショック後の時代」へ――《エンドゲーム》とマノエル・デ・オリヴェイラの旅|noirse
懐かしい「コロナショック後の時代」へ――《エンドゲーム》とマノエル・デ・オリヴェイラの旅
Cinema in the Pandemic――Endgame and Manoel de Oliveira
Text by noirse
※《アベンジャーズ/エンドゲーム》、《アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー》の結末に触れている箇所があります
1
COVID-19は社会に影響を与え続けている。ソーシャル・ディスタンスひとつ取っても、経済活動から日常生活まで、大きな変化をもたらした。
当面、この状況は続くだろう。ワクチン開発には通常1,2年はかかるという。それまでは他人との接触に慎重さが求められる以上、気軽なコミュニケーションでさえ憚られることになる。またウイルスは変容するものだから、ワクチンを打てば安心というものでもない。毎年インフルエンザが流行るように、これから何年ものあいだ、冬になる度にソーシャル・ディスタンス要請なりロックダウンなりが繰り返されることも考え得る。もう二度と、コロナショック以前の世界に戻ることはできないかもしれない(杞憂であってほしいが)。
本稿では主に新作映画を取り上げていたが、映画館の営業が再開されるまで、「パンデミック下で映画を見る」というコンセプトでコロナショック以降の視点から過去の映画作品を見直している。わたしが住む東京でもようやく映画館が再開し始めたが、少なくとも今回までは同じ路線を続けていきたい。
2
「世界の関節は外れてしまった」。おなじみ《ハムレット》の一節だ。パンデミックが巻き起こってから、真っ先に思い出した言葉がこれだった。そして同時に連想した映画が《アベンジャーズ/エンドゲーム》(2019)だった。
《アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー》(2018)で人類が世界の半分の命を失ってから5年後。人類は未だ悲嘆に暮れ、主人公のひとりトニー・スターク(アイアンマン)も、息子のように思っていたピーター・パーカー(スパイダーマン)を救えなかったことに苦しんでいる。
しかし転機が訪れる。アベンジャーズはタイムトラベルに成功し、過去を遡って失った命を取り戻す。けれど甦った人々の時間は当時から止まったままで、人類半分のあいだに5年という「距離」が立ちはだかる。その後の《スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム》(2019)を見ると、5年間の空白が社会に大きな影響を与えていることが分かる。どれだけ努力しても、その距離を完全に埋めることはできないだろう。
ところで今回はタイムトラベルに注目してみたい。通称「タイム作戦」会議中、ヒーローたちは《ターミネーター》(1984)や《スタートレック》、《ある日どこかで》(1980)や《ビルとテッドの大冒険》(1989)、そして《バック・トゥ・ザ・フューチャー》(1985)などのタイムトラベル映画を例挙していく。
さて、これらの映画には、タイムトラベル・テーマという以外にも共通点がある。どれも80年代の作品なのだ(《スタートレック》はドラマ《新スタートレック》のエピソード〈永遠への旅〉を指すらしく、これのみ1994年)。
《レディ・プレイヤー1》(2018)、《バンブルビー》(2018)、《ワンダーウーマン1984》(2020年公開予定)、Netflixのドラマ《ストレンジャー・シングス 未知の世界》(2016-)などなど、最近のハリウッド映画は空前の80年代ブームにある。マーベルも例外ではなく、《ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー》(2014)や《スパイダーマン:ホームカミング》(2017)などは80’s文化への目配せが色濃い。
今のハリウッドを支える第一線のクリエーターが、みな80年代に青春を過ごした世代になったということだろう。とはいえ「過去に戻って犠牲者を救いたい」という物語が、80年代の作品群に紐付いているのは示唆的だ。というのは、《エンドゲーム》は何重にも渡って過去への憧憬が織り込まれている作品だからだ。
タイム作戦でトニー・スタークは70年代に戻り、若き日の父親と接触する。アベンジャーズ・シリーズはトニーの成長物語にもなっており、この邂逅は迷いの多かったトニーの「決意」の後押しになる。スティーブ・ロジャース(キャプテン・アメリカ)も、失った恋人ペギーが生きていた1940年代に戻っていく。
少し範囲を拡大してもいいなら《キャプテン・マーベル》(2019)は90年代オマージュだったし、トニーと宿敵サノスが引退後に農場に落ち着き家族を思って過ごす姿は、西部劇以前まで遡る、古典的なアメリカン・ライフのイメージだ(昨年、本稿で《エンドゲーム》を取り上げた際に言及した)。つまり《エンドゲーム》は、どういった世代が見てもどこかしらノスタルジックな感情を喚起するように作られているのである。
そもそも戦前からの歴史を持つマーベル作品の映画化という企画自体が回顧的だ。過去に読んで感動した作品がスクリーン上で甦るとあらば、ファンが「あの時代」を求めてくることは明らかだ。
《エンドゲーム》のタイムトラベルはただストーリー上の出来事ではなく、作品自体が「過去に戻りたい」という思いで構成されている。批評家の石岡良治は《BTTF》を論じ、このように述べている(《視覚文化「超」講義》)。
過去に魅力があって、現在は汚染されているという認識は一面的ではないか。私にはそれは「マイルドなトラウマ的状況」に見えるのです。
人類はその半分を失い、悲嘆に暮れている。悲しみを癒すため、アベンジャーズは過去を遡る。その結果、犠牲者たちはあの時の姿のまま甦り、トニーやスティーブまでもが人生を取り戻す。《エンドゲーム》とは、「トラウマを克服するためにノスタルジーで治療する」という映画なのだ。
3
《エンドゲーム》はノスタルジーを肯定する、保守的な価値観に支えられた映画だ。とはいえ、それ自体は悪いことはない。
世界の関節を元通りに戻すことはできない。映画と違い、(当たり前の話だが)過去に還ることはできない。しかし過去の世界を諦め、完全に頭を切り換えられるものでもない。人はそう簡単に生活や習慣を変えることはできない。
一旦政治思想から離れて保守という言葉に立ち戻ってみよう。今までの生活習慣や伝統を変えたくないという考えはありふれたものだ。この先ずっとソーシャル・ディスタンスを続けなければいけないと言われて、不満ひとつない人がいるだろうか。どんなにリベラルな政治信条を持つ者でも、たとえ過激派でさえも、ここだけは譲れないという一線はあるはずだ。
けれども世の中はうつろいゆくものだ。いつまでも同じ生活が続くとは限らない。ではわたしたちは、ピーターやペギーを失ったトニーやスティーブのように、喪失感を抱えながらCOVID-19が駆逐されるのを待つしかないのだろうか。
4
最後にポルトガル映画《世界の始まりへの旅》(1997)を紹介しよう。一種のロードムービーなのだが、テーマはノスタルジーについてで、俳優たちが郷愁について意見を交わしていく独特の作品だ。
サウダージ(Saudade)という言葉をご存じだろう。日本で近い意味を持つのは郷愁だが、憧憬のようなニュアンスもあり、完全に合致する言葉はない。かつて行ったことのない土地から感じる郷愁。逆に、実際に幼少期を過ごした地に立ち戻っても得られない何か。この作品はそうした言葉にしがたい感情に、ゆっくりと輪郭線を与えていく。
監督は巨匠、マノエル・デ・オリヴェイラ。2015年に105歳で亡くなるまで、1,2年に1本というハイペースで新作を発表し続け、どれも高く評価された驚異的な人物だ。傑作・怪作揃いの中で《世界の始まりへの旅》はあまり言及されないようだが、個人的にはこの作品が最も忘れがたい。ちなみにマルチェロ・マストロヤンニの遺作でもある。
映画監督のマノエルは幼少期に過ごした町を辿る旅に出る。フランス人俳優のアフォンソも同行するが、初めて目にするポルトガルの田舎の風景に郷愁を感じていく。死んだ父親が生まれた地域だったのだ。
マノエル一行は、アフォンソの伯母マリアが住む土地に辿り着く。その地は経済的発展から見放され、荒廃しつつある。マリアは夫に「わたしたちがいなくなったあと、誰がこの土地を耕しに来るのか」と尋ねる。夫は「世界の始まりに戻るんだ」と答える。アフォンソは必ずこの地に戻ることを約束し、立ち去っていく。
虚しさを覚えずにはいられない光景だ。オリヴェイラは当時89歳。これを年配者特有の達観だとか、ニヒリズムと受け取るのはたやすい。たしかにこの土地には、いずれは誰もいなくなるのだろう。
だがアフォンソの記憶には残っていくし、またいつか、そこから何かが始まっていくかもしれない。この映画は、すべてが無に帰す虚しさを嘆いているだけではない。「世界が常に始まり続けていること」を説いているのだ。
わたしたちの現在は、必ず誰かの過去になる。幼い子供は、ソーシャル・ディスタンスを自然な習慣と受け取り、馴染んでいくかもしれない。そのとき彼らが見る光景は、わたしたちとは異なるものだろう。それは新しい世界の始まりなのだ。
コロナショック以降にも、新しく誕生していく何かが必ずある。しかしコロナショック以降の世界を戻すべきものとしてのみ捉えてばかりでは、新しく誕生したものを見逃し、排除してしまいかねない。
もちろん過去に戻りたいと思うこと自体を否定するわけではない。けれど同時に、既にひとつの世界が終わりを迎えたことを少しずつでも受け入れ、新しい世界の誕生を肯定することもできるのではないだろうか。そうすれば、もしかしたらわたしたちにも、 コロナショック以降の世界を懐かしく思える日が来るかもしれないではないか。
—————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中