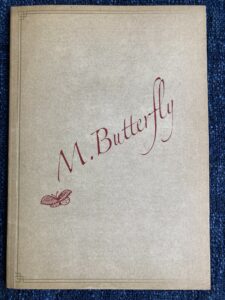梅田芸術劇場「M. バタフライ」|田中 里奈
 梅田芸術劇場「M. バタフライ」
梅田芸術劇場「M. バタフライ」
Umeda Arts Theater, M. Butterfly
梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、2022年7月13日~15日
(鑑賞回:2022年7月13日 18:00)
2022/7/13, Umeda Arts Theater, Drama City, Osaka
Reviewed by 田中 里奈 (Rina Tanaka)
原作:デイヴィット・ヘンリー・ファン
翻訳:吉田美枝
演出:日澤雄介(劇団チョコレートケーキ)
美術:山本貴愛
衣装:前田文子
照明:松本大介
音響:角張正雄
ヘアメイク:宮内宏明
京劇指導:張春祥
所作指導:飛鳥左近
ステージング:当銀大輔
演出助手:長町多寿子
ドラマトゥルク:下平慶祐
舞台監督:藤崎遊
出演:
ルネ・ガリマール/ピンカートン:内野聖陽
ソン・リリン:岡本圭人
ヘルガ:朝海ひかる
チン同志/スズキ/シュー=ファン/外交官:占部房子
女ルネ/ピンナップガール/パーティの女/外交官:藤谷理子
トゥーロン/裁判官/パーティの男/外交官:三上市朗
マルク/シャープレス/パーティの男/外交官:みのすけ
アンサンブルダンサー:南部快斗、新井健太
—
デイヴィット・ヘンリー・ファンによる1988年の戯曲『M. Butterfly』を基にした舞台である。1988年にワシントンDCで初演され、トニー賞を受賞した。日本初演は1989年の劇団四季版(演出:ジョン・デクスター)で、今回の梅田芸術劇場によるバージョンが、実に33年ぶりの再演となる。1993年には、デイヴィッド・クローネンバーグ監督による映画版『エム・バタフライ』(英題は戯曲に同じ)が制作され、当時話題を呼んだので、映画から同作を知った人も少なからずいるのではないかと思う。
あらすじは次の通りだ。1980年代フランス・パリの刑務所に、国家機密情報を漏洩した罪でフランス人外交官のルネ・ガリマール(内野聖陽)が投獄されている。彼が、観客に向かって自らの謎めいた過去を語り始めると、舞台は1960年代の中国・北京にさかのぼる。文化大革命前夜、中国駐在フランス大使館に赴任してきたガリマールは、とあるパーティでオペラ『蝶々夫人』で主役を演じた京劇役者のソン・リリン(岡本圭人)と関係を深め、妻を持つ身でありながらソンと恋仲になる。実は、ソンは中国共産党のスパイで、なおかつ男性であったが、彼はガリマールとの20年にわたる関係(二人は同棲どころか、のちに結婚して一児をもうけている)において完璧な女性を演じることで、ガリマールから機密情報を得ていたのである。ソンの真実を知り、投獄されてもなお、幻想を追い続けてきたガリマールは、ついに独房内で自殺を図る。
一見、荒唐無稽に思える物語だが、なんと実話に着想を得ている。京劇俳優の時佩璞が、性別を女性と偽ってフランス人外交官ベルナール・ブルシコと婚姻関係を結び、1964~83年の間、外交機密を入手していたという事件である。戯曲化にあたって実在の人物名は変更されたが、ブルシコが明らかな証拠を見るまで、時のことを男性だと認めなかったのは史実通りである(ファン氏曰く、ブルシコが刑務所で自殺を図り、失敗した出来事を彼が知ったのは、戯曲の結末を書いたあとだった1。なお本稿では、劇作家ファンを愛好家を指す「ファン」と区別するため、前者に「氏」を付けて記載する)。
戯曲版『M. Butterfly』(1988)
戯曲では、オペラ『蝶々夫人』がたびたび引用され、この作品に対してさまざまな意味で大きな影響を及ぼしている。ただし、『M. Butterfly』がハニートラップ的なゴシップを悲恋風に描き出そうとしているのかと問われれば、まったくその逆である。そうではなく、この戯曲でかの有名なオペラを借用して試みられたのは、オリエンタリズムとジェンダー・ステレオタイプの問題をいっそう批判的に問い直すことだ――マダム・バタフライのイメージに象徴された、ある特定の属性に対する荒唐無稽な幻想を、未だに私たちは他者に(あるいは自分自身に)押しつけてはいないだろうか。
ファン氏の作品に通底したアジア系アメリカ人のアイデンティティをめぐるテーマ性に鑑みれば、『M. Butterfly』を、アメリカ合衆国という特有の社会におけるステレオタイプへの「批判的模倣(critical mimesis)」だとみなす視点はもちろん重要だ2。社会の鑑としての同作の役割は、2017年のブロードウェイ・リバイバル版では、「初演時と比べて、ジェンダーの流動性(gender fluidity)に関する私たちの考え方は大きく変化した」ことを受けて台本を抜本的に改訂したことからもわかる(なお、今回の日本公演は1988年初演版台本を底本としている)3。だが一方で、1988年に出版された戯曲の末尾に、ブロードウェイ以外の都市で上演されることを念頭に置いた注意書きが付され、「初演後にこの作品を上演する人は、比較的自由に、自分たちの解釈を追っていい」と、ファン氏が書き添えていることも重要だ。つまり、各地の異なる文脈の中で作品が新たに解釈されることで、「作品の意味をより明らかにするアプローチが出てくる」可能性も失われていない4。ただし、この戯曲の内容が国際レベルの政治的な権力構造の歴史と必然的にかかわる以上、上演される場所や観客にかかわらず、オリエンタリズムとジェンダーの問題を無視することはできないだろう。
梅田芸術劇場版:ガリマール中心の心理劇
日澤雄介の演出は、戯曲に書かれた内容を手堅く呈示していた。登場人物同士の関係の推移、または舞台上の登場人物と客席にいる観客との関係を強調した演出は、複数の山台を組み合わせて、段差とシンプルな橋状のスペースから成るミニマルな舞台美術(山本貴愛)と調和していた。『M. バタフライ』は、いっそ徹底したエキゾチシズムのもとでスペクタクル化する方法もあったと思うが(初演版の舞台美術を石岡瑛子が担当したというのは象徴的だ)、今回のような心理劇風の形式にしたのも頷ける。反面、戯曲通りに上演することで、日本という場から連想される文脈、例えば、『蝶々夫人』から続くジャポニスムの系譜や、日本の〈西洋としての自己意識〉――帝国主義以来、この国が欧米諸国の中で自明的に取り続けてきた姿勢――への応答は回避されていたように思う。
関係に焦点を当てたことで、9名の出演者たちの役割はいっそう重くなった。主要な3名の役とダンサーを除いて、4名の俳優が複数の役を兼任していたが、いずれも漏れなく機能していた。各キャラクターのステレオタイプ的な表象が、場面の進展につれて異化的に働いている点にも注目される。
なかでも、ガリマール役の内野聖陽は芝居がかった演技の塩梅が絶妙であった。彼の演じるガリマールが、開幕冒頭から時代遅れな恋愛観やら東西観やらを、時代がかった吟遊詩人風に語り出した時点で、観客としては違和感を持たざるをえない。そこに、場面の合間に時折入るメタ会話がさりげなく蓄積されていくことで、観客は上演がほぼガリマールによる一人称の回想――妄想と言った方が近いかもしれない――であることを徐々に理解するのである。
心理劇にしたことで、どうしても焦点がガリマールに行きがちになってしまうのだが、岡本圭人は技術的にも演技的にも難役のソンをきちんと制御して演じていた。ソン役にはオペラと京劇を演じる場面があり、さらに、着物を身につけて登場する場面が複数ある。舞台上で女性を演じることに関しては、ガリマールの言うような「完璧な女性」に本当に見えるかどうかが重要なのではなく、自己願望を他者に投影し続けるガリマール中心のドラマを違和感なく進行させ、後述する第2幕後半の場面にどうつなげていくかがポイントだろう。その点で、岡本のソンは十二分に役目を果たしていた。
着替えと全裸――第2幕の2つの場面をめぐって
さて、『M. バタフライ』における異性装は、「イケメン俳優の女装」という広告的なイメージだけでなく、作中に登場するさまざまなジェンダー・ステレオタイプを転覆する意味でも用いられていた。なかでも、第2幕でのソンによる2度の暴露――舞台上で女装から男装へと着替える場面と、ガリマールの面前で全裸になる場面――は、皮肉を解する観客にとって、視覚的な面白さ以上の意味を持ち得ただろう。だが、筆者の居合わせた梅田芸術劇場での公演ではまったく機能しておらず、それどころか、梅田芸術劇場に集った少なからぬ数の観客が、岡本圭人が服を脱いだりペニスを晒したりする度にいちいち大げさに驚き、後者では笑い声すらあげていた。
観客の反応は自由でもちろん構わない。観客の反応をコントロールすることは不可能だし、言うまでもなく、そのようにすべきでもない。だが、〈観客に期待される反応〉というテーマとは全く別個に、『M. バタフライ』で筆者が出くわした観客の反応は非常に危ういものだったと、筆者は判断した。
まず、作中における2つの場面の役割について確認しよう。前者の着替えの場面で、まずソンは、役としての演技をいったん中断し、場面の進行を拒むガリマールを制止する(「話を進めなきゃならないし、私は着替えないと。」5)。次に、観客に対して、着替えに5分ほどかかる旨をあらかじめ前置きして、舞台上で着替えを始めるのである。全編を通してガリマールによって力説されていた、〈美しくけなげな理想の東洋人女性〉という意匠を、舞台上でソンは文字通り脱ぎ捨てて、アルマーニの男性用スーツに着替えるのだ。
ソンが行為遂行的にジェンダー規範を演じていることは、これまでにも台詞の中でたびたび言及されるものの(例えば、京劇における異性装について、ソンは「女がどう振舞うべきかを知っているのは男だけ」6と述べている)、この場面では、彼が女を演じていたから女性らしく見えていたのだということが、着替えという行為を通じて、観客に明示される。演技の中断により、観客はガリマールの一人称視点の物語に没入することを中断せざるを得なくなる。それと同時に、ソンによってこれまで演じられてきた〈美しくけなげな理想の東洋人女性〉のイメージが、東洋人に本質的に備わったものではなく、そのように演じられることによって生み出されてきた構造にも気付かされるのである。
後者の、ソンが裸になる場面はこの作品のクライマックスである。法廷でソンに事実を暴露されてもなお、ソンを男だと頑なに認めたがらないガリマールに向かって、ソンはその場で全裸になってペニスを見せる(今回の公演では、岡本は観客に背を向けて下着を脱ぎ捨てた)。ガリマールはそれを見て笑い出し、次のように言うのだ。「やっと幻想と現実の区別ができるようになった[…] 私が取るのは、幻想だ」7。
全裸になった後、アルマーニのスーツを「ポン引きみたいな服」8とガリマールに揶揄され、舞台上から退場させられるソンは、もはや悲劇的な道化の様相を呈している。ここで特筆すべきは、本当の自分を見てほしいとガリマールに迫るソンもまた、ガリマールによって追い詰められているということだ。20年以上連れ添ってもなお(それがスパイ業務の一環だとはいえ)、連れ合いに決して正面から向き合ってもらえず、それどころか、自分に投影されていた勝手なイメージへの愛を、連れ合いから滔々と語られることが、虚しくなければなんであろうか。
作中で繰り返し語られる、〈本質的に男性的な西洋〉が〈同じく本質的に女性的な東洋〉を正当に支配してきたとする歴史的認識は、前述したソンによる着替えの場面で暴露され中断された。これに対し、ストリップの場面では、ガリマールがバイアスのかかった認識をなぜそこまで強固に続けられたのかが、劇的かつシニカルに示される。ガリマールに必要なのは自分の理想を投影できる相手であって、目の前の人間が誰であろうが何であろうが関係ない。それは、物語の展開にはお構いなしに、目の前の俳優が脱げば自然と声を上げる観客の姿に似ている。
無化される異化
舞台上で追い詰められていくガリマールとソンを見ているのは、決して快いことではない。彼らをめぐる関係はどこかできっと見たことのあるものだからだ。『M. バタフライ』は観客それぞれが自分のバイアスに違和感を持つことを誘発するポテンシャルを持った作品だ。だが、作品がそのように機能するためには、観客のチューンアップも必要である。この関連で確認したいのは、訳者の吉田美枝がブロードウェイ公演を振り返って、次のように述べていることだ。
歌舞伎の女形を見なれた私には、ソン役のB・D・ウォンは演技力は別として、決して「美しい」とは 思えなかったのだが、アメリカ人の友人たちは異口同音に、「美しかった」、「東洋的な繊細さがあった」と言う。私はこれこそ、そう見たかったからそう見えたという「ガリマール症候群」ではないかと思った9。
見たいものだけを見たいように見続ける限り、ソンはいつまでも美しくけなげな「バタフライ」の幻想を被せられたままだろう。私たちが支配と被支配の関係にあまりにも慣れ親しみすぎて、この公演で語られる内容を、どこか遠くの、自分とは無関係の話だと感じてしまえば、異化の仕掛けが無化してしまう。そうなれば、20世紀におけるオリエンタリズムの問題から一歩進んで、交差するバイアスの問題にたどり着くこともないだろう10。これを「愛の話」(日澤、公演プログラムより引用)と締めくくるのは、いささか自慰的に過ぎてぞっとしない。
(2022/8/15)
—
1 David Henry Hwang, M. Buttefly, Broadway Revival Edition with an Introduction by the Playwright, New York: Plume Books, 2017, vi.
2 Karen Shimakawa, National Abjection: The Asian American Body Onstage, Durham: Duke UP, 2002, 121. なお、2005年までの『M. Butterfly』に関する研究は、原恵理子の『音楽とアイデンティティ : D・H・HwangのM.Butterflyにみる文化のポリティクス』(『東京家政大学博物館紀要』、第10巻、2005年、75-88)に詳しい。
3 Hwang, M. Butterfly, 2017, vi.
4 David Henry Hwang, M. Butterfly, New York: Dramatists Play Service Inc., 1988(引用は訳書『M・バタフライ』吉田美枝訳、劇書房、1989年、140頁).
5 『M・バタフライ』吉田美枝訳、劇書房、1989年、113頁。なお、実際の上演に使われた台本と完全に同じではない。
6 同上、92頁。
7 同上、129頁。
8 同上、129頁。
9 同上、150頁。
10 ソンが東洋人女性という二重に被支配的なイメージを逆手に取って中国大革命直前の時代を生き抜き、革命が始まれば、同性愛者の売国奴として同胞からのリンチを受ける過程での、交差した(intersectional)権力との関係や、ガリマールが異性との性体験を語る際、明らかにみられる幻滅や強い抑圧の暗示するものについては、今回の公演では受け手を失って投げっぱなしになってしまった感があった。