評論|西村朗 考・覚書(34)「あちら」と「こちら」―音の原人たる西村朗|丘山万里子
西村朗 考・覚書(34)「あちら」と「こちら」―音の原人たる西村朗
Notes on Akira Nishimura (34) “There” & “Here”
Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)
ハンブルク公演と草津公演と、どちらがどう、という比較も判断も難しい。
音、声、動作の三位一体、あるいは身口意は、それぞれに完成度が高く、固有の美的世界を表出している(ハンブルクを多弁に過ぎるとか、草津を途中で飽きるとか述べてはいるが、いずれもビデオ視聴レベルの話)。
ただハンブルクでは音、声、動きが非常にクリアで、全てのライン(動線)が明確に交錯し、オペラの全体像が鮮明なドラマとして立ち上がってくる。同時に、それらは全て弾力を持ち時空間に放物線を描く(エネルギーの放出における様相といったら良いか)。
一方、草津ではそれらがどこか揺らぎ、揺蕩い、ぼかし、滲み、かすれ、といったいわば存在の境界線、輪郭を消すような働きによって、このオペラのじっとり重く粘っこい地下帯流のようなものを感触させる。
つまり、ドラマトゥルギーの相違により見える世界が異なるわけで、西村はその両方を可能にする器としてのオペラを書くことに成功していると筆者は思う。
もう一つ指摘しておきたいのはピッコロの扱いで、このオペラに内在する情動の「肉声」たるピッコロの音質(音霊)を、いずれの公演もピシリと射当てていることには感服であった。『太陽の臍』の篳篥ソロをはじめ、西村は協奏曲でのソロを管楽器とすることが多いが、彼の内なる声の生理が自ずとそれを選ばせるのではないか。
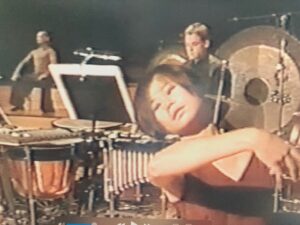

振り返るなら、『太陽の臍』(1989)『チェロ協奏曲』『永遠なる混沌の光の中へ』(1990)『二重協奏曲“光の環”』(1991/ヴァイオリン、ピアノとオーケストラのための)の4連作を西村は「アジア的宇宙観、生死観等に影響を受けての、生命連鎖の永遠性、人間の生と死と魂の再生といった観念的なドラマ」と言ったが、その観念的イメージを実体化する過程が、続く3連作『星曼荼羅』『アストラル協奏曲“光の鏡”』(オンドマルトノ/いずれも1992)『光のマントラ』(1993)に示され、「人間の内宇宙の一つの響きのマンダラ」の希求と設営となって立ち現れた。そこに筆者は「“宗教儀礼”としての総合形を希求する“汎アジア的宗教音楽家”たる西村朗の姿」を見た。(第30回『光のマントラ』)
神々の召喚と人々の祈願の「場」の造営行為そのものが「マンダラ」という宗教儀礼(所作・行為・行法)であれば、『絵師』もまたその響きのマンダラの実体化の延長線上にあり、そのオペラ化であったと言うこともできよう。
いや、そもそも人間の作劇それ自体が、原始の儀礼から発したもので、オペラの原型もまた古今東西、音、声、行為の三位一体、身口意の儀礼なのである。
そうして『絵師』のテーマが他ならぬ「地獄」と「人間の宿業」であれば、そこに個我と宇宙の合一、あるいは大日如来と自分が合一する即身成仏・梵我一如の行法を重ねることは、さほど突飛でもあるまい(『紫苑物語』第2幕第6場の「行・行・行」の連呼を想起したい)。
何より草津の能版で筆者がキモと指摘した2点、愛娘の凄惨な死を眼前に見据えての絵師という良秀の「宿業」の発動、「虚無地獄の創出」(と言うべきだろう)には、それがありありと示されていたと思う。
このオペラは西村の「マンダラ」そのものなのだ、ともう一度言っておく。
『太陽の臍』から『光のマントラ』までの7作を「光」のステージとすれば1)、1994年、訪れたインド、ベナレスの日没と日昇に見た生死の実相は、観念的宇宙世界の「光」から、生きとし生けるものに必ず訪れる死、冥界すなわち「闇」のステージへと彼を導く。狭間たる「黄昏」はピアノ独奏『三つの幻影』(1994)、管弦楽『黄昏の幻影』(1995)、室内楽『黄昏』(1995/ソプラノ、トランペットとオルガンのための)に描かれる。黄昏を古来、逢魔の時と呼ぶのは実に示唆に富もう。寂光院からの帰路、古知谷阿弥陀寺への道を「冥界への道」と感触した17歳の西村の直感は、こうして光から黄昏へ、そして管弦楽『流れ〜闇の訪れた後に』『蓮華化生』(いずれも1997年)の「闇」へと彼を曳き込んでゆく。
ついでに言うが、筆者はこの古知谷阿弥陀寺が何であるかをさして気にせずにいたが、今回、ふと気になって調べたところ、大原のこの寺(西村は堂と表記しており、それに準じたが本稿より寺とする)は慶長14年(1609)、弾誓上人の開基による如法念佛の道場とのこと。上人は尾張国海辺村に生まれ9歳で出家、修行を重ねこの古知谷で開山、4年後に即身成仏(入定1年前に掘らせた巌窟に、石龕に生きながら入り成仏する)となった。筆者は新潟にほど近い村上温泉の観音寺で日本最後と言われる仏海上人のそれを見たことがあるが、異様以外の言葉がない。17歳の西村は、それと知って訪れようとしたのだろうか。


ともあれ、その「闇」に踏み入る前に、筆者は火焔のオペラ『絵師』にスライドした。というのも2003年、病を得て、観念ではなく具体として自らの死に直面した西村は、「闇」というよりむしろ「光」の内面化へと向かうからである。
その前後の交響作品をいくつか拾ってみよう。
『ヴィオラ協奏曲〈焔と影〉(1996)
『ヴァイオリン協奏曲第1番〈残光〉』(1998)
『アルト・サクソフォン協奏曲〈エシ・イン・アニマ(魂の内なる存在)》』(1999)
『光と影の旋律』『オーボエ協奏曲〈迦楼羅〉』(2000)
『ヴァイオリン協奏曲第2番〈秘密~マニの光〉』(2001)
『交響曲第3番〈内なる光〉』(2003)
『ピアノ協奏曲〈シャーマン〉』『ハープ協奏曲〈風媒〉』 (2004)
すなわち、「闇」に彷徨うより、我が内なる光へと潜航の様相を呈する。さらに、退院後の協奏曲が〈シャーマン〉〈風媒〉であるのもまた興味深い。
こう辿ってゆくと、『絵師』の立ち位置は、やはり光と闇、生と死の交錯点におけるマンダラそのものと思える。
なお、西村は第32回『絵師』(1)〜芥川龍之介と三島由紀夫の「地獄変」掲載後に、以下のメールをくださった。
「私は、生死と関わる炎が好きなんですね。子供の頃から響きは光で、時に恐ろしい炎のようだと感じていました。」
響きを光、と感じる感性は、振り返れば小学校校庭での眩しい陽光とシューベルトでもあろうし、それを恐ろしい炎、と受け取るのもまた、原初における篝火(文明の火の意もふくめ)のような炎の持つ威嚇と魔性への直覚であろう。
その炎については、第16回 「ヘテロフォニー(Ⅲ)『2台のピアノと管弦楽のヘテロフォニー』」で触れているが、その回を終えての氏のメールにはこうある。
「『無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番〈炎の文字〉(2007)、『ピアノのための〈炎の書〉』(2010)。これらに言う“炎”は、護摩祈祷などでの舞い踊るような火炎のごとき響のマントラ、そういったイメージ。」
西村は目黒不動での護摩祈祷を折に触れその日常に織り込んでおり、むろん創作にあってそれは重要な儀礼であった。『絵師』が「生死と関わる炎」として光〜黄昏〜闇の途上に現れるのはやはり必然であったのだと改めて思う。
 焚き火もそうだが、火焔と舞い散る火の粉をひたすら眺める時間に人は何を思うのか。陽光と異なり、それは妖しく踊り狂い爆ぜ飛ぶ… 2)。
焚き火もそうだが、火焔と舞い散る火の粉をひたすら眺める時間に人は何を思うのか。陽光と異なり、それは妖しく踊り狂い爆ぜ飛ぶ… 2)。
さて筆者はここで、ベナレス体験から流れ出る『蓮華化生』等の作品群に戻るのでなく、このまま『絵師』での普遍的命題たる「宗教と芸術・音楽」を追い、その姉妹編と考える『清姫〜水の鱗』(2012)、『紫苑物語』(2019)に一気に進むことにした。
宗教・芸術の根底にあるのは無論、生死の問題であり、だからこそこの二領域は人類の産んだ壮大な「あやかし」(妖)なのではないか。西村はその両者の往還にあって音を創造する人、いや、往還というダイナミズムでなく、それらの始源に立つ「音の原人」3)(宗教的音楽家とはもはや呼ばない)ではないか。
筆者には今、そういう問いがある。
続く『清姫』『紫苑物語』は必ずその手がかりとなろう。
『絵師』における能表現で、筆者の関心はその「面」(おもて)に向いた。
能の主役であるシテは神や鬼、幽霊など異界の者が多い。橋がかりの幕の奥を「幽界」(あちら)、本舞台を「現世」(こちら)とし、その二つの世界をつなぐ形で演じられるが、異界幽界に属するシテは「面」をかける(つける)ことで、主人公に変化(へんげ)変身する。
面(おもて)はその名の通り、オモテに見せる顔であり、演者はそのウラの暗闇の中に姿を隠すという。したがって面を「かける」とは、魔法にかける、の意を含み、面が演者に憑依する、すなわち、異界の者が面を通して演者に乗り移るということだ。
能が異界との交信劇のようなものであれば、これもまた一種の儀礼の形であろう。
筆者は先般、能『翁』を見たが、この演目は演者が直面(素顔)でまず現れ舞台で面をかける。なるほどまさにトランスフォーメーションである。また能楽師が、代々の演者の呼吸の染み込んだ歴史ある面をかけると、なんとも言えない圧がかかり、その念のようなものに圧倒されると語るのを聞き、面の持つ力の凄まじさを感じたものだ。
 その能面に「あやかし」(怪士)と呼ばれるものがあり、これは男神や武将の霊の役に用いられる。この「あやかし」という言葉に筆者は「妖怪」「奇怪」「怪異」など「怪し・奇し・妖し」き何ものか、を思い浮かべる。妖怪は物怪(もののけ)とも呼ばれ、人間の理解を超えた奇怪で異常な現象、それらを起こす不可思議な力を持つ「何か」のことだ。
その能面に「あやかし」(怪士)と呼ばれるものがあり、これは男神や武将の霊の役に用いられる。この「あやかし」という言葉に筆者は「妖怪」「奇怪」「怪異」など「怪し・奇し・妖し」き何ものか、を思い浮かべる。妖怪は物怪(もののけ)とも呼ばれ、人間の理解を超えた奇怪で異常な現象、それらを起こす不可思議な力を持つ「何か」のことだ。
西村が2003年病の快癒後に『ピアノ協奏曲〈シャーマン〉』(2004)を書いているのは、彼の音楽のシャーマン性の本能的な噴出であると筆者には思える。いつぞやの若者たちのブラスバンドによる『秘儀シリーズ』全曲演奏に立ち会った折に感じたシャーマン性。陸上自衛隊中央音楽隊による『秘儀VIII 地響天籟』初演時も、そこに滾る西村マグマが奏者たちを焚き付け煽りあげての音の狂乱火柱に、その音の呪力・魔力を実感した。〈シャーマン〉に次いでの〈風媒〉(ハープ協奏曲)はハープゆえ風と光の戯れだが、ハープが化身となるのを筆者は篠崎史子の『ハープの個展ハープの個展ⅩⅤ』で先般まざまざと体験した。この〈風媒〉も彼女の委嘱作。西村が異界霊界冥界と最も近づいた痕跡を残す2作のように筆者は思う。
この種の「何か」を以前、三井寺「ながらの座・座 庭と音楽2020〜風の息、呼吸する音」での諸井誠『対話五題』(1965)に筆者が体感したことはすでに述べた。尺八の情念の塊り、その響きに庭園の木立、岩岩が突如蠢き、クラリネットがそこに引き摺り込まれ2者がもつれ斬り合う凄まじさ。庭全体が揺れざわめき、周辺一帯の地霊、神霊、心霊が一斉に飛び交う気配に驚愕した。
音とはそういう呪力を持つ。
西村の音もまた。
人類に原始信仰、シャーマニズム(呪術、祭祀)が現れるのはおよそ2万年まえのこと。マンモスの骨を使っての各種楽器制作は2.2万年前。動物崇拝のクマ祭りの痕跡がヨーロッパに発見されるのはさらに約6万年前だ。古代原始の人々は、あちらとこちらの間を往来する世界観に生きていた。いや、共存していた。そこに境界はなく、彼らは自在に行き来していたのではないか。そうして常なる「自然」の恩恵と脅威にあって、そこに多様な「あやし」き現象、不可思議力を実感、畏れ敬う心を持ち、それらとの往来・交信を様々な形で行った。祭祀も儀礼も全てそこから生まれたものだ。
憑依、変化(へんげ)、化身の類は、「あちら」と「こちら」を区別なく自在に飛翔する能力、想像力、創造力、いわばファンタジーを彼らが持っていたことを明かす。西村がヴィシュヌ化身をはじめ、半人半獣を題材に書いてきた多様な作品を思うなら、そのような世界を仮想と見るより、自身を虚実ないまぜ界の住人としばしば直覚していたからではなかろうか。
![]() 現象世界をどのように腑分け言分けしようと、スーパーヒーロー、アバターが飛びまわる現代仮想世界もまた、人類史の始原と変わらぬひとのファンタジーを示していよう。
現象世界をどのように腑分け言分けしようと、スーパーヒーロー、アバターが飛びまわる現代仮想世界もまた、人類史の始原と変わらぬひとのファンタジーを示していよう。
筆者が西村を音の原人と呼ぶに至ったのは、それと気づいたからだ。
『絵師』の良秀は火焔に巻かれる娘の眼前での絶命に、「あちら」に投身しつつ、「こちら」で筆を走らせた。筆者はそれを良秀の宿業と言ったが、面と所作、それを生む音響には確かにそれが宿っているように思えた。ゆえ、「業」とは何かという問いも生まれたが、ここではそこにこそ「行」があるのだろう、と言うにとどめたい。
ともあれ、「化す」とは、「化ける(ばける)」であるゆえ、「誤魔化し」「まやかし」「たぶらかし」の類は全てある種のいかがわしさ、すなわち宗教と芸術の「化かし力」にある紙一重のニュアンスを言い当てていることに留意したい(化学とはよくいったものだ)。
宗教・神話の発生は必ず、自然界の不可思議現象、事象への気づきが必須だ。人知を超えた不可思議力の働きにどう対応したら良いか。我が身に起こる天変地異・厄災、仲間・家族の死などに向き合う時、人がまず行うのは祈祷という行為であり、それは胸の痛み、湧き出る涙といった具体的な肉体的・生理的現象の自覚から自ずととる姿勢であり所作と筆者は考える。
まずはおのずからなった祈祷の仕草がある。そこに「人間」というもの、すなわち人と人との間、関係性の初発の自覚があり、同時に「ひと」としての「振る舞い」(タマフリ・タマシズメ/魂振・鎮魂)たる祭祀儀礼への成形と伝承によって、「ひと」は「ひと」となったとも言えよう。
ちなみに世界最古として知られる洞窟画はスペインのネアンデルタール人(65,000年前)のものでホモ・サピエンスではないことが明らかになったが 4)、続いてインドネシアの島、カリマンタン島やスラウェシ島で発見された壁画もまたこの年代に匹敵する古さという 5)。
彼らがすでに神の概念と物語る力を持っていたであろうことが推察されるように、ここに原人の化ける力、化かす力を読み取ることができよう。
筆者の言う「原人」とはその意だ。
『日本霊異記』を見るまでもなく、どの地であろうとどの時代であろうと、人々はこのような怪異と共に在ったし今も在る。
「呼びかけ」は境界を超え、おそらく今も人と人、何かと人、何かと何かが互いに呼びかわしている。現代人はそれに鈍感もしくは無感覚になっているだけとも言えようか。
ゆえ、根源音響に耳をこらし、そこからヘテロフォニーを掬い取り、一即多の中に音を求める西村を、音の原人と筆者は呼ぶのだ。
西村の変化・化身は、『清姫』、『紫苑物語』、そうして2023年最新作、絶筆とも言える『胡蝶夢』(7月8日@住友生命いずみホール初演)にまで及ぶ、とここで言っておく 6)。
さて室内オペラ『清姫―水の鱗』(二人の独唱者、混声合唱とピアノのための/2012)だ。
このオペラは能の演目『道成寺』を下敷きとする。
『道成寺』とは紀州道成寺にまつわる安珍・清姫伝説で、思いを寄せた僧の安珍に裏切られた清姫が大蛇に変化、彼を追いかけ日高川を渡り、道成寺の鐘中に隠れた安珍を恋の炎で焼き殺す話だ。
大蛇の化身と炎と死。
梵鐘と読経。
まさに西村ワールドである。
次回としたい。
(2023/10/15)
註
- 2023年9月7日、西村朗氏は冥界に入られた。今後、氏に事実確認その他をする術は無くなった。掲載ごとの感想をお聞かせいただくこともできなくなった。本稿以降は、これまでにいただいたたくさんのメールから一部を適宜引用、氏の肉声として脚注でご紹介、あるいは本文に織り込ませていただく。第30回掲載後にいただいたメールを以下にご紹介する。
「30年前の創作時の心象が鮮やかに蘇りました。『光のマントラ』の最後の持続音響は純粋な光そのものの表象で、連作7曲をその光明が抱きとめ包みます。私の初期の創作の最後のシーンかもしれません。」
メール拝読の際はさほど気に留めなかったが、7連作の位置付けを自分なりに「光のステージ」と名付けてみると、やはりそうであったか、と思う。 - その他の焔、炎関連作品は以下。
『紅蓮Ⅰ 尺八と箏のための二重協奏曲』(1984)、『炎の幻声 独奏二十絃箏と弦楽合奏のための協奏曲』(1988)、『火輪 尺八と打楽器のための』(1989)、『炎の孤悲歌 無伴奏混声合唱のための』(1992)、『前奏曲〈焔の幻影〉』(オルガンのための/1996)、『炎の挽歌 無伴奏女声合唱組曲』(2000)。 - 「音の原人」という言葉は、『光の雅歌』ほか、多数の西村本の伴走者であった編集者高梨公明氏とお話ししている時に成った言葉である。私はそのイメージをうまく言語化できずにいたのだが、西村氏がかつて国立劇場の木戸敏郎氏と「ウル」(urとは原初、原型/シュメールの古代都市)についての対話を希望されていたとのこと。
以下、その折の企画メモを高梨氏よりいただいた。
「『原(ウル)音楽考――古代が呼ぶ創造精神』(仮題)
木戸敏郎&西村朗(対話)
企画の趣旨:「創造論」の展開として。要点:日本、アジアの芸術創造のキーワード(倍音・虚階・残楽・間、等)をめぐって音楽の根源にある美的要素を解明しつつ、芸術・芸能における日本的なるもの、アジア的なるものを希求する。 日付2010年6月18日とあり。」 - ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史』に指摘されるホモ・サピエンスに駆逐もしくは絶滅させられたというネアンデルタール人の謎(彼はサピエンスの「言語獲得」がその絶滅の因ではないかと述べている)、あるいはジョーゼフ・ジョルダーニア『人間はなぜ歌うのか?』における人類初発の呼びかけ(問い)がジャワ原人、北京原人であることなど併せ考えると実に興味深い。
- 『WIRED』https://wired.jp/2020/01/23/a-43900-year-old-cave-painting-is-the-oldest-story-ever-recorded/
- 未完の『ピアノ協奏曲』が1作、遺された。
◆書籍
『人間はなぜ歌うのか?』ジョーゼフ・ジョルダーニア著 森田稔訳 ARC出版 2021年
『サピエンス全史 上』ユヴァル・ノア・ハラリ著 柴田裕之訳 河出書房新社 2016年
『 Akira NISHIMURA A Complete Catalogue 2021』全音楽譜出版社 2021年
『儀礼のオントロギー』今村仁司+今村真介著 講談社 2007年


