パリ・東京雑感|私たちをおびやかす『苦海浄土』 石牟礼道子さんを失って|松浦茂長
私たちをおびやかす『苦海浄土』 石牟礼道子さんを失って
Text by 松浦茂長 (Shigenaga Matsuura)
石牟礼道子さんが亡くなった。池澤夏樹氏が世界文学全集30巻を編集したとき、ただ一人の日本人作家として石牟礼を選んだ。『苦海浄土』は、20世紀後半の文学のおそらく頂点をなす作品だろう。今の僕にはその深遠な思想を読み解く用意がない。
10年以上前、妻の長患いの最中に、自分自身のために書いたメモのようなものを、オマージュのかわりとするのをお許しいただきたい。
『苦海浄土』には聖書のヨブ記を思わせる場面があります。6歳のとき水俣病にかかり、目も見えず、動くこともできず、知能の失われた少女が、おしめをあてた17歳の美しい娘になった。マスコミが「ミルクのみ人形」と名づけた少女ゆりの母が、不条理に抗議します。
「とうちゃん、ゆりは、とかげの子のごたる手つきしとるばい。死んで干あがった、とかげのごたる。そして鳥のごたるよ。目あけて首のだらりとするけん。」
「ゆりはもうぬけがらじゃと、魂はもう残っとらん人間じゃと、新聞記者さんの書いとらすげな。そんならとうちゃん、ゆりが吐きよる息は何の息じゃろか。草の吐きよる息じゃろか。」
脳神経の破壊された少女を「ぬけがら」と規定する近代世界の人間像に向かって、ゆりの母は渾身の抗議をします。「草の吐きよる息じゃろか」のひと言には、<ものを考えものを生産する存在=人間>とする軽薄な近代固定観念を粉砕する強靱なもの、祖霊と地霊に支えられる確かさがこめられていませんか。
「あんたなあ、ゆりに精魂が無かならば、そんならうちは、いったいなんの親じゃろか。うちはやっぱり、人間の親じゃあろうかな。」
ゆりの母が「人間の親」と主張するとき、それは、人間を否定する圧倒的な仕掛けへの絶望的な怒りに他なりません。工場廃液に有機水銀が含まれているのを知りながら、隠し続け、うそをつき続けた工場。漁民の命より企業の利益を優先することに疑問を感じなかった経営者と技術者たち。目の前で漁民が次々と狂い死にするのを見ながら、「水俣病患者の111名と水俣市民4万5千とどちらが大事か」と大合唱し、工場を守ろうとした地元住民のエゴイズム。戦後の日本の経済復興を支える精神は、人の命の驚くべき軽さという点で、戦争中の日本人の精神と大して変わらなかったように見えます。経済の戦いに勝つために、命が失われても、小さな家庭の幸せが奪われても気にかけることはない。公害という抽象的な言葉の背後にある、野獣のようにどう猛な経済原理を、ゆりの母は、見抜き、その酷薄な世界に抗議し続けます。
やわらかい方言の響きでリズミカルに繰り返されるゆりの母の訴えは7ページにわたり、読者は波に揺られる船の乗客のように、次第に常識の世界を離れ、彼女の世界、『草の親』(この章のタイトル)の逆転した世界に運び込まれて行きます。それはわが身の不条理を神に向かって抗議し続けたヨブのように、根源的な抗議です。ゆりの母は、ついに、「人間の母」であることすら放棄します。
「ゆりが草木ならば、うちは草木の親じゃ。ゆりがとかげの子ならとかげの親、鳥の子ならば鳥の親、めめずの子ならばめめずの親。なんの親でもよかたいなあ。鳥じゃろうと草じゃろうと。うちはゆりの親でさえあれば、なんの親にでもなってよか」
もはや、ゆりを生んだ不条理に抗議するのではなく、ゆりという不条理に、母自身も成りきる。不条理に徹するのです。逆転した世界に居直るのです。しかも、逆転した世界に仏の救いがあるものか、彼女にはわからない。世俗化した寺と僧侶しか知らなければ、仏様だって世間の秩序の延長としか映らないだろうし、ゆりの母にとって、娘は宗教の光も射さない絶対的不条理なのです。
「ただの病気で、寿命で死ぬものならば、魂は仏さんの引きとってやらすというけれど、ユーキ水銀で溶けてしもうた魂ちゅうもんは、誰が引きとってくるるもんじゃろか。会社が引きとってくれたもんじゃろか?ゆりからみれば、この世もあの世も闇にちがいなか。ゆりには往って定まる所がなか。うちは死んであの世に往たても、あの子に逢われんがな。とうちゃん、どこに在ると?ゆりが魂は。」
水俣病患者の境遇は、まことに「この世もあの世も闇」としか言いようのない孤立無援の状態でした。工場が漁民の訴えを突っぱねただけでなく、住民からも差別され、軽蔑され、憎悪されました。「神も仏もあるものか」――徹底的不条理に突き落とされたのです。しかし、ゆりの母は娘の不条理にたじろがない。どこまでも娘に寄り添い、神も仏もない不条理の闇の底にまで、一緒に沈んでゆきます。ゆりの『息』に彼女の息をあわせ、救いの光の射さない悲しみの底に、ともに沈んで行きます。
「あきらみゅうあきらみゅう。ありゃなんの涙じゃろか、ゆりが涙は。心はなあんも思いよらんちゅうが、なんの涙じゃろか、ゆりがこぼす涙は、とうちゃん」
突然ゆりに後光が射すようなどきっとするシーンではありませんか。ゆりの涙は母の涙、石牟礼の涙でもあるでしょう。人の不条理と悲しみに最後まで勇気をもって寄り添うとき、奇跡が起こります。『苦海』がそのまま『浄土』となる不思議です。
石牟礼が漁民の悲しみの底にまでのめり込んだとき、強い怒りがわき上がります。読者をたじたじとさせる崇高な怒り。その怒りによって、水俣の漁民の悲劇が日本人全体の不幸の圧縮された表現であることが明らさまにされます。
日本社会の価値の転落をあざやかに表したのが、葬列のシーンです。発狂して死んだ患者の葬列にトラックが容赦なく泥をはねかけ、位牌も供物も喪服も泥にまみれます。
「一昔前まで、(中略)旗一本立てぬつつましやかな葬列といえども、道のど真ん中を粛々と行進し、馬車引きは馬をとめ、自動車などというものは後にすさり、葬列を作る人びとは喪服を晴れ着にかえ、涙のうちにも一種の晴れがましささえ匂わせて、道のべの見物衆を圧して通ったものであった。」
馬車引きも見知らぬ人の死に哀悼の気持ちを示す。共同体のそんなやさしさは、国土建設の大義のもとに押しつぶされて行きます。「トラック様のお通りだ」の傍若無人の光景は、そのまま水俣の工場の廃液垂れ流しの論理でもあります。
(パリではいつも同じ道路わきに暮らしていたホームレスの老人が死んだとき、人々はその場所に花を供え、たくさんの哀悼のメッセージが置かれました。)葬列を追い越すことの許されない共同体には、人間の死を敬虔に見つめるまっとうな心が守られていました。
人の生死に対する正常な感受性が失われ、全ての価値が経済原理に従属させられた。水俣の悲劇をともに生きぬくことを通じ、石牟礼は、日本社会の倒錯に対する根源的糾弾の言葉を獲得します。
昭和43年9月、水俣病の患者発生から15年目に、政府は工場の責任を正式に打ち出します。その4日前、園田厚相が水俣を訪れ、患者たちは涙を流して迎えます。『苦海浄土』のヒロインのひとり、ゆきも大臣を待望したひとりでした。ゆきは再婚して3年で発病し、痙攣がひどいため食べ物を「せっかく口に入れてもろうても飯粒は飛び出す、汁はこぼす」有様になりました。元気なときのゆきは夫といっしょに漁に出て、ぴったり息のあった夫婦でした。
「彼女は海に対する自在な本能のように、魚の寄る瀬をよくこころえていた。そこに茂平を導くと櫓をおさめ、深い藻のしげみをのぞき入って、
『ほーい、ほい、きょうもまた来たぞい』
と魚をよぶのである。(中略)海とゆきは一緒になって舟をあやし、茂平やんは不思議なおさな心になるのである」
海のシーンの幻想的な美しさは、薄幸のゆきの心の清さを映し出しています。同時にそれは、水俣の自然の失われた調和を象徴しているのでしょう。ゆきは、離婚させられ、精神に異常をきたしますが、大臣を迎えるころには微笑みをもらすほどに立ち直っていました。それでも、極度の緊張から、いつもの痙攣発作が起こり、医師たち3人がかりでとりおさえられます。そのとき
「注射液を注入されつつ、突如彼女の口から
『て、ん、のう、へい、か、ばんざい』
という絶叫がでた。 病室中が静まり返る。大臣は一瞬不安げな表情をし、杉原ゆりのベッドの方にむきなおった。
(中略)
そくそくとひろがる鬼気感に押し出され、一行は気をのまれて病室を離れ去った。」
感激の頂点で叫ばれた「天皇陛下万歳」は、何を意味するのでしょう。それは、不条理の深い淵から搾り出された、正義へのあえぎ。(ロシアの農奴は、いつかツァーが自分たちを救ってくれると、皇帝の正義を信じたといいます。地主、貴族の暴力と収奪の毎日に、農奴ははるか上からの救済を夢見るほかなかったのでしょう。)水俣の漁民たちに、助けの手を差し伸べてくれる人はなかなか現われなかった。科学も左翼もかれらの上を素通りして行ったのです。近代そのものが彼らに敵対し、無視してきたのです。だから、ゆきの精神の古層から天皇が突如噴出することになったのでしょう。
ともあれ、このときゆきは、大臣に勝った。人間としての品位において、大臣とその一行を威圧しました。「かつて人類史がさしのぞいたこともない受苦をくぐることによって、洗われつつある精神の高貴さ」、そこからほとばしる真実が、「原初の神も土俗の信仰も失った軽文明」を圧倒したのです。もちろん大臣と一行は負けたことに気づかない。真実を真実として受け取る能力を失った人たちですから、それを不気味――「鬼気感」と感じとるほかありません。
そして読者の僕も、真実を「鬼気感」として恐れたじろぐ「軽文明」の奴隷であることに気づかされます。正しく生きるとはどういうことなのか?『苦海浄土』は、私たちに実存的問いをつきつけ続けます。
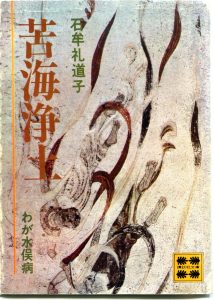
(2018年2月25日)




