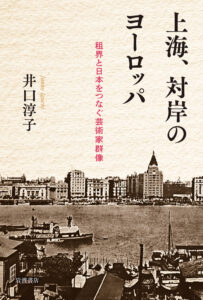Books|上海、対岸のヨーロッパ|丘山万里子
井口淳子 著
2025年3月初版発行
岩波書店
定価2,700円+税
Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)
1842年南京条約以降、西欧人居留地となった上海租界は、第一ロシア革命(1905)からの亡命ユダヤ人も流入、東洋のパリ、東方のペテルブルクと呼ばれる一大芸術都市として、日本に最も近い「夢の楽都・魔都」であった。ラトビアに生まれその地に流れ着いた一人の男、アウセイ・ストローク。極東一のインプレサリオ(興行主)として辣腕をふるい、大規模なアジアツアーを含め、日本の楽壇の基礎をも築いたそのストロークを中心に、当時の芸術家群像をダイナミックに、何より愛と敬意を込めて描く。前書『亡命者たちの上海楽壇―租界の音楽とバレエ』(2019)に続き、フランス人音楽評論家シャルル・グロボワ、ラジオで活躍した女性冒険家クロード・リヴィエール、さらに上海での体験から日本の戦後を拓いた朝比奈隆ら邦人音楽家、バレエダンサー、彼らを支えた日本のパトロンたちの動きまでを、時代の動きとともに丹念に拾う。
著者は学生の頃、初めて北京を訪れて以来(1981)幾度となく中国農村でのフィールドワークを重ねており、その語りは、いわゆるクラシックの音楽学者とは異なる「人肌」を感じさせる。西欧にしろ日本にしろ、支配被支配の構図の名残を今日に見る著者のそれとない眼差しに気づく時、山深い村落の人々の暮らしぶりや、大都市裏の路端にたむろする若い路上生活者らの姿もまた、この人には見えているのだろうと思うのだ。
あるいはパンデミックによって現地調査がかなわぬ中、各地に散らばる上海租界研究・関係者のネットワークを駆使、得た資料からストロークの、グロボワの、リヴィエールの像を立ち上げてゆくその筆先には、著者の人間力といったものが感じられ、本書の大きな魅力となっている。上流階級の娯楽社交、占領国の文化工作であっても、芸術至上主義を貫くストロークや音楽家たちを活写しつつ、たとえば《エピローグー戦後のグロボワ》で評論家グロボワの遺品の写真の大半が、当時校長を務めた学校の生徒たちのもので、彼を取り巻いた著名な音楽家、芸術家、華やかな社交界などのものがなかったことに「ああ、やはりグロボワとはまず教育者だったのだ」と腑に落とすあたり、それが柔らかに伝わってくる(p.198)。
全8章、コラム4篇で、章立ては以下。
第1章:ラトビア生まれの興行主、アウセイ・ストローク
コラム:大正時代のオペラ体験
コラム:上海租界の今昔
第2章:フランス人音楽評論家、シャルル・グロボワ
コラム:『ル・ジュルナル・ド・シャンハイ』(『法文上海日報』の再発見)
第3章:女性冒険家クロード・リヴィエール
第4章:グロボワの音楽評論、楽壇の灯台として
第5章:ストロークのアジアツァー(1918〜56)
コラム:ストロークの素顔
第6章:上海バレエ・リュスの軌跡と遺産
第7章:戦争に抗う芸術家たち
第8章:戦後、花開く上海人脈
以下、筆者の興味に沿ってのピックアップ。
第2章:グロボワが上海唯一の仏語新聞に書き続けた音楽評論は300篇をこえ、戦時の山田耕作、朝比奈隆の演奏も含まれる。ブルージュ、パリからフランス租界の教育総監に着任した彼の音楽評論は余技であったが、時事的な問題に触れることなく、作品の歴史的背景や専門的解釈を伝えることを重視、演奏には公平かつ厳密、辛辣であった。山田については、「西洋からの確かな影響や、時にはそれぞれの作曲作品に一貫する論理が確立していないゆえに起こる、さまざまな方法の並列を指摘することは容易であるが、しかし、独創性は極めて著しい」(p.36)。『明治頌歌』にスクリャービンの影響を指摘するあたりもさすがだ。
一方、朝比奈については、上海のオーケストラに「自分の存在を受け入れさせ、それと同時に彼らに理解してもらい、各演奏家の興味を引くこともできたのである。――中略――メッテルの影響が如何なるものであるにせよ、これは学べるものではなく、一個人の人格によるものだ。」と喝破している(p.39)。
改めて、歴史に残る「批評」というものの価値を痛感した次第。
第3章:教育、音楽評論、ラジオ放送など多岐にわたって活躍するグロボワの最大の協力者となったのがリヴィエール。ワルシャワ生まれの彼女は、フランス領タヒチから、サモア、ハワイ、インドなどを流れ歩き、上海に至る。ラジオ放送での「芸術と文化」という名称の音楽番組を担当、テーマを決めての多彩な作品群を紹介、また自身の放浪、冒険から得た広範かつ多様な話題での「マダム・リヴィエールの談話」で、民族や政治の壁を越え、戦時にあっては疲弊した人々の心を潤わせた。
ストロークも含め、これまで語られることのほとんどなかった(忘れられた)彼らを歴史の海から浮かび上がらせ、戦後日本へ、今日へと繋いでゆく著者の情熱には圧倒される。
第5章:アジアの「ミカド」と呼ばれたストロークのマネジメント手法列挙も、実に興味深い。
1、アーティストを厳選、チケット料金も超高額
2、ストロークのディレクションであることを明示する
3、レコード販売。ラジオ放送との連携
4、プログラム冊子のデザイン
彼は、典型的な西欧中心主義者だったが、日本の熱狂的なファンを目の当たりに、変化してゆく。戦後、日本に戻り、聖路加病院で逝去、墓は横浜。人情に厚く、人と人との信頼関係を最大の財産としたという。筆者は上記4点に日本の大手マネジメント、かつての梶本音楽事務所(現KAJIMOTO)を想起したが、創始者梶本尚靖がストロークの日本での遺産「大阪国際フェスティバル」の流れを汲む大阪人であったことを知れば、なるほど、なのだ。さらに言えば、後継の梶本眞秀がいち早くアジア市場に目をつけ、北京事務所を開き、ベトナムへと手を広げているのも頷ける。
ここからは筆者の脳内話だが、戦後渡米、1956年ニューヨーク事務所を構えたストロークのすぐそばには1953年、小さな代理店を開いた若者がいた。その後、コロムビア・アーティスツ・マネジメント(CAMI)社長就任、クラシック界の音楽マフィア、そのゴッドファーザーとなったロナルド・ウィルフォードだ。半世紀ほど年の離れた彼は、ストロークの「一流・高額」手法に似てはいるものの、飽くなき金と権力で世界の覇者となった。そこに群がる人々と、上海芸術家群像の間の相違を思わずにいられない。ラジオやレコードなどメディアの発達に伴う音楽の大衆化時代のストロークのモチベーションは芸術への愛にほかなるまいが(本書を読むとそう思う)、ウィルフォードを生んだ巨大な消費化社会にあるのは金と権力への欲望だ(ちなみに梶本はかつてCAMI日本支店と呼ばれた)。
それは一個人の姿ではなく、時代の姿に他ならない。
そうして、パンデミックを経ての今は?
第8章:戦後の日本の楽壇でのストロークの最大の功績としての「大阪国際フェスティバル」は、朝日新聞社社長令嬢村山未知に託された。欧州各地の音楽祭を視察、それを日本に実現した彼女が「大新聞社社主の道楽として芸術祭を主催したのではなく、使命感と確たる芸術審美眼をもち、まだ名をなさない若手指揮者や演奏家の才能を見出し、その才能を見極める確かな評価軸を持っていた」(p.195)との記述に、ストロークのマネジメント手法ばかりでなく、その精神を継いだ村山への敬意を筆者は読む。
上海、大阪、東京、ニューヨークまで、戦前は航路、戦後は空路で復活した「ミカド」。
最後に彼の印象的なエピソードを一つ挙げておこう(第5章)。
日本支配下の上海にあって活躍した日本のマネージャー「ハラゼン」と呼ばれた原善一郎*が、当時ユダヤ人指定地域に強制移住直前にあったストロークを内閣直属、対中政策機関の仕事に誘う。すると彼はこう答えたという。
「わたしは今日まで自分の名誉のために立派な芸術家と仕事をして来た。決して、上海の音楽家や舞踊家が立派でないとはいわないが自分の手はいつも清潔にしておきたい。」(p.115)
「“日本軍の片棒は担がない”という意志を貫くのは平和時に考えるほど容易なことではない。」とは、著者のコメント(同上)。
戦後80年、平和ボケした私たちに、本書は様々なことを問いかけ、示してくれる。
筆者はたまたま著者より1年早く、1980年に北京に滞在、さらに2000年代には満州の山田耕作の足取りを追ってその地を旅した。占領下の中国ばかりでなく、開拓団という名で送られた日本の東北貧村などの人々が土を舐めるような労苦を重ねる一方、政府高官らが集った華やかな西欧文化の名残を目にするにあたり、どこに身を置いても胸を切り刻まれるような経験であった。だけに、音楽を心の糧に激動の上海を生きた人々の生き様を伝える本書に、どこか救われる気持ちにもなったのである。
なお、著者の中国農村での経験を綴った『送別の餃子』(灯光舎 2021)はその人間力を伝えるにあまりある。その最後の言葉はこうだ。
「人を信じよ」。
副読本として、お薦めしておく。
*原の同僚が大阪国際フェスティバル事務局長の野口幸助、そのもとで修業したのが梶本尚靖。
(2025/7/15)