低音デュオ第十七回演奏会~低音のカタログ~|伊澤文彦
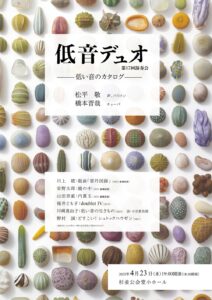 低音デュオ第十七回演奏会~低音のカタログ~
低音デュオ第十七回演奏会~低音のカタログ~
Bass Duo 17th Concert – Catalogue of Bass Sounds –
2025年4月23日 杉並公会堂 小ホール
2025/04/23 Suginami Public Hall, Small Hall
Reviewed by 伊澤文彦(Isawa Fumihiko):Guest
Photos by 後藤天/写真提供:低音デュオ
〈演奏〉 →foreign language
松平敬:バリトン、声
橋本晋哉:チューバ、セルパン
〈曲目〉
福井とも子 『doubletⅣ』(2019)
川崎真由子 『低い音の生きもの』(2023/25)改訂初演 詩:小笠原鳥類
山田奈直 『内裏玉』(2025)委嘱初演
安野太郎 『鏡の中』(2025)委嘱初演
川上統 組曲『雲丹図録』(2025)委嘱初演
野村誠『どすこい!シュトックハウゼン』(2021)
 今回で十七回を迎える低音デュオのコンサートでは、相変わらず、声と音あるいは音と音楽との狭間にある深淵に潜っていくような実験が続けられている。一曲目の福井とも子の作品『doubletⅣ』では、チューバと声の重音は幾重にも変調され、息が音になり、音が音楽になる。チューバも人間の身体も音を響かせるための一つの管であることを思い知らされるような作品だ。三拍子の小声でひそひそと交わされていた音の往還は、奏者の足音やシンバル、スネア・ドラムのスクラッチによって分断されながら再統合される。一見唐突にも思えるパーカッションによる緊張感の挿入は、声と音という不可分な現象を増幅して、私たちに提示する。
今回で十七回を迎える低音デュオのコンサートでは、相変わらず、声と音あるいは音と音楽との狭間にある深淵に潜っていくような実験が続けられている。一曲目の福井とも子の作品『doubletⅣ』では、チューバと声の重音は幾重にも変調され、息が音になり、音が音楽になる。チューバも人間の身体も音を響かせるための一つの管であることを思い知らされるような作品だ。三拍子の小声でひそひそと交わされていた音の往還は、奏者の足音やシンバル、スネア・ドラムのスクラッチによって分断されながら再統合される。一見唐突にも思えるパーカッションによる緊張感の挿入は、声と音という不可分な現象を増幅して、私たちに提示する。
続く二曲目、川崎真由子の『低い音の生きもの』では、「朗読」という形式が差し込まれる。元来、詩は音楽的な要素が含まれている芸術ジャンルであるが、詩を読み上げる、あるいは歌い上げるという行為に加えて、チューバを通して読み上げる行為も付加される。小笠原鳥類が描く「低い音のいきもの」は、サンプリングされた脈絡のない言葉がキメラのように飛躍しながら連なっている。そうした不可思議かつ魅力ある言葉たちを様々な奏法に基づいて表現していく作曲者と奏者たちの力量は非常に優れており、詩の言葉を音として、あるいは意味として受け取りながら、「生きもの」の発する音がイメージとして立ち上がって聞こえてきた。
 三曲目の山田奈直による『内裏玉』は、橋本の演奏するチューバの管とゴムホースが接続され、ホースの片側を口にくわえた松平が二人羽織のような体勢に なりながら音を出すという、セッティングからして面白い作品である。二人の息の入れ方と発音については、どのような対応関係があるかわからなかったが、奏者が発音に対しての影響をお互いに与えあいながら演奏する状態は、「中動態的な音楽」と呼んでもよいだろう。2人の奏者はチューバを媒介しながらそれぞれの息を管に共鳴させ、身体に共鳴させながら新しい音世界を作り上げている。「演奏」という行為自体に対する批評的な視座を持つ作品だと感じた。
三曲目の山田奈直による『内裏玉』は、橋本の演奏するチューバの管とゴムホースが接続され、ホースの片側を口にくわえた松平が二人羽織のような体勢に なりながら音を出すという、セッティングからして面白い作品である。二人の息の入れ方と発音については、どのような対応関係があるかわからなかったが、奏者が発音に対しての影響をお互いに与えあいながら演奏する状態は、「中動態的な音楽」と呼んでもよいだろう。2人の奏者はチューバを媒介しながらそれぞれの息を管に共鳴させ、身体に共鳴させながら新しい音世界を作り上げている。「演奏」という行為自体に対する批評的な視座を持つ作品だと感じた。
 休憩明けの四曲目には、安野太郎の『鏡の中』が演奏された。この曲は、ワレリー・ブリューソフの短編『鏡の中』をもとに、テキストを翻案して制作したものである。安野は通称「ゾンビ音楽」という奇妙なロボットが演奏する音楽のプロジェクトで著名な作曲家であるが、こうしたテキストを使用するタイプの作品は初めて視聴した。はじめは朗々としたバリトンの発声とチューバの単純なユニゾンのように聞こえ、メロディも単調で少々退屈さを感じたが、次第にバリトンの発声からナレーション原稿を読むような冷静な発話に切り替わり、そこから一気に引き込まれた。
休憩明けの四曲目には、安野太郎の『鏡の中』が演奏された。この曲は、ワレリー・ブリューソフの短編『鏡の中』をもとに、テキストを翻案して制作したものである。安野は通称「ゾンビ音楽」という奇妙なロボットが演奏する音楽のプロジェクトで著名な作曲家であるが、こうしたテキストを使用するタイプの作品は初めて視聴した。はじめは朗々としたバリトンの発声とチューバの単純なユニゾンのように聞こえ、メロディも単調で少々退屈さを感じたが、次第にバリトンの発声からナレーション原稿を読むような冷静な発話に切り替わり、そこから一気に引き込まれた。 そして跳躍する音程にも即座に対応する松平の技巧に魅せられていった。また、そのようなバリトン/声の切り替えの激しさとは対照的に、チューバは楽音としての響きを十分に保ちながら、規則的な音型を抑制的に反復していた。各奏者の差異が顕在化し、鏡合わせのように一方の旋律を追いかけあう場面もあり、緩急のつけ方も聴衆を飽きさせないものであった。
そして跳躍する音程にも即座に対応する松平の技巧に魅せられていった。また、そのようなバリトン/声の切り替えの激しさとは対照的に、チューバは楽音としての響きを十分に保ちながら、規則的な音型を抑制的に反復していた。各奏者の差異が顕在化し、鏡合わせのように一方の旋律を追いかけあう場面もあり、緩急のつけ方も聴衆を飽きさせないものであった。
五曲目は川上統による組曲『雲丹図録』である。奇妙な曲名だが、この作曲家のタイトルとしては通常運転の範疇であろう。十七曲の組曲『甲殻』によって不可思議な生物の描写を音楽によって執拗に表現し続けた、日本が誇る生物種組曲作曲家の川上である。今回の題材は「雲丹」であり、しかも組曲。俄然期待が高まる。プログラムノートを見ると、見たことも聞いたこともない雲丹の名前が並んでいる。十三曲の組曲だが、その響きは圧倒的な描写力によって支えられる。まるで雲丹がそこにいるかのような音によるイメージの連続がたたみかけるように突きつけられる。擬音が多用される発音や、不規則なスタッカートの連続は、音楽に造形的な動きをもたらす。歌い上げるような旋律を演奏したかと思えば、急にリップロールを繰り出したりする予想のつかなさは、まさしく生物種組曲にふさわしい。川上にとって全ての音は造形的な運動を描写するためにあるのではないかと錯覚するくらい、音楽的描写の技術を感じ取ることができた。
 最後の六曲目は、野村誠による『どすこい!シュトックハウゼン』。シュトックハウゼンの相撲に関するレクチャーを題材にした曲であり、行司の掛け声や四股など、相撲特有の振る舞いが随所にちりばめられていた。時折、奏者同士が相撲の取り組みのように顔を見合わせる場面もあり、パフォーマンス性にあふれていた。最後は駆け上がるようなポップな旋律が歌われたあと、「待ったなし!」の掛け声で唐突に作品が終わる。元の題材がレクチャーなだけあって、一つの舞台を観劇したかのような満足感のある曲であった。
最後の六曲目は、野村誠による『どすこい!シュトックハウゼン』。シュトックハウゼンの相撲に関するレクチャーを題材にした曲であり、行司の掛け声や四股など、相撲特有の振る舞いが随所にちりばめられていた。時折、奏者同士が相撲の取り組みのように顔を見合わせる場面もあり、パフォーマンス性にあふれていた。最後は駆け上がるようなポップな旋律が歌われたあと、「待ったなし!」の掛け声で唐突に作品が終わる。元の題材がレクチャーなだけあって、一つの舞台を観劇したかのような満足感のある曲であった。
(2025/5/15)
―――――――――――――
伊澤 文彦 (Fumihiko Isawa)
1993 年、長野県生まれ。
武蔵野美術大学造形学部芸術文化学科卒業後、横浜国立大学大学院都市イノベーション学府建築都市文化専攻博士前期課程修了。
現在、福島県立美術館学芸員として勤務。専門は実験工房など前衛芸術家集団の研究。領域横断的なインターメディア・アートに関心がある。
—————————————
<Players>
Baritone,Voice:Takashi Matsudaira
Tuba,Serpent:Shinya Hashimoto
<Program>
Tomoko Fukui:doublet Ⅳ(2019)
Mayuko kawasaki:Low-pitched creatures(text by Chorui Ogasawara)(2023/25)
Nanao Yamada:Dairi-gyoku(2025)
Taro Yasuno:B зеркало(2025)
Osamu Kawakami:Catalogue of sea urchins(2025)
Makoto Nomura:Doskoi!Stockhausen(2021)


