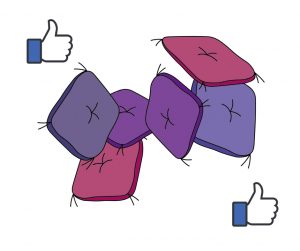緊急特別企画|もう一度「モノ消費」へ‐感染症騒動から(せめて)何かを持ち帰るために|多田圭介
 もう一度「モノ消費」へ‐感染症騒動から(せめて)何かを持ち帰るために
もう一度「モノ消費」へ‐感染症騒動から(せめて)何かを持ち帰るために
Text by多田圭介(Keisuke Tada)
1.感染症騒動から
2.ソーシャルネットワークの「閉じる力」
3.モノ消費からコト消費へ
4.自立と依存をめぐる丸山と吉本の対話
5.もう一度、「モノ消費」へ
1.感染症騒動から
この原稿を書いている3月末現在、感染症の影響がどこまで広がるか予想すらできない状態にある。あらゆる舞台公演が中止ないし延期を余儀なくされ、これがいつまで続くか先が見えない。文化芸術を愛好し、生業とし、日常生活の一部とする私たちにとって、生活からの文化芸術の切断は日常の切断と等価である。私たちは、自力ではどうにもできない力で生きる意味を切断されてしまった。ただ、現実に切り離されてしまった今、私たちは、この騒動から「何を持ち帰るか」を同時に考え始めなくてはならないだろう。
ワクチンや治療法がない感染症といえば、2009年の新型インフルエンザもそうだった。ただ、そのときは、多くの犠牲者を出しはしたものの、ここまでの騒動に発展することはなかった。あのときと今の状況で決定的に異なるのは、ソーシャルネットワークの普及であろう。事実、WHOも、「Pandemicであると同時にInfo-demicだ」と公式に表明している。もちろん、文化批評を主戦場とする筆者が疫学的な事柄に言及できるわけはないし、すべきでもない。だが、Infodemic=情報氾濫を引き起こした事実と、そこに太く流れる私たちの隠れた欲望、そしてその集合的無意識、これらに正しくアクセスすることはおそらく可能でありかつ必要な作業になってくるだろう。この作業は、結果的に文化現象の価値とその受容の意味を再考することになるし、なにより、誰もが書くことが当たり前になった時代に、私たちが未来に残すに値する言葉、世界にポジティブなものを投げる言葉とは、いかなる言葉であるのかを、もう一度考え直す契機になるはずだ。そして、やはり、私たちが愛する文化現象がその触媒であることにもう一度気づき直すことになる。
2.ソーシャルネットワークの「閉じる力」
まず、現行のソーシャルネットワークが本質的に持っている「閉じる力」について考えてみよう。え?SNSって広げるものじゃないの?そう思うかもしれない。もちろん、繋がり、広げるところにSNSの目的はある。しかし、私たちは繋げること、交流させることが発動してしまう、あまりに強い「閉じる力」に多くの場合、無自覚だ。SNSでは交流することで相互に「いいね」を付け合い、そしてこの数値が可視化される。そのことで、互いにフォローし合っているコミュニティのなかで、関心が、いま語るべき「問題そのもの」から、否応ない仕方で「問題をどう語るかで誰が株を上げたか」に移ってしまう。例えば、いまの感染症騒動で言えば、ある人が騒動の初期の頃に「危険だ」という発信をしたとしよう。彼/彼女は、経過を注視するなかで、潮目が「大騒ぎするほど危険ではない」という方向に傾くと、自分が誤った知識を発信したと評価されることを恐れ「やはり危険だ」と解釈できるソースを大量にリツイートすることになる。そうしてフェイクニュースも簡単に拡散するようになる。逆もまた然りだ。これを繰り返せば繰り返すほど、いま考えるべき「問題そのもの」はネットワークの圏外に弾き出されることになる。が、それを、発信する本人が自覚するのは難しい。
さらに、そうして閉じた相互の監視(評価)が閉じる力を強めるほどに、いま話題のテーマについて、いかに上手に擁護するか、またはdisるか、だけが関心となる。そしてその評価に応じて座布団(いいね)がいくつ貰えるかという、ほとんど大喜利のようなゲームに埋没することになるのだ。そして、最も警戒すべきことは、AかBかという、この話題を肯定するか否定するか以外の選択肢、つまり、そもそも問題にすべき価値がない、という違う視点を発動すると、このコミュニティでは「いいね」がつかなくなり、フォロワーが減り、そうして違う視点から事態を眺める眼は、圧殺される。さらに、閉じたコミュニティでいかに座布団を貰うかに血道をあげるようになると、いかにもTwitterっぽい文体、いかにもFacebookっぽい文体で事柄を語るようになる。ここに書くのだから、こういうものだろう、という先入観を介してしか世界を視ることができなくなる。そうした感覚が、人間の想像力をいかに制限しているか、そこから発せられる言葉がいかに凡庸で、画一的で無内容であるか、閉じたコミュニティに埋没すると気づくことができなくなるのだ。
3.モノ消費からコト消費へ
ここで起きている事態は、私たちにとっておそらく人間の最も強い欲望に根ざしたものであり、その欲望は、それを悪として退けることでは回避できないほど強いものである。私たちは、20世紀までは、本の向こう、ないし、モニターの向こうの「誰か」のストーリー、つまり他人のストーリーを楽しむことで時間を消費していた。小説、映画、テレビドラマ。いわゆる「モノ消費」だ。しかし、インターネットの登場によって、私たちは、自分のストーリーを消費する、言い換えれば自分が主役になる快楽を覚えてしまった。人間は、それがどれほど凡庸で退屈なものであっても、自分が主役になる物語をより好む、この事実は覆すことができない。恋人とのLINEを遮断させる力をテレビドラマは持たない。これが「コト消費」の隆盛の正体だ。20世紀的な「モノ消費」から21世紀的「コト消費」へ(CD販売から握手会や参加型のフェスへ)と地盤が変動したと巷間叫ばれている。その事実の背景には、自分のストーリーを語る快楽の強さとインターネットによるその欲望の解放がある。クラシックの演奏会や舞台も、この構造に組み込まれると、終演後に催しの内容について誰が上手に語って座布団を何枚貰ったかだけが関心となり、催しの内容そのものが関心の圏外になる。本質的に自分にしか興味がない私たちが、その傾向に拍車をかけられた状態で、本来、文化現象の核心であるはずの自分の「外側」の大事なもの、自分の外側、「こだわり」を保持することは難しいのだ。
だからといって、SNSが悪だといいたいわけではない、むしろ、SNSとは、人間の本質を可視化する装置だ。それゆえに、元来、人間が持っている本質を露呈させてしまうのだ。では、ここでいう「本質」とは何か。それは、自立すること、自分の頭で考えることの難しさ、すなわち私たち一人一人の依存的な性質と言える。いま私たちは、20世紀の日本最大の思想家であった丸山真男と吉本隆明がかつて火花を散らした、自立と依存をめぐる対話を、後ろ向きに、無自覚に反復している。彼らの先見の明を讃えるよりも、彼らが抉った世界構造の本質を現代のSNSが可視化しているというほうがおそらく正しいだろう。
4.自立と依存をめぐる丸山と吉本の対話
吉本は『共同幻想論』において、西欧の父権的な国家観に対して、アジア的な母権的コミュニティを対峙させた。吉本によれば、人間は3つの幻想を構成することで社会的な存在として生きる。自分で理解している自分像=「自己幻想」と、配偶者や家族との関係性=「対幻想」、そして天皇性や、民主主義のようなイデオロギー=「共同幻想」。この3つだ。吉本は、「天皇制」や「戦後民主主義」のような、自らが拠って立つ大樹=イデオロギー=共同幻想に依存することなく、そこからの自立を訴えた思想家だ。国家レベルの幻想に依存(同化)し自分が大きくなったような錯覚に生きるのではなく、家族的な対幻想の領域に足場を置くべきだと考えた。吉本は、この身近な私たちの生活の領域を「大衆の原像」と名付ける。「大衆の原像」は、丸山真男の「無責任の体系」に対する批判的応答として提起されている。丸山は、戦後日本社会の主体性の欠如を批判しその性格を「無責任の体系」と呼んだ。明確な意思を欠いたまま互いに空気を読むことで意思決定される日本型社会を批判し、そこにイデオロギーを注入することで、大衆ではなく近代的市民として自立することを唱えたのだ。吉本的に言えば、丸山は「共同幻想の積極的肯定者」ということになる。それに対し吉本は、例えば、デモに行くような意識高い系の「近代的市民」(丸山的自立)ではなく、デモが行われているそのさなかに、デモに出動した市民を客に「出店」を出して日銭を稼ごうとする「大衆」に立脚すべきだと考えた。
両者とも、自立した主体であれと訴える。丸山は、そのために共同幻想への積極的同化を、吉本はそこからの「自立」を唱える。ここに、目を逸らしてはいけない点がある。吉本は、対幻想に足場を置くことでイデオロギー(共同幻想)からは自立することができるだろう。しかし、そうすることで、かえって、出店を仕切る何らかの集団に再び埋没することになる。デモの現場で他人が勝手に出店したり、了解を得ずに利益を独占するような商品を売ったとしたら、その店は間違いなく潰される。その排除を行うコミュニティに参加しているなら、共同幻想からの自立は再び別の思想への依存と区別できなくなるのだ。丸山的な理想論に対し、ただ「大衆の原像」を対置するだけでは自分の頭で考えたことには到底ならない。依存から脱することは簡単ではない。この2人の対話の核心は、議論を重ねる中で彼ら自身がそのことの自覚を深めたところにある。寄りかかるものがなければ生きていけない人間には寄りかかる「何か」が必要なのであり、それが右であるか左であるかは本質的な問題ではないのだ。彼らの対話は、現在の私たちのSNS上のコミュニケーションの死角を的確に表現している。それは、SNSの閉じた相互評価のコミュニティにおける安易で肥大化した自己幻想の表現が、フェイクニュースにも単なる扇動的な動員にも抵抗力を持つことができずに、簡単に共同幻想に同化(依存)してしまい、フィルターバブルを起こすということだ。いざそうなったとき、自立的な思考を回復することは難しい。フェイクニュースを人々が信じるのは、それが正しいと判断するから、あるいは、ウソであると気づかないからではない。そうではなく、そこに埋没して考えることをやめるのが心地よいからだ。真に問題とすべきは、それを望んでしまう私たちの欲望のほうにある。ただ、誤解しないでほしいが、フェイクニュースの検証と批判が不要だと言いたいわけではない。前提としてそれは必要だが、それだけでは決定的に足りないのだ。
しかし、吉本はやはり偉大だった。自立を求める思考が依存に巻き込まれるだけでは終わっていない。吉本は、実は、<共同幻想への依存か><対幻想への依存か>の二者択一を単純に迫ったわけではない。そうではなく、共同幻想から対幻想へと視線を向き換えるときに、依存が一時的に失効し、自己の依存的性質が丸ごと視界に入ってくることに注目していたはずだ。視線を向け直そうとするその瞬間に、デモに参加する意識高い「市民」と、彼らに食べ物を売る出店の「大衆」にという、二者択一に見えていた世界が、選択肢を生む問題そのものが絡み合う現実とともに、一時的にではあれ眼前に開けるはずだ。私たちの「外」の現実だ。だが、ほとんどの場合は、AではなくBへと依存先を変更することで、再びこの現実は閉じられてしまい私たちはそれに気づかない。この現実が開けた瞬間、私たちは、実は問題設定から改めて思考し直す可能性にも開かれているのだが、依存先のない状態に人は不安を覚えるので、すぐに依存先を変更し現実は閉じられる。吉本の共同幻想論のメッセージは「依存の一時的な失効」の意味、一瞬の現実の開示にこそあるとも解釈できる。だからこそ、吉本は、次作『ハイ・イメージ論』では、対幻想ではなく自己幻想へと足場を変えたし、絶えず立脚点を模索し続けたのだ。
5.もう一度、「モノ消費」へ
さて、依存の一時的失効を介すことなく自立の可能性について語ることはできない。SNSの閉じる力から一時的にでも私たちを自由にしてくれるもの。それは何か。それは、自分の「外側」の文化現象に他ならない。私たちの社会は、モノ消費から必然的にコト消費へと移行したが、もう一度、自分の「外側」の文化現象によって、つまりモノ消費によって自分の世界理解が異化されるような経験が固有に持っている快楽に目を向ける必要がある。それは自分のストーリーを語る快楽より、遠くにあり、難しい快楽であるが、おそらくは、自分のストーリーを語るようなお手軽な快楽よりも、もっと強度と深度を備えた快楽であるはずだ。依存を失効させ、世界が多様化し、そうすることで未来に残すに値する言葉が胎動を始めるような世界経験の深化。
こうした、世界を深く掘る眼なしには、毎日のように舞台に触れようとも、世界の果てまで旅行しようとも、それをSNSで発信し「いいね」をもらうことを目的にするほどに、言葉は画一化され、凡庸になり、世界を視る眼は鈍る。そうして、そこで語られているはずの「自分のストーリー」は、ほとんど誰のものでもない画一的なものになる。
私たちは、文化現象の経験を、目の前の世界から意味を読み取り、そうして世界を刷新する言葉を取り戻す経験へと回復させるべきではないか。各々がそうして時間をかけて熟成した言葉をSNSで発信し、そして受け取り手も丁寧に距離を取って読みとることができるようになれば、SNS上のコミュニケーションは、20世紀的なモノ消費から、いま現在私たちが生きているコト消費を経て、もう一度接続し直された「モノ消費」として経験することもできる。いわば21世紀的にアップデートされた「自分のストーリーを語る快楽」だ。インターネットの登場によって本質的に掘り起こされた、私たちの「発信する快楽そのもの」はやはり悪ではないはずなのだ。
感染症という世界規模の危機から私たちは何を持ち帰ることができるか。それは、誰もが書くこと、すなわち自己幻想を表現することが当たり前になった時代に、自立した、未来に残すに値する言葉、世界にポジティブなものを投げる言葉とは、いかなる言葉であるのかを探り直すきっかけにすることだ。その言葉は、自立すること、自分の頭で考えること、と言い換えてもいい。この感染症騒動を、それをもう一度考え直す契機にすること、それは、21世紀的なコト消費を迂回してもう一度取り戻されたモノ消費において実現するのではないか。このコラムのタイトル、『もう一度「モノ消費」へ』にはそんな想いが込められている。
(2020/4/15)
————————-
多田圭介( Keisuke Tada)
北海道大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。専門は、哲学・倫理学、音楽評論。評論の分野では、新聞や雑誌等に定期的に音楽評やコラムを寄稿するほか、市民向けのクラシック音楽の講座等も担当している。また、2018年に札幌地区のクラシック音楽&舞台芸術の専門批評誌「さっぽろ劇場ジャーナル」を立ち上げ、執筆と編集の責任者を務めている。現在は藤女子大学講師、ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員、さっぽろ劇場ジャーナル編集長。