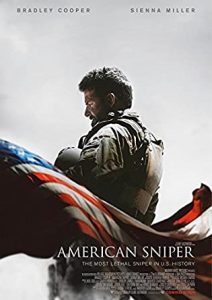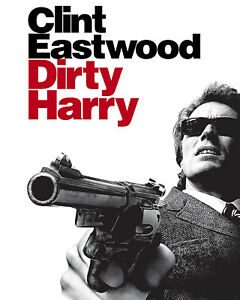小人閑居為不善日記|ハリウッド・スタンダードの行方――《パラサイト》と《リチャード・ジュエル》|noirse
ハリウッド・スタンダードの行方――《パラサイト》と《リチャード・ジュエル》
Parasite and Richard Jewell
Text by noirse
1
リッパだけど、そんなにオモシロイ作品が選ばれるわけではないと思っていた「アカデミー賞」。C・イーストウッドの《許されざる者》が選ばれた時は、もうまるで自分のことのようにうれしくて、眠れませんでした。
マンガ読みにはおなじみ、《ジョジョの奇妙な冒険》の単行本(33巻)のカバー袖に掲載された作者・荒木飛呂彦のコメントだ。荒木は映画についての著書も刊行するほどのマニアだが、社会派や文芸ものなどの「リッパ」な映画より、サスペンスやホラーなどの娯楽作品を好んでいる。娯楽映画のファンには、アカデミー賞はこのような認識なのだろう。
確かにアカデミー賞は「リッパ」な映画に与えられる賞だ。だが立派さというのは(なんだってそうだが)、杓子定規に図れるものではない。時代や状況に即して価値基準は変わっていく。
アカデミー賞授賞式の前に書いた先月の本稿で《パラサイト》(2019)を取り上げたが、ノミネートはされても大穴程度だろうと構えていたので、作品賞まで受賞したのには驚いた。けれどもそれは、韓国映画が受賞したなどの理由からではない。ハリウッド業界人のポリティカル・コレクトネス(PC)、「社会的弱者」への「忖度」「お気持ち配慮」がそこまで来たという事実に驚いたのだ。
2
この連載でも何度も書いてきた通り、ここ数年のアカデミー賞は、それまでの白人男性優位だった時代へのカウンターとして明確なリベラル志向、ダイバーシティへ傾斜している。特にトランプが大統領選を勝ち抜いた2017年以降は《ムーンライト》(2016)、《シェイプ・オブ・ウォーター》(2017)、《グリーンブック》(2018)と、有色人種差別やジェンダー問題をテーマにした作品の受賞が続いていた。けれど昨年の《グリーンブック》は、結局白人にとって都合のいい黒人しか出てこないとして、強く批判もされていた。
そこで《パラサイト》だ。韓国の製作で、韓国のスタッフによる、韓国人キャストのみが出演した、韓国語の映画。《パラサイト》には白人の影なぞ微塵もない。失墜しつつあるアカデミー賞の名誉を挽回するには、《パラサイト》の受賞こそふさわしい。文句のつけようがない「リベラル」で「ダイバーシティ」な結果だ。
もちろん《パラサイト》がつまらないわけではない。韓国映画全体の底上げが著しいのも確かだし、監督のポン・ジュノは、韓国はもちろん世界でもトップを走り続けている才能だ。けれど他のノミネート作品、《1917》(2019)や《ジョーカー》(2019)とそう差があるとも思えない。
荒木の言葉を借りれば、アカデミー賞は「そんなにオモシロイ作品が選ばれるわけではな」く、より「リッパ」な作品が受賞するものだ。いや正確に言えば、「どの作品が受賞すればアカデミー賞とその会員がリッパに見られるのか」が重要なのだ。
「《パラサイト》がオスカーを欲しがる以上に、オスカーが《パラサイト》を欲しがっている」。批評家のジャスティン・チャンが授賞式以前にコメントした言葉ほど、今回のアカデミー賞の状況を見事に言い当てた表現はないだろう。
3
アメリカ民主党の大統領候補者争いはサンダースとバイデンの一騎打ちの様相を示してきたが、どちらになってもトランプの再選は止められないと見る向きは多い。となると当分、ハリウッドの「忖度」ムードも続いていくに違いない。
これはハリウッドだけの傾向ではない。強まる一方のPC的配慮については、しばらく前から好ましく思わない人が増えている。
その一例がキャンセル・カルチャーだ。PC的に好ましくない表現や発言が炎上し、不買運動や活動自粛に繋がる現象を指す。ハーヴェイ・ワインスタインのセクハラ問題などはキャンセル・カルチャーが「正しく」発揮された例だが、過去の発言を掘り起こされ、ディズニーから解雇されたマーベル映画の監督ジェームズ・ガンなどの場合は過度に感じられた(その後復帰したが)。そして最近その対象となったのが、クリント・イーストウッドが監督した《リチャード・ジュエル》(2019)だ。
リチャード・ジュエルは実在の人物で、1996年のアトランタ・オリンピックで警備員として職務中に爆弾を発見。爆破テロから市民を守ったにも関わらず、その後一転してFBIやマスコミから容疑者扱いされてしまった。実在の事件に材を取った社会派ものという、アカデミー賞好みの作品だ。
だが《リチャード・ジュエル》はアカデミー賞の本選には残らなかった(助演女優賞でのみノミネート)。実在する記者の行動が正確でなく、女性蔑視的に描かれており、さらに彼女は亡くなっているため反論もできないなどの点が問題視されたのが影響したのだろう。そのせいか興行も失敗、予算さえ回収できない始末となった。典型的なキャンセル・カルチャーだが、その対象がイーストウッドだったというのは今回の興味深い点だ。
1930年生まれで今年90歳を迎えるイーストウッドは、もはや伝説の存在になりつつある。セルジオ・レオーネとドン・シーゲルという巨匠の現場で映画作りを学んでおり、それにより得られた演出力の評価はすこぶる高く、一部では現役監督最高峰の如き扱いを受けている。いわば100年余に渡るハリウッドの、伝統の継承者なのだ。
一方共和党支持者としても有名で、作品からも保守的な思想が容易に見て取れる。リチャード・ジュエルも映画では、もともと国家に献身的な価値観の持ち主だったがFBIに裏切られて個人の自由を重んじる自由主義者へと変化するように描かれている。いかにも保守層が好みそうな話だ(保守主義者がイコール国家主義者とは限らない)。
《ダーティハリー》(1971~)シリーズでイーストウッドが演じたキャラハン刑事は黒人や女性への蔑視を隠そうともしないし、《ハートブレイク・リッジ 勝利の戦場》(1986)は海軍の協力を得て製作された。タリス乱射事件の際犯人に抵抗したアメリカ人を描いた《15時17分、パリ行き》(2018)も《リチャード・ジュエル》と同種の英雄譚だし、イラク戦争の伝説の狙撃手を取り上げた《アメリカン・スナイパー》(2014)は、政治的に曖昧な態度を取った結果、多くの論争を呼んだ。
とはいえイーストウッドは強硬な右派ではなく穏健派だ。同性婚や妊娠中絶にも寛容で、イラク派兵には反対していた。86年にはカーメルの市長まで勤めているが、リベラルな気風のカリフォルニア州で支持されたこと自体が、彼のポジションをよく示している。
だから前回の大統領選中にトランプを擁護するような意見を述べたときは、少なからず波紋を呼んだ。といってもトランプに対してはレイシストだと簡単に切り捨てている。注視されたのはトランプと絡めて出てきたPCへの苦言だ。みんな心の中ではPCにはうんざりしているし、多少のことでも昔は差別的などと騒がれなかった、トランプはくだらない人物だが、必要以上に責めすぎだ――。現在の風潮からすれば老害とも取られかねない発言ではある。
キャラハン刑事は、差別的な態度を取っても、根っからのレイシストではない。気が合えばどこの誰だろうと信頼し、友情を結ぶ。取っ付きにくく、口が悪いだけなのだ。イーストウッドは「キャラハン刑事」から少しも変わっていない。けれど今、キャラハンのような男に居場所はない。
《ダーティハリー》は、今ではごく普通に見られる「一匹狼の刑事が上司や組織に反発し独自に犯人を追う」という刑事アクションの先駆のひとつだ。法で裁けない凶悪犯を、キャラハンは容赦なく射殺する。こうした超法規的行為も映画では許されるし、観客はそこにこそ共感し、留飲を下げる。《ダーティハリー》のヴィジランティズム(自警主義)やリバタニアニズム、マッチョイズム、差別的な言辞は散々批判されてきたが、彼が切り拓いたキャラクターや価値観は、結局ハリウッドの、いや世界のスタンダードとなった。
4
イーストウッドはまったくブレていない。それどころか、50年近く経っても変化のない彼の作品こそ、ハリウッド映画の中心的な価値観を示していたといっていい。記者の問題さえなければ、《リチャード・ジュエル》も「ごく普通のアメリカ映画」のはずだった。しかし2020年の今では、もはや「ハリウッド・スタンダード」ではないのだろう。
イーストウッドの作品をことさら持ち上げるつもりはないが、こうした映画が評価されにくい「空気」も好きではない。業界人は《パラサイト》を評価するかもしれないが、一般のアメリカ人は韓国映画に興味はないし、イーストウッドのようなかつての「スタンダード」を望む者もいるはずだ。考えすぎかもしれないが、もしこれから「昔日のスタンダード」が許されにくい時代が訪れるのだとすれば、それはそれで不自由なことではないのか。
リチャード・ジュエルは国家や市民に迫害され、自由に目覚める。もともと自由主義者だったイーストウッドも、自分の方法論を変えなかった結果、周囲と齟齬を来すようになってきた。イーストウッドは今、自らが描いた《リチャード・ジュエル》そのものの状況に置かれている。けれどこのような作品を好む観客から、「リッパ」なハリウッドの業界人やアカデミー賞が距離を置くとすれば、これもまたひとつの断絶だ。そういう状況こそ、トランプの快進撃の一因にもなっているのではないだろうか。
(2020/3/15)
—————————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中