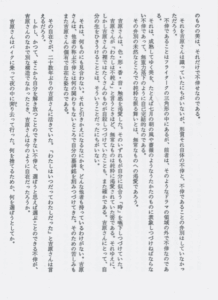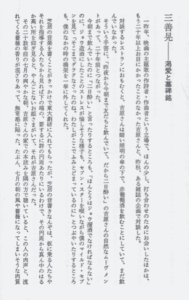評論|三善晃の声を聴く(7)青春譜|丘山万里子
(7) 青春譜
Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)
【朔太郎世界で〜三善晃と吉原幸子】
◆三善晃の決闘
第4回で三善が『トルスⅡ』に連なる一つの物語として『決闘』を独自に編んだことを指摘した。そこにはどんなVISION、あるいはコンテクストがあったのか。
『トルスⅡ』における《殺人事件》は玻璃(はり)の衣裳の探偵が恋人殺しの犯人を追う追走劇。《見えない兇賊》は、しろがねの服を着こんだ覆面片目の兇賊、その背後に迫る未知の犯罪を描く。「ぴすとる」「玻璃」「まっさをの血」「きりぎりす」「大理石」「白金」「片目」といった言葉の持つ喚起力。
一方、『決闘』は《霊智》でのやはり「ぴすとる」発砲、「金の山脈」「黒曜石」、《白夜》では手に銀の凶器をかざす輩、「微光」「柳」、最後の《決闘》は緑の中、光る靴、手に刃の決闘でのわが肉の歓喜。「みどり」「光」「魚」「刃」といった言葉の連なりだ。
『トルスⅡ』『決闘』いずれも「殺人」というモチーフを、くっきりした色彩で縁取る絵柄である。朔太郎にとっての殺人とは、「誰か」の殺害ではなく、内なる「自分」だ。歌人河野裕子が「探偵」と「曲者」を「自我分裂を起こした結果の分身」と呼んだように。「決闘」もまた刃を合わせ、額に傷を負い、けれども緑を踏んで「ああ、いまするどく鋭刃(やいば)を合せ、手はしろがねとなり、 われの額きずつき、 劍術は青らみつひにらじうむとなる」(原文第2連)。朔太郎は我が分身をぴすとるで撃ち、刃を振り上げ流す血はまっさをに氷結する。
だが、この第2連以降の詩節を三善は捨てた。第1連の「よろこび樹陰におよぎ」からプレストのまま突っ走り、「黒曜石」や「ラジウム」に凍結することなく滾る熱情をいっさんに虚空へ放り上げている。思うに三善はそうやって、自らの「青春」を脱ぎ捨てたのだ。
彼にとっての決闘は、自身に巣食う朔太郎的「蒼白い自我」であったのだろう。
◆吉原幸子の《兇器》
朔太郎の自我分裂世界に、少女期からとっぷり浸っていたのが東大演劇研究会仲間だった吉原幸子だ。やはり高校で演劇部、同級生に女優の荻昱子、朗読家の幸田弘子(三善の兄、音楽評論家三善清達と結婚)、2年後輩に宝田明がおり、大学ではサルトルやブレヒトなどの現代劇に出演した。留学直前の三善がその舞台音楽を担当しているのは前回述べた通り。
彼女が第一詩集『幼年連祷』でデビューするのは1964年(三善『決闘』と同年)だが、そのほぼ10年後の1973年、朔太郎世界を色濃く映す《兇器》(第四詩集『昼顔』所収 p.22 )を見たい。
《兇器》
溶かしたくない
溶けたい
吸ひこみたくない
吸ひこまれたい
殺したくない
死にたい
でも殺したい
溶けるために
ああ 血 ぴすとる ないふ
わたしの持てないたくさんの兇器
ことに刃もの
のしろい光
つきたてたい 世界に すべてに
つきたてることによって加はりたい
吸ひこまれたい とどかないすべてに
つきたてることによって殺されたい
いま 血を流す雲のまへに立って
血を流すあなた
わたしの持てないたくさんの 死
吉原もまた、自我分裂にあり、我が分身(彼女の場合、それは「あなた」ともなるのだが)を持て余しているようだ。
ちなみに吉原の本格的詩作は大卒の年(1956)に仏文系出身者の同人誌『沙漠』への寄稿からで、『幼年連祷』のいくつかはすでにそこに掲載されている。1962年、『歴程』同人となった。朔太郎傾倒については、のち、自宅本棚にピストル(いわゆるモデル・ガン)と刃物の類が飾ってあった、と谷川俊太郎が回想している(『現代の詩人12 吉原幸子』p.217)。
本作に見る彼女の詩句の運び「ことに刃もの のしろい光」という行替えの呼吸(強調)は、他作にもしばしばあり、独特のリズムを生む。「〜〜たい、たくない」の反語フレーズも一貫した語法の一つ。
◆三善晃の自作詩歌曲『北恋ひ』
同じような詩風を、筆者は三善の自作詩歌曲の第1作『北恋ひ』(1961/ソプラノとピアノのための)に見る。『北恋ひ』は『トルスⅡ』と同年、帰国後の作品だが、かなりの数の自作詩作品の中で、これだけぽつんと一つ書き置いた青春譜のようだ。歌人朔太郎少年期のポエジーに似る古典的な抒情世界。いかにも素朴な懐疑の句も微笑ましいが、吉原の反語フレーズはこれに近い。ここに挙げておく。
『北恋ひ』
一)
風見 葉隠れ
陽炎 巣懸け
玻璃 葉裏より
四季の 葬列(とむらひ)
夕べ ひば病み
石英 蒼み
彼処(かしこ) 海戦の
匂ひ いちめん
二)
といふやうな季節(とき)には
一夜(ひとよ) 北恋ひにぬれそぼり
シマウマノシマモヨウハ
クロジニシロナノカ
シロジニクロナノカ
と 考へて居よう
押韻、リズム、アウフタクトや行替えによる詩句の強調、色彩、漢字・カタカナの配分の妙、シマウマ模様疑問などなど、詩句を眺めるだけでもその転調具合や呼吸が分かろう。とりわけ第2連の漢字、ひらがな、カタカナの使い分けは、日本語表記の視覚面への明確な意識を伝える。音声的には、母の読み聞かせの声が聞こえるような、まさに日本語のカダンス世界。初演は畑中更予でピアノも三善本人が弾いたが、ピアノパートには何も書いていなかったとのこと。参照自筆スコアもスケスケで、ピアノに達者な三善らしく「高度に易しい」即興であったと思われる。


と、こう、三善の『北恋ひ』、吉原の『兇器』を眺めると、年代こそ隔たるが、創作世界は映じ合っているように思える。演劇部での「演者」の語り・身振り、その演者に「音楽を書く奴」の語り・呼吸。互いの朔太郎を通し、詩歌の上でも響応する世界があったのではないか。
詩歌は古来、朗誦・朗詠されるものであったことを思えば、彼らはこの時期にその本源を無意識にせよ模索、三善いうところの「イメージに、いろいろな菌を仕込み、培養していた」のだ。吉原はその後、朗読詩を書き(1968)、「詩の朗読とジャズの会」で朗読に参加(1972)、谷川俊太郎とのジョイント・コンサート「うたから詩(ことば)へ/詩(ことば)からうたへ」第1回公演(1982)へと歩む。
一方、三善の「語り」へのこだわりも『遠い帆』にあきらかなように、終生変わることはなかった。
前回触れたが、三善のパンフレットでのコメント「そこで人が死につつあったら、可愛いハモニカを吹き、和やかな炉端では、低絃で增四度を撥いてあげよう。劇音楽のモラルは、傍観者の諦観から出発して居る様ですから。」に、彼の劇音楽創作姿勢が伝わると同時に、彼らが求めた「表現としての“声”と“言語”」の姿が筆者には浮かんでくるのである。
◆吉原幸子の《これから》《黒い夜に》〜青春の通奏低音「希死願望」
さらに、もう一つ、芥川の『河童』の詩人トック、あるいは芥川自身の自死、朔太郎、三善ら、青春の通奏低音たる「希死」願望、「生まれること 生まれないこと」「生まれたこと 生まれなかったこと」の無限の振り子にうずくまる胎児の感覚を思わせる吉原の《これから》と《黒い夜に》を挙げておく。こちらは『幼年連祷』と同年、対の詩集『夏の墓』(1964)収録の作品だ。(『現代の詩人12 吉原幸子』p.61〜62 )
《これから》
わたしは 生れてしまった
わたしは 途中まで歩いてしまった
わたしは あちこちに書いてしまった
余白 もう
余白しか のこってゐない
ぜんぶまっ白の紙が欲しい 何も書いてない
いつも 何も書いてない紙
いつも これから書ける紙
(書いてしまへば書けないことが
書かないうちなら 書かれようとしてゐるのだ)
雲にでも みの虫にでも バラにでも
何にでも これからなれる いのちが欲しい
出さなかった手紙
うけとらなかった 手紙が欲しい
これから歩かうとする
青い青い野原が欲しい
これに続くもう一作《黒い夜に》は、生々しく暗い。その一部を。(同上p.62~64)
《黒い夜に》
わたしは駆けぬける 愛の間を
虚しかった すべての間を
もう要らない 何も かなしみさへも
思い出したくない わたしが生きてゐることを
ああ むごたらしい 凹みに 凹みに
わたしは虚しさの卵を宿した
虚しいものと 虚しいものとから
虚しくないものの 生れる筈があらうか
――中略――
もう 要らないのに
それでもわたしは 生みおとす 黒いよるに
血のやうに
黒い卵を
「生まれてしまったわたし」という意識こそ、彼らに共通する青春の「純粋病」「小児病」(吉原いうところの)ではなかったか。芥川『河童』の胎児の自殺のように「生まれたくない私」の裏返しとしての「生まれてしまったわたし」を思うなら、その通奏低音たる「希死願望」はここにも響いている。『凶器』の「つきたてたい」「殺したい」「つきたてることによって殺されたい」の声は、すでにこれらの詩に聴こえていよう。
ちなみに吉原は『幼年連祷』は白い本、『夏の墓』は黒い本、2冊で1冊(ポジとネガ)と語っており、『夏の墓』については「このひとりぼっちの相聞歌を、誰でもなく、誰であっても良い(あなた)に捧げる。さうして別れを告げる」(『詩人 吉原幸子 愛について』p.39)とNOTEに記している。彼女は自作詞解説として創作にまつわる恋愛模様を「告白」する性癖があり、詮索すれば色々出てこようが筆者にそういう興味はない。ここではその作品に青春の通奏低音「胎児の自殺」「希死願望」が流れていることだけ、指摘しておく。
* * *
【青春譜】〜谺する声声
◆『オンディーヌ』
『トルスⅡ』から『決闘』の間にある2つの放送詩劇『幸福な王子』(ワイルド原作、台本・作詞:谷川俊太郎)と『オンディーヌ』(フーケ原作、岸田衿子詩)にも触れておく。いずれも1959年、NHKによる放送詩劇で、NHKに在職していた兄、三善清達を通しての仕事であったと思われる。
『幸福な王子』のスタッフは以下。
幸福な王子:幸田弘子、ツバメ:里見京子、語り:篠田英之介、東京放送児童劇団、管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団、指揮:石丸寛。
三善の音と谷川の詩句の最初の遭遇である。
谷川は哲学者谷川哲三の息子で2歳年上だが同じ杉並に生まれ育ち、環境的には似たもの同士と思われる。彼との最初の歌曲『かっぱ』(1976/声とピアノのための)は「かっぱかっぱらった かっぱらっぱかっぱらった」(なぜか「かっぱ」だ)といった言葉遊びの歌。谷川と三善の協業はここから最後の合唱作品『その日―August 6』(2007/混声合唱とピアノのための)まで続く。声とオーケストラ領域では『三つのイメージ』(2002/童声・混声合唱とオーケストラのための)が最終作で、青春期から最晩年まで、声と言葉と音の旅のおそらく最良の同伴者であった。
 一方、『オンディーヌ』のスタッフは以下。
一方、『オンディーヌ』のスタッフは以下。
構成・音楽:三善晃、詩:岸田衿子、歌唱:友竹正則(Br)、語り:山本安英、幸田弘子、岸田今日子ほか。演出 : 三善清達、技術 : 浅見啓明、演奏:森正指揮 NHK交響楽団、女声合唱団、本荘玲子(オンドマルトノ)、鈴木清三(ob)、NHK電子音楽スタジオ。芸術祭賞、イタリア賞受賞。
この2作の参加メンバーを見ると、青春期の演劇に集った若者たち誰もが「イメージに、いろいろな菌を仕込み、培養していた」ことが知れよう。なお、作詩の岸田衿子は後年のTVアニメ『赤毛のアン』(1978)の主題歌・挿入歌の折も担当している。
三善についてなら、幻のオペラから『遠い帆』までは確かに長い道のりであったが、詩劇(オペラ)作家としての彼の目指すところは一貫している。
『オンディーヌ』はフランスの劇作家ジャン・ジロドゥの戯曲で1939年にパリ初演。だが、三善の『オンディーヌ』はジロドゥ作ではなく、原作であるドイツのフリードリヒ・フーケ『ウンディーネ』を用い、岸田衿子が作詩したもの。いずれにしても水の精霊オンディーヌと人間の騎士ハンス(本作ではポール)との悲恋物語である。プロローグ、第1部:オンディーヌとポールの恋、第2部:人間界でのオンディーヌとポール、第3部:ポールの死によるオンディーヌの永遠の恋の成就、エピローグの構成で、ホワイトノイズやパルストーンなどを使用、幻想性を高めている。オーケストラと合唱が背景を美しく描き出し、歌唱と語りが物語を進める。スコアを見ると三善の電子音響のための細かい指示が書き込まれており、新たな音響材料への彼の熱中ぶりが伝わってくる。
「選ばれた一つのクリック音から、望みの効果音を一つつくり出すのに、徹夜。それらを数台の機械にかけ、それに一人ずつのプロデューサーがつき、さて、合成録音、となれば、ロケットの打ち上げよりもおおごとだった。」「中学時代からやっていた芝居づくりを、音でできたことが何よりも嬉しくて、熱中した。」(『遠方より無へ』p.112~113)


なお、吉原は三善『オンディーヌ』の13年後、1972年第三詩集『オンディーヌ』を上梓、そのNOTEの最後には「私にとって、詩とはいつも、遺言のやうなものであった。」とある。
三善はこの年、『レクイエム』を世に出している。
◆吉原幸子《選択》と三善晃《渇愛と墓碑銘》
 三善と吉原の協業は唯一、1978年映画『翼は心につけて』で。
三善と吉原の協業は唯一、1978年映画『翼は心につけて』で。
主題歌作詞:吉原幸子、作曲:三善晃、歌:横井久美子、監督:堀川弘通。原作は関根庄一著『翼は心につけて―ガンと闘って死んだ十五歳の少女が教えてくれたこと』(一光社)。
同年、吉原は第七詩集『夜間飛行』(1978/思潮社)を出版、そのうちの第2章《選択》の一部を拾っておく。(『現代の詩人12 吉原幸子』p.212)
《選択》
〈世界に深入りしたくない〉
と言った さびしいひとは
逃げて行った たぶん
もうひとつの“世界”のはうへ
――中略――
(掌の傷を 舐めながら)
逃げて行ったひとに
電話をかける
〈死んだあとの 幸せの味は
いかがですか
こちらやっと不幸
まだ 肥りすぎてゐないなら
会ひませう いちど〉
この3年後出版された『吉原幸子全詩Ⅰ・Ⅱ』(1981/思潮社)の栞に、三善は《渇愛と墓碑銘》という短文を寄せている(2012年復刻版付録小冊子「吉原幸子 人と作品」には草野心平、粟津則雄、谷川俊太郎、白石かずこ、三善晃の短文が収録)。
いかにも難解な三善節だが、ここにその一部を引く。
《渇愛と墓碑銘》
一昨年、映画の主題歌の作詞者、作曲者という立場で、ほんの少し、打ち合わせのためにお会いしたほかは、もう二十年以上お目にかかったことのなかった吉原さんと、昨秋、ある雑誌の企画で対談した。
――中略――
芝居の音楽を書くことがきっかけで東大劇研に入れてもらったが、芝居の音書きなんぞは、板に乗る人たちやそれを指導する人たちから見れば下っ端の、要するに群の円周あたりにいるわけで、その円周から真ん中のはるか高い所を仰ぎ見ると、やんごとないお姫さまがいて、それが吉原さんだった。
その二十数年前の7月の爽やかな朝、吉原さんの家での本読みを隅の方で聴いていると、この人の肉声と、流れてくる薔薇の香りが混ざりあって、無感覚に陥った。たぶん、7月の朝の風や薔薇になってしまいそうな内質のものの美は、それだけで不倖せなのである。
――中略――
吉原さんは、色・香・音・触感を渇愛した。そのいずれもが自分に似合う「時」を嚥下し続けていた。
吉原さんが「私は不純よ」と言う時ほど、無常なものは純粋に渇愛されていた筈である。それゆえに、しかし吉原さんの裡ではたくさんのものが自殺し続けていたことも、また確かである。吉原さんにとって、自分の生を引き受けることとは、そういうことだったにちがいない。
――中略――
吉原さんは、他者の称ぶ不倖とは何の関わりもないところで自分の墓碑銘を刻み続けてきた。
そのための苦しみもまた吉原さんの個有で自在な姿なのである。
――中略――
しかし、かつて、そこから自分を解き放つことのできない不倖と、選ぼうと思えば選ぶことのできる不倖が、吉原さんの中で別な構造でなかったとき、吉原さんは今のように自在だったろうか。
吉原さんはバイクに乗って夜の中に奔り去って行った。何を捨てるためか、何を選ぼうとしてか。
時空を超えて、谺する青春の声声が聞こえようか。
* * *
【悲しき決闘】
朔太郎、三善、吉原。それぞれの青春の「決闘」。
そこに通底するものは何か。
朔太郎には『悲しき決闘』(『純正詩論』1935)という小論がある。
親友の室生犀星との詩をめぐっての喧嘩(論争)を八百長、という人々に強く反駁し、こう綴る。
僕にとつては日本に生れた自分のライフを決定すべき、必死の宿命的の爭鬪である。室生君勝てば僕が亡びる。僕が勝てば室生が亡びる。東洋精神か西洋精神か。俳句か抒情詩リリックか。僕と室生の對立したこの世界は、互に兩立できない世界であり、地球の南極と北極である。しかももつと悲しいことは、二人が互に親友であり、その上にも文學する精神の第一義感を、ぴつたり一致してゐることである。僕は室生君の文學は(詩も小説も含めて)日本で一流の者だと思つてゐる。東洋精神のすぐれた善さが、室生の文學について一番よく解るのである。そしてしかもその東洋精神は、僕が射撃する標的なのだ。こんな矛盾したことはない。こんな悲しいことはない。
僕と室生犀星とは、いつも必死の捨身になつて、刀のツバをせり合はせてゐる。どつちか引けば、引いた方が切られるのである。――中略――刀の合せたツバの下から、二人は顏を見合せて笑つてゐるのだ。その笑ひの意味することは、お互に何もかも解りきつてる。君を斬る必要もなく、僕が斬られる必要もない、といふのである。こんな悲しい決鬪が何處にあるか。
さらに芥川の自殺当時、室生が朔太郎の身上を憂えたについて、
「今度萩原が死んだら承知しないぞ。靴で蹴つて撲り殺してやる。」この話を聞いた時、僕も腹を立てて「ヒドイことを吐かしやがる。餘計な世話だ。」と呶鳴り返してやつたが、後で考へてみれば、死んだ以上はいくら撲られても無感覺だし、殺されたつても同じことだ。何も腹を立てて怒る必要はなかつたわけだ。室生君には友人が極めてすくなく、親友といへば僕と故芥川君ぐらゐのものである。僕等はツバぜり合ひの刀の下で、永久に默笑し合つてる仇敵である。
「決闘」の標的は我が分身から、真逆の世界を持つ親友へと転じ、かつ、東西精神の対立にあっても両者は根源(詩の世界)で同一、刃の下で黙笑、との自覚に至っている。詩『決闘』から小論『悲しき決闘』までを、青春のセンチメントからリアルへ、と言ってもよかろう。
我が分身とは「感覺でない、激情でない、興奮でない、ただ靜かに靈魂の影をながれる雲の郷愁である。遠い遠い實在への涙ぐましいあこがれである」。この「故しらぬ靈魂の郷愁」「実在へのあこがれ」を、筆者は魂の「飢餓」と言い、洋の東西を超え芸術創造に必須の資質と述べた。同時にそれは明治以降の「西欧に触れることで獲得された“私”(個我)」という認識、つまり西欧近代への日本の恋わずらいとも。(第2回)
日本とは、外来文化の流入にあたり、常に彼の地(インドであれ、中国であれ、欧米であれ)への見果てぬ憧憬に身を焦がす「夢見る青春びと」なのかもしれない。鎖国の年月(と言ってもたかだか210年ほど)から怒涛の開門、明治文豪期から朔太郎ら口語自由詩時代がどれほど気負ったものであったか。「戀を戀する人の愁(えれじい)」(朔太郎)が彼らの主調であり、その拠ってきたるところは、「日本に生れた自分のライフ」への悲嘆。ありていに言えば、かの憧れの地に生まれたかったのに、あろうことか日本に「生まれてしまったわたし」という恨み節。この種の自己否定、引き裂かれ方、そこから生じる希死願望は、やはりこの時代特有の、かつ今なおその尻尾あたりに居る日本最後のインテリゲンチャの恋わずらいとも言えよう。
いや、その底をさらに覗き込むなら、詩人たる朔太郎の「僕等の孤獨な詩人の嘆きが、文壇の一部にも共通する嘆きであり、日本現代文化の矛盾と悲劇を内容するところの、痛ましい實相」であり「“我等何處へ行くべきか”といふ標題は、必ずしも詩人ばかりの標題ではない。小説家も評論家も、日本のすべての智識人種は漂泊者である」との悲嘆は、とどのつまり、「日本語」による文学表現(西欧近代モデルに倣う)への絶望、「声を言葉(日本語)にする」ことの困難であったという気がする。
ともあれ、朔太郎は『氷島』で詩作を捨て評論へと転身、日本主義(と呼ぶのは適切とは思えぬが)へ回帰、若き詩人の苦悩を卒業、敗戦を知らずに没する。
一方、三善は少年期を戦時に過ごし、「根こそぎの喪失」を味わい、かつ留学で彼の地の日常にさらに深い喪失を重ね、だからこそ、明治の近代化と昭和の軍国化という朔太郎の時代とは異なる、自分の「リアル」を探す力を得た、とも言える。
明治生まれの朔太郎の「日常」には逃れようなき漢文化圏の素地があったが、昭和の三善や吉原らにそれはほぼない。だが、敗戦による根こそぎ喪失は黒船より決定的だったろうし(観念文化論でなく現実人間論ゆえ)、パリの日常はさらなる疎外で彼を鍛えた。
三善の『トルスⅡ』から『決闘』に至る道のり、その VISIONもまた、朔太郎同様、青春からの卒業であったと言えよう。吉原はといえば、卒業を拒み、ずっと青春であり続けた気がする。そこに筆者は朔太郎が熱く賛美、彼の永遠の青春の少女であった鎌倉時代の恋愛歌人式子内親王を想う。
その2首を引いておく。
「日に千たび心は谷に投げ果てて有(ある)にもあらず過る我が身は」
「見しことも見ぬ行く末もかりそめの枕に浮かぶまぼろしの中」
青春とは、遠ざかってなお、ふいに疼くものではあるけれど。
留学前後、演劇を通して出会った詩人たちは、彼の声・言葉世界の基底となった。
同人誌『歴程』(1935~)は、草野心平・中原中也・逸見猶吉らによって創刊、宮沢賢治、石垣りん、井上靖、入沢康夫、北杜夫、串田孫一、宗左近、高田博厚、谷川俊太郎、中上健次、野上彰、吉原幸子、吉行理恵らが参加している。吉原も谷川も宗もこの輪の中にいた人々だ。
宗左近『河童』(1964)は芥川の流れに浮かぶ。『燃える母』(1967)を読んだ吉原は《非力》(『昼顔』1973 p.74)でこう歌う。
みんなが傷口をもってゐる
《燃える母》を読みかへして
はじめて泣いた
誰にとっても人生胚胎の季節、青春。
生と死の通奏低音を響かせてうねる豊饒の海。
母の読み聞かせから、蒼い声声の呼びかわしの波間に、三善もまた言の葉、音の光粒子をすくい取り、確たる創作の道へと翔び立つ。
そこに『決闘』がある。
それは「表現」としての“声”と“日本語”と“音”への、挑戦の決意でもあったろう。
筆者はふと思った。
パリから帰国の機窓に眺めた羽田が真っ黒、墨絵の世界、「まだ白骨が生々しくその辺に散らばっていて、それを拾い集めて僕なりの墓を建て、銘を刻んで墓守になる」(『波のあわいに』)と三善は語ったが、「墓碑銘」とは、ただ戦時の記憶にとどまるものではなかったのだろう、と。
おそらく、作品そのもの一つ一つが墓碑銘である、という感覚を、彼はずっと持ち続け、だから62年、あんなにも多作であったのではないか。
書いたからこそ、彼はその「希死」を脱することができたに違いないと。
思えば、『弦楽四重奏曲第1番』『三つの抒情』『白く』『ピアノ協奏曲』『嫁ぐ娘に』『合唱物語「金の魚の話」』『組曲「会話」』『聖三陵玻璃』8作のそれぞれが、器楽、声楽、合唱、劇(物語)という各ジャンルでの青春の墓碑銘とも思える。
ちなみに矢代秋雄は『弦楽四重奏曲第1番』を「低回趣味」で「彼がふと足を踏み入れた湿地帯に咲かせた、青いひかげの花だった。が、幸にして、まもなく彼はそこを脱出したか、干拓事業が成功したか、どっちかだったらしい。『ピアノ協奏曲』では、そのようなジメジメ、ウジウジしたヒネた色彩は、めでたくも一拭された。」と述べている。(『オルフェオの死』p.178)
* * *
最後に、三善の自作詩に触れておく。
歌曲は6曲(1961~1976)で、第1作『北恋ひ』を除き、教育出版社の教科書用で『仔ぎつねの歌」など、子供たちが歌いやすいシンプルなもの。「音と言葉を同時に発想することでその制約(教材としての/筆者注)から自由になることができた」「今日の子供たちにとって、母国語とはどのようなものなのか。いや、それは私たちすべての自問でもある」と『三善晃歌曲集』(全音楽譜出版社解説 1995)で述べている。
合唱曲は16曲(1976~2006)で、『貝がらのうた』(歌曲の合唱版/童声とピアノ)から。以降、9作が童声合唱。ちなみに最初の童声合唱作品は『オデコのこいつ』(蓬莱泰三詩 1971)で、『三つのイメージ』(谷川俊太郎 2002)、『みんなみんな』(まどみちお詩 2005)まで、三善が心を託す最も大切な「声」となった。
彼は自作詩について「言葉の“かたち”としての“旋律”が海から立ち上がって見えてくる」。あるいは自分の言葉のほうがやりにくい、「生まれたてで頼りない」し、「“本当にいいのかな”というところ」があると語っている。(『波のあわいに』p.84)
改めて『北恋ひ』を振り返ると、留学後の三善の「母国語」への最初の一瞥が、ここにあるように思う。漢文化圏の押韻、ひらがな、カタカナ表記の配列とバランス。古代から今日へと至る日本語の歴史とその特性への問いと試みがそのまま素直に、自然に形となっている。
模索の始まりは、ここだったのか。
そんな思いにとらわれた。
先般6月に、合唱15作目『葉っぱのフレディ』(2003/混声・童声)の実演を聴く機会があったが、三善の生まれたての声、言の葉の柔らかさ、掌で慈しむような優しさ溢れる名品であった。
(2025/8/15)
参考資料)
◆書籍
『詩人 吉原幸子 愛について』 編集:コロナ・ブックス編集部 平凡社 2023
『昼顔』 吉原幸子 サンリオ出版 1973
『現代の詩人12 吉原幸子』 編集:大岡信、谷川俊太郎 中央公論社 1983
『続・吉原幸子詩集』思潮社 2003
『萩原朔太郎全集 第九卷』筑摩書房 1976 (『純正詩論』萩原朔太郎 第一書房 1935)
『遠方より無へ』三善晃 白水社 1979
『オルフェオの死』 矢代秋雄 深夜叢書社 1977
『波のあわいに』 三善晃+丘山万里子 春秋社 2006
◆楽譜
『トルスⅡ』 音楽之友社
『決闘 ソプラノと管弦楽のための』 音楽之友社 1967
『北恋ひ』 全音楽譜出版社 1961 自筆譜
『オンディーヌ』 音楽之友社 1959 自筆譜
◆ CD
『響層Ⅱ』「トルスⅡ」ほか NARD-5032 藤井宏樹指揮 Ensemble PVD
『三善晃の音楽』Camerata CMCD-99036-8 2008
◆ Youtube
『ソプラノと管弦楽のための「決闘」』
天羽 明恵, 沼尻 竜典 2004
『オンディーヌ』
『葉っぱのフレディ』(部分)
1) 春
2) 夏
3) 秋
4) 冬
5) 雪