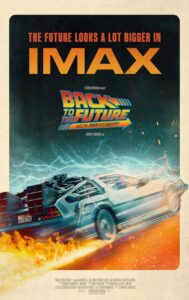特別寄稿|『リビングルームのメタモルフォーシス』と『愛と正義』―二つの音楽劇から|内野 儀
『リビングルームのメタモルフォーシス』と『愛と正義』―二つの音楽劇から
Text by 内野 儀 (Tadashi Uchino) : Guest
Photos by 前澤秀登(『リビングルームのメタモルフォーシス』)
Photos by 宮川舞子(『愛と正義』)
はじめに
『キーワードで読む オペラ/音楽劇研究ハンドブック』(2017)の「日本のミュージカル」(中野正昭)によれば、「1980年代以降に盛んになりミュージカルと似た演劇ジャンルに音楽劇があ」り、「ここでの音楽劇は、音楽や歌を使った演劇の総称ではなく、作家や公演主催が意識的・戦略的に作品名に『音楽劇』と銘打つ場合を指す」。そして、たとえばオンシアター自由劇場の『上海バンスキング』(1979)が、その事例とされる。
–(略)ミュージカルが台詞を歌唱で表現するのに対して、これらの音楽劇では台詞は通常通り発せられ、導入的に劇中歌・曲が多用される。従って、物語そのものは歌や曲を除いても成立する点が、ミュージカルとは異なる。作り手が、既存のミュージカルやオペラとは異なる歌や曲の演劇的利用を形式・方法論として意識していることに特徴をみることができる。(377)
本稿では上記の説明を手がかりに、小劇場系の劇作家・演出家[i]によるふたつの「音楽劇」、岡田利規作・演出『リビングルームのメタモルフォーシス』(2023、以下『リビングルーム』)と、山本卓卓作・益山貴司演出『愛と正義』(2024)を取り上げ、音楽劇というジャンルにおける両作の位置づけと意義を検討する。
新しい音楽劇を目指して―岡田利規と藤倉大の挑戦
岡田はその上演に、これまでも音楽をさまざまに取り入れてきたが、ドイツ・ミュンヘンのカンマーシュピーレにおける『NŌ THEATER』(2017)以降、音楽家・内橋和久との協働で、俳優の身ぶりと語りに音楽を重層的に絡めた音楽劇的作品を追求してきた。これらの作品では、俳優が歌うことはなく、語られる台詞と俳優の身ぶりとの複雑な関係のうちに、内橋の音楽が置かれていたのである。
『リビングルーム』はその延長線上に位置づけられるが、今回はロンドン在住の現代音楽作曲家・藤倉大との初コラボレーションである。コロナ禍の中、リモートによるやりとりを含む創作過程を経て完成した音楽は、ヴァイオリン2、ヴィオラ1,チェロ1、ファゴット/コントラファゴット、クラリネット/バスクラリネット、チェレスタからなる7名編成の室内アンサンブルによって演奏された。しかもその7名は舞台前面に広がって着席し、6名の俳優は、舞台下手奥のリビングルームをイメージさせる空間にいる。そして、この配置のまま、上演は開始される。
物語は、家父長的な〈男主人〉[ii]に支配された女性たちの〈家族〉が、〈リビングルーム=家〉から解き放たれていくという比較的シンプルなもの。ただし得体の知れない〈気配〉(俳優が演じる)が出現し、舞台空間を浸食して装置の具体性を解体していく。その過程で女性たちは、時として演奏家たちの間をぬって舞台前方に進出する。結果、俳優と演奏家が共存するかのような〈曖昧な空間〉が生起し、〈リビングルーム〉のみならず、人物たちの多くもまた、名指すのが難しい何かへと〈メタモルフォーゼ=変容〉してしまう。世界の終わり? 近代家族の終焉? はたまた、現実と虚構の境界崩壊?
このどれでもよいのだが、いずれにせよこのシンプルな物語は、時に具体的な情景あるいは人物たちの心のなか、それとも世界全体の〈不調〉を示唆するような、表情豊かで多様な音色的レジスターの、藤倉による音楽あるいは音の群れとともに語られる。さらに、俳優の特異な身ぶりがそこに加わる。
演出の岡田は、本作の制作過程で、新たな試みを行った。リハーサル段階で、戯曲テクストとは別の言葉を俳優に渡して語らせ、そこで出てきた動きを身ぶりの語彙として出演する俳優に確保してもらったのである[iii]。そして俳優は、自身の記憶にある固有の身ぶりを、本作の戯曲テクストを語るときに、音楽との関係を意識しつつ、半ば直感的に〈引用する〉という複雑な手続きをとって生起した動きをすることになった。
観客はこうして、言葉・身体・音楽が極めて複雑な関係を生起させる瞬間の連なりを経験することになる。藤倉も、本作においては、演劇と音楽の〈割合〉が50対50だったと語っており[iv]、その点が本作における音楽劇の形式的新しさということになる。新しければよいということではないが、その結果としてのきわめてシンギュラーな劇場体験をもたらしたことが、本作の演劇史的意義だと言ってもよいのではないか。
はじめての音楽劇―山本卓卓が大きな一歩を踏み出す。
劇団範宙遊泳を主宰する劇作家・演出家の山本卓卓は、これまで自作の演出を多く手がけてきたが、KAATプロデュースによる新作の音楽劇『愛と正義』では、劇作のみを担当した。演出は劇団子供鉅人の益山貴司、音楽はイガキアキコ、振付に黒田育世というメンバーで、山本にとっては新たな挑戦となった。
本作はKAAT中スタジオの三方を囲む観客席の空間で上演され、場面ごとに簡素な道具や高さのある移動式の櫓が用いられた。基本的には客席と至近距離での演技空間である。
物語はコスチュームをまとったヒーローとして街の平和を守るヒノムラ・コチ(一色洋平)とその妻ソチ(山口乃々華)を中心に進行する。何らかの〈異能〉―コチの場合は風を操る能力、ソチは自身ではコントロールできない予知能力―をもった人物たちが活躍し、二つの世界線と過去と未来が交錯するサブカル・SF的時空が舞台である。
中華街近くの劇場での上演を意識したのか、数日後に来る春節で、コチが従兄弟のウチ(坂口涼太郎)に殺されるというソチの予知夢を端緒に、この世界線に生きる人びとが「愛食み(あいはみ)」なる現象で「愛」を失って暴力的になっていく。その事態に、コチとその仲間のイセガメ・カレ(福原冠)とその恋人サクラザカ・カノ(入手杏奈)を巻き込みながら、どう対処するかが主筋を形成する。
ウチは別の世界線から来たアク(坂口が演じる)と表裏一体の関係で、アクとして、この世界にいる人びとの心を破壊しようとする。「愛食み」にあうと人は鬼になるのだ。しかしアクによれば、この世界線をカオス化することで、アクがやってきた別の世界線が救われるという。果たしてソチの予知夢は現実となるのか。
「愛と正義」というタイトルは、両立困難な価値を象徴する。アメコミ原作の「アヴェンジャーズ」シリーズや「鬼滅の刃」といった近年のサブカル・SF映画・アニメの世界観との親近性を示しつつも、本作はポップで同時に詩的である山本独自の語り口で、同時代的問いを観客に突きつける。近年、多くの人びとにとって明らかになってきた「正義」の徹底した相対化という世界史的事態である。この相対化のモメントに対し、「愛」はまったくもって無力でしかない(のか)。
益山の空間内の高低をダイナミックに使った演出に、黒田による高度な身体性を俳優に求める振付けが、山本の世界観を着々と具体化していく。さらに、卓越した歌唱技術と情感を必須とする、エモいバラード調から攻撃的なアップテンポで複雑なリズムを刻むイガキの12のナンバーを、俳優たちはしっかりと歌いきる。
本稿冒頭の音楽劇の説明に戻ると、本作での台詞は、比較的「通常通り発せられ、導入的に劇中歌・曲が多用される」傾向が強い。しかし、「物語そのものは歌や曲を除いて」は成立しない。台詞が通常通り発せられつつ、劇中歌が物語の展開に不可欠な点で、ミュージカルと音楽劇の中間的形式をとっている。この形式は、決して中途半端なものではなく、むしろその間にこそ語りうる主題があると、本上演は主張してやまない。劇作家・山本卓卓はまた、新たな一歩を踏み出したのである。
[i] 小劇場演劇は、1960年代後半に登場するアングラ演劇を淵源とする演劇実践のことで、1980年代の小劇場ブームを経過し、その後の展開のなかで、一定の美学的・思想的規範を共有する現代演劇のジャンルとして確立したと筆者は考えている。
『リビングルームのメタモルフォーシス』と『愛と正義』―二つの音楽劇から Metamorphosis of a Living Room and Love and Justice: Two Singular Music Theatre Works
[ii] 『リビングルーム』はウィーン芸術週間で2023年5月13日初演され、その後、ドイツ・ハノーファー、オランダ・アムステルダムを巡演した。さらに、2024年、東京芸術祭で日本初演され、神戸と名古屋でも上演された。キャストに変更があるため、本文中には記していない。初演時には、音楽はクラングフォルム・ウィーンが、東京及び名古屋ではアンサンブル・ノマド、神戸では神戸室内管弦楽団がそれぞれ担当した。出演者としては、青柳いづみ、朝倉千恵子、大村わたる(欧州公演のみ)、石倉来輝、川﨑麻里子、椎橋綾那(欧州公演のみ)、矢澤誠、渡邊まな実(日本公演のみ)がクレジットされている。
内野 儀(Tadashi Uchino)
[iii] この点については岡田と筆者の個人的な対話によるが、他の機会にも口頭で岡田が話していた記憶がある。一方、たとえば、東京芸術祭の同作品のHPには、「俳優たちはナラティブとは別の基準によって作られた振付を遂行し、次第に変態していく」とある。
岡田利規作・演出、藤倉大・音楽『リビングルームのメタモルフォーシス』、Playwright / Director: Toshiki Okada, Composer: Dai Fujikura “Metamorphosis of a Living Room”
[iv] たとえば、チェルフィッチュHPにおける藤倉の発言(「岡田さんと僕は、平和的かつ創造的なコラボレーションを行いました。岡田さんの脚本と俳優への演出に僕が反応し、岡田さんの脚本も僕が作曲した音楽に反応し、彼の演出を反映させました。これこそ、50-50のコラボレーションと言えるでしょう。」)https://chelfitsch.net/activity/2025/03/metamorphosis-online.html
内野 儀 (Tadashi Uchino)
—————————————
内野 儀 (Tadashi Uchino)
1957年京都生れ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了(米文学)。博士(学術)。岡山大学講師、明治大学助教授、東京大学教授を経て、2017年4月より学習院女子大学教授。専門は表象文化論(日米現代演劇)。著書に『メロドラマの逆襲』(1996)、『メロドラマからパフォーマンスへ』(2001)、『Crucible Bodies』 (2009)。『「J演劇」の場所』(2016)。公益財団法人セゾン文化財団評議員、公益財団法人神奈川芸術文化財団理事、福岡アジア文化賞選考委員(芸術・文化賞)、ZUNI Icosahedron Artistic Advisory Committee委員(香港)。「TDR」誌編集協力委員。