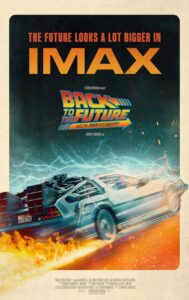五線紙のパンセ|言論と作曲──言霊の道行|桑原 ゆう
 言論と作曲──言霊の道行
言論と作曲──言霊の道行
桑原 ゆう(Yu Kuwabara):Guest
2024年12月7日に「不惑」の代に突入した。いまのところ、惑いも迷いも、無くなりそうもないが、それでも、なにかを決定したり選び取ったりすべきときの瞬発力と確度は、年々、多少なりとも向上しているように感ぜられる。
そのほぼ1週間前の12月1日、板橋区東新町の由緒ある真言宗豊山派の寺院、安養院の瑠璃光堂にて、「言祝会(ことほぎえ)」と題した公演を執りおこなった。
6月17日にKAIROSからリリースした、初の作品集「音の声、声の音」の記念企画は、京都と東京の2箇所で、異なる内容の併催とし、作曲家としてのこれまでの営みを、多角的、包括的に振り返る機会になるよう提示した。京都篇「桑原ゆう個展『音の声、声の音』」は、前回の寄稿で詳細に回顧したように、「記譜と作曲」を主旨として、全7日間の楽譜の展示個展と、3日間全7回のパフォーマンス・トークとで構成し、「聴くこと」と「視ること」について問いかけた。
一方、東京篇「言祝会」は、「言論と作曲」を主眼に据えた。自身の音楽観や創作活動、作品について、自らの声と言葉で解説することを「ことほき」と捉え、合わせて演奏をお聴きいただく内容で、休憩を含め約3時間半の長丁場となった。作品集CDリリースを自ら「ことほく」だなんて、どれだけナルシシストなのかといわれるに決まっているし、我にかえった途端こっぱずかしくなってしまいそうで、躊躇する気持ちもあるにはあったが、「言論と作曲」というテーマや、リリースからの一連の流れをかえりみればかえりみるほど、「言祝会」以上にぴったりくる公演名は他にないと思われた。
連載第1回の作品集解題 でもおこなったように、白川静「字訓」で「ことほく」を引いてみる。
ことほく【寿(「寿」の旧字体)・賀】
四段。「言寿(旧字体)く」の意。祝いのことばを述べること。本来はことばでほめたたえ、ほめることによってその呪能(じゅのう)を励まし、祈ることの実現を求めるものであった。単に「ほく」ともいい、そのことを「ほかひ」という。…【中略】「ほく」は祝い禱(いの)ることをいう。言霊の呪能を高めるために「護言(いはひごと)を以ちて言寿(旧字体)く」ので、その実際は酒を醸むときの歌にもみえている。…
[白川静「字訓」平凡社 294頁]
鍵語となる「言霊」については、「ことほく」の1ページ前にこのようにある。
ことだま【言霊(「霊」の旧字体)】
ことばには霊があって、ことばとして述べられたことは、その霊のはたらきによって、そのまま実現されるという観念があった。ことばにはそのような呪能があり、「ことあげ」「ことだて」「ことどひ」「ことほく」「ことわざ」など、みなその観念を含む語である。…
[同293頁]
「言」によって、自身の音楽を確固たる「事」にする。そういう儀式に、多くの人に立ち会ってもらう──これが「言祝会」をおこなう真意だった。うかうかしていると、すべてがあれよあれよという間に流され、忘れ去られてしまう現代において、これは大いなる出来事なのだと、「言霊」の力と、言葉の「音(おん)」の波動と振動とを借り、この世に「徴」として刻みつけたかったのだ。また、作品が内包するエネルギーと、その前提となる音や音楽の言語構造そのものが最大限の力を発揮するよう、「言」によって励まし、演奏がより実感をともなう「事」として、聴く人びとに届くことを目指した。
「言」は、話し言葉と書き言葉の両方の「しかた」で提示した。話し言葉と書き言葉とは、性質のちがうものだからだ。
…周知のように、彼(ソクラテスのこと)は、生涯、一行も書かなかったのである。彼の考えによれば、書かれた言葉は、絵にでも描いたように、いつも同じ顔を、どんな人の前にでも、芸もなく曝しているだけのもので、語るべき人には語り、黙すべき人には口をつぐむという自在な術を、自ら身につけている話し言葉とは、まるで異なったものだ。話し言葉も、いずれ、書かれた言葉と兄弟関係にはあろうが、父親の正嫡の子という事になれば、やはり話し言葉だという考えなのだ。【中略】「言霊」について、ソクラテスは、どのように語っているか。それを見つけようとすれば、直ぐ見つかる。──この相手こそ、心を割って語り合えると見た人との対話とは、相手の魂のうちに、言葉を知識とともに植えつける事だ、──「この言葉は、自分自身も、植えてくれた人も助けるだけの力を持っている。空しく枯れて了う事なく、その種子からは、又別の言葉が、別の心のうちに生れ、不滅の命を持ちつづける。──」
[小林秀雄「本居宣長補記 Ⅰ」新潮社『小林秀雄全作品 第28集』261-262頁]
話し言葉と書き言葉の優劣をいっているのではなく(実際、私はいまこの原稿を書いているわけだし)、もともと、話し言葉が先だった。いわずもがな、文字は人類最大の発明のひとつで、日本語にとって、漢字の渡来は大事件であった。されど、本居宣長がいうには、日本語は、話し言葉の構造で以て、書かれる以前に完成していたのだ。
…「古語のふり」とは、古学が明らめねばならぬ古人の「心ばへ」の直かな表現、宣長の言葉で言えば、その「徴(シルシ)」だからだ。と言う事は、更に言えば、未だ文字さえ知らず、ただ「伝説(ツタエゴト)」を語り伝えていた上ッ代に於いて、国語は言語組織として、既に完成していた…
[小林秀雄「本居宣長補記 Ⅰ」新潮社『小林秀雄全作品 第28集』279-280頁]
つまり、話し言葉と書き言葉とでは、あつかえる領域が異なる。私の解釈では、そのちがいは作曲と即興のちがいと重なるところがあるように思う。要は、作曲が書き言葉で、即興が話し言葉である。
作曲とは、ありとあらゆる選択肢を検討したうえで、これが答えだと決定することだ。決定までの過程が如何に練られているか、また、決定における確信と精度とが、音楽の強度にそのまま反映される。私もこれまで、たくさんの小さな決定を積み重ねてきた。展示個展のステイトメントで、頭と手の結びつきについて述べたように、身体中を張りめぐる神経を行ったり来たりしていると、やがて、答えが自ずと頭をもたげてくる。
対して即興は、その瞬間の最適解を出すことであろう。もしくは、反射神経のようなもの。その精度は、経験値と感覚の鋭さとによるだろうが、許容できる質の間口が作曲よりも広い。新たな解をその場その場で示し、その都度更新していけばよいという態度でないと、やっていけないだろうと思われる。即興はコミュニケーションの手段としての役割も大きいので、空間の力に導かれ、時を共有する仲間と一緒に答えを発見していくような営みであって、作曲とはやはり性質が異なる。
ただし、作曲された音楽も、奏者が演奏するたびに変わる。同じ演奏家が同じ作品を演奏しても、だ。時と場所、気候、目的、聴衆の様子、あるいは、奏者の年齢や体調、ありとあらゆる事情が演奏に還元される。これは、話し言葉の持つ側面ともいえる。
前置きが随分と長くなったが、書き言葉としての「言」は、プログラムの配布を以て共有した。プログラムというよりは「同人誌」とでもいおうか、全54ページの冊子である。
「言祝会」のコンセプトや、当日演奏した楽曲作品のプログラムノートはもちろん、これまでに書き溜めた随筆や論考を一挙にまとめ、思索や思想の総体とした。加えて、作品集のブックレットに掲載した白石美雪先生による短評を配し、さらに、原塁さんに新しい論評を書き下ろしていただくことで、主観的なだけの内容にならないよう、目配りしたつもりである。
話し言葉による「言」は、私自身が舞台にあがっての解説による。曲間に逐一、プロジェクターで投写した楽譜や写真画像、映像も用いて、作品やその周辺に関するお喋りをしたので、「言祝会」は3時間を超えたのだった。「音」と「声」の対峙に端を発する作品集CDリリースから、記念企画への一連の流れを納めるために、自らの「声」に還ってくる必要があった。
こんな企画をするのだから、人前で話をするのがさぞかし好きなのだろう、何か言いたくてしょうがないのだろうと思われるかもしれないが、生来そういう人間ではないと考えている。(自身のことは自分がいちばん知らないものではあるにせよ。)正直なところ、話さないで済むのならば、できれば話したくない。話さずに音楽のみでなにか伝わらないものかとも思うし、音楽の純粋な力だけを信じようとする価値観があることもじゅうぶん承知している。しかしながら、作曲家でありたければ、おそらく、話さなければならないのだ。これまで、音楽という「道」をつくり、拓いてきてくれた先人たちの背中がそういっている。文章にして言語化する習慣も、作曲家でありたいと願うから、意識的におこなってきた。それに加えて、私が「音」というものの起こりに、「声」という身体的働きを重視する以上、やはり話さねばなるまい。自らが話すことで、「音」と「声」がどのように関連するかを、証明する必要があるからだ。
とはいえ、未だに人前で話をするのは緊張するし、さっぱり上手にならない。毎週大学で授業をしていればある程度は慣れるものだが、それでも、言葉にならないときや、言葉にしがたく言いよどむとき、何を言ったらいいかわからなくなるときは、多々ある。ただ、それならそれで、言葉にしようと四苦八苦したり、思わず口をつぐんでしまったりする、ありのままの態度を見てもらえばよいと、わかってきた。それこそが話し言葉であり、言葉にしがたいところをどうにか乗り越えて言葉にしようとする、その身体の内部の働きや状態は、作曲において音を選ぼうとするときの、身体の内部の働きや状態そのものでもあるのだから。
…要するに、「神代記」から引用しながら、宣長が想い描いたのは、磐戸の中の日ノ神と外の神々との間を取り結んでいる「言霊」の「幸はふ国」であった、と言っていいだろう。そして、其処で、神々の間を行き交い、神々を動かしている言葉は、意(ココロ)としての、と言うより、むしろ文(アヤ)としての言葉であったという事になる。宣命の言霊は、先ず宣るという事(ワザ)が作り出す、音声の文(アヤ)に宿って現れた。これが自明ではなかった人々に、どうして「宣命譜」などが必要だったろうか。何も音声の文(アヤ)だけに限らない、眼の表情であれ、身振りであれ、態度であれ、内の心の動きを外に現わそうとする身体の事(ワザ)の、多かれ少なかれ意識的に制御された文(アヤ)は、すべて広い意味での言語と呼べる事を思うなら、初めに文があったのであり、初めに意味があったのではないという言い方も、無理なく出来るわけであり、少くとも、先ず意味を合点してからしゃべり出すという事は、非常に考えにくくなるだろう。
[小林秀雄「本居宣長」新潮社『小林秀雄全作品 第28集』47-48頁]
この言語共同体を信ずるとは、言葉が、各人に固有な、表現的な動作や表情のうちに深く入り込み、その徴(シルシ)として生きている理由を、即ち言葉のそれぞれの文(アヤ)に担われた意味を、信ずる事に他ならないからである。更に言えば、其処に辞書が逸する言語の真の意味合を認めるなら、この意味合は、表現と理解とが不離な、生きた言葉の裡にしか現れまい。
[同49頁]
宣長が、「古事記」を釈いて、はっきり見定めたのは、上ッ代の人々が信じていた、言霊と言われていた言語の自発的な表現力、或は自己形成力と言ってもいいものの、生活の上で実演されていた、その「ふり」であった。
[小林秀雄「本居宣長補記 Ⅰ」新潮社『小林秀雄全作品 第28集』279-280頁]
話された内容ばかりを重視しがちだが、じつは、声色、抑揚、顔の表情、態度などをふくむ、内容以前の「文(アヤ)」や「ふり」といったものが、言語の肝要なのである。先述のソクラテスについて参照した箇所もふまえると、「文(アヤ)」や「ふり」を「相手の魂のうちに、言葉を知識とともに植えつける事」が、話すこと=「ことほき」である。
長年、このような言語の性質とその重要性について、作曲という手段を用いて考えてきた。また逆に、そういう言語の力を借りて作曲してきた。それを「言祝会」で示したかった。自分が、「言霊」の「幸はふ国」の作曲家であることを証明したかったのである。
「言祝会」の「会」は法会(ほうえ)を意味する。「言祝会」を瑠璃光堂でおこなった理由は、ここにある。法会とは、お寺で僧侶がつとめる会式(えしき)そのものを指す言葉だ。たとえば、お釈迦様の誕生日を祝う花祭りは「灌仏会(かんぶつえ)」といい、お釈迦様が亡くなった日に執り行うのは「涅槃会(ねはんえ)」や「常楽会(じょうらくえ)」、お盆におこなうのは「施餓鬼法会(せがきほうえ)」という。
各宗派のさまざまな法会に参列して感じるのは、法会の「かたち」の有機的な美しさと無駄の無さである。各法会の次第には、ちがった働きを持つ複数の経文が、在るべき位置に正しく配置され、正しい所作で唱えられることによって、各々役割を果たし、光りかがやく。全体が細部を欲し、細部がそれぞれに力を発揮しながら結びつくことで、法会の意味が立ち上がる。全体としての形式と、なかを覗いた時の形式、細部と全体とが相互に機能する、まさに曼荼羅的な構造になっている。
私は法会に立ち会う機会がとても好きで、大事にしている。内容によっては4、5時間におよぶことも、夜を徹することも、数日にわたることもある。そこには、忙しない日常とはまったく質のちがう時間がある。その非日常の時間に没入することで、身体の働きが自然に還るよう、調整される。近年、音や音響の問題から時間や構造の問題へと興味関心がうつってきていることもあり、そういう時間をあつかう音楽をつくれないかと、日々考えている。
 「言祝会」の次第を考えるうえで最も重んじたのは、はじまりに「唄(ばい)」を置くことだった。塚越秀成師に、真言宗豊山派の《如来唄(にょらいばい)》を唱えていただいた。この《如来唄》の見せかたについては、ぎりぎりまで思案した。古典声明を紹介する公演も、私が関わってきた新作声明の舞台も、ホールを使用する場合は聴衆に向いて唱えるが、本来のお唱えは、ご本尊に向かってするものである。さて「言祝会」ではどうするのがよいだろうか。瑠璃光堂というくらいだから、そこにはお薬師様がいらっしゃる。開場時間の直前まで迷いに迷ったが、お客様に背を向けることになっても、「言祝会」という「法会」のはじまりにふさわしいのは、薬師三尊に向かって「唄」を引いていただくことだと結論づけた。演奏として聴衆に披露するのでなく、会を鎮める、本来の意味での「唄」。延々と引きのばされた一字一字が、雲のようにたなびき、空間にひろがっていく。結果的に、聴く人びとが受け身でなく、「唄」のお唱えに自ずと参列するような趣になり、唱え終えた塚越師が向き直って礼をした際、拍手は起こらず、全員が一礼した。その後の静寂——挨拶と最初の解説のために、堂内に一歩足を踏み入れたときに感じたそれ、は、忘れられない。通常の演奏会では感じることのない、あまりにもしんとした静けさだった。
「言祝会」の次第を考えるうえで最も重んじたのは、はじまりに「唄(ばい)」を置くことだった。塚越秀成師に、真言宗豊山派の《如来唄(にょらいばい)》を唱えていただいた。この《如来唄》の見せかたについては、ぎりぎりまで思案した。古典声明を紹介する公演も、私が関わってきた新作声明の舞台も、ホールを使用する場合は聴衆に向いて唱えるが、本来のお唱えは、ご本尊に向かってするものである。さて「言祝会」ではどうするのがよいだろうか。瑠璃光堂というくらいだから、そこにはお薬師様がいらっしゃる。開場時間の直前まで迷いに迷ったが、お客様に背を向けることになっても、「言祝会」という「法会」のはじまりにふさわしいのは、薬師三尊に向かって「唄」を引いていただくことだと結論づけた。演奏として聴衆に披露するのでなく、会を鎮める、本来の意味での「唄」。延々と引きのばされた一字一字が、雲のようにたなびき、空間にひろがっていく。結果的に、聴く人びとが受け身でなく、「唄」のお唱えに自ずと参列するような趣になり、唱え終えた塚越師が向き直って礼をした際、拍手は起こらず、全員が一礼した。その後の静寂——挨拶と最初の解説のために、堂内に一歩足を踏み入れたときに感じたそれ、は、忘れられない。通常の演奏会では感じることのない、あまりにもしんとした静けさだった。
次第は3部に分けて構成し、各部のあいだに10分程度の休憩をはさんだ。先述の真言宗豊山派古典声明《如来唄》、その「唄」を音楽的に発展させた、ヴァイオリン独奏のための《唄と陀羅尼》、ヴァイオリン、チェロ、三味線の三重奏による《はすのうてな》 で、第1部とした。私の音楽観を育ててくれた、仏教的世界観の提示が主旨であった。各作品については、リンク先を参照されたい。
第2部は「逢魔が時」シリーズより、チェロ独奏による《逢魔が時のうた》 、三味線独奏による《やがて、逢魔が時になろうとする》を披露し、文学的世界観を示して見せた。




 第3部では「音」と「声」についてあらためて問うべく、まず、弦楽三重奏のための《三つの聲》 をお聴きいただいた。解説では、以下のクローデルの文章を引いたところ、大きな反響があった。
第3部では「音」と「声」についてあらためて問うべく、まず、弦楽三重奏のための《三つの聲》 をお聴きいただいた。解説では、以下のクローデルの文章を引いたところ、大きな反響があった。
…これらの合奏に、楽師たちの発する長い叫び声がしばしば加わってくる。それは、一方は低くもう一方は高い、二つの音の上に成り立っており、「ほう-くう、ほう-くう」と聞こえる。その声は、まるで夜、野を渡る声、自然からの無形の呼びかけのように、広大な空間と隔たりとの異様で劇的な印象を与える。あるいはまた、それは人間の言葉になろうとして暗闇の中で努力する動物の叫び声、発せられては絶えず裏切られるあの声、絶望的な努力、苦痛に満ち定まるところのない証言ともいえよう。
[ポール・クローデル著、内藤高訳「能」講談社学術文庫『朝日の中の黒い鳥』119頁]
私が書きたい音とは、クローデルが「夜、野を渡る声、自然からの無形の呼びかけ」「人間の言葉になろうとして暗闇の中で努力する動物の叫び声、発せられては絶えず裏切られるあの声」と表現する、前言語的な「声」だ。言葉にならないのに、どこかにいる相手に向けて発せられた、意図を伝えようとする身ぶりをたたえたものである。
「動物の叫び声」に、「クローデルにとって、野生の状態から人間の言葉に変わろうとするときの受苦そのものが何よりも重要な意味を持っていた」と註がついているが、たいへんよくわかる。「受苦そのもの」とは、人が己れの感情をどうにかしようとするときの、内部の働きのことであろう。人が思わず知らず、声を出してしまうのは、外から何らかの圧力がかかったときである。とくに、悲しい事や堪え難い事があったとき、私たちは心ともなく口をつぐむ。息がつまり、呼吸が止まり、緊張の状態になる。その状態から解放されるため、内部に感じられる混乱を整えようとする働きが、ひとつのため息や、ひとつの感嘆詞を、口から外に放出させる。人が自然に取る、このような動作から「ほころび出」た、言葉以前のひとつの声は、すでに意図や質を備えた、エネルギーとしての音声である。
「──猶かなしさの忍びがたく、たへがたきときは、おぼえずしらず、声をさゝげて、あらかなしや、なふなふと、長くよばゝりて、むねにせまるかなしさをはらす、其時の詞は、をのづから、ほどよく文(アヤ)ありて、其声長くうたふに似たる事ある物なり。これすなはち歌のかたち也。たゞの詞とは、必(かならず)異(コト)なる物にして、その自然の詞のあや、声の長きところに、そこゐなきあはれの深さは、あらはるゝ也。かくのごとく、物のあはれに、たへぬところより、ほころび出て、をのづから文(アヤ)ある辞が、歌の根本にして、真の歌也」
[小林秀雄「本居宣長」新潮社『小林秀雄全作品 第27集』259頁]
ちょうど「言祝会」の開演前、《三つの聲》のリハーサルをおこなっていて、車のエンジン音がとりわけ大きく響いた瞬間があった。瑠璃光堂は、いわゆるコンサートホールのように完全に防音された空間ではないので、ほとんどの音は気にならないが、あまりに大きなノイズ、自然音や放送音などは聞こえてくることがある。そのとき、そのエンジン音はまったく邪魔でなく、むしろ、堂内で繰り広げられている音空間に食い込み、参入してくるかのように聴こえたのだった。そんな感想を抱いていたら、昼食のときに「エンジン音が参加してきたよね」という話題になり、奏者も演奏しながらそのように感じたのだと、うれしくなった。
「言祝会」では時間がなく、紹介できなかったが、この文章も引いておきたい。
もう一人の楽師は長い棹のついた日本のギター、白い革の張られた三味線を手にしている。象牙の撥によって、おそらく古代の竪琴にかなりよく似た音を時折爪弾く。しかしさらに、鼻歌のような人形浄瑠璃の歌全体が彼のみに拠っているのである。この男には言葉を話す権利はない。唸り声と叫び声を上げる権利しかない。胸の奥から直接湧き上がってくる動物的で文字のない音、われわれの中にある舌や様々な弁が息とぶつかって生じる音をたてる資格しかないのである。彼は問いかけ、喜び、不安になり、苦しみ、望み、怒り、怯え、何やら考え、ぶつぶついい、泣き、嘲り、罵り、疑い、ほのめかし、猛り狂い、怒号し、愛情を示す。その役目は聴衆を惹きつけることである。聴衆みんなが「おー」とか「あー」とか叫ぶのはひたすらこの男によっている。ただ言葉(バロール)のみがこの男には欠けているのだ。
[ポール・クローデル著、内藤高訳「文楽」講談社学術文庫『朝日の中の黒い鳥』154頁]
 《唄と陀羅尼》から《三つの聲》までは、すべて作品集CD関連楽曲である。チェロ独奏曲《逢魔が時のうた》は収録していないが、ヴィオラ・ダモーレ独奏曲《逢魔時の浪打際へ》の類似作品だ。が、最後に演奏した《観音廻りの段》は、声明、ヴァイオリン、チェロ、太棹三味線の編成に書き下ろしたまったくの新作で、世界初演であった。作品集リリースを「ことほく」といっても、作品集は既に過去に制作したものであり、なにかひとつでも未来に向けた視線を示すことで、はじめて「言祝会」として成り立つと考えたからだ。
《唄と陀羅尼》から《三つの聲》までは、すべて作品集CD関連楽曲である。チェロ独奏曲《逢魔が時のうた》は収録していないが、ヴィオラ・ダモーレ独奏曲《逢魔時の浪打際へ》の類似作品だ。が、最後に演奏した《観音廻りの段》は、声明、ヴァイオリン、チェロ、太棹三味線の編成に書き下ろしたまったくの新作で、世界初演であった。作品集リリースを「ことほく」といっても、作品集は既に過去に制作したものであり、なにかひとつでも未来に向けた視線を示すことで、はじめて「言祝会」として成り立つと考えたからだ。
いつか、日本語の発声と歌唱方法を駆使した、日本語の大きなオペラを作曲したい。日本語を如何に語り、唄い、唱えるか、また、それをどう記譜するか。これは、私のライフワークともいえる問いである。子音が弱く母音優位であることも含め、日本語ならではの音、響き、語感、そして、日本語のもつ巨きな言語構造や意味世界を表現するのに、いわゆる現代曲でおこなわれている音楽化の方法は明らかに不自然だと感ずる。かといって、言葉から音の部分をはぎとって、効果音としてのみ用いることもしたくない。それでいて、「作曲」という西洋由来の方法でこの問いに取り組み、楽譜に書き留めようとしているわけだ。矛盾していることは百も承知ながら、どうにか答えを見出そうとする。それが私の創作だと考える。
いつかオペラを書くそのときが来たら、テクストに何を選ぼうか。近松門左衛門の戯曲は有力候補だ。その「練習」ではないが、はじめの一歩を踏み出そうと思い、「曽根崎心中」より、現在では文楽でも歌舞伎でもほとんどの場合上演されない、導入部分「お初観音廻り」をあつかうことにした。観世音菩薩に救済を願う、お初の三十三所の道行が、此岸から彼岸への渡りを見立てたものだとしたら、浄瑠璃でなく、声明で唱えてもよいのではないかと考え、声明の語りの様式である「講式」で、音楽化することを試みた。
《観音廻りの段》で声明の「声」に還ってくることによって、《如来唄》にはじまる「言祝会」が成就する。それは、お初の三十三所の道行とも重なり合う。「言祝会」とは、作品集リリースを「ことほく」ための、ひとつの「かたち」をさぐる試みであり、また「会」そのものが、ひとつの作品だったわけである。
(2025/2/15)
—————————–
桑原 ゆう(くわばら・ゆう)Yu KUWABARA
日本の音と言葉を源流から探り、文化の古今と東西をつなぐことを軸に創作を展開する作曲家。第31回芥川也寸志サントリー作曲賞(旧名:芥川作曲賞)受賞。英国音楽レビューサイトBachtrackにて「2023年注目の女性作曲家8人」に選出。2024年、ウィーンの現代曲レーベルKAIROSより初の作品集アルバムをリリース。2026年、第6回高松国際ピアノコンクール委嘱曲作曲家。国立劇場、静岡音楽館AOI、神奈川県立音楽堂、横浜みなとみらいホール、箕面市立メイプルホール、ルツェルン音楽祭、ワルシャワの秋、アハト・ブリュッケン(ケルン)、ZeitRäume(バーゼル)、Transit 20·21(ルーヴェン)、I&I Foundation(チューリヒ)等、国内外で多くの委嘱を受け、世界各地の音楽祭や企画で作品が取り上げられている。東京藝術大学および同大学大学院修了。楽譜はEdition Gravis、Edition Wunn(共にドイツ)より出版。「淡座」メンバー。2025年2月現在、国立音楽大学、洗足学園音楽大学及び大学院非常勤講師。
https://3shimai.com/yu/
淡座リサイタルシリーズ Vol.3 作品集CDリリース記念 特設ページ
インストア・イベント開催決定!
桑原ゆう初作品集発売記念 ミニライブ、トーク&サイン会
4月19日(土)16:30開演 タワーレコード渋谷店8Fイベントスペース
https://towershibuya.jp/2025/02/08/209830