小人閑居為不善日記|石を拾う――つげ義春、モリス、ヴァルダ|noirse
石を拾う――つげ義春、モリス、ヴァルダ
Pick Up a Stone――Yoshiharu Tsuge, William Morris, Agnès Varda
Text by noirse
1
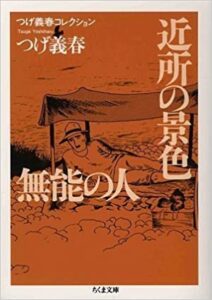 10月某日、わたしは是政付近の多摩川の河原で、石を拾っていた。ゴミ拾いではない。罰ゲームというのでもない。いいと感じた石を無心に拾う、それだけだ。
10月某日、わたしは是政付近の多摩川の河原で、石を拾っていた。ゴミ拾いではない。罰ゲームというのでもない。いいと感じた石を無心に拾う、それだけだ。
うららかな日曜の午後、わたしを含めた数人の大人が黙々と石を拾っている様は、不思議な光景だったろう。何かの拍子に石拾いをしてみたいという話をしたら、何人かがノッてくれて、こうした運びに至ったのだ。
では石を拾ってみたかった理由は何だったのか。つげ義春のマンガを読んだからだ。十代半ばにつげ作品に出逢ったわたしは、たちまちその世界に魅了された。中でも〈石を売る〉(1985)からの連作には強く心を奪われた。
主人公はマンガ家だが、創作に見切りをつけ、拾った石を売ることで食べていけないか思案し、実行してしまう。当然石屋などうまくいかず、妻になじられ、子供にも不安がられる。それでも生きかたを変えることのできない情けない男を、つげはユーモアと、一抹の共感を持って描いていく。
2
石にも色々あって、一部の鉱物や水石というような種類は高く取引されることもある。主人公も見栄えのする石を求めて右往左往するのだが、つげが本当に描きたかったのは、価値のある石を追い求めることではないだろう。
それは忍耐や功績によってもたらされたのでは決してない。相場も値段ももっていない。売りものではないそれらの価値は、いかなる貨幣にも換算できない。それは購買力と金本位制とを嘲笑する。それは労働や商品に変換できない。
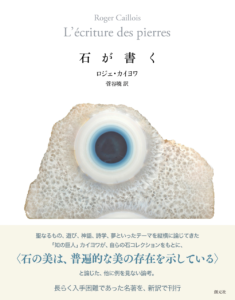 先日復刊されたロジェ・カイヨワの《石が書く》(1970)からの一節だ。カイヨワが言うように石自体には価値がないが、彼は石に魅せられ、本まで書いてしまうくらいに熱中した。もっともカイヨワが収集したのは瑪瑙や風景石など、価値があるとされる石だったが。
先日復刊されたロジェ・カイヨワの《石が書く》(1970)からの一節だ。カイヨワが言うように石自体には価値がないが、彼は石に魅せられ、本まで書いてしまうくらいに熱中した。もっともカイヨワが収集したのは瑪瑙や風景石など、価値があるとされる石だったが。
けれど、簡単に拾えるような石にも魅力がないわけではない。和田博文による《石の文学館 ――鉱物の眠り、砂の思考》の解説によると、斎藤茂吉や種村季弘、松山巌にも石を拾う趣味があったらしい。平凡なただの石だからこそ、魅せられる何かがあるのだ。
たいていの石には価値はない。だから、いいと感じた石を拾うしかない。つまり、どの石がよいかどうかの基準を握るのは自分だけということになる。そのため、目の前の石のどこがいいのか、常に自問自答しながら拾うことになる。
今のようにSNSが影響力を持つ状況下では、自分の判断や意見が何だったのか、自分自身でも分からなくなってしまいがちだ。そのようなしがらみを捨て去って、自分と石だけの関係に向き合うのは、とても貴重な時間ではないだろうか。
3
もっとも今回わたしが石を拾っていた是政は府中に近く、つげが散策した調布とは少し離れていた。そこから競馬場方向へ少し歩くと、「アーツ・アンド・クラフツとデザイン ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで」を開催中の、府中市美術館に着く。
 モリスやアーツ・アンド・クラフツ運動については説明不要だろう。モリスが社会活動家や詩人だったこともよく知られているはずだ。ただ、彼にはもうひとつ、ファンタジー作家としての顔もあったことを忘れてはいけない。ハイファンタジーの先鞭として、トールキンにも影響を与えたと言われるくらいだ。
モリスやアーツ・アンド・クラフツ運動については説明不要だろう。モリスが社会活動家や詩人だったこともよく知られているはずだ。ただ、彼にはもうひとつ、ファンタジー作家としての顔もあったことを忘れてはいけない。ハイファンタジーの先鞭として、トールキンにも影響を与えたと言われるくらいだ。
モリスの小説には中世への憧憬が強く刻印されている。彼は「生まれる時代を間違えた」とこぼすほどの中世愛好家で、ロンドンから離れたレッドハウスでは、妻ジェーンと中世の「コスプレ」をして暮らしていたとか。彼の手掛けたデザインにも、中世趣味が濃厚に見て取れる。
わたしはデザインについてはよく分からないのだが、モリスにだけは興味があって、美術館にまで足を運んだのも、こうした彼の動機が、つげ作品に通じる逃避的な側面があるからだ。ファンタジーは現実逃避だと揶揄されることがあるが、小さな逃避はむしろ有用と考えるべきだろう。仕事に疲れて帰宅しても、モリスの中世趣味をあしらったインテリアに包まれてひと息つけるのなら、それはいいことではないか。
ただ、ファンタジーの現在地と言える「異世界もの」は、ひとつの社会からまた別の社会への移行を描くパターンが目立つようだ。所属する社会で評価されなかった主人公が、別の社会で成功するというものが多数を占めているという印象がある。
それが安易な逃避と考えるかどうかは見る人次第だが、モリスも似通った問題に直面した。彼らの製品は本来ターゲットとしていた労働者ではなく、モリスが嫌った資本家から持て囃されるという、皮肉な結果に至った。モリスの旅の結末は、彼が夢見た平等な社会の実現ではなく、近代が生んだ新しいデザインの世界の第一人者という座だったのだ。
4
さて、ファンタジーには旅を描いた作品が多い。もともと「ここではないどこかへ行きたい」という動機で読まれる作品なのだから、そうなるのは当然だろう。異世界ものも旅先で評価を獲得していくというのが定番なのだが、だからよくないとは言えない。そもそも旅とは「何かを得るために行く」という要素が重要だからだ。
旅を通して主人公が成長するビルドゥングスロマンは枚挙に暇がないし、17世紀の英国で流行したグランドツアーは、貴族の子弟がヨーロッパ旅行を通して「成長」するものだ。イニシエーションの旅とまとめてしまえば、人間が太古から行っているものでもある。ひと時流行った自分探しの旅というのも、この範疇に入るだろう。
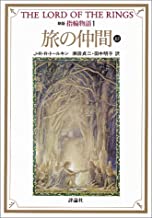 ただ一方、「何かを失うため」の旅もある。ファンタジーにロードノベルが多いのは、嚆矢たる《指輪物語》がそうだったからという理由もあるだろうが、この作品における旅の目的は、指輪を捨てることにある。ご存じの通り指輪とは「力」のことで、《指輪物語》とは力を失うための旅を描いた物語である。
ただ一方、「何かを失うため」の旅もある。ファンタジーにロードノベルが多いのは、嚆矢たる《指輪物語》がそうだったからという理由もあるだろうが、この作品における旅の目的は、指輪を捨てることにある。ご存じの通り指輪とは「力」のことで、《指輪物語》とは力を失うための旅を描いた物語である。
《指輪物語》は1960年代に何度目かのブームを迎えた。アメリカでペーパーバックとして発売され、これが当時の若者に広く読まれたのだ。その世界観は当時の学生運動や政治運動、カウンターカルチャーとリンクしていった。
同時期に映画界ではニューシネマが登場、《イージー・ライダー》(1969)や《真夜中のカーボーイ》(1969)など、いくつかのロードムービーを産出していった。それらの作品には、夢や理想、時には命など、何かを失うための旅が描かれた。
数あるロードムービーの中でも、思い入れがあるのが《パリ、テキサス》(1984)だ。妻子を置いてテキサスの闇に消えていく主人公の姿に十代のわたしは魅せられてしまった。
あれからしばらく経ち、《パリ、テキサス》が男性の身勝手なロマンチシズムだと分かるくらいには、客観的に見ることができるようになった。しかしそれでも、「何かを失うための旅」への憧憬を捨てきれるわけではない。それはきっと、つげ作品の石に魅せられるのと共通する感情なのだろう。
5
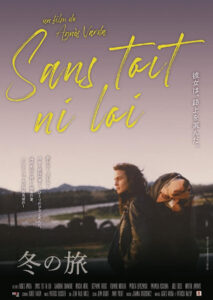 現在、《冬の旅》(1985)という作品がリバイバル上映中だ。監督はヌーベルバーグのひとりに数えられるアニエス・ヴァルダで、ロードムービーのひとつの極北と言っていい。
現在、《冬の旅》(1985)という作品がリバイバル上映中だ。監督はヌーベルバーグのひとりに数えられるアニエス・ヴァルダで、ロードムービーのひとつの極北と言っていい。
映画の冒頭、主人公の少女モナが、旅の果てに凍死してしまうことが早々に明らかにされる。1980年代のフランスは複数の経済問題を抱えており、特に若年層の失業は深刻化していた。若くして浮浪者となったモナもそうした社会状況を反映しているが、この映画の真価はそこではない。
私は人から人への関係にモナを繋ぎ留めました。彼女は私から逃れ、私は彼女を捉えることはできません。(略)私はモナという野生の鳥を捕らえることも理解することも選びませんでした。
ヴァルダ自身のコメントだ(《アニエス・ヴァルダ 愛と記憶のシネアスト》)。ヴァルダはモナの旅に過剰なドラマやメッセージを盛り込もうとはせず、淡々と冷たくカメラに収めていく。
《パリ、テキサス》とは真反対の、男性的ロマンチシズムを一切排除した、フェミニズム的手法によるロードムービーと位置付けられるが、ここではそれは置いておく。《冬の旅》が突出している点は、ヴァルダの透徹した視線にある。ヴェンダースやつげが憧れる、いまここから消え去りたいという「何かを失うための旅」は、所詮身勝手なロマンでしかない。すべてを捨てて旅に出れば、その結果は死しかないのだ。
もっとも、ヴェンダースはともかく、つげはそれを重々理解していた。つげは蒸発を描くとき、ユーモアを忘れることはなかった。世の中から消え去りたいが、すべての責任を放棄するわけにもいかない。旅の果ての死にも微かな憧れを抱きつつ、みっともなく生きることを手放すこともできない。そして石は、そういった人間の懊悩とは関係なく、ただそこにある。
自分の創作の基調はリアリズムだと思っているのですが、リアリズムは現実の事実に理想や幻想や主観など加えず「あるがまま」に直視することで、そこに何か意味を求めるものではないです。あるがままとは解釈や意味づけをしない状態のことですから、すべてはただそのままに現前しているだけで無意味と言えますね。
このつげの言葉には(《つげ義春 夢と旅の世界》)、ヴァルダによる《冬の旅》へのコメントに共通する視座が見て取れる。と同時に、まるで石について語っているようではないか。
つげやモリスやヴェンダースが憑りつかれた、ここからいなくなりたいという衝動から、解放されることはないだろう。けれど実行もできないまま、映画やアニメや小説で、小さな逃避を繰り返すことしかできまい。石を拾うのもきっとその一環なのだろう。生活、責任、意味、まとわりつく諸々を、石は忘れさせてくれる。
二時間ほど経って、陽が落ち始めたのを機会に、わたしたちは石拾いをやめ、多摩川を後にした。少し歩いたところにある 温泉施設に向かい、汗を流し、お酒や食事を頂き、解散した。多摩川での石拾いと温泉、つげ読者にとってこれほどたまらないことはない。
拾った石をどうするかは何も考えていない。多摩川下流で少し探したくらいなので、特筆すべき収穫があったわけではない。その辺に捨ててしまえば、たちまち他の石と見分けがつかなくなるだろう。でも、それでもいい。だってただの石なのだから。そう思うと、何故か肩の荷が下りるような気分になるのだ。
(2022/11/15)
——————————————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中


