評論|落合陽一×日本フィル プロジェクト VOL. 5「醸化する音楽会」|田中 里奈
落合陽一×日本フィル プロジェクト VOL. 5 「醸化する音楽会」アンコール配信
[Streaming] Yoichi Ochiai & Japan Philharmonic Orchestra Project VOL.5 “Sound of Digital Fermentation”
Text by 田中里奈(Rina Tanaka)
サントリーホール、2021年8月11日(ライブ配信あり)
再配信:2021年8月21日、22日
アンコール配信:2021年12月26日(筆者鑑賞回)、2022年1月2日
公演プログラム
1.黛敏郎:オリンピック・カンパノロジー
2.伊福部昭:土俗的三連画
協力:渡辺かよ・西山知花(阿寒湖アイヌシアター「イコロ」)
3.和田薫:《交響曲 獺祭~磨migaki~》第2楽章“発酵”
(休憩)
4.J.シュトラウスⅡ世:シャンパン・ポルカ
5.バルトーク:ルーマニア民俗舞曲
6.ペルト:カントゥスーベンジャミン・ブリテンへの哀悼歌
7.ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲《展覧会の絵》より バーバ・ヤガー~キエフの大門
(アンコール グリーグ:《ホルベルク組曲》より「サラバンド」)
演出・監修:落合陽一
指揮:海老原光
映像の奏者:WOW
進行アシスタント:江原陽子
演奏:日本フィルハーモニー交響楽団
コンサートマスター:田野倉雅秋(日本フィル・コンサートマスター)
ゲスト・ソロ・チェロ:門脇大樹
照明デザイン:成瀬一裕
照明:ライティングカンパニーあかり組
撮影:井村宣昭(井村事務所)
録音:塩澤利安(日本コロムビア)
配信:MUSIC/SLASH
舞台監督:井清俊博
音響コーディネーター:高村弘幸(アルファソリューション)
主催・企画・制作:公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団
助成:令和3年度日本博イノベーション型プロジェクト、文化庁/独立行政法人日本芸術文化振興会、公益財団法人歴史文化財団アートカウンシル東京
協力:株式会社エモハウス、WOW、TBWA/HAKUHODO、株式会社プリズム、森ビル株式会社
協賛:旭酒造株式会社、小川香料株式会社、春日井製菓株式会社、株式会社セイビ堂(50音順)
————-
落合陽一×日本フィルプロジェクトは、「テクノロジーによってオーケストラを再構築する」というテーマのもと、2018年以来、実験的な音楽会を4回5公演打ってきた。そのうち、Vol.3 Part2 《交錯する音楽会》については大田美佐子評と藤原聡評が、Vol.4 《__する音楽会》については能登原由美評と丘山万里子評が、本誌にそれぞれ掲載されている。
本稿では、同プロジェクトの成立背景から、「醸化する音楽会」の構成とコンセプトへと、順に見ていきたい。
落合陽一×日本フィルプロジェクト——プロジェクトの「目撃者」になる
まず興味深いのは、同プロジェクトの建て付けだ。毎回の演奏会にかかる企画開発費と開催費のため、助成金獲得に加えて、クラウドファンディングサイト「READYFOR」で出資を広く募っている。初回の2018年当時には、事前に公演プログラムと企画コンセプトを公開し、聴覚支援プログラムの開発・調整を目的に掲げていたことは、出資応募ページのアーカイヴから今でも確認できる。「クラウドファンディングを通して、ご支援いただいたみなさまにもお客様として、あるいは当日来られない方もサポーターとして、このプロジェクトの「目撃者」になっていただけたらと思っています」1と呼びかける落合×日フィルのこの手法は、劇場に足を運んで聞くという役割しか与えられていないと思いがちな今日の観客=「お客様」像を押し広げ、「サポーター」も含めた、広がりのある関与のあり方を提供していた。
「醸化する音楽会」
第6回目(振り番号はVol. 5)となった「醸化する音楽会」の、「今こそ、音楽と身体性を取り戻す」2というキャッチコピーは筆者の関心を引いた。長期化するコロナ禍の影響下における身体性の不可逆な変容は、ライブ・パフォーマンス全体において避けて通れない問題だからだ。
同音楽会における「身体性」というキーワードは、嗅覚や味覚を用いたワークショップに加えて、選曲の方にも反映しようと試みられていたことが、公演資料を読んでいくとわかる。演出・監修を務めた落合陽一が公演プログラムに寄せた「ステートメント」によれば3、同音楽会の動機は、「コロナ禍によってそれぞれの地域に分断された」ことを受けて、「今我々の周囲にあるもの,そして今我々から距離があるものについて考えたい」という、自らの身体の置かれた状況に基づいた、素朴で率直なものだ。筆者が気になったのは、次の箇所である。
分断によって気がついたもの.それは我々が土着の文化の中で継承されたDNAのようなものであり,それぞれの文化圏における土着の発酵性から生まれる新しい可能性である.
落合は続けて、「東洋的美的感覚と西洋的美的感覚の対比構造,その中にある発酵の意味性の違いに目を向け」ることが、「今我々の周囲にあるもの,そして今我々から距離があるもの」についての具体的な方法だと説明している。この考えが音楽会の構成に反映され、プログラムの「前半が日本の楽曲、後半が西洋のクラシック楽曲で構成され」た4。
だが、「醸化する音楽会」の構成は、次の2つの理由で破綻している。
第一に、構成の根拠となっている「東洋的美的感覚と西洋的美的感覚の対比構造」が、実際のプログラムにおいて機能していない。音楽会の公式プログラムとして演奏された7つの楽曲は、いずれも西洋近代音楽からの避けがたい影響のもとで成立し、この大きな潮流との緊張関係を有している。したがって、これらの楽曲を「東洋」対「西洋」の図式に当てはめて鑑賞することは本来不可能である。
「東洋」を「日本」と抵抗なく言い換えることの問題は本稿で後述する。後半の楽曲については、改めて詳細に論じられるべきであり、これ以上立ち入ることはしないが、後半4曲は西洋音楽史のいわゆる「古典」と距離があるため、「西洋のクラシック」と括るのは無理がある。
以上のことから、落合の言う「東洋的美的感覚と西洋的美的感覚」とは、音楽作品の構造や音楽史に基づいたものではなく、落合独自の感覚に依るものだと判断されるが、コンサート内外ではあたかも自明であるかのように用いられている。
第二に、「東洋的美的感覚と西洋的美的感覚」や「我々が土着の文化の中で継承されたDNAのようなもの」といった理解を自明視する音楽会のあり方は、落合陽一×日本フィルプロジェクトにおいて模索されてきた広がりのある観客集団を、複数の側面から否定している。
くわえて、ここでの「我々」が、日本フィルハーモニー交響楽団の本拠地であり、このコンサートの会場でもある日本と明確に結びついている一方で、「土着」や「DNA」という語の援用によって、「東洋的美的感覚」にルーツを有した「日本」像があたかも自然であるかのように演出されていることにも、注意を払わなければならない。
「我々が土着の文化の中で継承されたDNAのようなもの」
「土着」という語を定義なしに用いることの危険性は、日本国内における思想の「土着化」をめぐる戦後の議論や5、「indigeneity」および「nativeness」の注意深い定義と運用——いずれの語も植民地主義の文脈と不可分に結びついていることから、今日まで多様な観点からの議論が続いている6——、あるいはビジネスの文脈における「土着化 dochakuka」(または「グローカライゼーション」)の国際的流行への批判的論証7をみても明らかである。
また、ここでの「DNA」は生物学的な本義で用いられているのではなく、ある文化的集団の中で先祖から子孫へ連綿と伝わり、集団に所属する誰もが自ずと共有している本性のようなものを指し示していると判断される。だが、ごく率直に、コロナ禍において移動が制限されたからといって、それまでに綿々と続いてきた人類の移動と交流の結果としての、ある集団内における多様性や交差性が失われるわけではない。「DNA」「遺伝子」と言った生物学的用語の比喩的用法が、集団の中で本性のようなものを自ずと共有できない個人を似非科学的な根拠で排除する思想に繰り返し用いられてきたことは、歴史上のさまざまな事例が示す通りだ8。思慮に欠けた政治家や文化人を騙ったインフルエンサーがこれらの語をいまだ濫用していることも、残念ながら事実ではあるが。
ゆえに、少なくとも、スペクトル楽派を先取りした音響分析に基づき、また東京オリンピック(1964)という場で上演された黛敏郎の「オリンピック・カンパノロジー」、阿寒湖アイヌシアター〈イコロ〉所属演奏家2名によるトンコリ演奏の「サプライズライブ」9、「日本狂詩曲」を経て自己のアイデンティティの問題に向き合った伊福部昭の「土俗的三連画」、そして、伊福部と池野成のもとで学び、演奏会のみならずポップカルチャーの領域でも盛んに活躍している和田薫の「交響曲 獺祭~磨 migaki~」を、ごく単純に、「我々が土着の文化の中で継承されたDNAのようなもの」の発露とみなすことには無理がある。
もしこれらの楽曲に表現されている「日本」らしき何かがあると仮定するのならば、各曲に多重的に織り込まれた文脈を紐解いていくことで、「日本」という概念の多面性や可変性をこそ追及するべきだっただろう。そうではなく、紋切型で表層的な意匠の映像や演出によって単一的な連想を強調した鑑賞空間においては、個々の観客が思いがけぬ自由な連想の拡がりを楽しむことは困難である。
「民族的に均質な日本人」論
だが、落合陽一の狙いは、むしろこの単一化にあったのではないだろうか。落合は、著書『日本再興戦略』(2018)の中で、「日本人は、どこまで行っても自然の中にある同質性・均質性にひもづいています」10と主張している。同書で彼の説く日本文化は次のようなものだ。
日本の文化は本当に多様です。昭和以降の文化と明治時代の文化には大きな違いがありますし、明治と江戸も全然違います。鎌倉時代と室町時代と戦国時代にも異なる美的感覚があります。たとえば、世阿弥が生まれるまでは、仕手や花、幽玄という考え方が美の中心に現れて来ることは稀ですし、本居宣長が問い返すまで『枕草子』などの文学が持つ意味は今と異なっていました。つまり、われわれの美的感覚は頻繁にアップデートされているのです。11
正確には、「幽玄」とは、古くは平安初期の『古今和歌集』に見られ、平安後期から鎌倉初期にかけての歌論において頻繁に登場し、歌風を評する語として広く定着していた(藤原俊成による『古来風体抄』が代表的)。世阿弥はそれを借用したのである。つまり、世阿弥以前に「幽玄」が「美の中心に現れてくることは稀」とする落合の論は誤りである12。言い添えると、落合は註の中で、世阿弥による『風姿花伝』を「芸術の技術本ではなく、精神について書いている本」13だと解説している。だが同書は、今日でこそ精神論として解釈されがちではあるものの、実際に読んでみればわかる通り、また能楽研究者の竹本幹夫による「能をいかに興行的に成功させるかという工夫の数々を、実演者としての立場から説いた、秘伝書」14とする解説にもあるように、稽古や本番中の演技、作品制作に至るまで、さまざまな場面におけるノウハウを非常に具体的に説いた技術書である。『日本再興戦略』の中で、落合は「我々はいったい何を継承してきて、何を継承していないのか。それを正確に把握した上で、今後勃興するテクノロジーとの親和性を考えていかないと、日本を再興することはできません」15と述べているが、その把握の内実には一考の余地がある。
「日本は同じ国の中でも、沖縄と北海道で文化が違う」16と説いたと思えば、「民族的に均質な日本人」17という語を何のてらいもなく繰り出す超論理的「日本」像は、「醸化する音楽会」の焦点の合わない構成と呼応している。落合の主張(「これから日本が東洋的な感覚を土台にしてテクノロジーを生かしていくためにも、まずは西洋的個人を超越しなければならない」18)と、音楽会の「ステートメント」における「東洋的美的感覚と西洋的美的感覚の対比構造」には相関関係が認められる。
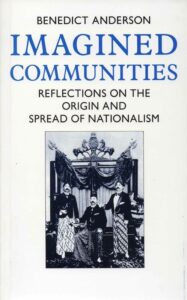 ここから類推できるのは、落合による「今我々の周囲にあるもの」と「今我々から距離があるもの」という二者の区分が、地理的な距離によるものではないということだ。感覚的な歴史叙述を論拠とした「我々」論の自明化、それは、E・サイードがかつて警鐘を鳴らした、西洋の帝国主義の枠組みの中で生み出された、本質主義に基づく自他意識にほかならない。
ここから類推できるのは、落合による「今我々の周囲にあるもの」と「今我々から距離があるもの」という二者の区分が、地理的な距離によるものではないということだ。感覚的な歴史叙述を論拠とした「我々」論の自明化、それは、E・サイードがかつて警鐘を鳴らした、西洋の帝国主義の枠組みの中で生み出された、本質主義に基づく自他意識にほかならない。
「西洋的本質に拘泥しつづけてきた個々の国家なり個人が、これぞ本質とみなしたものに対し、その周囲に「西洋」という名の防衛的境界線を引くという戦略」は、「支配的文化が、じっさいにはあらゆる文化の構成要素となっている不純性や混血性を抹消してきたプロセス」でもある19。「想像の共同体」(B・アンダーソン)としての国民国家が、同質的ではない「他者」を除外してきたことは、近代日本にも当て嵌まる20。そのことを知っていれば、「民族的に均質な日本人」という語が飛び出すこともあり得なかっただろう。
分断の深化に加担する
芸術作品と芸術作品の作り手とを安易に結びつけるべきではないという立場と、その立場から論ずることの意義を、筆者も理解しているつもりだ。だが、「醸化する音楽会」において、落合陽一が単なる監修・演出という役割を超えたブランドとして機能していることは明らかだ。上記の書籍を含む、落合のこれまでの業績が彼のネームバリューを支え、それが同音楽会の集客や価値基準に影響を与えている。
コンサートにおいて、観客は公演主催者の定めたプログラムを通じてのみ、作曲家と演奏家の音楽に接するほかない21。そこでの鑑賞体験は、開演前から終演後に至るまで、観客に提供されるさまざまな手立て——公演プログラムに掲載された曲目紹介、ホームページ上に載せられたコラム、上演中に舞台上から客席に向けて発されるさまざまなアナウンス(司会進行役による曲の合間の導入や解説、同音楽会においては聞香やグミの試食も含まれる)——の影響をどうしても受けざるをえない。コンサートという一回的な出来事は作り手と受け手の双方の関与によって成立するものではあるが、ここでの観客は、あくまでも提供されたプログラムを従順に受け容れることを暗に求められる立場にあり、時に拍手によってそれを承認することを半ば強いられる。
そして、このような音楽をめぐる聴取のあり方は、これまでに音楽が社会に関与し、社会において活動してきた不断の歴史の結果として制度化されたものである。それこそ、前述したサイードが文学批評の立場から切り込んだ領域であり、また、近年の音楽学がさまざまな周辺分野と連携し、音楽活動を超域的に追究してきたものである。筆者はそこに与する一研究者として、上記に述べてきた構造を許容することはできない。
従順な受容を暗に求められ、時に承認を半ば強いられる場において、安易で無批判な一元化と図式化に基づいた音楽会が起こすものは、五感の解禁ではない。安易な「日本」の括りと、「東洋」対「西洋」の乱暴な構図、そしてそれらを「身体性」「人間性」といった語で包み込んで提供するプログラムは、距離的な「分断によって気がついた」というよりも、内面化された分断から生まれ、分断のさらなる深化に加担する動きだと筆者は理解した。だが、落合と日フィルによるこれまでの長い歩みに鑑みれば、違和感を覚える人は黙って立ち去り、より同質化されたサポーターによって、このプロジェクトは守られ続けるだろう。
(2022/1/15)
-
- 落合陽一 × 日本フィルハーモニー交響楽団「《耳で聴かない音楽会》テクノロジーで挑む、音楽のバリアフリー」2018年4月20日募集終了。
- 落合陽一 × 日本フィルハーモニー交響楽団「醸化する音楽会|8/11 五感、解禁。音楽と身体性をとり戻す。」2021年7月25日募集終了。
- 日本フィルハーモニー交響楽団「【配信あり】落合陽一×日本フィル プロジェクトVOL.5 《醸化する音楽会》」
- 落合陽一×日本フィルハーモニー交響楽団「曲目紹介04 音楽会の構成(1)東洋的美的感覚と西洋的美的感覚」2021年07月22日。
- ごく一例を挙げると、例えば丸山眞男『忠誠と反逆』、澤井啓一『〈記号〉としての儒学』、上山春平『日本の思想──土着と欧化の系譜』など。
- ここでは、次の定義と議論を参照した。Guenther, M., “The Concept of Indigeneity,” Social Anthropology, vol. 14, iss. 1, 2006, 17-32; Sarivaara, E., Määttä, K. and Uusiautti, S., “Who is Indigenous? Definitions of Indigeneity,” European Scientific Journal, vol. 1, 2013, 369-78.
- 例えば、Roudometof, V., Glocalization: A Critical Introduction, 2016, Routledgeなど。
- Dar-Nimrod, I. and Heine, S. J., “Genetic Essentialism: On the Deceptive Determinism of DNA,” Psychol Bull, 137(5), 2011, 800–18.
- 落合陽一×日本フィル プロジェクト【公式】Twitterによる、2021年12月20日付けのツイート。
- 落合陽一『日本再興戦略』NewsPicks Book(kindle)、位置530.
- 同上、位置218.
- 落合は展覧会「映像と物質」(Art & Science gallery lab AXIOM、2017)で、「幽玄」を手掛かりにしている。
- 前掲、落合、位置393.
- 世阿弥、竹本幹夫『風姿花伝・三道 現代語訳付き』角川ソフィア文庫(kindle)、位置6363.
- 前掲、落合、位置119.
- 同上、位置1066.
- 同上、位置473.
- 同上、位置515.
- エドワード・サイード『音楽のエラボレーション』大橋洋一訳、みすず書房、2004[1995]、pp. 100-1.
- 近代日本におけるレイシズムが、血統や衛星、文明化の度合いなどの指標を時と場合に応じて持ち出す、すぐれて恣意的なものであったことは、例えばタカシ・フジタニが指摘している(タカシ・フジタニ「日本の天皇制と近代人種主義」斉藤綾子・竹沢泰子編『人種神話を解体する〈1〉可視性と不可視性のはざまで』東京大学出版会、2016)。
- 同上、p. 68.






