五線紙のパンセ|私が正しいという感性|稲森安太己
私が正しいという感性
Text & Photos by 稲森安太己(Yasutaki Inamori)
2020年10月、ウイルスの脅威が収束する気配も見せぬ中、11年間生活したドイツを後にして日本へと完全帰国した。帰国した理由はコロナウイルスによるものではないが、ドイツでの仕事もいくらかキャンセルになったりしていたこともあって、無事に日本に帰り着いたことに一安心している。日本で何かすべきことが決まっているということもなく、ドイツにいたときと同様に作曲を続ける日々が懐かしい環境で始まった。ただ、「同様に」と書いたが、現在の半ロックダウン生活の中で作曲作業が難しくなった懸案が一つある。人に近い距離で会うことがためらわれることである。ここ数年の私の創作を振り返ると、制作関係者と緊密な打ち合わせを繰り返してコラボレーションする作品が多くなってきていた。そのようなコラボレーションから出来上がった作品は、近年私が作品を提供する演奏会の在り方に対して感じていた些末な違和感に一つの答えとなりうる道標を示してくれたように思う。2つの事例をこの3回の連載で紹介したい。今回と次回は私のオペラ『WIR AUS GLAS』について書こうと思う。
 ドイツにはミュージック・シアター(オペラやダンスを伴うパフォーマンス、実験音楽的パフォーマンス等を含む)を専門のテーマとした音楽祭がある。バイエルン州の州都ミュンヘンで2年に一度のペースで開催されるミュンヘン・ビエンナーレである。シアター作品を一度にたくさん初演するフェスティバルは上演回数や公演会場を確保することが普通は難しく、個性的な現代音楽祭としてミュンヘンの街が力を注いでいる催し物である。私は2018年6月に自分にとって初めてとなるオペラ(と言ってよいのか難しいが、聴いてくださった方々からは「しっかりオペラだった」との意見を聞いた)『WIR AUS GLAS』(『ガラスの私たち』、2016-2018)が上演された。ビエンナーレはそれ自体で劇場を持っているわけではないので、ドイツ各地の劇場に打診してパートナーとなる劇場を見つけ、その劇場が客演公演としてミュンヘンで初演を含む公演をした後、地元の劇場でも公演するという仕組みであった。私の作品を上演してくれるパートナーとなったのはDeutsche Oper Berlin(ベルリン・ドイツ・オペラ)で、ミュンヘンで5回、ベルリンで5回の10回公演となった。
ドイツにはミュージック・シアター(オペラやダンスを伴うパフォーマンス、実験音楽的パフォーマンス等を含む)を専門のテーマとした音楽祭がある。バイエルン州の州都ミュンヘンで2年に一度のペースで開催されるミュンヘン・ビエンナーレである。シアター作品を一度にたくさん初演するフェスティバルは上演回数や公演会場を確保することが普通は難しく、個性的な現代音楽祭としてミュンヘンの街が力を注いでいる催し物である。私は2018年6月に自分にとって初めてとなるオペラ(と言ってよいのか難しいが、聴いてくださった方々からは「しっかりオペラだった」との意見を聞いた)『WIR AUS GLAS』(『ガラスの私たち』、2016-2018)が上演された。ビエンナーレはそれ自体で劇場を持っているわけではないので、ドイツ各地の劇場に打診してパートナーとなる劇場を見つけ、その劇場が客演公演としてミュンヘンで初演を含む公演をした後、地元の劇場でも公演するという仕組みであった。私の作品を上演してくれるパートナーとなったのはDeutsche Oper Berlin(ベルリン・ドイツ・オペラ)で、ミュンヘンで5回、ベルリンで5回の10回公演となった。
私はたまたまオペラを発表することになったが、実は自分の作曲家としてのキャリアの中でオペラを発表することを夢見たことがそれまでなかった。それと言うのも、自分が過去にオペラの上演を観に行った多くはない経験上、オペラという形態に拭えない違和感があり、自分の音楽を実現する場として適しているかどうか判断が難しかったことがある。その違和感とはすなわち今日の聴衆の多くが持つ「神の視点」に起因するところが大きい。新しく発表された音楽とは一聴しただけでは本当はよく分からないことも多い。しかし、現代を生きる私たちはしばしば「よく分からない」から価値なきもののように感じ、判断を早まる。これは慣れの問題が大きいと思っている。今日先進諸国に生きる人間のほとんどにとって、音や音楽が氾濫している日常を送ることは珍しくない。人は聴きたい音楽(あるいは一部分)を、自宅で、聴きたい時に、聴きたい音量で聴くのである。この傾向は現在猛威を奮っているウイルスの影響で更に強まるであろう。嗜好によって音楽を吟味することが容易で、自らの音楽的立場を整えた今日の聴衆は、演奏会で出会う知らない音楽すらも自らの経験から蓄積された嗜好(音の嗜好に限らない)に寄り添って即座に自らの中で価値を与えるだろう。価値なきものと判断されれば、その後の聴取は苦しい。音楽を聴く時間は録音再生技術のなかった時代に比べてすでに特別な時間としての意味が薄くなって久しい。
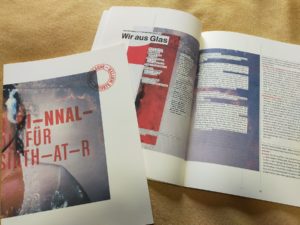 私自身、そのような「神の視点」的な感性が知らず知らずのうちに育ってしまったきらいがある。よほど自覚的に対策を講じない限り、時代や土地が求めるスタンダードな生活基準に添ったライフスタイルから人は自由ではない。未知の音楽を鑑賞する際には危険とも思われるこの自分基準すなわち「神の視点」が、私のオペラ鑑賞の愉しみを長年阻害してきた。シリアスなオペラの古典作品における主人公の背負う悲劇的な宿命は私には無関係に思えるし、コミカルなオペラの主人公たちのユーモアは今日的な感覚とズレているようにも感じる。それでも主演の演者の歌が大層上手であったら音楽的な歓びが損なわれることはないが、話の筋に感じる時代錯誤感とその想いをドラマチックに伝えようとする音楽的意図にはやはり違和感を感じていたし、オペラにおいてはそれがしかも長い。外国語も厳しい。私は劇場に字幕を読みにいくのか、それとも舞台で起こる様々を目撃しに行くのか。外国語や著名な物語の筋に不勉強な者は愉しむ資格がないと言われれば諦めるしかないが、シアターというものが知識人たちの知的満足感を充足させるためだけにあるのではないことも確かだと思う。そんな鑑賞の困難がありつつも、それとは別に舞台美術やコスチューム等、総合的な舞台から迸るエネルギーを生で浴びることに全く感動がないわけでもないのである。とにかく、オペラというジャンルはなんとも感動の質を捉え難い手に余る様式という認識があった。そして自分で自分の嗜好の有り様が正しいと感じていた若い頃は、こういった感動の質が捉え難い経験は嬉しくなかった。
私自身、そのような「神の視点」的な感性が知らず知らずのうちに育ってしまったきらいがある。よほど自覚的に対策を講じない限り、時代や土地が求めるスタンダードな生活基準に添ったライフスタイルから人は自由ではない。未知の音楽を鑑賞する際には危険とも思われるこの自分基準すなわち「神の視点」が、私のオペラ鑑賞の愉しみを長年阻害してきた。シリアスなオペラの古典作品における主人公の背負う悲劇的な宿命は私には無関係に思えるし、コミカルなオペラの主人公たちのユーモアは今日的な感覚とズレているようにも感じる。それでも主演の演者の歌が大層上手であったら音楽的な歓びが損なわれることはないが、話の筋に感じる時代錯誤感とその想いをドラマチックに伝えようとする音楽的意図にはやはり違和感を感じていたし、オペラにおいてはそれがしかも長い。外国語も厳しい。私は劇場に字幕を読みにいくのか、それとも舞台で起こる様々を目撃しに行くのか。外国語や著名な物語の筋に不勉強な者は愉しむ資格がないと言われれば諦めるしかないが、シアターというものが知識人たちの知的満足感を充足させるためだけにあるのではないことも確かだと思う。そんな鑑賞の困難がありつつも、それとは別に舞台美術やコスチューム等、総合的な舞台から迸るエネルギーを生で浴びることに全く感動がないわけでもないのである。とにかく、オペラというジャンルはなんとも感動の質を捉え難い手に余る様式という認識があった。そして自分で自分の嗜好の有り様が正しいと感じていた若い頃は、こういった感動の質が捉え難い経験は嬉しくなかった。
作曲経験を重ねるうちに自分の嗜好を自作に活かすということが作曲活動の目標ではなくなっていった。そんなことをわざわざ考えなくても、続けていれば自分らしい音しか書けないことに気付く。私の趣味嗜好が正しいという感性も薄れた。別に自分の感性や感覚を無価値と見做しているわけでもないが、もう少し意味が分からない難解なものもじっくり考えてみたいし、難しい作曲にも挑戦したいという欲が育っていったのだ。そうするとこれまで苦行のようであったオペラ観劇も、別の味わい方を考えるようになった。いくらかのオペラ鑑賞から感じた違和感はそのまま私の作曲における表現課題かもしれないという視点を持った。そんな時分、ミュンヘン・ビエンナーレ音楽監督のマノス・ツァンガリス氏が私に打診してきた。
 ミュンヘン・ビエンナーレではその年の音楽祭のテーマを掲げる。新曲の依頼を受けた作曲家たちはそのテーマを個々に吟味し、テーマが持つ社会的メッセージや芸術的価値を作品に反映する。私が『WIR AUS GLAS』を発表した2018年の音楽祭テーマは「私的なこと」(private matter)であった。実はこの2年前の2016年の音楽祭で発表することはどうかとツァンガリス氏から2014年にすでに打診があったのだが、諸々の理由で2016年の発表は叶わなかった。しかし、時が経ち新しく発表されたテーマを聞くと私の創作意欲が俄然湧いた。「私的なこと」というテーマであれば、私がオペラ鑑賞時にしばしば感じる違和感と相対し創造的に取り組むことが出来るかもしれない。
ミュンヘン・ビエンナーレではその年の音楽祭のテーマを掲げる。新曲の依頼を受けた作曲家たちはそのテーマを個々に吟味し、テーマが持つ社会的メッセージや芸術的価値を作品に反映する。私が『WIR AUS GLAS』を発表した2018年の音楽祭テーマは「私的なこと」(private matter)であった。実はこの2年前の2016年の音楽祭で発表することはどうかとツァンガリス氏から2014年にすでに打診があったのだが、諸々の理由で2016年の発表は叶わなかった。しかし、時が経ち新しく発表されたテーマを聞くと私の創作意欲が俄然湧いた。「私的なこと」というテーマであれば、私がオペラ鑑賞時にしばしば感じる違和感と相対し創造的に取り組むことが出来るかもしれない。
少しだけ補足しておきたいのは、上述した今日的な音楽聴取の感覚を私は嘆いていないということである。今の時代の日本にたまたま生まれて自然に備わった感覚を喜ぶ必要もなければ呪う必要もない(自由に音楽活動が出来る国と時代に生まれた事実は結構嬉しい)。古い時代に書かれたものが今日多少の違和感を示してくることも自然と思う。しかし、先人の思考、作曲に無関心でいることは怠惰だと信じており、研究と作曲を通して思索することを止めずにいようとしている。次回は『WIR AUS GLAS』の制作と発表に関わるお話を書く。
noteに毎週短い記事を書いています。自作のことや他の作曲家の曲を読んで聴いた感想等。
https://note.com/yasutaki_inamori
————————————————————
稲森安太己 (Yasutaki Inamori)
1978年東京生まれ。 東京学芸大学にて作曲を山内雅弘氏に、ケルン音楽大学にて作曲をミヒャエル・バイル、ヨハネス・シェルホルンの両氏に師事。作品は西ドイツ放送交響楽団、ギュルツェニヒ管弦楽団、ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団、新日本フィルハーモニー管弦楽団等の演奏団体によってドイツ、イタリア、アメリカ、ベルギー、日本ほかの国で演奏されている。2007年日本音楽コンクール第1位、2011年ベルント・アロイス・ツィンマーマン奨学金賞、2019年芥川也寸志サントリー作曲賞ほか。


