小人閑居為不善|BLMをよく知るための「白人」映画――ジョン・フォードからランボーへ|noirse
BLMをよく知るための「白人」映画――ジョン・フォードからランボーへ
“White” Movies to learn more about BLM
Text by noirse
※《ランボー ラスト・ブラッド》の結末に触れている箇所があります
1
 映画館が再開して、早速《ルース・エドガー》(2019)を見に行った。黒人をステレオタイプに当てはめてレッテル化することの欺瞞を引き剥がしていく内容でよく考えて作ってあり、ブラック・ライブス・マター(BLM)運動と繋がる点からも評判はいい。
映画館が再開して、早速《ルース・エドガー》(2019)を見に行った。黒人をステレオタイプに当てはめてレッテル化することの欺瞞を引き剥がしていく内容でよく考えて作ってあり、ブラック・ライブス・マター(BLM)運動と繋がる点からも評判はいい。
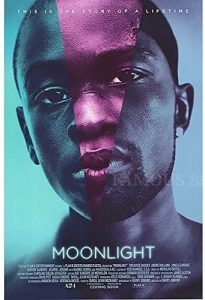 BLMデモが再燃している。映画界も無縁ではなく、数年前から《フルートベール駅で》(2013)、《デトロイト》(2017)、《ゲット・アウト》(2017)、《ブラック・クランズマン》(2018)など、BLMとリンクする作品が製作されてきた。評価はどれも高く、《ムーンライト》(2016)はアカデミー賞作品賞まで射止めた。
BLMデモが再燃している。映画界も無縁ではなく、数年前から《フルートベール駅で》(2013)、《デトロイト》(2017)、《ゲット・アウト》(2017)、《ブラック・クランズマン》(2018)など、BLMとリンクする作品が製作されてきた。評価はどれも高く、《ムーンライト》(2016)はアカデミー賞作品賞まで射止めた。
けれどこれらの映画には不満もある。立派なのは間違いないし、つまらないわけではない。ただ手に汗を握るほど「おもしろい」と感じたこともなかった。
このところネットメディアで「BLMを知るための映画〇選」というような企画をいくつも見かけた。そこでも上記のような作品が紹介されているが、「勉強のために見る映画」という印象は拭えない。もちろん映画を勉強目当てで見るのはいいことだが、おもしろいかどうかは別だ。
注意しておくが、ここで使う「おもしろさ」という言葉はわたし個人の印象に留まるものではない。知的興奮という言葉がある通り、勉強も娯楽になる。けれど理性でなく感情に直接訴えることを目的とした作品と比べて、それらはどう機能するだろうか。
 その後《ランボー ラスト・ブラッド》(2020)を見てきた。シルヴェスター・スタローン主演で人気のシリーズ最終作で、率直に感情に訴えかける「おもしろさ」に特化した内容だが、そこを越えて2020年の今、とても重要な映画だと感じた。その理由を探っていけば、「BLMを知るための映画」の弱点も分かっていくだろう。
その後《ランボー ラスト・ブラッド》(2020)を見てきた。シルヴェスター・スタローン主演で人気のシリーズ最終作で、率直に感情に訴えかける「おもしろさ」に特化した内容だが、そこを越えて2020年の今、とても重要な映画だと感じた。その理由を探っていけば、「BLMを知るための映画」の弱点も分かっていくだろう。
2
 ベトナム帰還兵ジョン・ランボーは心に深い傷を負い、アメリカ各地を放浪していた。ところがある町の警察署長に目を付けられて強引に逮捕され、反発したランボーは保安官事務所を脱走。山狩りを開始した警官たちを前に、たった一人の戦争が始まる。
ベトナム帰還兵ジョン・ランボーは心に深い傷を負い、アメリカ各地を放浪していた。ところがある町の警察署長に目を付けられて強引に逮捕され、反発したランボーは保安官事務所を脱走。山狩りを開始した警官たちを前に、たった一人の戦争が始まる。
《ランボー》1作目(1982)には、ベトナム戦争の暗部、帰還兵差別など、手応えのあるテーマが随所に見受けられる。しかしその後の2作、《ランボー/怒りの脱出》(1985)、《ランボー3/怒りのアフガン》(1988)は、敵を逡巡なく殺戮していくアクション大作に変化してしまった。シリーズのブロックバスター化も一因だが、共和党を支持するスタローンには「強いアメリカ」を打ち出したいという意図もあった。
《ラスト・ブラッド》はどうか。4作目《ランボー/最後の戦場》(2008)の最後、アリゾナの実家の牧場に帰郷したランボーは、旧友のマリアとその孫娘ガブリエルと共に静かな生活を送っていた。ところがガブリエルがメキシコのマフィアに誘拐され、ランボーは救出に向かう。深い傷を負ったランボーは屋敷のポーチのロッキング・チェアに腰を落とし、遂に安息を掴むことができなかった人生の終末を噛み締め、シリーズの幕が下りる。
苦いラストが味わい深いものの、無法地帯のようなメキシコの描写が移民などへの差別を助長するとされ、アメリカでは非難轟々の結果に終わった。この批判はもっともだが、これだけで片付けてはこの映画の持つ意味が見落とされてしまう。
3
《ラスト・ブラッド》は馬に跨ったスタローンの姿から始まり、ポーチから夕焼けに照らされた牧場を眺めるシーンで終わる。これだけで映画ファンには、スタローンがランボーという器で西部劇を撮りたかったのだとピンとくるだろう。
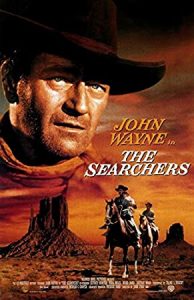 もっと言えばジョン・フォードだ。誘拐された娘を取り戻しに行くというストーリーは、フォードの代表作《捜索者》(1965)が決定的な作品として知られている。
もっと言えばジョン・フォードだ。誘拐された娘を取り戻しに行くというストーリーは、フォードの代表作《捜索者》(1965)が決定的な作品として知られている。
これは表面上の話に留まらない。フォードは共和党を支持し、ベトナム戦争にも賛成していた。熱心な共和党支持者だったジョン・ウェイン主演のフォード作品を見れば、自分の信念に基づいて行動する、自由主義的な価値観が容易に見て取れる。
 後の世代にもフォードの美意識と思想は受け継がれている。クリント・イーストウッドが主演した《マンハッタン無宿》(1968)はフォード作品の登場人物が現代のNYに彷徨い込んだような作品だが、これは《ダーティハリー》(1971)の原型となった。ハリー・キャラハンは一匹狼タイプの刑事ものの映画やドラマの走りで、フォードの影響力の大きさが分かる。ランボーも同じ信念の持ち主だ。
後の世代にもフォードの美意識と思想は受け継がれている。クリント・イーストウッドが主演した《マンハッタン無宿》(1968)はフォード作品の登場人物が現代のNYに彷徨い込んだような作品だが、これは《ダーティハリー》(1971)の原型となった。ハリー・キャラハンは一匹狼タイプの刑事ものの映画やドラマの走りで、フォードの影響力の大きさが分かる。ランボーも同じ信念の持ち主だ。
もうひとつ重要なのがトンネルだ。初作でのランボーは、山中の洞窟に身を潜め警官たちを罠にかけていった。《ラスト・ブラッド》でも敵を牧場の地下トンネルに誘い込み、一人ずつ無残に殺していく。牧場でのランボーは表面上は静かな生活を送っていたが、ベトナムの狂気はまだ彼を囚えて離さず、意味もなくトンネルを掘り、生活の幾分かを地下で送っていた。
ベトナムのゲリラ兵は洞窟を拠点とした。アメリカ兵はそこへ入らざるを得ず、暗闇の中で多くが命を落とし、生きて戻った者もPTSDに悩んだ。ランボーも同じだったのだろうが、彼はトンネルの闇から逃げ回るより、恐怖と同化することを選んだ。
年老いたランボーは、普通の生活を送ることを許されなかった自らを呪詛する。今回の事件は彼が原因ではないが、死の恐怖に彩られた自身の運命に周囲を引き寄せたと思っている。トンネルの闇から脱しきれなかった自分を許せないのだろう。
4
 死の恐怖。ここでホラー映画を挟んでみたい。テキサスの片田舎に棲む殺人鬼レザーフェイスとその一家を描いた《悪魔のいけにえ》(1976)は、スプラッター映画の先鞭をつけた作品だ。だが監督のトビー・フーパーはただ残酷な映画を作りたかっただけではない。自らの出身地テキサスの気風を寓話化し、作品に落とし込んだのだ。
死の恐怖。ここでホラー映画を挟んでみたい。テキサスの片田舎に棲む殺人鬼レザーフェイスとその一家を描いた《悪魔のいけにえ》(1976)は、スプラッター映画の先鞭をつけた作品だ。だが監督のトビー・フーパーはただ残酷な映画を作りたかっただけではない。自らの出身地テキサスの気風を寓話化し、作品に落とし込んだのだ。
テキサスは元来共和党の牙城で、銃規制にも反対する保守州だ。自衛意識が強く、政府からの干渉を忌避する傾向がある。レザーフェイスたちは彷徨い込んだ人間を殺して食すカニバリズム一家だが、この異常な「自給自足」のライフスタイルは、テキサス魂の極端なカリカチュアとなっている。
こうしたテキサスへのシニカルな目線は《悪魔のいけにえ2》(1986)でさらに加速する。レザーフェイス一家は廃業した遊園地の地下に潜み、人を殺してはその肉を秘密裏に卸している。そこに前作で親族を失ったテキサス男が復讐に乗り込むが、二刀流でチェーンソーを振り回す彼も正気とは思えない。フーパーはテキサスという地を徹底的に風刺していく。
これはとりもなおさず、アメリカ社会のグロテスクなパロディでもある。たとえばプレッパーだ。自宅にシェルターを作りいつでも立てこもれるように準備している人々で、共和党支持者に多い。レザーフェイス一家が住まう地下空間はプレッパーを彷彿とさせる。
ランボーもプレッパーだが、度を越して残虐な「自衛」はもはやモンスターで、レザーフェイスの領域に近付いている。スタローンはこの作品をフォード映画に連なる伝統の中に置きたかったのだろうが、一方で一部の白人が抱える不安を救い取り、かつ娯楽的な過激さを追求するあまり、フーパーが誇張して描いた「アメリカ」に近付いてしまったのだ。
5
ロックダウンが始まる中、銃を買い求めるため行列する人々。BLMデモを前に、銃を構え並ぶ白人たち。彼らが《ラスト・ブラッド》を見れば、メキシコ描写の可否はともあれ、ランボーに感情移入し、理屈抜きに楽しむことができるだろう。よくも悪くも、「BLMを知るための映画」の対極にある「白人映画」と言えよう。
「BLMを知るための映画」より《ラスト・ブラッド》の方が「おもしろい」と述べた点はここだ。これらの映画は《ラスト・ブラッド》のようには理屈抜きに感情を揺さぶり、観客を煽ることはない。直接家族に危害が加えられるとなれば、法に触れても守りたいと思う人は少なくないはずだ。誰だってそうした感情を仕舞い込み、表面的には法が大事と嘯いてみせるものだ。
フォードからイーストウッド、スタローンに連なる「白人映画」は、そうした感情操作の上で興行を賑わせ、今に至る評価を築き上げてきた。BLM関連の映画はそれらへのカウンターとして製作されているが、理性的な彼らの作品は、《ラスト・ブラッド》ほどは(当事者たる被差別者を除いて)直接感情に訴えかけてはくるまい。
それは国内の反応を見ていると分かる。前述の通り《ラスト・ブラッド》の本国の評価は低く、レビューサイトRotten Tomatoesが調査した支持率は27%だが、日本のレビューサイトFilmarksでの初週満足度は1位を記録している。SNSでの評判を眺めていても、復讐に燃えるランボーに共感する向きは多いようだ。
日本人はひとたび白人社会に出れば差別される側だ。コロナショック以降、欧米ではアジア人差別が横行しているとも言う。けれど日本国内では不思議なことに、自分たちを白人側=差別者側に置いてしまう傾向がある。BLM関連の映画を見て黒人に共感する一方で、ランボーに感情移入することもたやすく行ってしまうのだ。
BLM関連の映画は、「白人映画」の率直さと比べ、どうしても分が悪い。これは構造的な問題で、その差を埋めるのは至難の業だろう。また今回は触れなかったが、ブラックスプロイテーション映画のように率直に感情に訴えようとする黒人映画も存在する。この差をどう埋めていくのかは今後の課題となるだろう。
《ラスト・ブラッド》はこうしたBLM関連の映画へのクロスカウンターのようでさえある。しかしその真価は「正しく」評価の得られなかったアメリカより、好意的に受け入れられた日本でこそ発揮しているように感じられる。BLMは対岸の火事ではない。「BLMを知るための映画」を勉強しようという前に、見つめ直すべき点があるのではないだろうか。
(2020/7/15)
————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中


