小人閑居為不善日記|シャロン・テートとウッディ・プライド――《ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド》について|noirse
シャロン・テートとウッディ・プライド――《ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド》について
Sharon Tate and Woody Pride
Text by noirse
※《トイ・ストーリー4》と《ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド》、
《イングロリアス・バスターズ》の結末について触れています
1
 7月に取り上げたブルース・スプリングスティーンの新作のテーマは西部劇だった。その後《トイ・ストーリー4》を見に行ったところ、こちらも西部劇が隠れたモチーフとなっていた。
7月に取り上げたブルース・スプリングスティーンの新作のテーマは西部劇だった。その後《トイ・ストーリー4》を見に行ったところ、こちらも西部劇が隠れたモチーフとなっていた。
主人公ウッディはカウボーイの人形だ。トイ・ストーリー・シリーズの見所のひとつは、ウッディたち玩具の、持ち主への変わらぬ愛情と忠誠心にあった。しかし新作でのウッディは、持ち主の元に留まることをやめ、見知らぬ世界へと旅立つことを決意する。
持ち主への忠誠心と言えば外聞はいいが、視点を変えれば束縛である。前作《トイ・ストーリー3》(2010)から10年、社会も大きく変化した。2019年にトイ・ストーリーをやり直すのであれば、旅立ちこそがふさわしいだろう。
しかし一部のファンは失望したようだ。持ち主の元での変わらぬ毎日をウッディに選択してほしかったのだろう。変化を望まず現状維持を望む、保守的な考えだ。
そう考えると、ウッディが西部劇の人形であるという事実は示唆的だ。自分たちの土地を脅威から守り家族(や仲間)を養っていく、このようなアメリカらしい保守思想が西部劇の根底にある。ウッディには保安官のイメージも託されているが、そこにはこうした保守的な思想が張り付いている。
しかしピクサーはそこからの離別を決意した。カウボーイといえば旅だ。変化を恐れないこと、それこそが今求められている。
けれど《トイ・ストーリー4》が毀誉褒貶あるように、皆がそう思うわけではない。
2
 もう1本、西部劇と関係する作品を取り上げたい。現在も公開中の映画《ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド》だ。監督のクエンティン・タランティーノはハリウッド屈指のオタクで、マニアックなネタを大量に投下していくのが彼の作風だ。
もう1本、西部劇と関係する作品を取り上げたい。現在も公開中の映画《ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド》だ。監督のクエンティン・タランティーノはハリウッド屈指のオタクで、マニアックなネタを大量に投下していくのが彼の作風だ。
映画はふたつのパートに分かれる。ひとつは実在の女優、シャロン・テートのパートだ。映画監督ロマン・ポランスキーと結婚後、妊娠中にカルト集団マンソン・ファミリーの襲撃に遭い、子供と共に惨殺された。映画は事件のしばらく前に遡り、彼女の幸せそうな日々を淡々とフォルムに収めていく(演じるのはマーゴット・ロビー)。
一方で、ポランスキー邸の隣に住む俳優リック・ダルトンと彼の専属スタントマン、クリフの毎日が綴られていく。リックはTVドラマのガンマン役で一世を風靡したが、時代の変化に対応できず、人気は下降線を辿っている。クリフはそんなリックを公私共に支える、唯一の親友だ。タランティーノは彼らに滅びゆくかつてのハリウッドを体現させ、レクイエムを奏でていく。
しかしやはり最大の注目はラストにある。ほとんどの観客はシャロンがどうなるか知っている。終盤に近付くにつれ、カウントダウンのように緊張感が高まっていくのは必然だ。だが映画は予想外の展開を見せる。襲撃者はリックとクリフに退治され、ポランスキー邸への襲撃自体なかったことになるのだ。シャロンは何の不安もなく穏やかな毎日を続けていくだろう。映画は幕を閉じる。
これ以上ないハッピーエンドだ。せめて虚構の世界でだけはシャロンに幸せになってほしいという思いが伝わってくるし、それは映画ファン全員の願いでもあるだろう。わたしもそこは変わらない。
それでも、のどに小骨が引っかかったような気持ちが残ってしまうのは、如何ともし難かった。
3
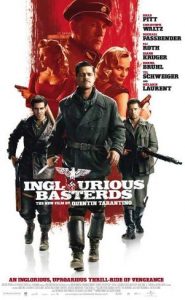 《ワンス~》のような歴史改変の手法を、タランティーノは《イングロリアス・バスターズ》(2009)で先に採用している。ナチスに家族を殺されたユダヤ人の映画館主が一計を案じ、映画館の中でヒトラーらナチの高官たちを焼き殺すという話だ。
《ワンス~》のような歴史改変の手法を、タランティーノは《イングロリアス・バスターズ》(2009)で先に採用している。ナチスに家族を殺されたユダヤ人の映画館主が一計を案じ、映画館の中でヒトラーらナチの高官たちを焼き殺すという話だ。
虚構の力で現実を変える。映画ファンに限らず、フィクションの世界に魅入られた者は、こういった手法に弱いものだ。それまでのタランティーノは得意の映画ネタを散りばめながらギャングたちの閉じた世界を描くことが多かったが、《イングロリアス・バスターズ》以降は変化し、《ジャンゴ 繋がれざる者》(2012)や《ヘイトフル・エイト》(2015)では黒人奴隷問題へ切り込んでいく。
村上春樹ふうに言えば「デタッチメントからコミットメントへ」というところだろうか。結果タランティーノはさらなる評価を得て、今ではアメリカを代表する監督のひとりとなった。
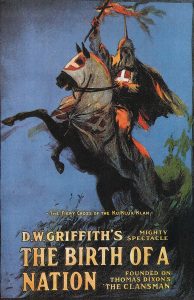 しかしわたしは、昨今のタランティーノに疑問を拭うことができない。たとえば《ジャンゴ》だ。この作品の背景には《國民の創生》(1915)の存在がある。映画表現を大きく拡張した「映画の父」D・W・グリフィスの畢生の大作だが、黒人を差別的に描いたことで、今では史上最大の問題作のひとつとなっている。タランティーノは《國民の創生》について否定的な発言を繰り返しており、《ジャンゴ》でも同作を批判的に扱ったシーンを用意している。
しかしわたしは、昨今のタランティーノに疑問を拭うことができない。たとえば《ジャンゴ》だ。この作品の背景には《國民の創生》(1915)の存在がある。映画表現を大きく拡張した「映画の父」D・W・グリフィスの畢生の大作だが、黒人を差別的に描いたことで、今では史上最大の問題作のひとつとなっている。タランティーノは《國民の創生》について否定的な発言を繰り返しており、《ジャンゴ》でも同作を批判的に扱ったシーンを用意している。
《國民の創生》は批判されても仕方がない作品だ。けれど100年も前の映画なのだ。どれだけ批判しようととっくに世を去ったグリフィスから反論されることはないし、「政治的に正しい」から誰も悪くは言えない。《國民の創生》批判は、安全に「差別と闘える」場所なのだ(非黒人のタランティーノがこうした作品を撮ることで、スパイク・リーからは批判されたが)。
 だから《ジャンゴ》を見ても、安全地帯で批判ごっこに戯れているようにしか見えなかった。本当に差別と戦うならば、今目の前で起きている問題を扱ったほうがいいに決まっている。《イングロリアス・バスターズ》も同じだ。ナチスがどれだけひどい目にあっても怒る者はいない。しかしタランティーノは、《イングロリアス・バスターズ》以降、現代を舞台にしようとはしない。
だから《ジャンゴ》を見ても、安全地帯で批判ごっこに戯れているようにしか見えなかった。本当に差別と戦うならば、今目の前で起きている問題を扱ったほうがいいに決まっている。《イングロリアス・バスターズ》も同じだ。ナチスがどれだけひどい目にあっても怒る者はいない。しかしタランティーノは、《イングロリアス・バスターズ》以降、現代を舞台にしようとはしない。
グリフィスのような大監督にマウントを取り、社会的な問題に切り込んでいるように見せながら、現実を直視することはない。タランティーノはデタッチメントなままなのだ。
4
《ワンス~》はどうだろうか。この作品は声高に社会問題を告発するような作品ではない。しかしそれは表面的な見方でしかない。
1969年。それまで過熱する一方だった反戦運動はニクソンの大統領就任で沈静化し、オルタモントのロックフェスでの殺傷事件やジミヘン、ジャニス、ジム・モリスンらの薬物死もあって、運動や意識変革の象徴だったドラッグ・カルチャーやロックも力を失っていった。
シャロン・テート事件は、このような時代の変化を象徴している。マンソン・ファミリーは皆ヒッピーで、セックスやドラッグ、ロックによって団結していた。その点だけ取れば、彼らは他の学生やヒッピーと変わらないただの若者だった。事件の全貌が明らかになるにつれ、一歩間違えていれば事件を起こしていたのは自分だったのではと感じた者もいただろう。マンソン・ファミリーは、ヒッピー・ムーブメントのネガだった。
今のアメリカは、1969年の「敗北」の上に立っている。しかし、もしあのとき若者たちが「勝って」いたらどうだろう。ニクソンが民主党に敗れ、ベトナム戦争が終結し、ジミヘンやジャニス、シャロンが生きていればどうだったろう。
《ワンス~》には、そうした思いが込められている。時代の流れをまるごと変えることはできない。だがせめてシャロンだけは、押し寄せる残酷な現実から救い出したい。映画の世界だけは、現実から無縁でありたい――。
お気付きだろう。この感情は《トイ・ストーリー3》と近似している。さらに言えば、トランプの「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン」ともそう変わらないだろう。
ピクサーは一旦閉じた扉をこじ開けてウッディを解放したが、タランティーノはリックを、シャロンを、そして観客をも、滅んでいった映画の時間に閉じ込めてしまう。もともとデタッチメントだったタランティーノだが、これほど閉塞的な作品はなかった。
「シャロン・テートは殺されてよかった」と言える人間はいない。あの幸福感に満ちたラストを見てしまうと、この映画に問題があっても、否定しにくくなってしまう。つまりシャロンを生かすことが、本作の安全地帯になっているのだ。言い換えればタランティーノは、シャロン・テートを人質にすることで、作品の成功を確保したと言えよう。
《ワンス~》を見ているあいだ、わたしは京都アニメーションの事件を思い返さずにいられなかった。何故シャロン・テートは、京アニの人たちは、死ななくてはならなかったのか。
《ワンス~》のラストは、それにひとつの回答をもたらしてくれる。彼らに死ななくてはいけない理由なんてない。さあ、彼らが幸せに生きている世界を想像しようではないか――。
残酷な現実を一時だけ忘れさせてくれる、魅力的なささやきだ。だが同時に、後ろめたく感じてもしまう。
タランティーノは確かに優れた監督だ。《ワンス~》の仕掛けは《イングロリアス・バスターズ》を踏襲しているが、遥かに周到で、監督として未だに成長しているのが分かる。
しかし彼のこうした態度は、やはり好きになれない。一度起きてしまったことはなかったことにはできない。《ワンス~》のささやきに身を任せるのは、シャロンや京アニを忘れ去ってしまうようなものだ。だからこそわたしは、この映画を全肯定する気にはなれない。シャロンとウッディは同じだ。一方的に閉じ込めるようなことはあってはならないのだ。
(2019/10/15)
————————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中


