小人閑居為不善日記|アベンジャーズの弱み、ポケモンの歪み|noirse
アベンジャーズの弱み、ポケモンの歪み
text by noirse
※《アベンジャーズ/エンドゲーム》と《名探偵ピカチュウ》の結末について触れている箇所があります
1
欧州議会議員選挙はEU支持の中道派が大きく議席を減らし、懐疑派が躍進した。一方、米ギャラップ社の発表ではトランプ大統領の支持率が同社調査最高の46%まで増加している。各国で進む保守化の大きな理由は移民への不信感だ。
わたしもトランプやサルヴィーニは好きではない。だが彼らに投票する人の気持ちも分からないではない。差別感情に基づいた支持者は当然別だが、実際に移民政策の影響で失職する人もいれば、残念ながら治安が悪くなった街もある(移民だけに問題を押し付けるわけにはいかないが)。自分が同じ立場に置かれたらどうだろう。
 今回は2本のハリウッド映画の話をしたい。1本目はロングラン中のマーベル映画、《アベンジャーズ/エンドゲーム》(2019)。マーベル映画は《ブラックパンサー》(2018)や《キャプテン・マーベル》(2019)などで黒人や女性の権利を高々に謳い、リベラルなメッセージが高く評価されている。
今回は2本のハリウッド映画の話をしたい。1本目はロングラン中のマーベル映画、《アベンジャーズ/エンドゲーム》(2019)。マーベル映画は《ブラックパンサー》(2018)や《キャプテン・マーベル》(2019)などで黒人や女性の権利を高々に謳い、リベラルなメッセージが高く評価されている。
だがこれは建て前だ。作品をつぶさに見れば、本音は別にあることが分かる。ひとつめのキーワードは「他者」だ。
《エンドゲーム》では、アベンジャーズ最大の敵のひとり、サノスというヴィラン(悪役)が登場する。ヒーローが束になっても適わない、宇宙最強の大ボスだ。
サノスは世界の救済のため、未曽有の大破壊を決行する。彼なりの論理はあるのだが、それは多くの犠牲を必要とする、自分勝手なロジックだ。サノスの行動は、ISなどのテロリストを想起させる。
だが一方、サノスは思いのほか人間味溢れる存在としても描かれる。目的のために養女ガモーラをも殺めるが、自責の念を覚え、目的を果たしたあとは引退して農場に落ち着いてしまう。
ここで注視しておきたいのは、サノスがアベンジャーズのひとり、トニー・スターク(アイアンマン)の鏡像として設計されている点だ。トニーは長らく軽薄なプレイボーイとして描かれてきた。しかし仲間との戦いを通して彼は成長していく。
その過程で重要となるのがピーター・パーカー(スパイダーマン)との出会いだ。ピーターはまだ高校生で、父親がいない。ピーターにヒーローの心得を教えていくトニーは、次第に父親めいた感情を覚えるようになる。
《エンドゲーム》でピーターを失ったトニーはひどく落ち込み、妻とのあいだに子供をもうけ、農場に引っ込んでしまう。父親としての苦悩。引退後の農場暮らし。ガモーラやピーターとの関係。この共通点の多さはどうだろう。
とどめは戦いの最後だ。トニーは機転を利かし、サノスを滅ぼす。だがその代償として、トニーも命を落としてしまう。ふたりの鏡像関係を踏まえて考えれば、これは自殺や心中に近い。
この仕組みはよくできている。理解しがたい思想を持つサノスも子供の前ではひとりの親であって、その点ではトニーとも、われわれ観客とも何ら変わることはない。言い換えれば、遠い異国の移民であっても同じ人間なのだから理解できるはずだというメッセージが隠されているわけだ。
2
――と、ここまでは建前だ。正直なところわたしは、今回のサノスの扱いには失望した。宇宙最強のヴィランを期待していたのに、スクリーンに映っていたのはただのしょぼくれたオヤジだったからだ。
《エンドゲーム》は空前の成績を上げており、全世界興行収入1位の《アバター》(2009)の座を奪取すると見込まれている。成功の理由のひとつは、10年以上、30本に迫る作品の中で、20人余に渡るヒーローをじっくり育ててきたことにある。戦いの過程で傷付き、悩み、苦しむヒーローたちに、観客は共感し、彼らのその先を知りたいと熱望したからだ。
だが「共感」はクセモノでもある。共感できないキャラクターは没入の妨げになり、興行にも響いていく。そのためにマーベルは巧妙に、共感しにくいキャラクターの性格を変更したり、出番を減らして対処してきた(詳しくは佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて》をお読み頂きたい)。
サノスの「農場のオヤジ」化もその一環だ。表面上は他者への共感を掲揚しているように見えるが、実際には共感できない者を遠方に追いやり、隠蔽しているだけに過ぎない。
もちろん売上を重視するのは悪いことではないし、そのために少しくらいの欺瞞や偽善に走るときもあるだろう。キャラクターの性格くらいなんだと思う人もいるかもしれない。
しかしその上で、理解はしておくべきなのだ。利益の為に共感を煽り、共感できないものは排除する。《エンドゲーム》で行われていることは、リベラルというよりも、トランプや欧州の保守政党の主張に近いのだと。
3
次に注目したいキーワードは「家族」だ。《エンドゲーム》にはしきりに家族重視のメッセージがちらつく。
たとえば世界を救うために、ある男女2人のキャラクターの、どちらかが犠牲にならなければいけなくなる場面がある。結果、犠牲になるのは女のキャラだ。別に性差別的な理由でそうなったわけではない。彼らには歴然とした違いがある。犠牲となった女には家族がおらず、生き永らえた男には守るべき家族がいたのだ。女は帰る家がある男を生かすべきだと考えて、自らを犠牲とする。もし家庭を築いていたのが女だったら、犠牲になったのは男の方だったろう。
トニーとサノスについても同じだ。圧倒的に能力差の劣るトニーが何故サノスに勝てたのか。簡単である。サノスは目的の為に家族を捨てたが、トニーは家族の為に自分を捨てたからだ。
こう並べてみると《エンドゲーム》では、「家族を大事にすべき」どころか、「家族を持つべき」という、ひどく保守的な価値観が作品を支配していることが分かる。
 ここでもうひとつの作品、《名探偵ピカチュウ》(2019)を見てみよう。「人間とポケモンとの共存」を掲げる街ライムシティを舞台に、疎遠だった父親の死の真相を探るため、主人公ティムはピカチュウと捜査に乗り出す。
ここでもうひとつの作品、《名探偵ピカチュウ》(2019)を見てみよう。「人間とポケモンとの共存」を掲げる街ライムシティを舞台に、疎遠だった父親の死の真相を探るため、主人公ティムはピカチュウと捜査に乗り出す。
ポケモンと人間は言葉を交わすことはできないが、ティムとピカチュウは不思議と会話が成立する。こうしてティムは他者であるポケットモンスターへの理解を深めていく。
ところが最後、思わぬどんでん返しが起きる。ピカチュウにはティムの父親の意識が転送されていた。だからティムはピカチュウの言葉が理解できたのだ。
後味は複雑だった。本作はいわゆるバディムービーで、BL風にいえばカップルめいた雰囲気さえ漂うほどだ。それなのに、ピカチュウの「中身」が父親だったのだから……。オンラインゲームで好ましいと思った異性のキャラのプレイヤーが、実は父親だったとすればどうだろう。
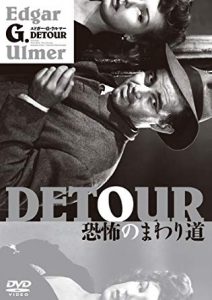 《名探偵ピカチュウ》には、もうひとつ重要なトピックがある。本作がフィルムノワールのコンテクストに沿っている点だ。
《名探偵ピカチュウ》には、もうひとつ重要なトピックがある。本作がフィルムノワールのコンテクストに沿っている点だ。
フィルムノワールという映画のジャンルがある。《深夜の告白》(1944)や《三つ数えろ》(1946)、《恐怖のまわり道》(1945)など、独特の表現形式から醸し出されるムードは未だに強い人気があり、ゲームやアニメでも模倣やオマージュが絶えない。
《名探偵ピカチュウ》の情景描写にも、ノワールの影響は色濃い。しかし物語自体のノワール色は薄い。ファムファタール(運命の女)のようなフィルムノワールの定石も、《名探偵ピカチュウ》では採用されていない。代わりにフォーカスが当たるのは家族だ。
その点を踏まえると、《名探偵ピカチュウ》はロス・マクドナルド以降の流れにあると見るべきだろう。ロス・マクドナルドは、それまで主に闇社会を舞台にしてきたハードボイルド小説と違い、どこにでもあるような家族を描くことに固執した。家族のいない人間はいない。マクドナルドは、「家族の悲劇」を描くことで、より身近なリアリティをもって、「アメリカの歪み」を読者に突きつけることに成功したのだ。
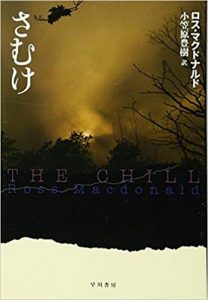 《名探偵ピカチュウ》での近親相姦めいたイメージは、ロス・マクドナルドが代表作《さむけ》(1976)で描いた、他者の介在を拒むドメスティックな家族像に近い。ポケモンは中沢新一が《ポケットの中の野生》(2004)で分析したように、他者との不意の出会いを想定したゲームだ。《名探偵ピカチュウ》も、ポケモンという他者との共存をテーマにしている。けれど実際は、ひどく内向的な関係の中に閉じこもっている。
《名探偵ピカチュウ》での近親相姦めいたイメージは、ロス・マクドナルドが代表作《さむけ》(1976)で描いた、他者の介在を拒むドメスティックな家族像に近い。ポケモンは中沢新一が《ポケットの中の野生》(2004)で分析したように、他者との不意の出会いを想定したゲームだ。《名探偵ピカチュウ》も、ポケモンという他者との共存をテーマにしている。けれど実際は、ひどく内向的な関係の中に閉じこもっている。
他者性を犠牲にし、家族を称揚する《エンドゲーム》。他者の存在を遠方に追いやり、歪んだ家族像に収斂していく《名探偵ピカチュウ》。現在ヒットを記録している映画のこうした傾向は、素朴な見方かもしれないが、どうしても世界各地で起きている、他者への不寛容を反映しているように感じる。
しかしこれは保守思想の率直な反映というより、案外リベラル側の本音なのではなかろうか。建前上は寛容を掲げながら、いざ身近に影響があるとなったら、こっそり保守政権に投票してしまう。この方が《エンドゲーム》や《名探偵ピカチュウ》の「建前と本音」とよく似てはいまいか。
わたしはこれらの作品を悪く言いたいのではない。ヒーローの強さの裏側にある弱さ。かわいらしいモンスターの中にある歪み。そうした心の弱みを、強いヒーローやかわいいモンスターに覆い隠してほしいという感情。作品に欺瞞や歪みがあろうと、その奥底に人間の弱さが刻印されているからこそ、わたしは《エンドゲーム》や《名探偵ピカチュウ》を否定しきれないのである。
(2019/6/15)
——————————————–
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中


