小人閑居為不善日記|葛飾、柴又、パリス、テキサス|noirse
葛飾、柴又、パリス、テキサス
text by noirse
1
先日用件があり、初めて葛飾柴又の、帝釈天に立ち寄ってみた。
余計な説明は不要だろう。《男はつらいよ》シリーズ、「寅さん」でお馴染みの江戸っ子、下町の地だ。到着したのは夕方で、ほとんどの店は閉まっていたが、なんとか草団子など買い求め、下町気分を堪能した。
ところが、同行してくれたK氏によると、葛飾は「江戸」ではなかったのだそうだ。江戸時代は武蔵国に属していて、都下となったのは昭和18年(1943)のこと。つまり寅次郎は、「江戸っ子」ではなかったのである。
とはいえ、ほどよくライティングされた柴又参道商店街は、スクリーンを通して親しんだ江戸の情緒、郷愁を感じさせる風情に満ちていた。訪れる観光客のほとんどは、そのような「失われた日本の風景」を求め、足を運んでいるはずだ。
だが、短い参道を横に折れると、風景は一変する。そこは、ごくごく普通の住宅街だ。日本の何処にでもありそうな、郊外の風景が広がっているのである。
お台場に、ヴィーナスフォートというショッピングモールがある。テーマパーク型のモールで、「中世ヨーロッパの町並み」(HPより)を再現した――というのがコンセプトだが、一方では「17~18世紀の南フランスや北イタリアのような魅惑的な街並み」ともあり、一貫性には欠けている(17~18世紀は中世とは呼ばない)。
だが、考証がいいかげんだろうと、それはたいしたことではない。買い物客が「中世ヨーロッパっぽい」雰囲気を楽しめれば、それで充分なのだ。柴又を訪れて感じたのも、ヴィーナスフォートと同じ「テーマパーク感覚」だった。江戸の下町情緒が感じられれば、問題はないのだ。
そのままK氏に連れられ、住宅街を抜けると、江戸川のほとりに出た。すっかり日も暮れ、辺りは真っ暗だ。東京と千葉県を隔てる江戸川の向こうは、森が生い繁げり、外れとは言え、東京の風景とは思えない。遥か向こうには、船橋や柏の、高層ビルの放つ光が瞬いていた。
2
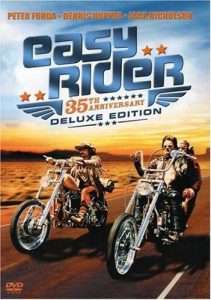 「ロードムービー」と呼ばれるジャンルがある。ざっくり言えば「旅」を扱った映画のことだが、実際にロードムービーという言葉が使われ出したのは1970年代以降で、それ以降の作品を指すことが多い。メルクマールとなったのは、マリファナを吸い、ロックを鳴らしながら、ハーレーで放浪する「だけ」の映画、ピーター・フォンダとデニス・ホッパーの《イージー・ライダー》(1969)だ。
「ロードムービー」と呼ばれるジャンルがある。ざっくり言えば「旅」を扱った映画のことだが、実際にロードムービーという言葉が使われ出したのは1970年代以降で、それ以降の作品を指すことが多い。メルクマールとなったのは、マリファナを吸い、ロックを鳴らしながら、ハーレーで放浪する「だけ」の映画、ピーター・フォンダとデニス・ホッパーの《イージー・ライダー》(1969)だ。
彼らがさすらうのは、かつての西部劇において、カウボーイたちが闊歩した土地だ。西部劇は、ただの娯楽ではなく、歴史の浅い「アメリカ合衆国」の、夢と理念を体現する存在だった。だが、父親にして名優、ヘンリー・フォンダを激しく憎んだピーター・フォンダと(父親の浮気が原因でピーターの母親は自殺した)、ジェームス・ディーンの薫陶を受けた反逆児デニス・ホッパーにとって、西部には求めるものも、語るべきものも、何もなかった。
だが彼らは、それを逆手に取った。語ることがなければ、「語るべきものがないこと」を映画にすればいい。彼らは脚本が完成しないまま撮影に入った。現場は混乱したが、作品にはプラスに反映した。夢も理念も存在しない、ありのままの西部をカメラに収めることが、彼らに許された唯一の「反逆」だったのだから。
ここにこそ、ロードムービーの本質がある。《イージー・ライダー》は、かつてのフロンティアが虚像であることを白日のもとに晒した。ロードムービーとは、「語るべきものがない」という「物語」を語ることに成功した、稀有なジャンルなのだ。
3
しかしロードムービーと呼ばれる作品のほとんどは、《イージー・ライダー》の理念を受け継いではいない。明確な目的を持った主人公が、起承転結のある脚本通りに「さすらってみせる」映画ばかりなのが、実際のところだ。
もちろんそれはそれで構わない。その中にも面白い作品はたくさんある。だが、少数ではあるが、《イージー・ライダー》の意思を継ぐロードムービーも存在する。
ヴィム・ヴェンダースは、ドイツ敗戦後に生まれ、西ドイツ側で育った。彼は折に触れ、「アメリカ映画とロックンロールとピンボールで育った」と述べている。彼の青春は、アメリカ文化と共にあった。
ヴェンダースは映画監督となり、映画革新運動「ニュージャーマン・シネマ」の中心的な存在と目されるようになる。だが他の監督と比べ、ヴェンダースはある意味異質だった。
戦後のドイツ映画は、戦争の反動で平和や平等を謳い上げる内容が多く、得てして平板となりがちで、若い世代からは退屈なものと目されていた(実際には一様ではなく、昨今再評価が進んでいる)。
ニュージャーマン・シネマの監督たちは、そうした戦後ドイツの欺瞞を暴きたてるため、過激であったり、実験的なアプローチを好む者が多い。作風はそれぞれ異なっていても、メッセージ性やテーマが前面に発揮されている点では似通っていた。
だがヴェンダースは違う。アメリカ文化に浸って育った彼には、ドイツ人としてのアイデンティティー自体が曖昧だった。映画的知識は豊富だから、ある程度体裁の整った作品なぞ、簡単に撮れただろう。しかしそれはあくまで、アメリカ映画から学んだ、「アメリカの物語」だ。ヴェンダース自身には、語るべき物語はなかった。
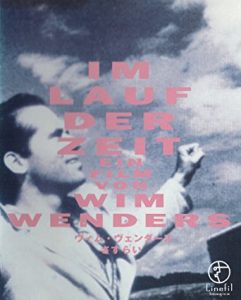 だからヴェンダースは、ロードムービーという形式を選択した。初期の代表作《さすらい》(1976)は、東西ドイツの国境沿いを進むふたりの男の宛てのない道行を、脚本を用意せず、即興的に撮り上げた作品だ。ヴェンダースにとって映画を撮るということは、旅そのものだったのだ。
だからヴェンダースは、ロードムービーという形式を選択した。初期の代表作《さすらい》(1976)は、東西ドイツの国境沿いを進むふたりの男の宛てのない道行を、脚本を用意せず、即興的に撮り上げた作品だ。ヴェンダースにとって映画を撮るということは、旅そのものだったのだ。
名声を得たヴェンダースは、アメリカに渡り、《パリ、テキサス》(1984)の撮影を開始する。この作品も、脚本後半が完成しておらず、先の見通しがつかない状態でクランクインした。ヴェンダースは、急遽サム・シェパードにヘルプを求める。もともと《パリ、テキサス》は、サム・シェパードのエッセイを膨らませて誕生した企画だった。
サム・シェパードはピューリッツァー賞も受賞した劇作家で、アメリカの伝統的な家族像の崩壊をテーマにしてきた。俳優としての知名度のほうが高く、《ライトスタッフ》(1983)などの演技でカウボーイと称されることもあったが、もともとホーリー・モーダル・ラウンダーズというサイケデリック・ジャグ・バンドがキャリアの出発点で、いわばアメリカの現在と過去を繋ぐ存在だった。
 《パリ、テキサス》は、西部劇の巨匠、ジョン・フォードの名作の数々が撮影されたモニュメント・ヴァレーから始まる。寡黙な男、トラヴィスが荒野の涯てから現れ、ふたたび去っていく。トラヴィスを演じたハリー・ディーン・スタントンは、往年の西部劇からニューシネマまで渡り歩いてきた、アメリカ映画の生き字引のような男だ。
《パリ、テキサス》は、西部劇の巨匠、ジョン・フォードの名作の数々が撮影されたモニュメント・ヴァレーから始まる。寡黙な男、トラヴィスが荒野の涯てから現れ、ふたたび去っていく。トラヴィスを演じたハリー・ディーン・スタントンは、往年の西部劇からニューシネマまで渡り歩いてきた、アメリカ映画の生き字引のような男だ。
トラヴィスは、テキサス州の「パリス」という、不思議な響きを持つ街の土地を購入しており、その写真を持ち歩いている。彼の地を実際に訪れたことはないが、いつかそこで安らかに生活することを夢見ている。映画の中でパリスは、まるで幻の地のように語られる(実際には、ごく普通の西部の街だ)。
パリスは、ヴェンダースにとってのアメリカそのものだ。安息の地を求めてさすらうトラヴィスには、彼自身の思いが投影されている。サム・シェパードとハリー・ディーン・スタントンの力を得て完成した《パリ、テキサス》は、カンヌ映画祭の最高賞、パルムドールを受賞。アメリカに対する屈折した思いを、作品に結実することに成功したのだ。
4
ヴェンダースが抱えたアメリカに対する屈折に、理解できる点はないだろうか。わたしもまた、アメリカ映画を見て、アメリカの音楽を聞き、アメリカのゲームを遊んで育ったものだ。日本人であることの境界線が何処にあるのか、実際のところ判然としない。
城址や寺社など、歴史の厚みのある場所を訪ね、日本文化に触れるのもいい。だがそれは、あくまでも観光に過ぎない。そこで「日本の心」などというものが醸成されたとして、それはメディア的な経験が演出したものでないと、果たして言い切れるだろうか。
寅次郎が声高に謳う「江戸の下町」葛飾柴又は、言ってみれば、失われた「日本人の故郷」像だろう。しかしそれは、実際には虚像に過ぎない。けれど、だからこそ、観客はそれを求め、年に何度も《男はつらいよ》を見に行ったのだろう。
そう考えると、寅次郎が江戸とうそぶく柴又と、それを取り巻く住宅街は、ある意味実に、日本らしい光景のようにも思える。郊外めいた風景に突然現れる、テーマパークのような「江戸」の下町。スクリーンの向こうにのみ存在する、日本人の故郷。これは、トラヴィスが追い求めたパリスに、どこか似てはいまいか。
サム・シェパードは、去る7月27日に、ハリー・ディーン・スタントンは9月15日に、世を去った。ヴェンダースは未だ現役で、新作『アランフエスの麗しき日々』が公開待機中である。
—————————
noirse
映像作家・佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中


