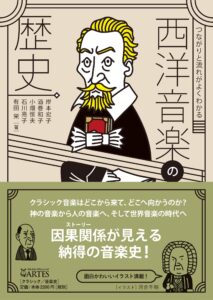Books | つながりと流れがよくわかる西洋音楽の歴史|大河内文恵
岸本宏子、酒巻和子、小畑恒夫、石川亮子、有田栄 著
アルテスパブリッシング
2020年10月出版
2200円(税別)
Text by 大河内文恵 (Fumie Okouchi)
読み始めようと表紙を開く。。。ひ、表紙がない?表紙だと思ったところは裏表紙でISBNや定価が書いてある。どこから読めばよいのだ?
ガツンと頭を殴られたようなこの衝撃は、西洋音楽史の本ならば、当然横書きで左綴じだろうという筆者の思い込みへの最初のインパクトだった。そのまま開いてみても、奥付、著者紹介、、もう諦めよう。ぐるりと回して反対側にようやく表紙を見つける。日本音楽史の本や新書ならともかく、右綴じの西洋音楽史の本など、見たことがない。
「西洋音楽史」とは何かという問題はひとまず措くとして、いわゆる西洋音楽史は横書きが一般的である。それには、西洋音楽史につきものの楽譜が左から右へ進むのだから、文章も左から右の横書きのほうが具合がよいとか、作曲家の名前やさまざまな用語がヨーロッパ由来の言葉であるため、原綴を補記にするには縦書きでは読みにくいなどといった理由が考えられる。
そういった利点をすべてかなぐり捨ててまで縦書きにしたのは何故だろう?その答えを探す前に、まず読み始めてみる。この本は、「ごあいさつ」から始まる。「はじめに」や「まえがき」ではなく、何故「ごあいさつ」なのかは、読み始めてすぐにわかった。
こういった本は通常、「である」調で書かれている。そのほうが簡潔で、より多くの情報を詰め込むことができるからである。にもかかわらず、本書は「ですます」調、もっと言うと、丁寧な語り口調で書かれている(ここでうっかり、「書かれています」とつられて書きそうになる)。偉い先生から有難い教えを受けるというより、この本の著者の方々が耳元でやさしく語ってくださっているような心地になるのである。
やれグローバル化だの、効率化だの、情報化だの世知辛い昨今において、ちょっと悠長すぎやしませんか?と言いたくなる風情。と思っていたら、いきなり次の衝撃が来た。「いくつかの大切なこと」として3つのポイントが挙げられている。まず、「私たちが『私たちの音楽』と信じているのは、実は明治維新になってから、欧米から輸入されたもの」であると、立脚点を明確にした後、「日本は、音楽の知識や技術は上手に輸入したけれど、そのバックグラウンドを知ることの重要性には、ほとんど注意が向けられて」こなかったことを指摘し、「困ったことに、『西洋音楽の歴史は、偉大な作曲家の伝記を繋げれば理解できる』と考えている人がほとんど」だと、従来の「西洋音楽史」をばっさり切り捨てる。
そのうえで、「それ(=西洋音楽)がどのように始まり、なぜ、どのように変化してきたかという、基本的なバックグラウンドを含めて、お話したい」とごあいさつは締めくくられる。近年、「西洋」でも偉大な作曲家の連鎖としてではない「音楽史」を志向する動きは出てきており、いわゆる「グラウトの音楽史」も新しい版ではそういったことに多くの記述が割かれるようになっており、英語にはなるがタラスキンの音楽史などはそれまでの時代区分や作曲家史に対して真っ向から反旗を翻している。
もちろん、日本語で書かれた「西洋音楽史」にもその流れは取り入れられ、社会的・芸術史的背景にも多少の目配りをした書物はみられるようになってきている。ただ、そういった背景にも言及し、歴史的な記述を心がけようとすると、(「グラウトの音楽史」が版を重ねるごとにページ数が増えていくことからもわかるように)当然のことながら記述は長くなり、書物は大部になる。
この本は、歴史の流れを的確に記述しつつ、コンパクトな1冊にまとめるという相反する2つの条件をどうやって同時に満たすことができたのか。その解決の一端は、たいていの音楽史の本に見られるものを気持ちよく追放することによって達成されている。作曲家の顔や有名な場所の写真、地図、絵画などの図像は一切なく、地図はごく限られたものが絵図になり、作曲家の顔や絵画の一部はイラストになっている。譜例も単なる曲紹介のためのものは割愛され、音楽上の技法などを説明するために不可欠なもののみに限られている。
さらに、詳しい説明が必要な項目(たとえば、ごく限られた作曲家の生涯、通奏低音やソナタといった音楽用語)は、コラムという形で文字のポイントを2~3段階落として、ぎっしり詰め込んで説明されている。作曲家の原綴や生没年といったお決まりの情報も本文中には記されていない。
そうやって、語られる本文だけを読んでいけば、「西洋音楽史」の流れが歴史の流れとともにすっと入ってくるようになっている。するするとあっという間に読めてしまうのは、語り口調であることに加えて、こういった「新しい」切り口を持った文章にありがちな、仮想敵を作ってそれを攻撃するという形を本文中では取っていないことも大きい。
ここまで省略されているものばかり指摘してきたが、本書には類書にはあまり見られない詳細な記述もみられる。コラムでは、作曲家ばかりでなく音楽理論家も取り上げられていたり、オペラについては、オペラのみの概説書にも負けないほどの情報量を誇る。一般の音楽史でパイジェッロやチマローザがその生涯の出来事や作品まで詳細に語られるのは珍しいし、ベッリーニやドニゼッティといったオペラの世界では有名でも通常の音楽史ではほとんどふれられることのない作曲家にも詳しく言及している。
すでに21世紀になって20年がたち、いつまでも「現代音楽」などという用語に甘えていないで、「20世紀音楽」「21世紀音楽」の歴史記述が必要なのではないかともいわれる中、20世紀の音楽史について非常に整理されているのも本書の特徴の1つであろう。この1月に中公新書から刊行された「現代音楽史」と併せて読むことによって、この1世紀に起きたことを理解する見取り図を得ることができるだろう。
本書の20世紀の記述のなかで「社会の動きと音楽」と立項された箇所では、ソ連とナチスが音楽にどれだけの影響を与えたのか、踏み込んだ記載がなされている。音楽は政治や社会とは別物だという人にはぜひ読んで欲しいところである。
これだけ充実した本書だが、取り入れて欲しかった項目についてもふれたい。モーツァルトとベートーヴェンについてはコラムが設けられているが、ハイドンがないのはなぜだろうか。音楽を専攻していても「ハイドンは弾いたことがありません」という学生もいるなか、また一度忘れられかけたものの研究者たちの熱意によって復活を遂げた作曲家の例としても取り上げて欲しかったと思う。
ハイドンに限らず、作曲家の大小(と敢えてここでは言うが)は、研究史や演奏史(上演史)とも切り離すことができないものである。音楽を「歴史」として語るのなら、そういった面も視野に入れるべきなのではないかと指摘しておきたい。
もうひとつは、日本における「西洋音楽史」の記載が限られていることである。たしかに「アジアと日本の現代音楽」の項で幸田延が留学生第1号として留学した記述から始まり、尹 伊桑などのアジアの作曲家にもふれるなど「アジア」への目配りも見られるが、瀧廉太郎からいきなり武満徹まで飛んでしまうのは、いくら紙幅に限りがあるとはいえ乱暴すぎるのではないだろうか。日本における「西洋音楽史」の脆弱性を問題にするのなら、日本における「西洋音楽」は単なる1項目にとどめるのではなく、1節を割いてもよいだけのトピックだと思うのは考えすぎだろうか。
じつはこの本を書店でみかけた当時、岸本氏は体調がすぐれないと風の噂に聞いていたので、「ああ本を出されるくらいお元気になられたのか、良かった」と能天気に思っていた。その直後に岸本氏の訃報を知り、動揺した。岸本先生には指導していただいたこともなければ授業を受けたこともないのだが、あの笑顔で「あとは頼んだからね」と言われたような気がした。受け取ってしまったバトンをどうしようか、ずっと考えている。
(2021/3/15)