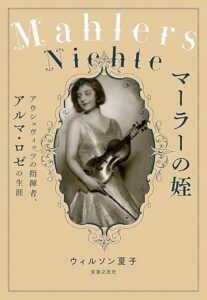Books|イアン・ボストリッジ『ソング&セルフ』 音楽と演奏をめぐって歌手が考えていること|秋元陽平
 イアン・ボストリッジ『ソング&セルフ』 音楽と演奏をめぐって歌手が考えていること
イアン・ボストリッジ『ソング&セルフ』 音楽と演奏をめぐって歌手が考えていること
イアン・ボストリッジ著 岡本時子訳
2024年1月25日発売
アルテスパブリッシング
Text by 秋元陽平(Yohei AKIMOTO)
歴史家、いや、歴史家に限らず、広い意味での学者が自らの知見をもとに書くということと、音楽家がみずからの演奏実践について書くということは両立するだろうか。両立したとして、それらは互いの立場が持つ独特の関心をそれぞれ押し殺してしまうことにはならないだろうか。本書を読む前に漠然と感じていたこの問いは、ボストリッジ自身によっても何度か控えめな自問として表明される。しかもそのことによって、彼の中で二つの関心が繊細なバランスで両立するのだ。演奏家の立場というのはたえず音楽学者や作曲家によって収奪され、与えられた指示をこなすことに汲々としかねないのだが、ボストリッジはある理論的なフレーム、つまり「パフォーマティヴな転回」を援用しながら、むしろ演奏家こそ演奏を通じてその都度作品と解釈をあらたに生み出す存在たりうることを示唆し、ラヴェルやモンテヴェルディについて書くときも彼はこの力線に沿ってすすむ。ところで、ポイントはここでもやはり、彼が歴史学者でもあるということだ。たとえばマダガスカル島が経験した植民の歴史について一つ一つ辿る丁寧な手つきは誠実な歴史家のものなのだが、ラヴェルが音楽を付した詩をめぐるこの興味深い史実が、最終的に歌曲解釈そのものに決定的な方向性を与えるか、ということについては、ボストリッジの答えは否である。この否はニュアンスに富んでいて、読者はこの事実と価値のあいだの深淵を前に、じっくり立ち止まる必要を感じることになる。それは音楽家のパフォーマンスが本質的に何か予め決定されたものを再演(re-present)するというものではないという先述の理論にもかなうものだし、歴史はあらたな芸術解釈のための素材を与えることはできても、音楽作品を一度きりのパフォーマンスのなかで彫琢することについて何か言うことはできないという歴史家的自制にもよるものだが、そもそも彼は、音楽あるいは文学テクストそれ自体がもち、自らを作品たらしめている多義性、非決定性そのものに関心を持っているように思われる。それは歴史家、演奏家のすがたにオーヴァーラップしつつも、それとは完全に重ならない、第3のボストリッジかもしれない。
非決定性は性、アイデンティティ、そして死に適用され、それぞれが近代芸術(モンテヴェルディやジョン・ダンにもモダニティは遡及する)の核を形成することになる。この見方は芸術の近代性にかかわるなんらかの人文学の言説に触れたことのある人にとってはなじみ深いものだろう。他方で、ボストリッジは、この曖昧さや多義性のうちに芸術作品の可能性を見る彼自身のスタンスについて、非決定の名を借りた芸術礼賛に陥る危険をたえず懸念していることが伝わってくる。最終的に作品解釈にいかなる直接的決定をももたらさないとしても、彼がたとえば植民主義や初期近代の女性史を丁寧に踏査するのも、このような自問が常にあるからだろう。「自分はこれらの曲を演奏すべきなのだろうか? 自分にははたしてそんなことをする権利があるのだろうか?」(p.126.)演奏家であることは、ゴルディアスの結び目を断ち切ろうと刃を振るうことではない。むしろ自身の直感をいちど括弧に括って、おのれの内で言葉の多義性を反響させながら慎重に問い続けることなのだ。彼は「セルフ」と銘打った本書であってもこうして自身のことについて語ることに禁欲的なのだが、それは分析の対象となるブリテンやラヴェルのようなある種のダンディストとは違った意味であるにせよ、どこか共通する芸術的な誠実さではないだろうか。そこに彼をして、とくにブリテン歌曲の(私見では)史上最高の解釈者たらしめているシンパシーがあるのかもしれない。距離化の実践者といえばブレヒトだが、ボストリッジは彼の演劇にむしろ観客として没入的に感動してしまったという。パフォーマンスはままならないものだ。その都度そこであたらしい懊悩が生まれ、思いもよらない規範が打ち立てられ、演奏家はそれに再び抗わなければならない。しかしだからこそ、演奏はひとつの思考でありうるのだ。
(2024/3/15)