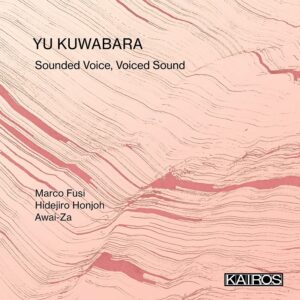Books|Between Two Kingdoms: A Memoir of a Life Interrupted|田中里奈
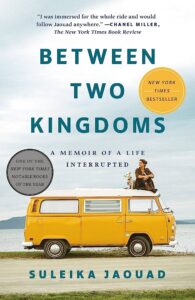 Between Two Kingdoms: A Memoir of a Life Interrupted
Between Two Kingdoms: A Memoir of a Life Interrupted
by Suleika Jaouad
Random House
2021年出版(2022年ペーパーバック版)
18.00 USD
Text by 田中里奈(Rina Tanaka)
———-
「この世に生まれた者は健康な人々の王国と病める人々の王国と、その両方の住民となる。人は誰しもよい方のパスポートだけを使いたいと願うが、早晩、少なくとも或る期間は、好ましからざる王国の住民として登録せざるを得なくなるものである」(スーザン・ソンタグ『隠喩としての病い』)1。
アメリカ人作家で癌サバイバーのスレイカ・ジャワード Suleika Jaouadによる初の書籍『2つの王国の間で:中断された人生の回顧録 Between Two Kingdoms: A Memoir of a Life Interrupted』(未訳)のタイトルは、そんなソンタグのことばに触発されている。22歳で白血病かつ長期生存率35%と宣告された彼女が、病の発覚前、治療中(「闘病」という言葉はこの本を形容するのにふさわしくないと思う)、そして治療終了後に、何を考え、どのように日々を過ごしてきたのかを極めて赤裸々に綴った書籍である。
 まだ日本語になっていないものの、西加奈子のノンフィクション作品『くもをさがす』(2023)にジャワードが登場するので、ひょっとして「あれか!」と思った人がいたら嬉しい。同書には、コロナ禍のカナダで乳癌を治療した西が、その間に考え、感じたことに加えて、その時々に読んだり聞いたりしたさまざまなテキストや歌詞の引用が出てくるのだが——等身大の体験を肌感覚で書き綴っていて、とても読みやすいのに心をザクザク刺してくる良い本なので、こちらもぜひオススメしたい——、その中にジャワードが2019年に出演したTEDトーク「死にそうになった経験が私に教えてくれたこと What almost dying taught me about living」が引用されている。「良くなったら、回復の過程は終わりではなく、むしろ始まり」2でしかないこと。人生の中断は不意に訪れること。その引き金が、病だけに限らないこと。
まだ日本語になっていないものの、西加奈子のノンフィクション作品『くもをさがす』(2023)にジャワードが登場するので、ひょっとして「あれか!」と思った人がいたら嬉しい。同書には、コロナ禍のカナダで乳癌を治療した西が、その間に考え、感じたことに加えて、その時々に読んだり聞いたりしたさまざまなテキストや歌詞の引用が出てくるのだが——等身大の体験を肌感覚で書き綴っていて、とても読みやすいのに心をザクザク刺してくる良い本なので、こちらもぜひオススメしたい——、その中にジャワードが2019年に出演したTEDトーク「死にそうになった経験が私に教えてくれたこと What almost dying taught me about living」が引用されている。「良くなったら、回復の過程は終わりではなく、むしろ始まり」2でしかないこと。人生の中断は不意に訪れること。その引き金が、病だけに限らないこと。
* * *
ジャワードは、チュニジア出身のイスラームでフランス語教師の父親と、スイス出身のカトリック教徒で芸術家の母親との間に生まれ、大学で中近東研究を修め、大学院で文学を専攻していた。修士課程卒業後にフランス・パリの法律事務所で働いていた最中、彼女は22歳で白血病と診断され、長期生存率35%と宣告される。ニューヨークでの抗がん剤治療、骨髄移植、それらの間に起こる感染症や大小さまざまな不調の最中、彼女はインターネットのブログに自らの体験を記し、それがきっかけで、『ニューヨーク・タイムズ』紙のデジタル版コラム「中断した人生 Life, Interrupted」の連載を始める3。同コラムは大きな反響を得、2013年にエミー賞を受賞した。
ここまでが書籍の長い前半部で、つづく後半部では、白血病治療を終えて退院したジャワードが、コラム連載時に受け取ったファンレターの差出人を訪れるために、愛犬オスカーを伴って、アメリカ合衆国を車で縦横断する顛末がアップテンポで語られる。なお、全部読み終えてからペーパーバック版の表紙を見ると、めちゃめちゃグッと来る。
 ここまで書いてきた内容は、この本を読まなくても知ることのできる情報にすぎない。前述のTEDトークや、ジャワードとその夫ジョン・バティステ——この、グラミー賞最多ノミネート記録保持者のすごすぎる音楽家と、彼女は白血病の再発が発覚した後の2022年に結婚している——のお宅訪問動画4、ついこのあいだ11月末に公開されたばかりのNetflixドキュメンタリー映画『ジョン・バティステ:アメリカン・シンフォニー』5などで、あらかた補完できてしまう。もし「関心はあるんだけど、洋書はちょっと…」と二の足を踏んでいる人がいたら、ぜひそちらの映像群を先に見てみてほしい。
ここまで書いてきた内容は、この本を読まなくても知ることのできる情報にすぎない。前述のTEDトークや、ジャワードとその夫ジョン・バティステ——この、グラミー賞最多ノミネート記録保持者のすごすぎる音楽家と、彼女は白血病の再発が発覚した後の2022年に結婚している——のお宅訪問動画4、ついこのあいだ11月末に公開されたばかりのNetflixドキュメンタリー映画『ジョン・バティステ:アメリカン・シンフォニー』5などで、あらかた補完できてしまう。もし「関心はあるんだけど、洋書はちょっと…」と二の足を踏んでいる人がいたら、ぜひそちらの映像群を先に見てみてほしい。
* * *
『2つの王国の間で』の真骨頂は、彼女の胸の内にあることの克明な記述が、修士課程を出たばかりの才気あふれる、けれど、ごくありふれた側面を持った22歳の女性が嫌と言える間もなく直面し、選択してきた出来事の連続をありありと描き出す点だ。
読者は各々がテキストを読むスピードでジャワードの旅に伴われる。それは感動的な闘病記とは似ても似つかない。彼氏が切れたことないんだよね、という冒頭の告白は、献身的に尽くしてくれた彼氏との悲劇的な破局の次のページに颯爽と登場したバティステに回収される(そこで噴いてエア・マックス事件でモヤッたのは私だけではないはず)。病室で延々と見るTVドラマの『グレイズ・アナトミー』(タイトルが懐かしすぎる)。癌治療中の女子会トークでセックスにおける不感症が話題に上る場面はよくぞ書いてくれたと思いつつ、これを誰にも相談できずに苦しんでいる人がいることを思うとやりきれない。
彼女の書く文章が、癌サバイバーから死刑囚に至るまで、人生の大きな変化を経験した多くの人々の心を揺さぶったことは、彼女のことばの一つひとつが危機におけるやり場のない心の機微を的確に捉えるからに違いない。「私の手から滑り落ちていったのは、自立性だけではなかった」6。「病が、人々が私に関して真っ先に目を向ける対象になった」7。「外から隔絶されて、私は視線を内に向けるしかなかった。ついに自由になっても、差し迫った死の脅威は私と隣り合わせで、私はますます自分自身の内側へと急速に落ちていった。[…]自分たちに子どもがいたらどんな風だろう、と遊びで考えるのは楽しかったけど、その言葉の途方もない重みに思い至る度にパニックになった。[…]私はもう誰とも付き合えないかもしれない。私が結婚や子どものような、先を見越した真剣な約束をするのは無責任かもしれない。再発するかもしれない。その根っこには、もっと深刻な不確実性がある——私はまだ死ぬかもしれないのだ」8。
ジャワードが自分の心の奥底に沈み込んでいた当時を振り返って描写する中、それを読み進めていた私は、自分で言葉を見つけて引っ張り上げることのできなかった昔の私の死骸が、深く潜っていくジャワードのすぐ近くに滞まっていることに気づく。そんな風に、当時の自分に救えなかった自分を本の中に認める時、それがどんなに痛々しくみっともない姿であったとしても、ああ良かった、救われたと思う。それは、漫画『三月のライオン』の主人公・桐山零が、学校で同級生にいじめられてもなお、自分の意志を貫こうとする川本ひなたの姿を見て、子供の頃にいじめられていた自分が時を超えて救われたように感じて、ひなたを守ろうと誓う、その極めて身勝手な自己救済の方法に似ている9。
* * *
ジャワードが傷つき、あるいは他者を傷つけながら、それでも「書く」ことにこだわり続けて至った境地には、強い力がある。「患者の立場から、自分の体[…]のことを描写し、気づいたことを言語化するよう、つねに求められ続ける[…]ことは、コントロールの感覚をもたらす。自分自身の置かれた状況を、自分のことばで捉え直す術を得る」10。ジャワードは、ジャネット・ウィンターソンの言葉を引用して、こう続ける。「それこそが文学の与えてくれるものだ——言葉には、ありのままを伝えるだけの力がある」11。
 そこで思い出されたのが、ヴァネッサ・スプリンゴラの『同意』(2020)だ。スプリンゴラは、14歳の頃に「同意」した著名な作家からの性的侵害について、長い紆余曲折の末、書くことを決心した動機を次のように説明している。
そこで思い出されたのが、ヴァネッサ・スプリンゴラの『同意』(2020)だ。スプリンゴラは、14歳の頃に「同意」した著名な作家からの性的侵害について、長い紆余曲折の末、書くことを決心した動機を次のように説明している。
怒りが金輪際ぶり返さないようにしたいのなら、人生のこの一時期を再び自分のものにしたいのなら、書くことはたぶん、最良の治療法である。[…]なぜなら、書くことは、私が再び自分自身の物語の主人公になることだったから。その物語は、ずっと長い間、奪われていた。12
病の経験と性暴力被害を単純な等号で結びつけることはできない。だが、病気の診断が私たちの識別コードを優先的に書き換えたり、何らかの事件に巻き込まれた人から個人性が真っ先に剥奪されて「被害者」というラベルを貼られたりすること、あるいは、当事者の心や体の中心に見知らぬ何かが突然居座り始めて、それに休む間もなく振り回され、疲弊し、それ以前の生活がままならなくなることには、何かしらの体験的な共通性がある。そうした時、誰かが勝手に書き換えてしまった〈私〉を元通りに戻すことは、どんなに表向きには昔と一緒の〈私〉に見えたとしても、本人がそのように装おうと心を砕いても、実際のところは無理である。
ジャワードが自らの人生に起こった変化をイニシエーションと捉えようとして旅に出たことは、神話学的に納得のいく話だ。神話における英雄譚が冒険の直後で終わるのではなく、もうちょっとだけ続くことが多いのは、「英雄」としてすべきことをこなさなければならない非日常から、〈私〉に戻って日常を送るために、それがどうしても必要なプロセスだからだ13。帰還はサバイバーのためのものだから、主観的な物語でしかありえない。「生きるために、私たちは自分たちに向けて物語をかたる」14。それによって、いったん人生を中断され、一人ぼっちの経験を余儀なくされた私たちに、自分とまったく異なる「中断」を経験し、自分を主人公にした別の物語を生きている他者の姿が見えてくる。他者を主人公に据えているために〈私〉の感覚が喪われた物語や、あるいは自他を混然一体のものと捉える共依存的な物語との、決定的な違いはそこにある。
だから、ジャワードのこの回顧録を自己中心的だと誹るのは、彼女が本当に周囲の人を振り回していたとしても、見るべきところが明後日の方向だと言うよりほかない。あるいは、彼女が二度目の白血病治療の最中、グラミー賞最優秀アルバム賞を受賞したジョン・バティステが壇上で言ったことが、この本の評価としてそのまま当てはまるだろう。「アートというのは主観的だ。その人に一番必要な時に届くものだ。[…]そこには、一番必要な人のところに届くレーダーが備わっているんだ」15。
(2023/12/15)
——————–
- スーザン・ソンタグ『隠喩としての病い エイズとその隠喩』富山太佳夫訳、みすず書房、1992年、p. 5。
- Suleka Jaoward. “What almost dying taught me about living.” TED Talk. April 2019. Translated by Charlotte Swift. Reviewed by Masako Kigami.
- 現在は連載のアーカイブが『ニューヨーク・タイムズ』紙公式ホームページで閲覧可能。
- Architectural Digest. “Inside Jon Batiste & Suleika Jaouad’s Soul-Filled Brooklyn Home.” YouTube. October 4, 2023.
- Matthew Heineman. American Symphony. 邦題:ジョン・バティステ アメリカン・シンフォニー. Netflix. 2023.
- Suleika Jaouad. Between Two Kingdoms: A Memoir of a Life Interrupted. Random House. Paperback. 2022, p. 136. 翻訳は引用者。以下同。
- Jaouad. 2022, p. 199.
- Jaouad. 2022, pp. 258-260.
- 羽海野チカ『三月のライオン』Chapter 71. 白水社.
- Jaouad. 2022, p. 107.
- “That is what literature offers—a language powerful enough to say how it is. It isn’t a hiding place. It is a finding place.” (Why Be Happy When You Could Be Normal?, Knopf, 2011.
- ヴァネッサ・スプリンゴラ『同意』内山奈緒美訳、2020年、203頁。
- Joseph Campbell. The Hero with a Thousand Faces. Pantheon Books, 1949.
- Jaouad. 2022, p. 337. Originally from: Joan Didion. We Tell Ourselves Stories in Order to Live: Collected Nonfiction. Knopf, 2006.
- Recording Academy / GRAMMYs. “JON BATISTE Wins Album Of The Year For ‘WE ARE’ | 2022 GRAMMYs Acceptance Speech.” YouTube, April 4, 2022.