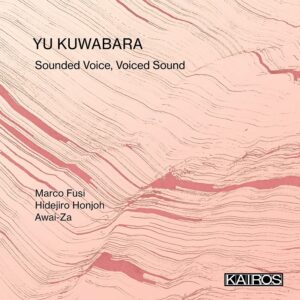円盤の形の音楽|「最も美しい愛の告白」|佐藤馨
Text by 佐藤馨(Kaoru Sato)
〈曲目〉 →foreign language
Disc 7
[1]-[4] ブラームス:ピアノ四重奏曲第3番ハ短調 Op.60
[5] シューマン:トロイメライ Op.15-7
ポール・トルトゥリエ(チェロ)
[1]-[4] ヨーゼフ・シゲティ(ヴァイオリン)、ミルトン・ケイティムス(ヴィオラ)、マイラ・ヘス(ピアノ)
[5] ジョン・ニューマーク(ピアノ)
〈録音〉
[1]-[4] 1952年6月、プラド
[5] 1958年9月、パリ
いつだったか、YouTubeである動画を見つけた。サルヴァトーレ・アッカルド、アントワン・タメスティ、ゴーティエ・カピュソン、そしてメナヘム・プレスラーという豪華な顔ぶれがピアノ四重奏で共演していた。後から調べるとそれは2008年のヴェルビエ音楽祭のコンサートで、メインはシューマンのピアノ四重奏曲op.47だったようだが、私が見たのはその後のアンコールのみを抜粋したものだった。すでにこの動画はYouTubeから削除されており、現在は曲のさらに後半部分を切り出したものしか閲覧できないというのは、残念なことである(とはいえ、medici.tvの会員ならコンサート全編を視聴することができる)。というのも、私にとって印象深いのは、演奏の内容ではなくむしろその前の出来事だからだ。拍手の中、ステージに戻ってくる四人。彼らが椅子に座り直すと拍手は止み、再びの静けさに包まれた会場で、口を開いたのはピアニストのメナヘム・プレスラーである。このなんとも柔和そうな好々爺は聴衆に向かって、これから弾く曲について手短に述べた。そうして、「これまで作曲された中で最も美しい愛の告白です」という言葉の後に彼らが弾き出したのは、ブラームスのピアノ四重奏曲第3番の第3楽章であった。
私はこの曲を五指に入るくらい愛している。聴くたび、全く知らない誰かの人生の荒波を、まるで自分が身をもって経験したかのように感じてしまう。自分の人生の背後には、実はずっとこの音楽が流れているのではないか? そう錯覚したくなるほどに、心が涙するような、何か本当に理想的なものがこの曲にはあるのだろう。第3楽章で深く心打たれるのは、この音楽がまさに最たる理想を示しながら、同時に自分から最も離れた何かを私に訴えかけてくるからに他ならない。これをロマンチックという言葉で片付けることはできない。ロマンチックというには痛ましく、聴く者を慰めるように見えて本当は傷つけているのだ。少なくとも私は、この熟れた音楽に接する自分の自傷癖じみたものを感じずにはいられない。
しかし、こんな考え方をしている私であれば、この曲をあっけらかんと「最も美しい愛の告白」なんて語ってしまうことは歯が浮くような事態である。逸話がどうであれ、そんな俗受けするような言い方で始末しないでほしいと、多少は軽蔑するかもしれない。
それが不思議なことに、プレスラーがそのように語るのを聞いた時、私は素直に「素敵な言葉だな」と思ってしまった。ボザール・トリオを率いて半世紀の長きにわたり活躍した、当時85歳の生ける伝説、そんな大人物の言うことだからと流されてしまったのか。あるいは、そんな彼の豊かな人生経験と含蓄に思いを馳せた結果だったのだろうか。一つ言えるのは、プレスラーの言葉を不覚にも素敵だと感じた以上に、そうやって心からの温もりを伴いながらこの曲を「最も美しい愛の告白」だと語って聞かせられるようになるのは、なんて素敵な人生だろうかと感じたのである。これもまた私の理想の話である。今の私は、このもつれ合うような音楽のしがらみを大事にして言葉を尽くそうとしてしまうが、ずっと歳を取ったら、そこに内包されている酸いも甘いも全てを引っ括めて解ったうえで、「最も美しい愛の告白」だとシンプルに言えるようになりたいものだ。
そうしたら、今の私が最愛と思う演奏について、歳月を経た自分はどんな風に語るのだろうか。1952年のプラド音楽祭でのライブ録音、ヨーゼフ・シゲティ、ミルトン・ケイティムス、ポール・トルトゥリエ、マイラ・ヘスの四人で行われた演奏がそれにあたる。トルトゥリエの廉価盤BOXを買ったらたまたま入っていた音源だ。それまで第3番は聴いてもあまりぱっとしなかったのだが、この演奏に接して一気に引きずり込まれた。初めこそ、ヘスのブラームスに外れはないからと手に取ったわけだが、いざ聴き始めると、最初の瞬間から演奏を決定的に色づけていたのはシゲティだった。このあまりに熟れ切った音色はどうしたことか。ちょっとした歌い回しの端々に、おおよそ不健康でどろりとした情緒が顔をのぞかせる。ヴィブラートも所々まるでわななきのように震えて響くし、抑揚の深さが拠り所のない不安な気持ちをかき立ててくる。これと対照的なのが、ヘスの堅牢で器の大きな演奏、ケイティムスの押し引きに長けた熟達の技、トルトゥリエの瑞々しい詩情で、三人との明らかなコントラストによって、いっそうシゲティの個性が強く存在感を放つ。ゆっくりしたテンポで波打つ第3楽章は、さながら空を朱に染めじりじりと傾いていく斜陽にまみえているようだ。夜が忍び込んでくる直前の、当てのない心が最もざわめく瞬間の音楽である。ここでのシゲティがこの演奏の全てだと言っていい。魂の最奥から引っ張り出してきたような歌は、もはや限界手前のギリギリの危うさで踏み止まっている。これこそ本当にロマンと言うべきものだ。
(2022/3/15)
—————————————
〈Tracklist〉
Disc 7
[1]-[4] Brahms : Piano Quartet No.3 in C minor, Op.60
[5] Schumann : Rêverie, Op.15-7
Paul Tortelier, piano
[1]-[4] Joseph Szigeti (Vn), Milton Katims (Va), Myra Hess (Pf)
[5] John Newmark (Pf)
〈Recording〉
[1]-[4] June 1952, Prades
[5] September 1958, Paris
——————————
佐藤馨(Kaoru Sato)
浜松出身。京都大学文学部哲学専修卒業。現在は大阪大学大学院文学研究科音楽学研究室に在籍、博士後期課程1年。学部時代はV.ジャンケレヴィッチ、修士ではCh.ケクランを研究。博士では20世紀前半のフランスにおける音と映画について勉強中。敬愛するピアニストは、ディヌ・リパッティ、ウィリアム・カペル、グレン・グールド。