Books|エドワード・サイード ある批評家の残響|柿木伸之
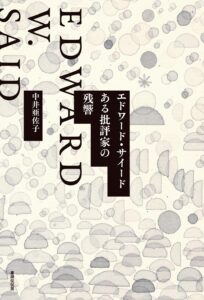 Books|エドワード・サイード ある批評家の残響
Books|エドワード・サイード ある批評家の残響
中井亜佐子著
2024年1月26日刊
書肆侃侃房
定価1700円
Text by 柿木伸之(Nobuyuki Kakigi)
パレスティナのガザ地区の住民の虐殺が現在も続いている。軍事的な暴力によって直接に殺されるだけではない。避難に次ぐ避難を強いられることによる生活環境の悪化によって、さらには飢えによって、ガザの人々は殺され続けている。そのことが忘れ去られつつあるのが恐ろしい。人がこのように殺されることが許されてよいのか。広島の友人たちは、昨年十月から毎夕原爆ドームの前に立ち、さまざまな表現で虐殺に対する抗議の意思を示している。その表現の一つに、「平和の前に解放を」という言葉があるのが印象深い。
中井亜佐子がパレスティナ人批評家エドワード・W・サイードを論じた新著が世に送られたのは、イスラエル軍によるガザへの攻撃が激化していた今年初めのことだった。『エドワード・サイード ある批評家の残響』において特徴的なのは、サイードの文学研究とパレスティナ問題へのアプローチを貫く批評が取り出されていることである。彼は批評を生きた。そして、批評は読むことから始まる。本書は、『最後の空の後で(訳題は『パレスチナとは何か』)』においてジャン・モアの写真を読むサイードにも光を当てている。
著者によるとサイードの読解は、欧米の市場で売られる茄子の農園で働くガザ在住の難民の姿などからパレスティナの植民地支配の構造を読み取るだけにとどまらない。片眼のレンズが割れた眼鏡をかけた初老の男性の写真からは、見る者を動揺させる要素、すなわち世界でひと括りに「パレスティナ人」と見なされる人物像を逸脱する要素を読み取っている。これを言葉として響かせるところに、サイードの批評意識が発揮される。本書は、この批評意識の展開を原点からたどる。その原点とは、ジョセフ・コンラッド論にほかならない。
コンラッドの文学の研究を専門としてきた著者は、サイードによる『闇の奥』の読解の特徴を精緻に取り出している。彼はコンラッドの代表作にニーチェの哲学との同時代性を見て取り、差異を含んだ反復によって、また対立を響かせる再現によって初めて起源が見いだされるという思想を、そこから読み取っている。近代都市ロンドンのテムズの流れがアフリカの奥にある世界の始まりに通じていることへマーロウの声の残響によって読者を誘う『闇の奥』という作品はさらに、サイードが実践する批評の寓意でもあるという。
コンラッドの小説の展開のなかで、いくつもの声が反響し合う。マーロウの語りは、そこから言葉にならない叫びをも聴き出そうとする。批評もまた作品の言葉を聴き取ろうとする。しかし、その言説が響かせるテクストの声とは、作者の声の痩せ衰えた反響ではない。本書によると批評はむしろ、作者という「他者の想像力を限界づけている構造の調和を、みずから雑音をたててかき乱す」。そのような雑音を「死せるテクスト」から取り出し、作者が想像しえなかったその作品のもう一つの始まりを見いだすところに批評の本領がある。
たしかにサイードは、西洋と異質な「東洋」像を形成し、「東洋人」を人間扱いしない植民地支配の下支えとなった「オリエント」についての言説の歴史を浮き彫りにした人物として知られている。しかし、『オリエンタリズム』を注意深く読むならば、そこに描かれているのは、「東洋」の表象の差異を含んだ反復であるという。それは「東洋人」を対象化する際に絶えず参照されるアーカイヴを形成する一方、反復の個々の出来事は、西洋人の他者像を逸脱する要素を孕んでいた。これを見いだすのが、批評意識にもとづく言説の読解である。
その方法としてサイードが『文化と帝国主義』をはじめとする著作で採用するのが、「対位法」にほかならない。著者によれば、「対位法的」読解とは、「テクストを可能なかぎり正確に歴史的コンテクストに置く」ことで、その文脈との対照においてテクストの声を一つの声部として響かせる技法である。たしかに作曲技法としての対位法は、厳密な規則によって音楽の和声進行を決定するかもしれない。しかし、現実の音楽の特徴をなすのは「制御不可能なままに残される不調和性」であり、サイードもそこに力点を置いているという。
それによって「オリエンタリズム」の枠組みから逸脱する要素が個々の言説に見いだされるとしても、西洋による「東洋」の支配が相対化されるわけではない。著者によると、『文化と帝国主義』におけるコンラッド論によって見いだされるのは、制御不可能なまでに自己を拡張していく帝国の支配の欲動である。そのうごめきは、『闇の奥』を対位法的に読むことによってのみ聴き取られうる。そして、この対位法をつうじてこそ、作品の結構も、支配の現実も、歴史的状況に巻き込まれた人の営みとして問われうるようになる。
そう考えるなら、批評の対位法とは、文学作品とその背景にある歴史を、神話から解き放つものと言える。この点でサイードの批評は、ヴァルター・ベンヤミンが『ドイツ悲劇の根源』などで実践した批評に通じる。それは、ベンヤミンが「星座」と呼ぶ時空を越えた関係のなかに作品を置く。それによって作品は、神話的な自己完結から解放されると同時に一つの「根源」として見いだされる。このことを目指す批評への思考から多大な影響を受けたのが、テーオドア・W・アドルノである。サイードは、晩年までアドルノに傾倒していた。
優れたピアノの弾き手で、音楽批評も続けていたサイードは、アルバン・ベルクに師事して作曲家を目指していたアドルノの音楽的思考から大いに触発されていた。アドルノは、アメリカ合衆国に亡命していた時期に著わした『ミニマ・モラリア』において、全体は虚偽だと述べていた。サイードにとっては、このことを具体的に指摘しながら、もう一つの声を響かせるのが批評の実践である。彼はアドルノの戦争の時代の「最小限の道徳」の書からさらに、同じ場所に居座らないという亡命知識人のモラルも学び取っていた。
このことは著者によると、サイードの自伝『遠い場所の記憶』に語られる、一個の定旋律に収斂することのない生の対位法として実践されることになる。それは批評を生きることにほかならない。『エドワード・サイード』は、サイードの批評意識を、コンラッドの文学を対位法的に見いだすその出発点から跡づけ、それがパレスティナの解放へ向けても貫かれるさまを浮き彫りにする。それによって批評家としてのサイードを批評する本書は、ガザでの虐殺が続いている現在における批評そのものの意義にも光を当てている。
批評は、神話によって「現実」に仕立てられている全体から言葉を、それを発する人を解き放つ。文字として回帰する言葉に耳を澄まし、批評意識を持ち続けるとは、不断に自己を解放することなのだ。それは同時に、非人間的な支配の歴史、とりわけパレスティナの植民地主義的な支配の歴史からの解放への意志を持ち続けることである。今求められているのは、その表現を越境的に呼応させる思考の回路だろう。本書はサイードの「人民」概念を論じることをつうじ、これによって生まれる連帯が新たな民を形成する可能性にも触れている。
(2024/8/15)


