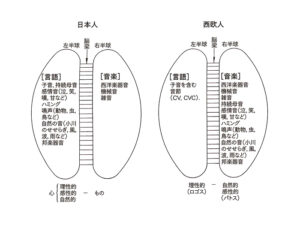評論|西村朗 考・覚書(35)西村朗と佐々木幹郎~作曲と詩作「死」「声」「言葉」|丘山万里子
西村朗 考・覚書(35)西村朗と佐々木幹郎~作曲と詩作「死」「声」「言葉」
Notes on Akira Nishimura(35) Akira Nishimura & Mikiro Sasaki
Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)
室内オペラ『清姫―水の鱗』は2人の独唱者(ソプラノ、テノール)、混声合唱とピアノのための作品で台本は詩人の佐々木幹郎。合唱指揮者、田中信昭主宰の「新しいうたを創る会」の委嘱で2012年初演(津山恵sop. 高橋淳ten. 中嶋香pf.)である。
本作に入る前に、西村と佐々木の協業を見ておきたい。
最初の作品は2009年合唱曲『夏の庭』(同声合唱とピアノのための組曲)、ついで2010年『大空の粒子』(混声合唱とピアノのための組曲)、『鳥の国』(無伴奏混声合唱組曲)、2011年『旅―悲歌が生まれるまで』(無伴奏同声合唱のための)、『清姫―水の鱗』と同年『鎮魂歌―明日―風のなかの挨拶』(無伴奏女声合唱のための)、2013年『うめきうたみっつ』(無伴奏混声合唱のための)と毎年合唱曲が続く。翌2014年室内オペラ『ふり返れば猫がいて』(児童合唱とピアノ)、2016年室内オペラ『中也!』(混声合唱とピアノ)、そうして2019年オペラ『紫苑物語』に至っている。
佐々木は10年の歳月、西村が言葉を共にした相方なのである。
ちなみに三善晃も田中信昭や栗山文昭によって合唱世界を開かれた作曲家だが、最も親しんだのは谷川俊太郎で『クレーの絵本 第1集』(1978)から最後の『その日― AUGUST6―』(2007)までほぼ30年にわたり22曲を書いている。三善は40代半ば、西村は50代半ばにそれぞれの詩人と出会い、伴走者となった(三善晃は宗左近と結びつけられることが多いが、三善の本質は一貫して谷川にあったと筆者は考える)。
作曲家と詩人とが互いの創造を見つめつつ同時代を歩むことができるのは、幸福と言えよう。
だが、この9月の西村の急逝でその歩みは絶たれてしまった。
ゆえここで、改めて両者の創作の重なりを眺めておく。
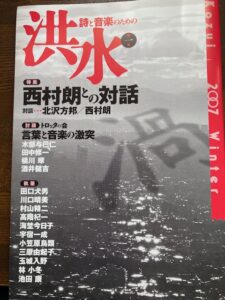 2人の出会いをセッティングしたのは詩と音楽のための雑誌『洪水』の編集者であり詩人の池田康。
2人の出会いをセッティングしたのは詩と音楽のための雑誌『洪水』の編集者であり詩人の池田康。
『洪水0号』(2007)は《伊福部昭を考える》で、執筆に白石かずこ、和合亮一、吉田義昭、津田於斗彦、山崎広光らが並ぶ。続く1号の特集が《西村朗との対話》(2007)で、音楽社会学、構造人類学の北沢方邦と対談している。北沢とは『清姫―水の鱗』の翌年2013年に室内オペラ『バガヴァッド・ギーター「神の歌」』(2人の歌手と打楽器アンサンブルのための)をものしており、西村は一時、傾倒したようだ。北沢のヨガなど実践論やインド神秘主義に惹かれるところがあったのだろう。筆者はこの実演に接したが、インドの古典説話に親しくない観客にはピンと来ないのでは、と疑念を覚えた。
この特集号には池田の西村論《垂直軸のアリア〜現代の音楽と新たなる宗教の海域〜》という小論も掲載されており、西村と宗教の問題が論じられているのが興味深い。インタビュー《2007.10.7》では西村がその宗教観を具体的に語っている。
6号は特集『佐々木幹郎、音に遊ぶ』(2010)で、西村との対談《詩の鳥葬、声の産卵》がある。奈良生まれ、世界とりわけアジア放浪の詩人佐々木と、大阪生まれの作曲家西村に、ほぼ同世代、関西文化圏とアジアに興味を持つという共通項を見る池田が引き合わせた。これが最初の出会いで、その詩について 西村は「一番感じるのは大河性なんです。長編小説よりももっと大きな世界を表現するのに小説の枠を超えてしまうので詩になる、という感じがする。そこが第一に僕が魅力を感じる点なんです。凝縮の方向ではなくて、より大きなものに届くためには、限定しなければいけない。言葉一つ一つが指し示すような世界が普通の詩とは違う立体感と広がり、風土感がある。」1)と語っている。このスケールと風土感は、両者に通ずるものがあろう。
西村は「一番感じるのは大河性なんです。長編小説よりももっと大きな世界を表現するのに小説の枠を超えてしまうので詩になる、という感じがする。そこが第一に僕が魅力を感じる点なんです。凝縮の方向ではなくて、より大きなものに届くためには、限定しなければいけない。言葉一つ一つが指し示すような世界が普通の詩とは違う立体感と広がり、風土感がある。」1)と語っている。このスケールと風土感は、両者に通ずるものがあろう。
また、「詩の言葉は皮膚です。佐々木さんの詩を読むということは、佐々木さんを食べることなんです。詩で鳥葬される。読葬される。」とも言う。西村らしい表現だが、チベットやヒマラヤを歩く佐々木の感受が皮膚感覚で伝わる、そういう生理的伝導力がその言葉にはあるのではないか。佐々木の旅する土地土地、風土で産まれるそれは、時に土塊の礫となり泥流となりつつ、どこか透明だ。
 だがそもそも、この詩人の自覚的出立は1960年代末、学生運動の頃、高校時代の友が羽田事件(1967年10月8日)2)で死亡したことにあった。その追悼詩『死者の鞭』(1970 年第1詩集『死者の鞭』に収録)は死の1週間後に書かれた。それを最後に詩作を断つはずが、評価されたことで戻び書き始めたという。
だがそもそも、この詩人の自覚的出立は1960年代末、学生運動の頃、高校時代の友が羽田事件(1967年10月8日)2)で死亡したことにあった。その追悼詩『死者の鞭』(1970 年第1詩集『死者の鞭』に収録)は死の1週間後に書かれた。それを最後に詩作を断つはずが、評価されたことで戻び書き始めたという。
『死者の鞭』から(1)「橋上の声」第3と第 4節開始部分、さらに最終節末尾をあげておく。
詩集前書きには「死は生者の語り 日は火を生む」とある。
ひと息ごとに遠のいてゆく歩道の経線を追い
同志の死を報じた新聞を抱かえ急ぐ
黙然と秋の日射しの距離を測っている
休日の公園の小砂利は
力なく広がり 午後
ふと僕は耳元の声を聞いたようだ
―――何をしている? いま
僕の記憶を突然おそった死者のはにかみのくせ
鋭く裂ける柘榴の匂いたつ鈍陽(にびひ)のなかで
永遠に走れ
たえざる行為の重みを走れ
軌跡は虹のように彼岸をめざす
(以下、略)
最終節はこう閉じられる。
(前略)
存在の路上を割り走り投げ
声をかぎりに橋を渡れ
橋を渡れ
佐々木は西村との対談の中で、こう語っている。
「何をしている、いま?」というのが、羽田で死んだ僕の友人が羽田に行く前、僕に質問した最後の言葉です。だから、今自分はここでこうしているよ、ということを詩の言葉でつねに表したかった。ずっと「私」というものが何であるかを問いつめているわけです。できればこの「私」をつぶしてしまいたい。粉々にして溶けた破片のようになり、飛び散らせて、それを見守るような視点で言葉を見つけたかった。そういうふうになるまでには、それから二十年以上かかったんじゃないかな。粉々にするために、いろんなところへ旅をするということも、そこから始めるようになったと思う。3)
友の遺した日記に、高校時代交わした会話や単語がたくさん出てきた、それを、これは僕の言葉だ、と思った時、言葉で追い詰められた。彼は言葉で残した、これは言葉で返されなければいけない。そう思ったと佐々木は言う。
続けて、
「私」というものを粉々にする手掛かりとして、例えば琵琶法師の声を聴きに行ったり、祭文語りを聴きに行ったり、今まで忘れていた声と出会って自分の原点である河内音頭の声の世界に戻ったりとか、大阪の音は何であったか、自分の身についた音や声からもう一度言葉を組み立て直していこうとした。
音、声、言葉。
ここに、西村と佐々木の響応は明らかだろう。
すなわち、「死」と「声」と「言葉」。
17歳の西村は寂光院からの帰路、黄昏の古知谷阿弥陀寺、即身仏のおわす寺への道を引き返すが、それが戻れぬ冥界を直覚してのことであれば、そこに「死」の気配を察知したと言えよう(だが気配とはなんだろう? それについてはいずれ)。
では、声への最初の反応は? やはり寂光院への道すがらの八瀬の「無音」、全き静寂を初体験(「電車が信号停止。すると無音。全くの静寂。おそろしいほどの静けさ。何も聴こえない。大阪の喧騒に育ったこの身をはじめてシーンとした静寂が包んだ。その数分間の特別な感覚を今もはっきり記憶している。」)、さらに院を辞すにあたり、背にかかる尼僧の見送りの声を「言葉を超えた何かが心にしみ入って、そのひと声の記憶は今も瑞々しい。」と感覚した、そのときではないか。
言葉を超えた何かを、言霊、音霊、歌霊と言い換えれば、すでにここで、西村の向かう道は示されていた、と言えよう。
最初の合唱作品『汨羅の淵より』(1978/田中信昭指揮、東京混声合唱団)はまさに死者への招魂であったし、この作品について西村は筆者に「“コウコウゲンソウ”とかいう漢詩を叫ばせたような記憶があり、お経みたいなもの」と語った。つまりは漢詩の韻律、読経、そして「滅びの美」に陶酔する彼の青春の美学、意味不明な言葉を叫ばせる生理的快感がすでにここに現れている。「言葉の意味」ではなく言葉以前の底の底を抉る彼の指先感覚は(「詩の言葉は皮膚です」)、神代文字ヲシデで書かれた古文書『ホツマツタヱ』にある『アワの歌』(言霊歌)での一音一音に宿る神を祀る古代人の感性に等しい。「一音成仏」すなわち「一即多」。その声の扱いの独特に西村ヘテロフォニーとは、彼の宇宙観、いや、生死観そのものだと改めて思う。
が、上述「死の気配」も含め、この死生観については改めてとしたい。
一方、当時19歳の佐々木にとっての「死」は激越だった。突如あちらとこちら(幽界と現世)に分たれた友の死、という具体に佐々木は立ちすくむ。その足裏の底の底で、死者への橋がかりとしての言葉が発火、「永遠に走れ たえざる行為の重みを走れ」と橋上を疾駆する。最後のリフレイン「渡れ 渡れ」の絶唱が空(くう)を穿つ。
ここで、「死」は、友の問いかける「声」として彼の耳元に響き、おそらく今も響き続ける。
佐々木の初動が「声」であったこと。人類が言分けする以前(言語の萌芽以前)に発していたであろう初発の声については第26回で述べた。思い出したい。あまねく人が共有しうるものは不可避の「死」であることを。その「死への応答」としてヒトの初発の発声はあり、言葉にならぬその「呼びかけ」(招魂のように)として、佐々木もまた、あちらとこちらの世界の橋梁、生死の橋がかり、死者たる親しき友の声に応じる言葉を投げる。「走れ 走れ」「渡れ 渡れ」。
筆者は西村ヘテロフォニーにある言霊、音霊、歌霊を「ある種の“動力”(ダイナミズム)、すなわちエネルギーそのものであって、どのようにも変化(へんげ)し、流れ、定まることなく、とどまることなき常動体・常動態ではないか。とこう考えると、そこに“一即多”が見えてくる、響いてくるように思う。」と書いたが、佐々木の言葉もそれだ、と西村は感受したのではないか。「凝縮の方向ではなくて、より大きなものに届くためには、限定しなければいけない。言葉一つ一つが指し示すような世界が普通の詩とは違う立体感と広がり、風土感がある。」とは、その意であろう。
佐々木の言葉はそれぞれの土地土地を踏みしめる足裏を伝い、昇ってくる。そうして中空に飛び散り、撒かれる。その風土感やスケールは、いわば曼荼羅設営に似る。佐々木の詩作とは、そういう行為なのではないか。
彼の詩魂、言霊は、粉砕して溶けた破片のようになった私を飛び散らせ、それを見守るような視点としての言葉となって降ってくる。散乱する私の粒子。西村、佐々木の合唱第2作、詩集『蜂蜜採り』からの《大空の粒子》に描かれる光景。長いが全文を引く(行替えママ)。
光りの中に人はいる
手をかざして 蝙蝠傘をさして
見つめるのは粒子
風を越えてやってくるもの
泥を食べる花々の
その芯の中から顔を出すもの
麦を煎る鍋の上で踊り出すもの
バケツ型の帽子の上で
帽子型の蜘蛛の上で
峠を越えて行きあう人は
喉の奥に食い込む
この
凄惨な
青黒い大空の
粒子を飲め
女たちの
耳たぶに光る小さな山の黄金
男たちの
畑の中で光る鉄の匙
岩の上で笑う仏塔
生きものの光りは
ここで生まれ
ここで死に絶える
石の道を走りながら
塩の谷を歩きながら
ヤクの毛を紡(つ)ぐ棒を回しながら
細い木を削りながら
さらに細くなり
土の顔で迎えてくれるものを求めて
光りはバターの匂いを撒きちらし
雲を突き抜け
澄んだ油となって
大空から落ちてくる4)
この詩はネパール、チベットへの旅で詠まれたものだが、ここで筆者の眼を異様に射るのは「凄惨な 青黒い大空の 粒子を飲め」の詩句だ。そこに筆者は『死者の鞭』の2節目の終句「アスファルトを蛇行するデモ隊の ひとつの決意と存在をたしかめるときフラッシュに映え たぎり落ちる 充血の目差しを下に向けた行為の 切断面のおおきな青!」を想起する。
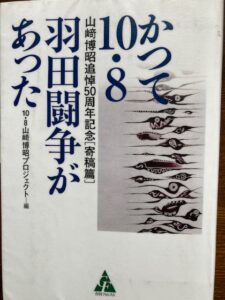 佐々木は友の死の50年後にまとめられた『かつて10・8 羽田闘争があった』(10・8山崎博昭プロジェクト編)への寄稿文で、「一つの集団やデモのなかにいるときの身体感覚」を語るものとして、この詩の節を引いており、「デモ隊の行列を大きな蛇に譬えたとき、その切断面が真っ青である、という頭も身体も空白の一瞬というもののなかで人間はいるのだ、いま生きているのはそういうことなのだ。」と述べている。なお、この書籍は友、山崎博昭追悼50周年記念「寄稿篇」5)として2017年に出版され、山崎の兄による評伝や山崎の遺稿、佐々木を含む多数の寄稿文61篇のほか、死因究明調査結果などが収められている。6)
佐々木は友の死の50年後にまとめられた『かつて10・8 羽田闘争があった』(10・8山崎博昭プロジェクト編)への寄稿文で、「一つの集団やデモのなかにいるときの身体感覚」を語るものとして、この詩の節を引いており、「デモ隊の行列を大きな蛇に譬えたとき、その切断面が真っ青である、という頭も身体も空白の一瞬というもののなかで人間はいるのだ、いま生きているのはそういうことなのだ。」と述べている。なお、この書籍は友、山崎博昭追悼50周年記念「寄稿篇」5)として2017年に出版され、山崎の兄による評伝や山崎の遺稿、佐々木を含む多数の寄稿文61篇のほか、死因究明調査結果などが収められている。6)
デモ隊の蛇の切断面が「真っ青」との言葉に、さらに筆者に浮かんだのは青頸(しょうきょう)観音、すなわち、西村の同声合唱作品『大悲心陀羅尼』(1990)7)だ。乳海撹拌で現れたデーヴァとアスラを害する猛毒を飲み干し、その毒で首が青くなった観音の陀羅尼がそれ。
第27, 28回参照
その『大悲心陀羅尼』に重なり響いてきたのは、佐々木が同じ寄稿文で述べている言葉、「受苦」だ。学生運動当時の彼の心に残ったマルクスの唯一の言葉は『経済学・哲学草稿』の中にある「受動的苦悩」で、10代の彼はそこに傍線を引いて囲い、横に「受苦」と言い換えた書き込みをしたと言う(p.103)。毒を飲み干し首が青くなった観音の「大慈悲心」と佐々木の「受苦」が響きあう。この「受苦」の感覚も佐々木の全ての詩作に一貫して流れる地下水流と筆者は思う。
さらに蛇とは『清姫―水の鱗』の変化(へんげ)。
「凄惨な 青黒い大空の 粒子を飲め」はそのように筆者を撃ち抜いた。
詩句に、言葉に触れた時に、自分の中の時空が拡張され、あるいは地底、水底に潜む小さな個の歴史が、時層地層、原土と源流に瞬時に接続される、そんな感覚。それを西村は「大河性」といい、スケールと風土と言ったのではないか。
それは西村の音に明瞭だ。
見てみよう。
西村は佐々木の『大空の粒子』をどう食べたか。

前奏pf. fdf低和音の一打の上に完全5度の透明な響き(光りの粒子)が舞う。続く低音分散アルペッジョにいざなわれ、全4声が「ひかりの ひかりの」と歌い出す。sop.(e~a),alt.(c~f)は3度の和音を響かせ4度順次上行。ten.(a~h), bas.(d~c)は5度で2度順次上行。「ひかりの」はこの冒頭で、ppからfまで、音程を順次上行しながら一気に5回繰り返される。
「のーーー」(f>p)が引き延ばされたのち、「ひかりのなかにひとは(わ)いる」の詩句がくる。
「てをかざして」は女声2でf、アクセントで強調を指示。男声2が「ha――」「こうぉーーもりかさをさして」と下で動き、「みつめるのは(わ)」は4声がずれながら追いかけ合う。増殖し追いかけてくる眼に怯むと、「りゅうし」が全声部で叫ばれ、迫り上がる。ここまでほぼ一息に近い。こういう攻め方、いかにも西村だ。

この、声の扱いにある言葉の反復とたたみかけ、細分とリズムのずらし(ケチャ風)。例えば合唱曲『青猫―五つの詩』(1996/萩原朔太郎)の『鴉』での「ずんずんずんずん」「おまえがおまえが、おまえが」。あるいは最初の歌曲『輪廻』(2004/朔太郎)での「あとからあとから」「べらべら」「くるくる」幾重にも襲う音形、とりわけ「べらべら」6回の執拗。
似ている、萩原と佐々木、と思ってしまうが、同じでは無論ない。
だが、まさに西村ワールドだ(前作『夏の庭』3篇もこの手法は明らか)。
「どろを どろを たべる たべる たべる たべる」の畳みかけは、全声部での「とうげをこえてゆきあうひとは(わ)」「のどのおくに くいこむ くいこむ くいこむ」と追い込み、一呼吸フェルマータののち「せいさんな〜〜〜(ここは全声部でのグリッサンド) あおぐろい(5連符) おおぞらの(3連符×2) ffりゅうしをーーーsubito pp のめ」。「りゅうしをーーー」の「をーーー」の引っ張り方(フェルマータがある)での山と谷、というより崖っぷちときたら空恐ろしいほど。で、「のめ」。これが前半のクライマックスだ。この間、音符も4〜8〜16を細かく振り当て切迫を創出する。
まさに筆者を射た句「凄惨な 青黒い大空の 粒子を飲め」の音景がここにある。
佐々木の皮膚を撫で、佐々木を食べる。いや、佐々木の肌を撫で回し言葉に食らいつく西村の生理衝動が、まざまざと現出していると言えるのではないか。
それにしても急く、急く。
と、一転「女たちの」からの次節は、なだらかにうたわれるが(決してゆったりではない)、その構造はかなり手がこむ。筆者が気になった「岩の上で笑う仏塔」、続く「生きものの光は ここで生まれ ここで死に絶える」は一貫してピアノのトレモロの上を波立つ。ここに描かれる情景は、この詩のもう一つのキモだろう。「岩の上で笑う仏塔」に筆者思わず『紫苑物語』の崖の仏頭、矢で射られ崩落するそれを重ねてしまったのだが。
で、1小節の休止(ピアノは残る)のち「石の道を走りながら」が来る。ここでは「いしのみちを」を2回繰り返し「いしのみちをはしりながら」と駆け、「塩の谷を歩きながら」では言葉のまま歩くが、やはり急ぎ足であることに変わりない。つい筆者は佐々木の「走れ 走れ 渡れ 渡れ」を思ってしまう。いずれにしても、この2句での「ながら」の韻は素通りされ、いきなりffpp「ha――」の発声からのヴォカリーズが9小節続く。4小節目でffの頂点、そこから4小節でppに。ここは大波である。ピアノのアルペッジョがそれを烈しく揺らす。

こう見ると、この長いヴォカリーズの挿入は、後続の「ヤクの毛を紡ぐ棒を回しながら」からの2句の「ながら」韻を一旦切る作用と思える。つまり、前に置かれた「生きものの光は ここで生まれ ここで死に絶える」の音調、声調、いや言霊、その残影を残す必要があった....。
「やくのけをつぐぼう(ぉ)を」(Tempo Ⅰ)は男声2で開始、「まわしながら」は全声部での16分音符でアクセントがつく。そして「ほそいきを けずりながら けずりながら けずりながら」「さらに さらに さらに さらに」と声が襲う。この間、ピアノは本作冒頭の和音の3連符形とアルペッジョ、あるいは16分音符の細かい刻みで伴走する。

つまり、「ながら」の韻は連続4句「走りながら」「歩きながら」「回しながら」「削りながら」だが、間にヴォカリーズを入れることで、後半の足から手(腕)へと昇る言葉を強調する。とりわけ、「削りながら」の畳み掛け、さらに続く「つちのかおで」の6回の繰り返しが、いっそう強く皮膚に食い込む、耳を削る...。ピアノは下降アルペッジョの波、最後は f のクラスターに近い音塊を打ち鳴らす。そうして一呼吸、フェルマータののち、p<fで「むかえてくれるものを もとめて」の終句が来る。「もとめて」は16分音符でアクセント記号つき。ピアノは高音の和音を一声カーンと響かせる。
詩句、言葉に沿っての動きの設計の細密!
休止を挟み、ここからMeno mosso(pp)で再び「ha――」のヴォカリーズが5小節。3声の水面に浮かぶsopはどこか聖歌風な光の聖性を帯び、美しいハーモニーが一気に別世界へと誘う。この部分にはそれまでの急迫からふうっと息を吐くような陶酔があり、一瞬の夢、のような感じだ。歌う人もここを目指してなんとか耐えるのではないか(と思ってしまうくらい厳しい作品、と言ってしまおう)。

最終節「光はバターの匂いを撒きちらし」からの最終景はこうだ。
「ひかりは(わ)」は各声部、互いにずらされ7回現れる。全声部下降3連符ha––に曲冒頭のピアノのパターン音形が寄り添い、p「バターのにおいをまきちらしー」がp<mfで歌われる。16分音符f「くもをつきぬけ」2回、「くもを」2回、「ha―」(ffpp<f)。
フェルマータ、女声2「すんだあぶらとなって」「あぶらとなって」、「おおそらから」(女声、男声のずらし)が4回、「そらから そらから」が6回降りてくる。ピアノは下降アルペッジョの小波。Tempo Ⅰで再び「ha―」(ffpp<f)3小節のちff「そらからおちて」、ピアノの下降上行アルペッジョに男声2が残りff。休符、のち、叫ぶ。「おちてくる」!

それにしても、なんと不安に満ちた作品であることか。
詩を読んだだけ(黙読)では、浮かんでこない情景だが、西村にはこう見えた。
だが、音読(佐々木は子供の頃はみな音読だった、学校で黙読せよ、と言われた時の不自然はなかった、とどこかで語っている)こそが本来、読むことの真実なのだ。
西村の「読葬」という言葉に、筆者、読経を思ったが、おそらくそれは通底する。「読葬」とはまた「読奏」に他ならない。詩を読む、詩をうたうそのことの真理。
今回はここまでとする。
実は筆者、とっとと『清姫―水の鱗』に取り掛かるつもりだった。
その前に並ぶ合唱作品を、とのぞいたら、さっと一瞥などできるものではなかった。
つまり、佐々木の詩と西村の音の間の話だ。
『大空の粒子』に収められている他の2篇には触れないが、第1曲《地球も》、第2曲《火を飼う》はこの第3曲でしか受け止め得ない詩・曲たちであったことだけ指摘しておく。
さらに、これらの詩が収録されている詩集『蜂蜜採り』について、また、2011年東日本大震災以降に書かれた作品について、書いておくべき重要なことが大きくまだ残っている。
次回に続く。
*本稿執筆にあたり、「新しいうたを創る会」の中嶋香氏、詩人の佐々木幹郎氏、洪水企画の池田康氏、合唱団「樹の会」藤井宏樹氏より貴重な資料のご提供をいただきました。
御礼申し上げます。
(2023/11/15)
註
- 『洪水6号』「音に遊ぶ」 DIALOGUE [詩の鳥葬、声の産卵] 佐々木幹郎 西村朗 p.22
- 羽田事件とは1967年佐藤栄作首相の南ベトナムを含む東南アジア各国訪問を阻止しようと10月8日、反日共系全学連の学生約2,000人が羽田空港周辺で警官隊と激しく衝突した。学生1人が学生の運転する警備車にひかれて死亡と報道された(死因については疑義あり)。その弁天橋で死亡したのが佐々木の高校の友人の京大生山崎博昭(当時18歳)であった。
- 『洪水6号』「音に遊ぶ」 DIALOGUE [詩の鳥葬、声の産卵] p.30
- 『続・佐々木幹郎詩集』思潮社現代詩文庫139 1996 p.90
- 本書は2巻に分かれており第2巻『記録資料篇』は2018年刊行された。
- 山崎の兄による評伝で家族が一時鴫野の長屋に住み、博昭が4歳から小学4年までを過ごし、西村朗と同じ城東小学校に通っていたことを知った。山崎は1948年生まれだから、西村より5歳年長。すでに博昭は転校しているが、同じ小学校の校庭で遊んだと思うと不思議な感覚に襲われた(本連載開始前に筆者は西村の実家跡を訪ね、この小学校にも足を運んだので)。長屋住まいの山崎兄弟は誰かの母親が「ごはんやで」と呼びにくるまで友達とわいわい遊んでいたという。一方、西村はばあやつきのぼんぼんであった。ただこの5歳の相違は、戦後というものの景色の相違を考えると非常に大きい。ベトナム戦争に反応した山崎世代と、学生運動を「知らんわい」とした西村世代の隔たりを改めて考えさせられた。
- 『大悲心陀羅尼』はこの8月初旬の川上村での合唱セミナーのコンサートで歌われる予定であった。西村氏と筆者はそこで会うはずであったが、二人とも体調崩し、結局聴くことはできなかった。このコンサートは録音され、後日届けられ音を聞いたが、すでに氏の病を知っていた筆者には辛い聴取であった。
参考資料)
◆書籍
『洪水1号』洪水企画 編集・発行人:池田康 2007 年12月
『洪水6号』同上 2010年7月
『佐々木幹郎詩集』思潮社現代詩文庫 76 1982
『続・佐々木幹郎詩集』思潮社現代詩文庫139 1996
『地球観光 深川・ミシガン・ネパール』佐々木幹郎著 五柳書院 1990
『旅に溺れる』佐々木幹郎著 岩波書店 2010
『かつて10・8 羽田闘争があった』(10・8山崎博昭プロジェクト編)合同フォレスト 2017
◆楽譜
『夏の庭』西村朗 佐々木幹郎詩 全音楽譜出版社 2010
『大空の粒子』同上 2010
◆ CD
『佐々木幹郎と西村朗の世界』
藤井宏樹/樹の会 合唱音楽の夕べvol.6 日本アコースティックレコーズNARC-2147
◆Youtube:
『佐々木幹郎と西村朗の世界』
藤井宏樹/樹の会 • アルバム
『大空の粒子』『鳥の国』『清姫』
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mhUXJLVhNdhlOzEJXwsnW-phBNc4AtnTQ