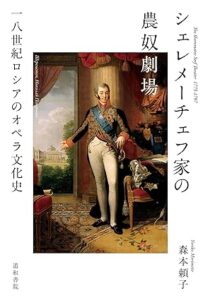書評|対訳 禅と日本文化 Zen and Japanese Culture|丘山万里子
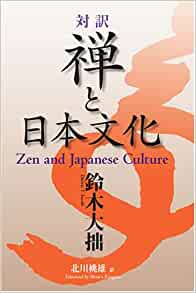 対訳 禅と日本文化 Zen and Japanese Culture
対訳 禅と日本文化 Zen and Japanese Culture
鈴木大拙著 北川桃雄訳
講談社 2005年
1800円
Text by 丘山万里子( Mariko Okayama)
鈴木大拙(1870~1966)は禅思想を欧米に広めた立役者で、仏教学者・思想家と位置付けられる。1897年渡米、仏教書『大乗起信論』『大乗仏教概論』を英訳出版、滞米は11年に及ぶ。帰国後の1911年Beatrice Laneと結婚、1936年には英米の大学で「禅と日本文化」(原書『Zen Buddhism and its influence on Japanese Culture』1935)を講じた。大拙といえば『無心ということ』(1939)『日本的霊性』(1944)が有名と思うが、筆者、何度か読んでは見たもののまったく性に合わず投げ出している。
1950年代日本の前衛が元気な時期、実験工房(1951~57)の武満徹、湯浅譲二、秋山邦晴らが『禅と日本文化』(日本語版1940年初版/岩波書店)に夢中になったこと、ケージがコロンビア大で大拙に接し傾倒、大きな影響を受けたことは『西村朗 覚書12』ですでに触れたが、日本の現代作品を考えるにあたり、やはりここを避けては通れないのではないか。どうせなら欧米に知られた原文で、と本対訳版を手にとった。
同時に、海外の日常で外国人から興味を持って問われるのは日本文化であって、西欧その他の文化でないことは当然なのだが、これに答えられる人はそう多くないのではないか。筆者は自国文化を真面目に勉強してこず、もはやその役目は果たせないが、国際舞台で活躍するこれからの世代に、本書は最も簡便かつ適切に思う。古き良書というのはそういうものだ。
ちなみに禅は8世紀初頭に中国に発達した仏教の一形態で、日本では12〜14世紀鎌倉室町時代に興隆を見る。栄西の臨済宗、道元の曹洞宗がそれだが、ここで扱われるのは宗派の教義云々ではなく、その精神がどのように日本文化に影響を与えたか、というざっくりした話なのでとっつきやすい。東西宗教・文化に通じ(西はほぼキリスト教のみだが、東は儒教、道教に触れている)、各領域に具体例をあげ、コンパクトに「禅」文化を語っている。「対訳」つきが肝だ。日本語で「無心」だの「霊性」だの言われても、西洋的思考癖で暖簾に腕押し、するりするりと逃げられる禅問答にうんざりするのだが、何しろ外国人知識層に理解させるのが目的だから、平易な英語で日本語よりスラスラ入ってきてわかった気になる。おまけに仏教用語も学べるわけで一石二鳥、私たちの日常にばらまかれている実は仏教由来語とその意味に気づく契機にもなる。
全6章は以下。中で筆者がなるほど、と思った箇所を抜粋する。
第1章:Preliminary to the Understanding of Zen 禅の予備知識
予備知識となっているが、存外に面倒で仏教用語に引っかかってしまう。が、例えば禅(仏教)の真髄を般若と大悲と述べるに、般若(智慧) Prajñāをtranscendental wisdom、大悲Karunaをlove or compassionと英訳。大悲は日本語でも見当はつくが、般若となるとお手上げ。それを彼はこう説明する。
Prajñā makes us look into the reality of things beyond their phenomenality, and therefore, when
Prajñā is attained we have an insight into the fundamental significance on life and of the world, and cease from worrying about merely individual interests and sufferings. ( p.12)
Zen undertakes to awaken Prajñā found generally slumbering in us under the thick clouds of Ignorance and Karma. 同上
Ignorance and Karmaは無明と業。
Anything in fact which has to do with creation in its genuine sense is really “untransmittable,”that is , beyond the ken of discursive understanding. Hence Zen’s motto, ”No reliance on words.”
No reliance on wordsは不立文字(言葉に頼るな)。(p.18)
「初めに言葉ありき」とは真逆である。ここらが当時の欧米知識層には魅力だったに違いない。
まとめの部分で言うに、知識を3種に分ける (原文に沿って抜粋)。
knowledge: we gain from reading or hearsay
scientific: the result of observation and experiment
intuitive mode of understanding
この第3のintution (直覚)が 全編を貫く禅の態度で、しょっちゅう出てくる。
which penetrates deeply down to the very foundation of existence, or, rather, which emerges from the depth of our own being. (p.22)
「深く存在の基礎にまで浸透している、というよりはむしろ、われわれの存在の深いところから出てくるもの」(訳文)
ちなみに大拙はハイデガーと親しかった。
抽象論に傾きやや難解だが、要点でもあるので、続く章を読みつつ戻って参照するのが良いのではないか。
第2章:General Remarks on Japanese Art Culture 禅と美術
禅は中国由来だが、中国より日本において独自の芸術的発展、文化として定着した、と具体例を挙げる。藤原定家らの歌、禅画(雪舟など)、建築物(日光東照宮)、庭園(夢窓国師)、禅問答などに、様々な名が上がっており、それぞれをサイト上ででも見学すれば、彼の言う禅の美のイメージは把握できる。日本史教科書で読んだもろもろ、美術館、はたまた旅先での記憶などを甦らせてもくれる。
ここは何より、わび、さび、だ。ここでは原文のみを挙げる。
Wabi:牧谿(もっけい)『叭々鳥図』の説明とともに
Wabi really means “poverty” or, negatively,”not to be in or with fashionable society of the time.
To be poor, that is, not to be depending on things worldly – wealth, power, and reputation, and
yet to feel inwardly the presence in oneself of something which is of the highest value above time and social position—this is what essentially constitutes wabi.
(poverty を訳者は「貧困」と訳しているのはどんなものか)(p.28)
Sabi:藤原定家の歌を例に
The artistic element that goes into constitution of sabi which literally means ”loneliness”or “solitude” is poetically defined by a tea-master thus,
“As I come out
To this fishing village,
Late in the autumn day,
No flowers in bloom I see,
Nor any tinted maple leaves.”
見わたせば 花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの 秋の夕暮れ
訳語は孤絶、孤独。(p.32)
そうして出てくるのが「一即他、多即一」で、禅の美意識を非均衡性、非対称性、「一角性」(one-corner)、単純性、さび・わび・孤絶性その他は全てこの「一即多、多即一」にある、とまとめる。
Unbalancing, asymmetry, the “one-corner,” poverty, simplification, sabi or wabi, aloneness, and other cognate ideas making up the most conspicuous characteristic features of Japanese art and culture—all those emanate from on central perception of the truth of Zen which is “ the One in the Many and Many in the One”.(p.38)
この後、“One in All and All in One”という句も出てきて、やはり「一即多、多即一」と訳され、ややこしい。その説明は以下。
“ All in One and One in All” is not to be analysed first to the concepts “One” and “All” and then to put the preposition between them; no discrimination is to be exercised here, but just to accept it and abide with it.” (p.54)
ここから仏教の根本義「空即是色、色即是空」へと展開するが本稿はここで止めておく。
第3章 Zen and Samurai 禅と武士
なぜ禅が武家社会に受け入れられたかを述べており、次章「禅と剣道」と合わせ、本書で最も長く、力が入っているのはやはり海外目線に合わせてのことだろう。
この稿の執筆は第二次大戦前だが、禅の精神性を宿す武士道、剣道の記述に「特攻精神」を重ねるのは容易だ。映画『切腹』(1962)の音楽は武満が担当しているが、おそらく読んでいたろう。映画自体は封建的武家社会のアンチテーゼであったが、海外では侍精神の悲壮美が愛でられた。かように、ものごとは見たいように見られるのである。
章は、そもそも慈悲の宗教(仏教)がなぜ武士の戦闘精神を励ますことになったか、から始まる。
武士は単純で哲学的思索に耽らない(知性でなく直覚を重視する)、その修行は単純、直裁、自恃、克己的。そこが禅だ、という風に展開してゆく。
とりわけ禅行者である武将、北条時頼(1227~1263)、その子時宗(1251~1284)の絶賛が続く。
彼らによって禅は日本人、とりわけ武士の生活に浸潤したという。「武士道」もここに存立する。
紹介されるのは17世紀中葉に編纂された『葉隠』で、有名な一節も出てくる。
“Bushido means the determined will to die.” 武士道といふは、死ぬ事と見附けたり(p/80)
さらに引用は続くのだが、割愛する。
続いて登場するのが武田信玄(1521~1573)、上杉謙信(1530~1578)。両者とも深く禅を学んだという。
上杉謙信の一句。
“Both Heaven and Hell are left behind;
I stand in the moonlit dawn,
Free from clouds of attachment.”
極楽も地獄も先づは 有明の月の 心にかかる雲もなし(p.94)
「潔く死ぬ、は禅の教えと一致する。日本人は生の哲学は持たないかも知れぬが、死の哲学は持っている」との大拙の言葉、当時の空気を考えると空恐ろしくもあるのである。(p.99)
第4章 Zen and Swordsmanship 禅と剣道
” The sword is the soul of the samurai.”から始まり、刀は忠と自己犠牲の象徴と語る。中で、こんな言葉が。活人剣と殺人剣につき、それぞれをいついかなる風に使うべきかを知るのは優れた禅匠のなすところ、に続き、文殊菩薩は右手に剣を、左手に経典を持つが、マホメットも同じだと。宗教で片手に剣とはどういうことか考え込んだが、鵜呑みせず、自分で調べることが肝要だろう。
ここでは沢庵和尚(澤庵宗彭1573~1646)の『不動智神妙録』の「剣禅一致」が中心となる。「心の置所」「本心妄心」「有心之心、無心之心」「応無所住而生其心」などキーワードが並ぶ。大拙は芸術もまた「無心」「無我」の境地を最上とすると述べており、肯けるところだ。まずは「心をどこにも置かない」から考え始めると、実に深い。演奏家、スポーツ選手など特に有用と筆者は読んだ。
“Have no thought , no deliberation, no discrimination, and the mind will be present everywhere, working itself to its fullest capacity and accomplishing the business then at hand.” (p.126)
スペイン闘牛士の剣の話から神影流、さらに宮本武蔵の剣の極意「空」にまで話は及ぶ。武蔵は水墨画の大家でもあり、筆者、先般、東寺でこれを見たものの通り過ぎたことを思い出し、自分の節穴を恥じた。
第5章 禅と儒教
禅はインド仏教を中国化したもので、むろん偉大なる孔子や老荘まで、儒教・道教を素地とする。とりわけ禅が儒教になじんだ理由など、歴史に沿って俯瞰する。インド仏教の「空」は彼らにはなかなか理解できない概念だったが、老子の「無」の観念に近いと知り受け入れたとのこと。
したがって日本の禅匠も儒学者であり、禅林(禅宗寺院)は編集印刷技術の活用により教育機関としての機能も果たしていたので、儒学の素養が一般に広まり、寺子屋の原型となった。これが明治期まで続くわけで、改めて日本文化の何たるかを思う。
私たちは明治期に日本のこうした文化を日常から放逐したのであるが、それもまた次なる異国文化への貪欲な欲望で、この摂取パターンこそ日本的と考えるべきか…。
ただこの章は大拙も駆け足で、中国禅の背景、つまり老荘中国を含む思想史はやはり自分で学ばねばなるまい。いかんせん、日本の僧たちは海の向こう中国に焦がれ、危険を賭して渡り、多くの経典を持ち帰り、広めたのであるから。
第6章 Zen and Tea-cult 禅と茶道
再びわび・さび世界に回帰する。
茶を日本に広めたのは栄西禅師(1131~1215)で中国から持ち帰った種子を禅院の庭にまき、栽培したのが始まり。彼の『喫茶養生記』という書物はもっぱら薬効が語られており、現在の茶の作法をもたらしたのは大徳寺の一休和尚(1394~1481)で弟子珠光(1422~1502)が茶道を確立した。茶は心身を爽快にさせるが、キリスト教のぶどう酒は酩酊させる、などクスッとするコメントもある。
茶の精神は「和・敬・清・寂」で、禅の生活に他ならない、と、それぞれについて詳述するが、ここではかの利休の歌から筆者が特に気に入ったものを一つだけ紹介するにとどめる。
“The snow-covered mountain-path
Winding through the rocks
Has come to its end;
[Here stands a hut,
The master is all alone;]
No visitors he has,
Nor are any expected.”
岩伝ふ 雪の細道 あとたえて 訪ふ人もなし 待つ人もなし (p.211)
茶湯のわび・さびについてはさらに深い論考が続くのだが、紙幅が尽きた。また、茶道ばかりで能楽に触れないのはいささか片手落ちに思うが、おそらく入り込むのに困難なところがあるのであろう。
ただ、末尾で大拙がふと漏らした「美的思慕」esthetic aspirationという言葉が筆者には実に印象深く、ひょっとすると日本文化の核心はこれにあるのではないか、とさえ思った。
異国文化への人一倍強い思慕。「日本的心性」は文化的恋愛体質なのかもしれぬ、など妄想が膨らむのであった。
最後に、ケージ1962年来日時に、大拙との対談で「先生の講義の中で、忘れられない言葉は、“山は山である。春は春である”という、あの名句です。私はその時“音は音である”と霊感のように思ったんです。」とのセリフへの対句を論中から引っ張っておこう。
When asked “What is Zen?” the master sometimes answers, “Zen, ” and sometimes “Not Zen”.
これを有名な「即非の論理」という。
少なくとも本書を上っ面でもなぞっておけば、あちらの人に問われてもドギマギせずにすむかもしれない。かの大拙によれば、と言えば良いのだ。私たちは年中、プラトンによれば、とかアドルノによれば、とか言いまくっているのだから。
(2022/1/15)