評論|西村朗 考・覚書(11)永平寺と『慧可断臂』(1976)|丘山万里子
西村朗 考・覚書(11)永平寺と『慧可断臂』(1976)|丘山万里子
Notes on Akira Nishimura (11) EIHEIJI&『EKADANPI』(1976)
Text & Photos by 丘山万里子(Mariko Okayama)
5月下旬に3日間、道元禅師(1200~53)の開いた曹洞宗大本山永平寺(1246~)に滞在した。
 いつか訪れたいとは思っていたが、この6月の《Music Tomorrow》開催前に、どうしても行っておきたかった。昨年、世界初演予定だった西村朗『華開世界~オーケストラのための』(2020)がコロナで延期、であればその前に道元世界に触れておきたい。
いつか訪れたいとは思っていたが、この6月の《Music Tomorrow》開催前に、どうしても行っておきたかった。昨年、世界初演予定だった西村朗『華開世界~オーケストラのための』(2020)がコロナで延期、であればその前に道元世界に触れておきたい。
「華開世界」とは道元『正法眼蔵』の〔梅華〕の巻にある「華開世界起」からのもの。本稿第1回で述べた通り、西村が道元に向き合う、というのが筆者にはやや意外だった。細川ならある意味、わかる。西村、『紫苑物語』の次の歩に、道元とは?第2部第6場「弓矢とともに滅ぶこと」<仏頭の歌>での「行、行、行」の連呼とそれに続く第7場「平太と<鬼の唄>」の平太『大日経』読経が、いかにも、であっただけに、そこから道元世界をどう望むのか、何を見るのか。本稿執筆への背を押したのは、その問いでもあった。
《Music Tomorrow》では細川俊夫『オーケストラのための「渦」』(2019/筆者既聴)と、両御大が並ぶプログラム、楽しみだ。
筆者は卒論でハイデッガー『存在と時間』をベースに演奏論を書き、そこから道元『正法眼蔵』の〔有時(うじ)〕を知った。1970年前後、日本の現代音楽最盛期にあって、ケージらが鈴木大拙の禅だのなんだのを引き合いに東洋思想を語るのに辟易しつつ、日本の作曲家たちが一斉に東洋回帰を唱えるのに辟易しつつ、だが、この違和感の依ってきたるところを自分で確かめねば何も始まるまいと考え、『”東洋の回帰”をめぐって』(1976/音楽現代)を書いた。いや、物心ついて以来、「コギト・エルゴ・スム(Cogito ergo sum)」の塊なる自我意識が身裡にはびこり、生きることの困難に絶えず喰み苛まれていた、それが因で、そのような世界了解(世界への向き合い方)でない了解の仕方として、例えばウパニシャッド最大の哲人ヤージニャヴァルキア(前700~750)の万有における最高原理を「このアートマンは内なく外なく〜不壊にして不断滅〜ただ“非”“非”というべきのみ」と説く、その否定を積む思考法に惹かれた、それが入り口だ。一切の差別的限定を退ける思考の形。
言ってみれば西欧的思惟でない(ちなみに助手論ではなぜかルカーチの弁証法をやったからずいぶん幼い理解ではある)東洋的思惟なるものを切実に知りたかったのだ。
その流れの中に、筆者の道元はそびえる。〔有時〕は『存在と時間』に匹敵する日本の哲学・存在論と理解、ずっと傍にあるからして西村の「華開世界」は気になる。ちなみに『正法眼蔵』(1231~1253)執筆の頃、中世スコラ哲学者トマス・アクィナスが『存在と本質』(“De ente et essentia” 1252/53)を書いており、道元の研究者玉城康四郎は両者とも「思考する」ことを軸に展開する点で同質だが、アクィナスは筋に従って行けば理解できるが道元は解読できず、ここに「思考する」の意味の相違がある、と指摘している。1.
無調もセリエリズムも偶然性も、そこから語り得る気がしていた。内外の作曲家らが(当時は宗教界もしきりに東西云々と賑やかだった)「東洋」を好きに食い散らすのを、我が事とまともに考え抜く音楽評論が日本にあってもよかろう、と不敵に考えたのだ。
東京から特急を乗り継ぎ福井、うねうね山道バス40分の山裾に永平寺はあった。5月の緑がまばゆく溢れ、参道に沿って瀬音高き永平寺川がしぶきを上げる。一段の冷気。人姿はほぼなし(コロナゆえか)。「霊山」の清冽にぎゅっと心身が引き締まる。そちこちで鳥のさえずり。日中も賑やかなカエルの歌声は夕暮れに一層勢いを増し、まさに大合唱。
初日はすでに閉門ゆえ川沿いを登り寂光苑で道元の稚髪像など見つつ、そばの「寂照の鐘」を撞く。誰でもいつでも鳴らして良く、禅師の遺徳を偲べるそうだ。むろん、撞いた。荘重と言うより澄んだ音色(ねいろ)で、筆者の自宅近くの禅寺の音より軽やかだ(毎夕5時にはそれが聞こえる)。ヨーロッパに暮らした時は教会の鐘の音で1日が回る日常を羨ましく感じたが、何のことはない、私たちにもそういう景色はあった、と改めて思う。永平寺の七堂伽藍には何箇所も鐘があり、それぞれの用いられ方で修行僧たちに合図を送り、また近隣の人々に日々の運行を伝える。
貸切状態の宿、とっぷり暮れた夜陰に、子狐やハクビシンが現れると宿の人が教えてくれた。
早朝5時、朝のお勤め(朝課)に参加すべく尼僧に連れられ門をくぐる。筆者母娘のほか誰もいない。伽藍内は若い新人修行僧の先導で長い長い階段、これでもかと続くおよそ700段を法堂(ほっどう)まで昇る。息が切れ、最後は手すりにつかまりつつ、だ。
まずは首座(しゅそ)法話で、過去・現在・未来はあるのでなく、自分がそれを生む(主体は自分)、といったことが説かれ、筆者は「それ、コギト的でないか」と躓いてしまったが、話は「生きる」のでなく「生かされている」「自己を修め、他者を思いやる」と和やかに収まったあたりさすがである。
ちょうど3ヶ月の夏安居(げあんご/雨季のおこもり)に入っており、通常とは異なる楞厳会(りょうごんえ)が行われる。期間中に魔障を除く神咒『楞厳咒』(りょうごんしゅ/サンスクリット)を唱えつつ、祭壇を右手に僧侶たちが堂内を整然と巡るもので、立ちあえたのは幸運であった。終盤に向け次第に読経が高揚、アッチェルランドしてゆくさまは形容しがたい。墨染、剃髪の僧侶たちのゆるゆると言うよりかなりの速さに感じられるその巡行の美しさと声の渦にただ見惚れ聞き惚れ、巻き込まれていた。
ブッダ足跡を辿るインド田舎旅、祇園精舎(サヘト)で見た風景を思い出す。緋色衣の修行僧らが炎天下、小塔の周りをぐるぐる回っていた、それと同じ、ブッダ説法時、ブッダを右周りに3周の礼拝作法が伝わるものだろう。遥かな時空の荘厳(しょうごん)の形がここ眼前、堂内に立つ。


続いて通常課となり、『宝鏡三昧』『五十七仏』『大悲心陀羅尼』が読誦される。筆者らには事前に経本が渡されており、新人僧がカンペで読経ページを教えてくれる。都度、墨染の袖をひるがえし、座す僧らの間を縫い、経を配り回る役僧の所作に心奪われる。ふわり袖裾舞う黒蝶のごとき幻想性はほとんど官能的だ。
バリトンの維那 (いの/唱導師) は若く長身、顔立ち整い、入堂時から独りオーラを放っていたが(ブッダ愛侍者アーナンダを思わせる)、その冴え冴えに和す僧らの声が、音の帯、あるいは渾然たる河となって開け放たれた外気に溶ける。とりわけ『大悲心陀羅尼』のやや高めの音韻音律は圧倒的で、基音(たぶんd)が細流となり、そこに広幅の帯が淡い虹のようにかかる。「なむからたんのー とらやーやー なむおりやー ぼりょきーちい」。
倍音の誘引するめくるめく妖しさを、身をもって知る。こちらも高揚加速(心理的な、と言うべきか)で句をぐんぐんたたみ込む威力、引力、まるでラップだ。これが陀羅尼(真言・マントラ)の真髄と得心する(と書くと意識が働いているようだが、さなかにあっては、ただただ流れにのみこまれている、に近い)。韻をふむその音律と調べのいざなう酩酊、法悦とはこれか。
『楞厳咒』が「渦」で基音が低めの (b)であったそのある種の凄み(魔除けであるからか)が残っていただけに、この陀羅尼の魅力は倍増であったと思う。
響きに身を浸しつつ、一瞬、西村のヘテロフォニーが頭をよぎる。
この読誦ののち、居並ぶ僧侶、筆者ら全員の名が出身地とともに列呼され(神社でのご祈祷と同じだ)、参拝者は別置の祭壇に進み出て礼拝、のち僧ら退場で終了。1時間ほどだったか。
先ほどの尼僧が、伽藍全体の案内へといざなう。法堂は全体の最上部にあり、その下に仏殿が位置し、中央に本尊釈迦牟尼仏が祀られている。七堂の中心部ではあるものの、修行道場たる法堂を上にいただく(背にする)のに、修行こそ第一義とする道元禅師の声が聞こえるようだ。
 その仏殿(1902改築)、本尊を挟み向かって右から過去・現在・未来の三世との説明とともに、右レリーフを見上げ、図が『慧可断臂』と聞き、えっ!と驚愕する。
その仏殿(1902改築)、本尊を挟み向かって右から過去・現在・未来の三世との説明とともに、右レリーフを見上げ、図が『慧可断臂』と聞き、えっ!と驚愕する。
 4月、『耿』スコアとともになぜか送られてきた自筆スコアが『慧可断臂』(1976)だったからだ。この作品は目録にない。存在を知らないから西村氏に依頼もしていない。おそらく、たまたま発見され、ついでに、となったと思われるが、筆者はこれもたまたま雪舟『慧可断臂』を目にしたばかりで、その絵とスコアが直結、どういう風の吹き回しか、といぶかしんだ。めくれば谷川雁詩集より『恵可』2.が綴じてあり、西村の書き込みがある。
4月、『耿』スコアとともになぜか送られてきた自筆スコアが『慧可断臂』(1976)だったからだ。この作品は目録にない。存在を知らないから西村氏に依頼もしていない。おそらく、たまたま発見され、ついでに、となったと思われるが、筆者はこれもたまたま雪舟『慧可断臂』を目にしたばかりで、その絵とスコアが直結、どういう風の吹き回しか、といぶかしんだ。めくれば谷川雁詩集より『恵可』2.が綴じてあり、西村の書き込みがある。
〜「断臂の図」—(恵可よりの試み)ソプラノとピアノのために〜
と。
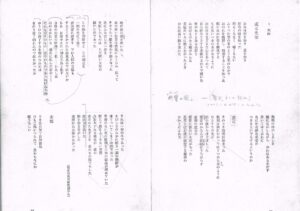 慧可(487~593)は中国禅の始祖菩提達磨(5-6C前半/ボーディ・ダルマ)3.を継ぐ二祖で、面壁9年の達磨に何度教えを乞うても許されず、半身まで雪に埋もれた夜、肘を切り落とし、求道の熱意を示したという故事で知られる。その図だ。谷川雁4.の詩には「雪舟作恵可断臂図から」とある。
慧可(487~593)は中国禅の始祖菩提達磨(5-6C前半/ボーディ・ダルマ)3.を継ぐ二祖で、面壁9年の達磨に何度教えを乞うても許されず、半身まで雪に埋もれた夜、肘を切り落とし、求道の熱意を示したという故事で知られる。その図だ。谷川雁4.の詩には「雪舟作恵可断臂図から」とある。
西村が鉛筆で囲い込んだ後半部分を写しておく。
この腕を切断せよ この頭足を
一閃の光にて裁て
青山常に運歩す では人間の苦悩も
するどく生かされた山水木石ではないか
ああ お前ゆえに一切は不具と化す
自我の幻覚の呼称....私....わたしは
石のなかにいる 湖水に沈んだ石のーーー
それも刃そのもの 光そのものであらねばならぬ
ゆうひの透了する生物のむれには
きのう遠く別れたのではなかったか
それは一秒の冬であった
きびしさのなかに眠る一滴の陶酔が
凍りついてしまう時刻であった
季節のない夜の隙間を六角の結晶が埋めていた
断じて劇をふくまない空間
白衣のすれる薄光が 彼の
青ざめたあぎとを 束のまの間てらした
彼は刃を抜いた
腕を切る音がした
達磨はなお動かなかった
この詩句からの西村のテキストは、以下。
彼はその後ソプラノからバリトンに変更している。
この腕を切断せよ この頭足を
一閃の光にて裁て
青山常に運歩す では人間の苦悩も
するどく生かされた山水木石ではないか
(この腕を切断せよ)
ああ お前ゆえに一切は不具と化す
自我の幻覚の呼称....私....わたしは
石のなかにいる 湖水に沈んだ石のーーー
夕日の透了する生物のむれには
きのう遠く別れたのではなかったか
彼は刃を抜いた
腕を切る音がした
達磨はなお動かなかった
永平寺を訪ねるにあたり、一応、氏にこの作品の由来をお尋ねしてはいた。道元が慧可に連なる禅師であれば、頭に入れておこう、くらいで、その図柄に遭遇するとは思いもよらなかった。
達磨が背を向け座し、それを見ながら腕に刃を当てる慧可。堂内は暗く、細部は見えにくいが、筆者は凝然と眼をこらした。
雪舟の絵は『対決 巨匠たちの日本美術』展(2008@東京国立博物館)で雪村との組み合わせで見ているが、その時の印象は無い。スコアが届いた時、購入した図録を引っ張り出して見比べ、改めて思うところはあった。
が、この地、堂内でこの図柄を見上げていると、東京でただ眺めていた西村の音が、静寂な空間を切り裂いて響き渡るように思った。
尼僧に促され、大庫院(台所)、浴室、山門、東司(トイレ)、僧堂と回る。仏殿(心臓)を中心に右側は日常、左側は修行と対向配置、結ぶ回廊は血管、そこを僧侶たちが血流となって流れるように設計されているという。朝課を終えた時刻であれば、大庫院からは朝餉の匂いが立ち上り、配達箱を手にした僧侶が次々出て行く。祀られているのは韋駄天で、食料配達の迅速を願うというから思わずUber Eatsね、と笑ってしまう。人間の考えることは大して変わらない。
すでに8時を回り、一般参観が始まる前に、宿へ戻って朝粥の朝食。
ほぼ3時間の修行修学で冷え切った身体にありがたく、いつになく完食した。
 コロナにより寺では中止の写経、宿の写経・座禅専用間で挑戦したが、心静かに一心に心を込めて、などいう境地とは程遠く、下敷きの手本にしおらしく従ったのは最初の一行、なに、写経ってなぞるわけ?と、あとはどんどこ好き勝手、あっという間に仕上げてしまった。無心無我どころか「我」がはみ出し暴れるのに我ながら呆れるばかりだ。
コロナにより寺では中止の写経、宿の写経・座禅専用間で挑戦したが、心静かに一心に心を込めて、などいう境地とは程遠く、下敷きの手本にしおらしく従ったのは最初の一行、なに、写経ってなぞるわけ?と、あとはどんどこ好き勝手、あっという間に仕上げてしまった。無心無我どころか「我」がはみ出し暴れるのに我ながら呆れるばかりだ。
再び向かう永平寺、またまた新たな発見をする。
 例えば、地元霊峰白山信仰を大切にした道元にならい、今も白山の水を大切に守り毎朝汲んでいること。なるほど彼も神仏ごたまぜなんだ。ちなみにこの霊水からなる郷酒「白龍」は僧侶たちの愛飲酒とかで、むろんいただいた。けっこう重めである。
例えば、地元霊峰白山信仰を大切にした道元にならい、今も白山の水を大切に守り毎朝汲んでいること。なるほど彼も神仏ごたまぜなんだ。ちなみにこの霊水からなる郷酒「白龍」は僧侶たちの愛飲酒とかで、むろんいただいた。けっこう重めである。
堂内では僧たちの邪魔にならぬよう左側通行。鐘の音につれ分刻みで動く修行僧たちはみんな若い。ちょうどお昼時、僧列が入るため開かれた僧堂の扉から中をチラ見し、各々与えられた居住空間は一畳、眠る時はブッダの涅槃にならい右を下に横寝で寝返りは不可、仕切りもなく横並び一列一畳のそれを目の当たりに、絶句する。
次いで先ほどの『慧可断臂』の前に座し、見上げて沈思黙考。
その間にも僧らがちらほらと動く。
食事はおろか東司、浴室も修行のうちとて無言、すべてに厳格な作法があり、大卒クラスの若者たちはその厳しさに逃げ出すこともあるとか。無理もない。規則や規律に縛られるのが嫌いな筆者には地獄だ。その手の人はここには来るまいが、いや、修行がそれをそぎ落としてくれるのか。オーラ発するバリトン維那を尼僧は「まだまだです」とあっさり言い下したが、確かに彼には「我ここにあり」が満ち満ちていた、と思い返す。
 入門を乞うにあたり、山門で列をなし待つのは春秋が多いが、厳冬下に雪に埋もれて立ち尽くすこともあるという。一度この門をくぐったら許可なしには出られない。
入門を乞うにあたり、山門で列をなし待つのは春秋が多いが、厳冬下に雪に埋もれて立ち尽くすこともあるという。一度この門をくぐったら許可なしには出られない。
さて、参禅だ。これまで写経も座禅も一切興味はなかったが、道元おわした山懐に抱かれ空気を吸ってみると、ここまで来て素通りはもったいない。何しろ二人しかいないのだし。
参加者が多ければ広間になるらしいが、筆者らは僧堂に似た部屋に案内され、まさに一畳に向き合う。ヘリの木の部分(20cmほど)は食事を置くなど神聖な場だから決して手で触れたり足を置いてはならぬ。丸い座布(座布団)を両後ろ手に掴みヘリに触れぬよう上に乗っかれと言う。無理無理。ぴょんと背面跳びでもせねばヘリをクリアできぬ。とにかく乗っかたら片手をつき足を動かし向うむきになれ。うう。結跏趺坐(けっかふざ)でも半跏趺坐でも、いやそれもできねば適当でよろしい。指導僧はこちらも朝と同様、新人で実に優しい。手の組み方(印)は「丸」らしくあればいいことに。呼吸は大きく、慣れたら普通に。すべて、ま、それでいいでしょう的に進めてくれる。身体の中心線を意識、最初は左右小さく揺らして軸をたて、次に大きく揺らして立て固定(律儀に努力する娘はここで気分が悪くなったそうだ)、目は半眼で45度。目の前の格子の隅っこに焦点を当て、いざ鐘の音とともに黙想(瞑想)開始。
姿勢はともかく(自分に一番楽な座姿を組んだが)夢想妄想幻想は筆者日常であるので、邪念を払い無の境地など目指さずたっぷり常と変わらぬ妄想にふけりまくり、やがて終了の鐘を聞く。時折背後を気にしたものの、打たれも触れられもせず、僧の気配はなかったし、へ、なんてことない、など思ってしまうこの浅はかさ。
信心も求道もなく、あるのは好奇心だけと言う我執の不心得をここでも知るのだ。
と、3日間を終えての帰路、バスの運転手さん、乗客2名への問わず語りに。
「生かされている」って、何に、だと思いますか。空気、水、暖かさ(お日様の光)です。これが私たちを生かしてくれているんです。だから感謝ですよね。
「感謝」の反対って何だと思いますか。うーん、筆者の頭には「恨み」?いや、この話の筋ではありえない....。
彼、嬉しそうに間をおき、「当たり前」です。
なんでも当たり前、と思えば感謝を忘れる、それがいけません。朝、起こしてくれる、弁当を作ってくれる、それを当たり前と思っちゃいかん、といつも子供らに言うんです。
「恨み」など思った我が心のドス黒さを恥じつつ、日々の暮らしの実感からの最高の「法話」に喝采したのであった。
* * *
『慧可断臂』のスコアを広げる。
行く前とはまるで異なる情景が浮き上がる。
1976年、作曲科4年前期課題が歌曲で、現代詩集にテキストを探すうち、この詩に出会ったと言う。
冒頭♩=ca.56でpf (ff)左手低音hから2オクターブaまで半・全音を交え駆け下る。その上に和音dis,gis, 装飾音gを伴うfis〜からの三連符がのっていったんフェルマータ。♩=ca.40 (pp<f)でゆったりas~g~f~e~zisと下降する単音トレモロの小波の収縮膨張からクレッシェンド、最低音 (f)dis,eからp跳躍五連符の上を白鍵グリッサンドがgis,zis,gisの和音まで駆け上り(sff)、再び単音トレモロgis~a~es~h~c~h~a~h~as~fと前出のラインの変容が現れ、そこから(ff) hへ下降、さらに2オクターブhまで駆け下りsubitoで(pp)のトレモロに消える。つまり2オクターブ下降形とトレモロ単音フレーズという造り。このpfの序奏ののち、「厳しく、決心を秘めて」のコメントと共に、♩=ca.30 fallsetの指示つき音型(p)es~d~ges~e~es 「このーうでーをー」、es~a上行「せつーだん」、a~as「せよ」とバリトンが入る。pf が下(pp)でfのトレモロを続ける。


思わず筆者が想起したのはピアノ作品『トリトローペ』(1978)。単音トレモロc~des~c~f~e~des~c~e~des導入部と楽曲「D」部終尾の烈しいas 2オクターブ下降形だ。『慧可断臂』から2年後、院生時代の作で、むろん単音トレモロのアジア的旋律が強い印象を与え、かつ、底に流れるfやh、a連打による強靭な持続とそこに飛び散るクラスター、きらめく高音など小品ながら変化に富んだ佳作と思う。タイトルの意味する「転回、反射、屈折」から音楽的変化の激しい曲だ、と西村は述べている。さらに、「曲頭と曲尾に出現するトレモロによる旋律の演奏法は、この曲の9年後の『2台のピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』(1987)という作品の中に、より大規模に登場することになります。」5.


振り返るなら『耿』(1970)の2年後のピアノ処女作『ピアノ・ソナタ』(1972)は本人の言葉通りプロコフィエフ、バルトーク、三善晃の影響をとどめるが、それよりむしろ当時入れ込んでいたらしいジャズの語法が全面を覆う感じでいかにも幼い。が、すでにこの『慧可断臂』ではピアノにおける技法、手法の特性が明瞭に現れており、ここからの分枝分流がその後の西村世界を創ったと言っても過言ではないと思える。『トリトローペ』同年の無伴奏混声合唱のための『汨羅の淵より』(1978)の読経を含む声の壮烈を合わせ考えれば、声と器楽の道の最初の一歩だ。
本作に戻ろう。上記以降は作曲者の書き込みコメントとテキスト、要点のみ拾う。
「自らに訴えかけるように。次第に激しく」
(mf)このーこうべ (falsetto)このーあしをー
(f)いっせんの ひかりにて たてーーー
「独白のように」solo
(p)せいざーん つーねーにー うんぽすーーー
「内面的に」
では(わ)
「切切と」
にんげんの (fals.)くのおもーーー
(mf)するどくーーい(fals.)かされたーーー(「緊張をゆるめず」)
「力を込めて」
(f))さんすいーーー( ff)
ぼくせきでは (falsetto) なーいーかーーー !!
〜〜ここでのpf (ff)の執拗な同型反復と「なーいーか!!」叫声のちの5段にわたる長いpf.soloでの鎮静、その場面転換は鮮やかだ。
「人の心の弱さを感じさせるように、ためらいと動揺を表出させて」
(p)このうでを このうでを (pp)せつだん
「ややうわずった感じで」
(p)このうでを (pp)せつだん (p)せーよー
〜〜全体が弱奏で歌もpfもシンプルに静まっている。
一息のち、
「ふりきるように」(f>p)
あ〜〜
「一息に」solo
(f)おまえゆえに いっさいは
「はきつけるように」
(f)ふぐと (ff)かす!
〜〜pfには「きびしく」の指示。
(mf)じがの (mp)じがの
(mp)げんかくの (mf)げんかくのーーー(f)よ(fals.)びな
(f)わたし (p)(fals.)わたし (mf)わーたーし(f)ーーー
〜〜ここでの「わたし」の強弱を伴う畳み掛けとファルセット、pf(pp)五連符の細波にアッチェルランドしてゆくさまの凄み。(ff)のpfを一句挟んで、
(p)わたしは いしのなかにいるーーー
(mf)みずうみにーーー(f)みずうみにーーー
(f)しずんだいしのーーーー
「内面への訴えかけとして」
いしのなかにいるーーーー
〜〜3段pfのsoloのち
「新たな強さで」
(mf)ゆうひのーーーゆうひのーーーとおりょーーするーーーーー
(f)いきものの むれにはーーーー
(ff)きのう(お) きのう(お)とおく わかれたのでは (ff)なかったかーーー
〜〜pfに現れる下降音型は(mf) aの長いヴォカリーズ 6段続き<(ff) !! の叫びののち、滝となって雪崩落ち、単音トレモロ(ffff)に収斂、そうして最後のシーンが来る。
「語り」
(f)かれはやいばをぬいた
(mp)うでを (sf)きる (p)おとがした
pfソロ、トレモロ(pp) モチーフ変容で3段。
のち、
pf (p)hトレモロから
(f)だるまはなお!
(p)うごかなかった
pf、poco cresc・・・(mf)で了。
詳細は追わない。
ただここに、器楽における音扱いと、歌曲における詩句、声の扱い、さらにそれらを合わせたドラマトゥルギー創出の工夫が随所に見られることを指摘しておく。
そして筆者がとりわけ注目したのは第3 節「ああ」から始まる部分の2段目「自我〜〜」からの一句だ。
ああ お前ゆえに一切は不具と化す
自我の幻覚の呼称....私....わたしは
石のなかにいる 湖水に沈んだ石のーーー
2回の「自我のf-e-e」は ♩から♪に音価を短縮、次いで3回繰り返される三連符「(f)わたしes-g-g」、以降ファルセットで「(p)わたしes〜ge〜ge」「(mf)わたしges〜~b~~b」と音価を広げ、音程を上昇させる間にもpfが無窮動的に細かなリズムパターンを刻み続ける。
それまでの逡巡、内なる問い、動揺を経て、「自我」をぐいと抉り出した最も重い部分と筆者には思える。その「自我」を「みずうみ(湖水)に沈んだ石の中にいる」と沈めた時、慧可はすでに一段登ったのだ。だから「新たな強さで」で次節「夕日〜〜」が来る。この部分でのpfの繰り返しパターンはaヴォカリーズの終わりまで続いてゆく。
切断への踏み切り板たる「自我」摘出のシーン、と筆者には思える。
これは一つの心理劇、オペラだ。
当初ソプラノをバリトンに変更したのも、そのオペラ的ドラマトゥルギーゆえだろう。



と、ここまで書いて、永平寺滞在で感じた、得た、様々なことごとが、この作品『慧可断臂』にそのまま真っ直ぐつながってくるのに粛然とした。
さらに大きく、これからの道筋、むろん『紫苑物語』に関わり、さらにおそらく『華開世界』のその先までを示唆する、宗教・哲学へと続く、その一里塚にある作品なのではないか。
考えたいこと、考えねばならないことがたくさんある。
筆者の頭はぐるぐる回り始めた。
ゆえ、この先は次回としたい。
* * *
なお、永平寺を訪れる前、『慧可断臂』についての問いに、氏より頂いた返事を氏の許可を得て記載する。
1、記憶によれば、最初は詩「恵可」の頭からテキストにして作曲を考えたように思います。ソプラノで歌曲にと。が、考えが変わり、この異常鮮烈な冬の禅の光景をオペラ的に切り出し、バリトンでファルセットを多用する異形の一種のアリアにしようと思いました。結果、詩は一部のみをテキストにしました。
2、絵とストーリーが先行知識(一般常識的に)で、しかしそれを音楽作品の題材にしたいとは全く考えていませんでした。作曲科4年前期の提出課題「歌曲」のテキスト探しで、現代詩集を貪欲に漁る中で、谷川雁のこの詩に出会いました。
社会派の行動的詩人としての谷川雁のことは当時全く知りませんでした。が、この作曲では絵や詩よりももっと血の匂いを出したかったように思います。
3、今にしてみれば、宗教信心についての自分のいい加減さや貧しさや恥ずかしさに対する、この時期なりの突っ張ったテキスト選びの作品であるようにも感じます。
当時は谷川雁の有名な「大正行動隊」も知らず恥ずかしいことで、社会派の詩の本質とはまるで異質な作曲だったかもしれないと思います。
とは言え、嬉しかったのは、この曲が藝大の旧奏楽堂の試験で初演された直後、審査員だった松村禎三先生から、「ピアノの弱音のトレモロは中国の琵琶(ピパ)のようで、少林寺に降る雪のようだ」と評されたことでした。
註)なお、氏は永平寺に2度行ったが、『慧可断臂』レリーフは見ていないとのことであった。
* * *
少林寺とは、中国洛陽郊外、達磨が修行した嵩山少林寺である。松村禎三には句集があり、筆者は好きだ。氏は少林寺は訪れていなかろうが、敦煌の旅の折、炳霊寺石窟に行き、湖に降る雪を詠んでいる(『旱夫抄 松村禎三句集』深夜叢書社 1991)。
西村作品への感想に、ふと思い浮かんだので、記しておく。
雪の速さで四囲沈みゆく石佛
み佛のその肩昏し雪降りつぐ
(炳霊寺にて 1981)
『慧可断臂』は76年ゆえ、松村が少林寺に降る雪を思ったのは想像か、あるいは何かでそれを見たか、だろう。けれども筆者はそのようにこの音の姿に何かを思い描き、それを伝える松村を、美しく、切なく思う。
( 続く)
(註)
- 『道元』 日本の名著7 玉城康四郎責任編集 中央公論社1983 p.8
- 詩のタイトルは「慧可」でなく「恵可」となっている。雪舟作品も同様。
『谷川雁詩集』 現代詩文庫 思潮社 - ペルシャもしくは南インドの王子出身で中国(南北朝・梁)に渡来、中国禅の始祖となった。面壁とは「壁観」、壁に向かっての座禅、あるいは我の内外に壁を立てるごとく峻別して行う瞑想法うんぬん。(『新版 禅学大辞典』大修館書店)
- 谷川雁(1923~1995)水俣生まれ。社会主義的なリアリズムを基調とした詩人で、評論集『原点が存在する』『工作者宣言』などは1960年代の新左翼に思想的な影響を与えた。1989年、作曲家新実徳英と共作で合唱曲『白いうた 青いうた』の制作開始。「曲先」「塡詞」の手法で多くの作品が生まれた。新実は芸大で西村に大きな影響を与えた親友作曲家。
- 『西村朗 ピアノ作品集 全音楽譜出版社 <前書き> 1995
参考資料)
◆ 書籍
『道元』 日本の名著7 玉城康四郎責任編集 中央公論社1983
『現代語訳 正法眼蔵4 』玉城康四郎 大倉出版 1994
◆ 楽譜
『西村朗 ピアノ作品集』 全音楽譜出版社 1995
◆CD
『オパール光のソナタ』
カメラータ・トウキョウ CMCD−28083 2005
◆ Youtube
『永平寺 大悲心陀羅尼』
(2021/6/15)








