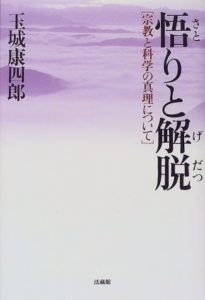Books|玉城康四郎『悟りと解脱』|丘山万里子
玉城康四郎著
法蔵館
1999年9月出版 5500円
Text by丘山万里子(Mariko Okayama)
著者、玉城康四郎は仏教学者とされるが、いわゆる学の人でなく、むしろ行者であった。
世界に誇るインド哲学の碩学中村元はその泰然たる笑顔とともに誰もに敬愛されたが、玉城は一部の信者に近い人々を集める特異な存在であったように思う。彼は自身の体験実感からしか語らず、だけに、その体験を我身に得た人のみが知る境地で遊び、論じたからではないか。
筆者に宗教体験はない。
周囲にはキリスト者も仏教者もおり、神や仏のいる人生を、はいはい最後は神様仏様で救われるんだからいいよね、と半ば羨み半ば冷ややかな気持ちを抱いてきたが、先方からは自意識に凝り固まった救いがたき自力の人と憐憫の眼を向けられている。
彼らには「神の召しだし」とか「あるがままで良い」なんて声が確かに聞こえるらしく、それが境地、つまり絶対の宗教的体験で、これは理屈抜きに揺るぎない。
筆者の評論領域に東西宗教・思想を学ぶのは必須と思い、常日頃向き合うように努めているが、玉城は境地の人ゆえ遠ざけていた。「ダンマが吹き通す」とか言われてもなんのこっちゃ、だから。
それを手にする気になったのは、輪廻だ涅槃だ、の音に取り巻かれている現況がある。その仙人のごとき風貌が筆者を招くのだ。ちなみに筆者が時折開く道元『正法眼蔵』は彼の現代語訳。
本書は最晩年、83歳の逝去直前まで書き継がれた遺稿で、第1章《解脱への道は》は死後、夫人により発見されたもの。内容は以下。
【第Ⅰ部】
第1章 解脱への道
1) 解脱とは何か
2) ブッダの解脱の重大問題
3) 重大問題に対する解答―私自身の禅定―
第2章 仏道の原態
1) 解脱の原点
2) ダンマの顕現と人間の本性
3) ダンマ・如来の無限活動
第3章 仏道の基幹線
1) 業熟体
2) 目覚めていく経路
第4章 宗教を超える真理
1) いのちの開示
2) ブッダとキリスト
3) パウロ
4) ソクラテス
5) 孔子
6) まとめ
【第Ⅱ部】
第5章 人類学とヒトの特徴
1) 二つの路
2) 科学的世界観と縁起説
3) アウストラロピテクスからネアンデルタール人へ
4) 後期旧石器時代
5) ヒトの特徴
第6章 科学といのちとの和解を目指して
1) はじめに
2) 医学的生命といのちとの和解
3) 科学的宇宙観といのちとの和解
第1章《解脱への道》で彼は言う。自分の禅定(坐禅のこと)とは、若い頃から「生きているということの不安に悩み、おびやかされ」、そこから発したものだと。その不安と怖れが吹っ飛ぶ歓喜随喜を体得した解脱実感を基に、東西哲学・宗教・思想・科学をまたぐ壮大世界が背後にせり上がる。個の実存から普遍への、玉城その人の階梯が宇宙に架かる壮麗図、が本書の魅力と言えば良いか。
初めての「解脱」快感は戦前、若き悩みさなかの結跏趺坐(瞑想坐法)のある日、
「突然、大爆発、木端微塵、茫然自失した。(中略)〜ハッと我に帰った瞬間に、腹底からむくむくと歓喜が燃え立ち、全身を包んだ。これこそ、長い間求めてきた解脱であり、手の舞足の踏む所を知らなかった。」
が、この体感はすぐと消え、以降、試練の日々が延々続く。戦中兵役にその心身訓練が坐禅と通じるとかの発見もし、戦後も変わらず禅定に邁進、こうした爆発の大小を度々経験することとなる。
するうち60歳近く、ブッダ開悟直後の第一声に遭遇、「ダンマが私自身に顕わになった」。ダンマとは「まったく形のない、いのちの中のいのち、いわば純粋生命とでもいう他はない」ものであり「如来」でもある(と言われても仏教者でない筆者にはせいぜい純粋生命がイメージできる程度)。
が、これまた失せ、解脱頻度も増えればその数だけ地獄のどん底に沈みもし、歓喜と絶望の大波小波に翻弄され続けるのだ。
が、78歳年の暮れ
「不図(ふと)、気がついてみたら、求める心がポトリと脱落していたのである」「以来、入定ごとに如来は自然に顕わになり、浸透し、通徹しつづけた。そして、どこまでも深く通徹して息むことがなかった」。
そしてついに、
「83歳の誕生日を迎える約一ヶ月前、突然、如来の通徹する方向が逆になったのである。(中略)〜ダンマが、向きを変えて、私の全人格から限りなき大空間に向かって放散されるようになった。そしてこの状況はその後変わることはない。つまり、ブッダの禅定がそのまま私の禅定として定着したのである。」
この「ポトリ」が道元いうところの「身心脱落」なのでもあろうが、ダンマがこちらに、でなく、自身と一体化、発光体となって定着というその姿、想像を絶する。
いずれにせよ「大爆発、木端微塵、むくむく歓喜」から「形なきいのちの顕現、人格体を通徹、そこからの放散、全宇宙を照らし抜く」体感は全章を通じ、幾たびも繰り返し語られ、これが全編を貫く命の鳴動。が、「体感」は個体のものゆえ、読者に共感・憧憬・違和・抵抗・反発・否定が生じよう。
ここで躓いてはならない。自身の体得からしか語らぬその肉声は、そこらの頭でっかち学者の上っ面寄せ集め知識なんぞをそれこそ木端微塵に粉砕する。すなわち、「識」とは種々個々学識の宝珠を貫き通す糸たる「我が身の生」によってこそ、「識」となる、と筆者は読みつつ思ってしまう。
第2章、第3章は仏道を知らぬ筆者にはあまりに咀嚼困難なのですっ飛ばしても、第4章で登場の東西「四聖」ブッダ、キリスト、孔子、ソクラテスの「全人格的営み」とくるとぐんと頭に入りやすい。曰くブッダの「禅定」、キリストの「祈り」、ソクラテスの「神の声」、孔子の「天命」いずれも「この現実の世に、形なきいのちを言動によって実現」しており、それは「舞台裏からのメッセージ」でそれを「私の全人格的営みにおいて受けとるとき、ついには表も裏もない表裏一体の、果てしなき“いのち”そのもの」となり、そこに人間の本来的原態、真理が証されているとする。
つまり四聖は等しく同一の根源句を発しているということだ。なるほど。
にも増してぶっ飛ぶのは、第2部第5章、第6章(この2章は1992年『宗教を超える真理と科学』をそのまま収録したものだが)。
第5章、彼は言う。「四聖」が証した真理を見るに、各宗教・学問・哲学領域の学習などいう捕囚の衣を脱ぎ、それら学びを一括するなら、「宇宙におけるヒト」とは何か、という課題に収斂する。そこを探るのだ。
で、400万年前に遡りヒトの祖たるアウストラロピテクスから語り始めるのだが、生命の起源や原始地球研究における科学的世界観と仏教の縁起説の酷似の指摘など、コロナでさらに大活躍のユヴァル・ノア・ハラリなんぞのはるか先を行く大胆さ。さらにヒト独自の特性として「根源的静態と根源的動態」に着目、「ヒトにのみ可能であるいのちの顕現は静まりと動きとの活用によって促される」。しかもこれを自らの座禅体験で裏打ち(「動きと呼吸と意識」)させる力技を見せる。
続く第6章はその体得と科学との照応。少し長いが冒頭を引用する。
「全人格的思惟における目覚め、言いかえれば、舞台裏から表舞台へのいのちの訪れ、さらに言いかえれば、いのちそのものの私自身の生体における発現。これこそ全人格体の実証そのものであり、即物的でさえある。科学もまた、パラダイムを転換しながら観察から実証へと進んでいく。いのちの発現も科学も、つづまる所は同じ実証そのものである。長い歳月はかかるにしても、科学といのちとがどうして和解しないことがあるであろうか。」
この確信をもとに、大脳生理学、免疫学からビッグバン宇宙観、さらに物理学の超大統一理論の構想にまで及び、科学の客観世界をぐいぐい我が境地に手繰り寄せ、自在に結ぶ「和解」ぶりはほとんどアクロバティック。
例えば、大脳生理学における「ホメオスタシス」(人間の内部環境が一定の状態に保たれていること/いのちの保証)との照応。禅定の基本三原則「調身・調息・調心」は脳幹-脊髄系であり、入定の都度必ず「全人格体が、眉間の中央から後頭部に線を引いたその中間、すなわち脳幹-脊髄系のあたりに集中してくる」から、このいのちの集中は「数億年来の爬虫類、数千万年来の哺乳動物、数百万年来のホモ・サピエンスとも生命を共感していることはいうまでもない」。
あるいはビッグバン宇宙観でも、物質世界としての宇宙を支配する四つの力「重力」「電磁気力」「弱い核力」「強い核力」を「いのちの訪れ」に照応させる。重力は宇宙の親和力、電磁気力は自他の区別の厳しさ、弱い核力はスピン粒子自転の中にヒトの根源的なる静態動態、強い核力グルオンの持つ強烈な結合力は個体の確立を表すと。筆者ついていけないが、なんかすごい、と思ってしまう。
これら独自解釈により「科学の側」の宇宙創生と「いのちの側」の宇宙通貫とを重ね、「いのちの側」はそれを確知しているのだから(我が解脱)、いずれの日にか両者は互いを承認し合う(和解)と説く。
いやはや徹頭徹尾「我が禅定での確知・実証」に貫かれた本書、ついては行けぬが、なんかすごいスケールだぞ、と気分晴れ晴れコロナ禍中びっくり読書には向いているのではないか。
筆者、ある正月に玉城氏宅に伺い、ゆるゆる何事かを語る氏の眼を見つめながらなんと一瞬寝落ちしてしまった。はっと我に返った時にも氏の眼はゆるぎなく、筆者を静かに見ているのであった・・・。これぞ境地?
(2020/12/15)