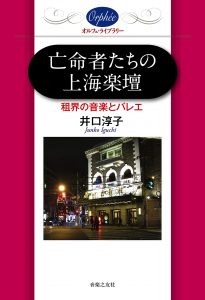Books|亡命者たちの上海楽壇 -租界の音楽とバレエ- |大田美佐子
井口淳子 著
音楽之友社
2019年3月 ISBN 978-4-276-37112-5
text by 大田美佐子 (Misako Ohta)
戦後の憲法で定められた象徴としての新天皇とともに令和を迎えた。その歴史と伝統とともに、個人にとっての「国」という存在を考えさせられる。歴史記述の多くは「国」を単位に考えられてきたことにも気づく。
国ではなく、都市を中心に歴史を見ると、個人の創造的な活動の詳細に宿るイレギュラーな面白さが見えてくる。上海はまさに「いずれの国家にも属さない」特異な都市空間 (p.5)として、大戦間期には革命を逃れロシアから、そしてドイツからは多くのユダヤ人が亡命した。
亡命者とは政治的に、なんらかの迫害により国を追われ、他国に逃れた人を指す。亡命者のたどり着いた上海租界では、どのような活動が行われていたのか。多様な国から来た芸術家たちの活動が、時間軸の縦にも横にも展開する。そして、大きな物語に吸収されず、複雑で美しいテクスチュアが浮かび上がる。
亡命研究そのものは1980年代後半、東西の壁崩壊を契機に盛んになった。シェーンベルクやヴァイル、コルンゴルトなど、著名な作曲家たちの亡命時代が様々な文脈で評価され、亡命者が新天地に与えたインパクトが語られた。彼らが支えてきた戦中戦後のハリウッドやブロードウェイなどの繁栄の物語は、実に魅力的だ。
こうして亡命についての研究は蓄積され、注目を浴びてきたが、なぜ亡命研究は私たちを魅了し続けるのか。ひとことでいえば、そのダイナミズムにあると思う。政治の悲劇が生み出した、多様な人々の数奇な邂逅の物語は、様々な価値観を巻き込んで、果てしなく展開していく可能性を秘めている。そこに生まれる文化のダイナミクスは、多様性とグローバルな視点を求められる現代やその学問に豊かな示唆を与えてくれる。
本書もそうした亡命研究の魅力で溢れている。中国の音楽、芸能研究の専門家でもある著者が、実際に上海やラトヴィアなどの現地に赴き、資料を読み解くだけではなく、読者が実際にその地を歩いているようなリアリティーに誘っていくその筆運びに魅了され、胸が踊る。そこで描き出されるのは、多様な人々の文化が独立しつつ、時に重なりあい、絶妙なバランスで繰り広げる、ある種の共生のかたちである。幾重にも交差する複雑な物語を読み解く必要がある亡命研究は、奥が深いだけに相応の困難がつきものだ。史料の不足、アクセスの問題など。本書では、英仏露中の新聞に焦点をあて、それらを比較し、特徴や繋がりを活写したが、対象を多角的に掘り下げるための言語の問題など、数々の困難があっただろう。上海租界で展開された亡命者たちの芸術活動を、粘り強く追ってきた著者の研究に魅了されてきたひとりとして、評者もこうして本になるのを待ち望んでいた。
本書の構成は5章からなる。第一章は劇場、第二章はオーケストラ、第三章は上海バレエ・リュス、第四章と五章では、演奏家と彼らの活動を支えて展開させる敏腕興行主、ロシア系ユダヤ人のアウセイ・ストロークと日本人の原善一郎にも光をあてた。
特に興味深いのは、そうして各国の読者を想定して発刊された新聞やプログラムのなかに、時代の移り変わりを読み込んだ鋭い指摘である。日本の支配により上演演目が変化し、劇場のまわりにも軍靴の音が響き渡るなかで、日本の支配下にあっても興行的な理由から、反日的な演目が上演され続けた(p.21)という意外な事実。
多国籍の外国人から構成されていた上海工部局オーケストラが、モダニストたちの音楽を取り上げ、上海の先進的な洋楽受容を象徴するだけでなく、山田耕筰、渡辺浦人、呉泰二郎らの作品を取り上げるようになり、また終戦間近には朝比奈隆が指揮台に立つなど、戦後の日本の音楽界に影響していく様。
ハルビンと上海で活躍し、多国籍の外国人と果敢に渡り合い、戦後日本の楽壇の発展にも足跡を残した興行主、原善一郎の姿。
そして、上海で輝かしい活動をみせる個々の音楽家たちの輝き。フランス人の批評家シャルル・グロボワをはじめ、当地の教育にも積極的に携わる演奏家や作曲家たち。その射程は音楽を超えて、戦後のバレエ界で大きな役割を担った小牧正英が踊った上海のバレエ・リュスの活動にも及ぶ。
かくして、亡命者たちの上海楽壇の物語は、日本のパイオニアを育て、戦後の楽壇の物語へと繋がっていく。資料の点と点を結び、本書で描かれた物語は、それぞれの戦後の行く先を照らし、果てしなく展開していくだろう。当時の批評は興味深く、それだけでも資料としての価値があるが、同時代の批評と比較して論じることで、その価値も解釈も新たな発見につながっていくかもしれない。途方もない努力で積み上げられた研究から、こうして新たな扉が開かれる。亡命研究の労作に感謝するとともに、その醍醐味にあらためて感じ入った。
(2019/5/15)