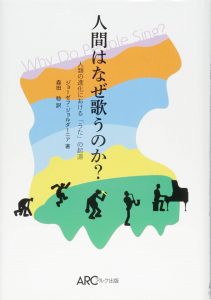Books | 人間はなぜ歌うのか? 人類における「うた」の起源|谷口昭弘
ジョーゼフ・ジョルダーニア著、森田稔訳
アルク出版
2017年4月出版 2900円+税
text by 谷口昭弘 (Akihiro Taniguchi)
人間が最初に生み出した音楽の形態は、楽器の音楽ではなく「うた」だろうということは何となく分かる。楽器を演奏するにはある程度の技術が必要だし、楽器を作るための工学的・音響学的な知識も必要だ。そもそも音が出せる楽器を作るだけでも大変だろう。そこで楽器ではなく「うた」に注目することになるのだが、そもそも、いつ頃「うた」がどこで、どのように生まれたのか、ということは解明できるのだろうか?とてつもない歴史のロマンを感ずる一方で、とてつもない難しさがあることを直感的に感ずる。
私は学校で音楽と人間社会との関係について教える時間をいただいているが、この難しい「音楽の起源」について教室で話すことがある。といっても、私自身は音楽起源論の専門家(そういう人がいるのかどうかは知らないが)ではないので、真剣に「うた」の起源を学問的に考察したり、教えたりすることはできない。だがしかし、こういった音楽の起源というのを考えることにより、人間にとって音楽とは何なのか、人間の文化的・社会的営みとしての音楽はどのようなものなのか、考えるにはとても面白い問題を提起してくれるのである。
ただ私がこれまでの授業で使ってきたのは、実はこのジョルダーニアの本ではなく、音楽民族学者である小泉文夫氏が、かつてラジオ番組として制作した『民族音楽』という講義の中で「音楽の起こり」について語っているカセット・テープである(この講義は、その後『小泉文夫の礎』というキングレコードから発売されたセット物CDの一部に収録されていた)。その中で小泉氏は音楽の起こりについて様々な「仮説」があり、それらについて一つ一つ検討していく。
例えば異性を惹きつけるために通常の声とは違う声で歌う「性衝動起源説」(ジョルダーニアの本でも、ダーウィンが提唱した説として紹介しているもの)、共同で息を合わせて作業をするために歌う「労働起源説」、言語と音楽との密接な結びつきから考える「言語起源説」、遠くの人に何かを伝えるために大声を上げたり音を出したことから始まったとする「信号起源説」、日常から離れた特別な力を必要とするために音楽が必要とされたという「呪術起源説」などである。
どの仮説にも説得力があり、同時に問題点があるものの、全世界の文化において、西洋人が「音楽」と認める音楽行為が認められる背後には、このような人間が音楽を必要とする様々な事象があったことは間違いないと信じられるのである。
この本においても、全5章の内の第3章以降(第2部とされている)は、そのように様々に考えられてきた「音楽の起源にかんするさまざまな考え方」が紀元前6世紀から2010年に渡って年代順にまとめられ、このトピックが人々の関心をずっと引いてきたことが分かる。
そしてジョルダーニアの議論の中で私個人としてとても驚かされたのが、鳥やザトウクジラなど「うた」を歌うと考えられてきた生き物が、いずれも地上には住まない、即ちライオンのような猛獣に襲われる危険がないところで生きているということであった。そしてその唯一の例外、すなわち猛獣とともに地上に生活しながら「うた」を歌う存在が人間だというのである。
ではどうして、人間だけが猛獣の住む地上にいながら「うた」を歌うのか。詳しくは本を読まれたいが、解説の岡ノ谷一夫氏の言葉を借りればそこに「威嚇起源説」がある。すなわち人間がライオンよりも強い存在であることを誇示することを音楽で行うということ。また猛獣との戦いに挑むにあたって人間の感覚を「戦闘トランス」状態にもっていくことが集団歌唱としては必要なのだという。なるほどそれも、一つの仮説として考えられるのかもしれない。今後、人間と社会を考える上で、この仮説も加えて議論するというのも面白いだろう。
第1章と第2章(第1部とされている)は、うたの起源に関する議論の前に、そもそも人間が実践する「うた」について、モノフォニーが先かポリフォニーが先かという議論が展開されている。西洋音楽史の概略を学ぶとなると(現在は使う本によって多少違っていることもあるが)、大抵は楽譜として残っている単旋律のグレゴリオ聖歌から始まり、その後、中世の後半からポリフォニーが開花し、複雑化していくという流れになっているように思う。声部が増え、リズムの理論が確立し、記譜法が発展し…となっていく。
しかし、著者のジョルダーニアは、「モノフォニーからポリフォニーへ」というのは間違いなのではないかという論を立てている。ただ彼のいうポリフォニーは対位法を駆使した「書き音楽」ではなく、何らかの形で複数の声部が同時に歌われることを指している。例えば斉唱時に生まれる偶発的な複数の音程、あるいはドローンの上に展開される旋律といったものも「ポリフォニー」の範疇に含まれるようだ。
なるほどそうであれば、楽譜に書かれた音程を正確に認知し、そこから離れないように斉唱するというのは、互いに音を聴き音程を認識し合わせる能力が必要だし、その音が記譜された音と整合しているのかどうかを知るには一定の知識がいることになる。
考えてみればグレゴリオ聖歌がまとめられるはるか以前に遡る旧約聖書の詩編などを見てみれば、聖歌隊が二手に分かれていたとか、声以外にもシンバルや竪琴が参加しているようなことも書かれており、複数の音が同時に鳴り響いていた状態は容易に想像できることなのかもしれない。むしろ典礼の統一とともにローマにおいて斉唱が特別な意味を持っていたのだろうか、そんなことを勘ぐりたくもなるというものだ。
ジョルダーニアはポリフォニーの存在について世界的な視野に立ち、非西洋音楽も広くカバーしてポリフォニーの分布を調査し、まとめている(これだけでも圧巻だ)。世界に存在する音楽様式を比較考察する比較音楽学は、その西洋中心主義的な発想から、そして世界各地の個々の民族を尊重する民族学からの影響で、過去のモノとなってしまったところもあるが、その意義もあるのではないかと著者は訴えており、もしかすると問題は比較そのものではなく、どれだけ他者を尊重できるのか、ということであり、比較そのものは、論ずる主題によって使う意義があるのではないかということも感じられてきた。
このように本書は、これまで定説とされてきたことや研究のあり方などに疑問を投げかける示唆に富んでおり、そのいっぽうで説得力のある論を展開している(少ない事象から大きな論を立てている部分もあることにはある。詳しくは岡ノ谷氏の解説を読まれたい)。もちろん著者の述べることすべてに賛同するかと言われると自信はないし、断言できるほどの知識を私は持っていない。それでも音楽に対する好奇心を湧き立て、いろいろと考えを思い巡らせてくれることは間違いない。とにかく知的刺激に溢れた一冊である。一度手にとってご覧になることをお勧めする。
(2019/1/15)