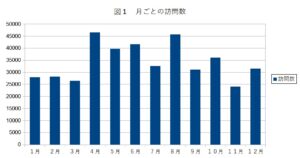好きな作曲家・演奏家との出会い|生まれ変わらなければ聞こえてこない|松浦茂長
生まれ変わらなければ聞こえてこない
text & photos by 松浦茂長(Shigenaga Matsuura)
3年前だったろうか、ブルックナーから今まで全く聞こえなかったものが聞こえてきた。とても静かだけれど、自分が別の人間になったような、不思議な喜び。「ああ、今までは何もわかっていなかったんだ」と、うれしいような恥ずかしいような感動だった。
ロマン・ロランの描いた作曲家ジャン・クリストフは死の床で思う。「芸術とは、自然の上に投げられている、人間の影だ。芸術も人間も、ともに太陽へ吸い込まれて消えてしまうがいい!芸術と人間とは、私が太陽を見ることを妨げている。」もちろんこれは音楽の否定ではなく、生の根底に達する音楽の力への賛美だ。
僕には、あのときまで、ブルックナーが垣間見たまばゆい太陽がわからなかった。おそらく音楽とは別の道で、太陽の光輝に初めて照らされ、その経験を経たおかげで、彼の音楽に太陽の反映を感じとれるようになったのだろう。
10年ほど前から、パリに来ると近所に住むお年寄りの神父、ポールさんに聖書の手ほどきをしてもらっていた。あるとき、イエスの「私は良い羊飼い」という言葉に触れ、ポールさんはエゼキエル預言書を読み始めた。「牧者が、その散っている羊とともにいるとき、群を心にかけているように、私(神)は、自分の羊を世話し、霧と闇の時に散ったところから、彼らを救い出す。……」。ポールさんはいつものように、抑揚のない淡々とした読み方だったが、次第に声がしめってきた。見ると目が潤んでいる。読むうちに、胸がいっぱいになり、抑えきれなくなったのだ。
そのとき、僕は意識しなかったが、ポールさんからあふれ出たものが、目に見えない川の流れのように僕の中に流れ込み、何かを変えてしまった。それが何だったか気付いたのは、ベートーヴェンの田園交響曲を聞いたときだった。嵐のあと野原に光が戻り、鳥がさえずる穏やかな情景を聞くうちに、今まで経験したことのない歓喜に捉えられた。歓喜と呼ぶにはあまりにも穏やかな、しかし圧倒的な強さで僕を包みこむ何か。「これだ!ポールさんが泣いたのはこれだったんだ」。自然が客体として向こうに美しく見える、というのではなく、全自然、宇宙全体が、輝き、満面の笑みを浮かべて迫ってくる。
<自然は愛の仮象なのだ>
ポールさんが「良き牧者」を読むとき、「私は愛されている」という自覚に圧倒されたように、ベートーヴェンは、自然を通して迫る愛に圧倒されエクスタシーに入った。その歓喜の意味が、ポールさんの信仰が僕に<伝染>するまで、全くわからなかったのだ。音楽に感動するとは、自分が不可逆的に変わること、生まれ変わることに違いないが、人生行路のある体験が、ある曲との運命的出会いを可能にする――人をメタモルフォーゼに向けて成熟させるのだ。
8年ほど前ブールジュのカテドラルを訪ね、そのときの驚きを、後に『パリ東京雑感』に書いた。
「祭壇奥のステンドグラスがどれも中世のままの良い状態を保っており、説明を読むと中央左は<放蕩息子の帰還>。教会に入り真っ先に目に入る大事な窓がキリストの生涯か最後の審判のような教義の中心テーマでなく、なぜたとえ話なのだろうと気になった。ところが翌朝同じ所に立つと、放蕩息子の窓が目のくらむ金色に輝いている。きのうは散文的な黄色だったガラスが朝の太陽をまともに受けてメタモルフォーゼした。燃えるような金色は、できの悪い息子が戻ったのを、全宇宙が歓喜して迎えるかのようだ。これで納得できた。ブールジュのカテドラルを建てた人は、彼自身の体験した<全宇宙的歓喜>を表現したかった、<放蕩息子の帰還>はそのために最もふさわしい物語だったのだ。」(2015年10月『カテドラルの誘惑』)
<全宇宙的歓喜>なんてケバケバしい言葉を使っているのは、その喜びが自分の体験になっていなかった証拠。当時は頭の中だけで想像していたのだ。
<愛されている>という思いに全身酔いしれる喜びを知らないうちは、ブルックナーは頭の中でしかわからない。ブルックナーはエクスタシーの時をしばしば持つ人だったのだろう。彼の音楽からは、ベルクソンの言葉を借りれば、神秘主義の余香であるparfum enivrant陶然とする香りが立ち上る。ブルックナーは、垣間見た太陽=愛の熱さを伝えたかった――彼の音楽は、ただそれを伝えることだけを目指している。
若いときから盤がすり切れるほど聞いたカラヤンからは、胸が裂けるような悲劇が聞こえてくるが、あの甘美な香りは、僕には感じられない。ギュンター・バントは構築の壮大さで圧倒するが、それはかえって「太陽を見ることを妨げる」筋肉的努力に聞こえる。愛の甘美がひたひたと迫ってきたのは、ベームの指揮する交響曲第8番の第1楽章だった。
(2018/10/15)