特別寄稿|ウィーン感傷記(1)|丘山万里子
(1) ムジークフェラインでウィーン・フィルを聴いた
Text & Photos by 丘山万里子(Mariko Okayama)
筆者にとっての最初のヨーロッパは1987年、ウィーン。
音楽評論を仕事として9年、まだ一度もその地を踏んでいなかった。
中原中也がパリの通りを誦(そらん)じていたほどの熱烈な憧憬はないものの、「夢に見たウィーン」であったことは確か。その夜のホテルも決めず、3歳と10歳の子供を連れ、暗い空港に降り立った筆者には、2月の寒さ以上に凍てつく震えがあった。幼子のいる女の海外での勉学などわがままという周囲の視線を撥ねのけての乱暴な旅立ちであったのだ。
そんな昔の懐古談、と笑わば笑え。
やっと見つけた郊外のプッツおじいちゃんの家の2階での生活がなんとか落ち着き、初めて聴いたウィーンの音がムジークフェライン「黄金のホール」(Großer Musikvereinssaal)でのバイエルン放送響、指揮はサー・コリン・ディビス。
その時の筆者に、その響きがどんなだったか。
ウィーンはその後何度か旅の中途で訪れたが、もろもろに一区切りついたこの秋9月下旬、懐かしきウィーンへの感傷旅行をしたのである。
ただ街ゆく人の流れに任せぶらぶら歩き、教会の片隅にぼうっといるだけで十分なはずが、たまたま黄金ザールでウィーン・フィルが演奏するのを知った。途端、疼いたのだ、聴きたい! だって私は黄金ザールでのウィーン・フィルを聴いていないんだから。やれプラハの春だ、ザルツブルクだ、バイロイトだと飛び回りつつ、国立歌劇場のオケ演奏で十分満足、わざわざ聴く気もしなかったのだ。
というわけで、9月29日午前11時からの定期演奏会にいそいそ出かけたのであった。
Daniele Gattiの振るIgor Strawinsky『Apollon Musagète, Ballettsuite』、Dmitri Shostakovich 『Symphony No. 10 』。まあ、感傷気分とはそぐわない指揮者であり曲目ではあったが、音さえ聴けばそれでよし。
37年前の私は、こう書いている。
「一歩入って、息を呑む。ああ、これがかの黄金のザールなのか。整然と左右に並ぶ柱は、すべて金色にまばゆい女体の半裸像で、彼女たちが等しく、豊かな胸を両腕で組み支え、その頭上に天井をいただいているのである。見上げれば一面、これまた黄金と、とりどりの色に描かれた天上世界。女神が、天使が、舞い歌っている。ああ、これがかの、と夢中にながめ回しているのは私くらいのもので、品良く整った服装の紳士淑女たちは、なごやかな談笑を交わしている。思わず日本の、なつかしくも灰色の東京文化会館を思い出し、激しい嫉妬を覚えてしまう。」
全くのおのぼりさんである。
 さて、なんとか確保した中央ブロック前から4列目、左端の席に着席、見回せばかなりの人がスマホ撮影、せっかくだからと筆者も。「ああ、これが...」なんて浸るどころか、思いっきりミーハーである。
さて、なんとか確保した中央ブロック前から4列目、左端の席に着席、見回せばかなりの人がスマホ撮影、せっかくだからと筆者も。「ああ、これが...」なんて浸るどころか、思いっきりミーハーである。
で、音だが。
かつての筆者が述べるに。
「ああ、これがオーケストラの音だったのか。音楽って、こんな風に聴こえるものだったのか。
オケの弦が、低く静かに鳴りはじめた時、それはホールの一隅から、絶え間ない微光を発しながら、足元に寄せてくる波のようであり、また、ふうわりと身を包みこんでくる柔らかな微風のようであり、私はその最初の1音で、すでに茫然と目を閉じてしまった。」
まさに、夢見心地。
今回はというと。
団員が揃う前からステージで練習する数人、中のチェロ奏者に気がゆき、そもそも「音」を待ち受ける気持ちがない。コンサートマスターの美しい女性が出てきて、指揮者が現れ、音楽は始まった。そして、通り過ぎていった...。
私は眼前の美しきコンマスに心奪われ、ひたすらその響きを追っていたのである。そうして、コンマスというものの存在、意味をたぶん初めて実感したと言って良い。そもそも、これほど至近に奏者を見ることがこれまでなかったし(この席しか取れなかった)。
彼女のソロはどこかロマの香りがした。濃い栗色の髪を後ろに束ね、キリリとした顎のラインが楽器と合わさってなんとも妖しい歌声がそこに聴こえた。アルベナ・ダナイローヴァ、ウィーン・フィルの最初の女性コンマスで、ブルガリアのソフィア出身。私はそういうことにあまり興味がなく、そうだったのか、と後で知ったのである。ダンスのつま先だった弾み方、ちょっとした溜め、旋律線の描くライン、微妙な歌い回し、そして音色の複雑味。
オーケストラはというと、その彼女の声質を際立たせながら、寄り添い、まろやかに包み込む。なるほどこれがウィーン・フィルの妙味か。
 そうして後半ショスタコーヴィチでは一転、暗く翳りある弦の響き、大活躍のティンパニ、管楽器の響きの安定と柔らかさ、各ソリストの名技を、やはりなるほど、と聴くのだった。でも、眼は常に栗毛のコンマスに吸い付いたまま。そうして全体が彼女のムードに染まっている気がして、これが今日のウィーン・フィルなのね、と納得したのであった。
そうして後半ショスタコーヴィチでは一転、暗く翳りある弦の響き、大活躍のティンパニ、管楽器の響きの安定と柔らかさ、各ソリストの名技を、やはりなるほど、と聴くのだった。でも、眼は常に栗毛のコンマスに吸い付いたまま。そうして全体が彼女のムードに染まっている気がして、これが今日のウィーン・フィルなのね、と納得したのであった。
指揮者? 颯爽勇猛果敢に指揮台上で体躯を揺すっていたし、圧倒的な第3楽章での咆哮に終楽章での盛大なブラボーを確信した。が、その歓声がいささか勢いと張りを欠くと思えたのは、定演につき高齢者が多かったせいだろうか。あちこちお隣さん同士で、やあやあ、お元気みたいな挨拶の輪ができているのも定演らしい。
とにかく、筆者が集中して見聞していたのはコンマスで、その他大勢は背景だったゆえ、ウィーン・フィルの演奏云々は語れない。
初回、筆者にとっての響きは、装飾豊かな美しいホールから生まれる特別なもの「黄金の女神たちに囲まれて、その光に抱かれ、いつくしまれ生まれ育ってきた音なのだ。天に舞う天使たちの、唇から漏れる吐息であり、歌なのだ。それらが、西洋の音楽を作り、またオーケストラを作ったのだ。管弦打の編成が、たとえようもない調和でホールを満たしている...」。
今回は、美しきコンマスに尽きる。
すなわち、この日のミューズは彼女だったのである。筆者はせっせと彼女に拍手を送り、いかんせん至近距離、目が合ったら嬉しいかも、などすっかりファン気分なのであった。
ホールを含む全てが「これがウィーン」と囁きそれに陶酔しきった初回と、コンマスのロマの香りに惹きつけられ、コンマスばかり追っていた今回。
当たり前だが、37年隔たっての感受の相違は、ウィーン・フィルの変化でもあり、筆者自身の変化でもある。
ジェンダー的に言えば、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の女性入団は1982年。一方ウィーン・フィルはウィーン国立歌劇場管弦楽団から選抜される入団オーディションに女性が応募することを1997年まで許さなかったのだから、その保守性たるや筋金入りである。ちなみにダナイローヴァのコンマス就任は2011年。
もちろん、女性指揮者も含め、閉ざされた扉が少しずつ開いているのは確かだが、筆者が彼女に注目したのはそのロマ性で、その感受は筆者自身の変化による。
ウィーンから5年後のミュンヘン滞在も含め、ヨーロッパ諸国、ギリシア、中東まで足を伸ばし見聞したもの。それは西欧に今なお揺るぎない「神」の存在で、どこへ行っても磔のイエスを祀る教会をはじめとする西欧文化に辟易した。祭壇に流れる血への悪寒が、その源流たるエジプト、イスラエルへと向かわせ、あるいはアジア、中東、米国、南米の旅へと筆者をいざなった。
そうした諸国巡礼があって、今回、ダナイローヴァのロマ性、ウィーンの地の意味を感じ取ったのだと思う。ゼセッションを再訪、クリムト『ベートーヴェン・フリーズ』に、むろん筆者はエジプトを見た。そうだったのか...と。
年月をかけ、私の中で世界地図は大きく変貌した。ヨーロッパだけでなくユーラシア全体を巡る道、ひと、響きを絶えず脳内に広げつつ、個々の事象にあたること。
そうして今、聴こえ見えるのは、ようやくの革新を試みる眼前のウィーン・フィルの先端にたつ女性コンマスの凛々しき歌声であったのだ。
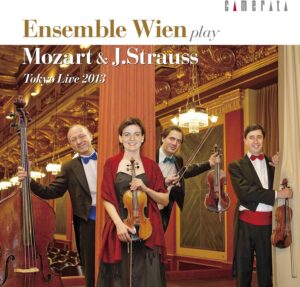 この人のこの歌にどれだけの地層時層が響きあっていることか。
この人のこの歌にどれだけの地層時層が響きあっていることか。
ちなみにダナイローヴァは2018年のインタビューでこう語っている(朝日新聞『Grove』)
「作曲家で、指揮者としてウィーンで活躍した)グスタフ・マーラーは“伝統とは灰を崇拝することではなく、炎を伝承することである”と語りました。
私たちオーケストラが伝承すべき炎とは音楽の核となる知識や技能から生まれる不変の響であり、それらは互いに呼吸をして音に耳を澄ませ合い、共に体感する、我々の中に宿るものなのです。」
「いま、ウィーン・フィルは国籍の面でも開かれています。人間は非常に多くの可能性のはざまで更に多くの自由を与えられていますが、私たちウィーン・フィルは開かれた多様なオーケストラの中に生きつつ、独自のスタイルを保つと言う、より重い責務を担っているのではないでしょうか。」
37年前の音楽の都、夢のウィーンは、豪奢な国立歌劇場での着飾った紳士淑女の佇まいに強烈に感じた階級性の一方で、雪に点々と染みる犬の放尿跡と老人ばかりの黄昏の街だった。筆者は郊外に住んだし、現地の幼稚園や小学校で子供や親たちとはたくさん触れ合ったが、たまに出る中心街で行き交うのは杖をついた高齢者がほとんどで、この街には若者がいないのかしら、と思ったくらい。
でも、この黄昏は、いつまでも黄昏であり続けるのではないか、沈まない夕陽に抱かれて。それがウィーン、そんな気がする。
秋のウィーンはすでにダウンを着込む寒さ。
主たるチェックポイントは観光客に溢れかえり、カフェもレストランも行列だ。
以前、街歩きの帰りに時おり立ち寄ったカフェ・モーツァルトも人だかり。行列ののちなんとか着席、筆者の定番アプフェルシュトゥルーデルとメランジュを注文したものの忙しなく動き回るウェイターたちに、遠い日のゆったりした午後のティータイム、その穏やかな日差しに流れていた静かなひとときを、やはり懐かしむのだった。

(2024/11/15)



