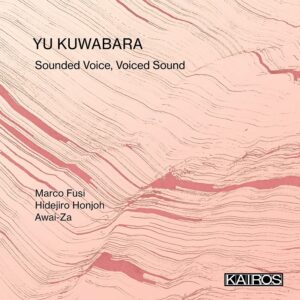PickUp(2024/2/15)|追悼・小澤征爾|藤原聡
『まったく追悼文然としていないわたしなりの小澤征爾に対する追悼文というか雑感。』
Text by 藤原聡 (Satoshi Fujiwara)
記憶が確かであるならば、小澤征爾の実演には3回しか接したことがない。
1回目はいつだかはっきりしないのだが(1984年12月の可能性は高い)新日本フィルを指揮してのベートーヴェン:第9公演、場所は懐かしの人見記念講堂だった気がする。テノールが若くして亡くなった山路芳久であったこと、第4楽章の例のテノールソロの箇所、小澤が山路を見ながら喜びの感情を顕にしつつ大きなアクションで足をバタバタさせながら指揮をしていた姿はよく憶えている。この視覚イメージは未だに目に焼き付いているほどだ。
そして2回目は1986年2月18日のボストン響を指揮しての来日公演で、プログラムはバルトークの弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽及びベートーヴェンの『英雄』。アンコールも演奏されたように思うが曲目は憶えていない。余談だが、この日の関東地方には極めて稀な大雪が降り―当時の記録を調べると東京で18cmの積雪があったようだ―、会場に到着することが出来るのかヒヤヒヤしたことを思い出す。今となっては詳細は憶えていないが、そんな天候でよくコンサートを開催したものだと思うけれども(行こうとしたこちらもこちらだが)、まだ大らかな時代だったのだろうか。客が来ようが来まいがまあやりましょう。
最後の3回目は1995年9月19日、サントリーホールにおいてブレンデルがソロを弾いての新日本フィル特別コンサート、演奏されたのはベートーヴェンの『エグモント』序曲、ピアノ協奏曲第1番と第4番。ちなみに上述した3回のコンサート、演奏内容はほとんど憶えていない。まだクラシックを聴き始めたばかりのガキであり、いずれも母親に連れられて赴いたコンサートであって自らの強い意志で聴きに行ったわけでもなかった。
それからのち、さらにクラシック音楽の泥沼に深くはまることとなり、その気があれば小澤征爾の実演をかなりの回数体験することができる環境にいたにもかかわらず結局この3回しか聴かなかったという事実。端的に言ってしまえばさほど興味が湧かなかったということになるが(身も蓋もない…)、なぜそうだったのか。あっさり述べれば未だ権威主義的、本場主義的な価値観が優勢であったクラシック評論の趨勢に絡め取られていたのだろう。ものの分かっている通はカラヤンや小澤征爾よりもフルトヴェングラーやワルターを聴くのである。若き日にそのような「洗礼」を受けると、自覚しないままに感性は排他的、内向きになる。
 トロント響との武満徹の『アステリズム』(ピアノは高橋悠治)、メシアンの『アッシジの聖フランチェスコ』(初演直後の1983年のパリ・オペラ座ライヴ)、ボストン響を振ったプロコフィエフの『ロメオとジュリエット』、アイヴズの交響曲第4番、あるいはベルリン・フィルとのプロコフィエフ:交響曲全集、シカゴ響との『シェエラザード』など、繰り返し聴いたお気に入りの録音はあるが、この辺りは申すまでもなく独墺系レパートリーではなく、いわゆる小澤が得意とする近現代のレパートリーである。わたしがこれから改めて聴くべきはベートーヴェンやモーツァルトなどのスタンダードなレパートリーであろうか(ある程度は聴いていたけれど)。恐らく、そこにはお仕着せではない小澤の軽やかで自由な感性の飛翔があるのではないか。曲がりなりにも多様な曲の多彩な演奏に接して来た今―良い意味で相対化できる余裕と視野が生まれた今に。
トロント響との武満徹の『アステリズム』(ピアノは高橋悠治)、メシアンの『アッシジの聖フランチェスコ』(初演直後の1983年のパリ・オペラ座ライヴ)、ボストン響を振ったプロコフィエフの『ロメオとジュリエット』、アイヴズの交響曲第4番、あるいはベルリン・フィルとのプロコフィエフ:交響曲全集、シカゴ響との『シェエラザード』など、繰り返し聴いたお気に入りの録音はあるが、この辺りは申すまでもなく独墺系レパートリーではなく、いわゆる小澤が得意とする近現代のレパートリーである。わたしがこれから改めて聴くべきはベートーヴェンやモーツァルトなどのスタンダードなレパートリーであろうか(ある程度は聴いていたけれど)。恐らく、そこにはお仕着せではない小澤の軽やかで自由な感性の飛翔があるのではないか。曲がりなりにも多様な曲の多彩な演奏に接して来た今―良い意味で相対化できる余裕と視野が生まれた今に。
―こんなことを書くとファンから「何を当たり前のことを今さら」と叱られそうだし、亡くなったのを機にそのような思いを抱くのも我ながら複雑な心境ではあるが。あるいは、なぜもっと小澤征爾の実演を聴いておかなかったのか、とも。遅いよ、遅い。
本稿、追悼文でもなんでもない雑文然としたものになったが、もっともらしいことは書けない。過去とこれからの「わたしと小澤征爾との関係」について思っていることを率直に書いたらこうなった。
(2024/2/15)