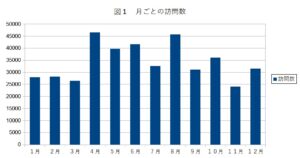私が書く理由|演奏会評覚え書き|西村紗知
私が書く理由(演奏会評覚え書き)
Text by 西村紗知(Sachi Nishimura)
 「私が書く理由」と尋ねられると存外答えに困るものだ。この『メルキュール・デザール』の存在ゆえ、と答えるのが一番シンプルだと思う。批評の独立性を目指す本誌の方針に、拙稿の性格がうまく適合した。私自身、自発的に内的欲求に従って行動するのが得意ではなく、実際のところ、「理由」と尋ねられて自らの執筆における内的欲求をここに書き留められる自信がない。あまり認めたくないが、締切がないと動けない質だ。
「私が書く理由」と尋ねられると存外答えに困るものだ。この『メルキュール・デザール』の存在ゆえ、と答えるのが一番シンプルだと思う。批評の独立性を目指す本誌の方針に、拙稿の性格がうまく適合した。私自身、自発的に内的欲求に従って行動するのが得意ではなく、実際のところ、「理由」と尋ねられて自らの執筆における内的欲求をここに書き留められる自信がない。あまり認めたくないが、締切がないと動けない質だ。
そんな私が本誌に正式に加入して一年と約半年足らず。拙稿に目を通してくれる人がどう感じているかわからないが、毎度執筆には苦労している。言うまでもなく、拙稿にはジャーナリスティックな性格も資料価値も少ない。記述されるのは私という一人の人間の一つの経験だ。ある一つの演奏会を、私の経験でまるごと包んでしまいたいといつも思う。その動機に演奏会の良し悪しなど関係しない。だから、にわかに信じがたいと思う人もいるかもしれないが、演奏会を褒めたことも貶したこともない。唯一、論調が辛くなるとしたら、社会的事象としてなにか重大な契機を含んでいるものに対してだろう。ただその場合には、自分の耳から少し離れたところで書かざるをえない。
経験を記述するのに苦労しないときはない。主観的な印象論に尽きるものでもよければ別だが、そもそも人を惹きつけるほど魅力的な主観を私が持ち合わせているわけでもない。そうして経験の記述のために次の二つのことを試みる。演奏会での出来事を、感性的な次元でとらえることができるか。その上で、自分の知識・経験に、どれくらい還元できるものか。ある程度書きたいことを決めて演奏会に向かうこともある。しかし大抵それは覆される。
演奏会評を書く上でやっている苦労はそういうものだ。他の人はどうなのか知らない。もし音楽批評を眉唾だと非難する人がいれば、自分の知識や経験に感性的な次元が左右されない人などいるのかと聞きたい。ついでに、音楽批評以外の文章で実証的に書かれているものについて、その知識・経験と感性的次元との協働という点につき、本当に眉唾でないのかというのもあわせて聞いてみたい。
事実、私はどのような演奏会に行っても、ここに書けないような子供じみた感想しか抱かない。誤解のないように言うが、それは意志的にやっているつもりだ。あまり最初から言葉でとらえたくはない。それはなんとなくつまらないことだから。では、きちんと言語化された演奏会評が出来上がるならやはり眉唾ではないか、と思われるだろう。違うのだ。時間が経つとなんとなく言葉の方に経験が落ちてくる。これには演奏会に行ってから最低一週間はかかるが、もし仮に落ちてこなかったら「落ちてこなかった」旨を書く。これは私の能力不足が原因かもしれない。案外、私の演奏会評は正直だと自分では思っている。
こうした演奏会評にまつわる個人的な諸々の苦労を、日々、寝食ばかりで良いことも悪いことも時間が経つと忘れてしまう存在である私は、唯一と言っても過言ではない人間らしい営みだと思ってやっている。都市生活者は特に、人間らしい営みを日々心がけるに越したことはないのではないか。
……と、執筆において意外と内的欲求があるのを確認したわけだが、「私が書く理由」について、一つの経験として記述する方法を苦労してまでなぜ選び続けているのか、と問い直すことができるだろう。一つは先ほど書いたように、それが人間らしい営みであるから、だけれども、もう少し執筆様式の選択肢の問題として。
実は意図して自分の方法を選んだわけではない。なにかへのカウンターとしてやっているつもりもなく、というのも音楽批評のヘゲモニーを思い描くことからして私には難しい。かつては吉田秀和や遠山一行といった、啓蒙活動に近いかたちで音楽評論を執筆し続けた偉大な先人がいたが、最近ではサブスクリプションサービスに加入すれば誰でも実に多様な音楽が聴ける環境にあって、啓蒙的なスタンスの執筆は常に存在意義を問われることとなる。もちろん、サブスクの大海に投げ込まれたリスナーが救命ブイのごとく音楽批評を求めることもあるのかもしれないが、ジャーナリスティックな性格も資料価値も少ない拙稿の出る幕ではないどころか、私自身も日々勉強中なので啓蒙する側に回るとしたらあと何年後のことになるか見当もつかない。
どういうふうにして書くかという選択肢は最初から手元になかった。それは、私がどうも制度的なものの内部に入っていけないということに原因がある気がしている。クラシック音楽の子弟制に基づく数多の営みからも、人文系学問の実践からも、今となっては距離ができてしまった。加えて、日本で多く言われるところの「批評」も、手本にするのに一苦労だ。私は政治の話を書くのが下手で、映画のリテラシーも低い(あんな暗い場所で大音量の音響を浴びながら同時に映像も見て、どうしてみんな平気なのか今でもわからない)。自分の郷里での経験とその頃都市部の方で経験されていたであろう「ゼロ年代」との乖離も耐え難い。そうして、端的に言えば、江藤淳も蓮實重彥も東浩紀も受容できない。もちろん読んでいて頭で理解することはできる。ただ読んでいる間中、何がわからないのかよくわからないというように感じられることが多い。そんな気がする。
だから、「私が書く理由」は非常に没歴史的なところにあるといえる。音楽、音楽批評、批評――いずれからも離れてしまっていて、おぼつかない。もちろん日々、それらのジャンルの書籍を読むようにはしているつもりだ。そうでなければ、演奏会評は絶対に書けない。
それでは何を支えに演奏会評を執筆するのか。そこには、きわめて私的な原体験が横たわっているのではないかと思っている。
私の母方の祖母は淡路島の方の人で、どうもその地では生活者として行う批評があったようだ。「文句いい」という言葉を聞いたことがある。私は関西の方の育ちではないので、私自身が文句いいであるかはわからない(お笑い芸人・中川家のフリートークは、文句いいを高度な話芸にまで高めたものだろう)。けれども、なんとなくその血が流れているような気がしている。
というのも、祖母も母も今思い返すと、外食に行ってそこに出されるものをまっすぐに褒めることがなかった。かといって貶すのでもないが、なにか一言いうのである。それは社交のためではないし、洗練されているのでもなければ、かといって、ネット上に散見されるクレーマー気質ともかなり異なるものだった。テレビを見ても新聞を見ても、野球観戦を楽しみお笑い番組でたらふく笑った後であっても、日常のあらゆることに対して、常になにか言っておかずにはいられない人々だった。
文句いいは、生活者のフモールなのかもしれない。例えば退廃から身を守る防衛反応のようなもの。なにか一言、それが感嘆詞のような意味をもたないものであっても、出てこなければあるいは家畜と同じこと――大袈裟に聞こえるかもしれないが、生活者には、意識することはないにせよ、日々そういう瞬間があるのだと思う。
とはいえ、文句いいそのものでは批評にはならない。これは常に私の課題だ。言葉の方に経験が時間を経て落ちてきて、そうすれば批評を書くことはできる。だが、あんまり自分のところに居続けると――社会的な私が意識できるようでないと――だんだん、自分の源流に呑まれていくような感覚がある。
だから、今のように演奏会評を書き続けると、どこかで躓くかもしれない。商業的な執筆様式への転向などよりも、そうやって自分のうちの源流との付き合いができなくなることの方がこわい。しかし、そうなったらそうなったまでのこと。
――それに私は、自分が演奏会評を書くような人間になるなどと、予測したことはこれっぽっちもなかったのである。
ここまで、諸々「私が書く理由」にあたるものを書き連ねてきたが、最後に、その他「私が書く理由」に関わるものを断片的に挙げてみる。
本稿に取り掛かろうとしたときに真っ先に脳裏に浮かんだ話題があった。それは次のような幼い頃の経験だった。図鑑を開く。それは爬虫類の図鑑だ、たぶん学研の。マムシのページがある。マムシというヘビは「花柄のような柄をもつ」という。私には、今も昔もマムシの柄は花柄に見えない。ひょっとしたらもう学術的なタームとして、あれを「花柄」と記述する習慣になっていたのかもしれない。けれど、今思い出しても、私はそういう記述を美しいと思う。おそらくそれは、専門知からにじみ出る筆先の狂いのようなもの。
それと、制度的なものへの感覚が元々強い。世の中音楽美ほど制度的なものはない。どういう音楽が良く、またどういう音楽が悪いか、などとプラグマティックに問いを立てて判断することは、本当は不可能だ。それが仮にできたと確信しても、すぐさま「そのように問いを立て判断するような制度内の人間なのだ」という印象で覆われる。音楽批評の眉唾は、実際の演奏会の良し悪しと執筆者の思惑との乖離ではなく、こういう制度内外の軋轢に由来するのだと思っている。
それに、言語化への切迫感は昔からあったような気もする(この場合ピアノを弾くなどの音楽表現もまた言語のひとつであろう)。それは制度的なものへの感覚の強さと関連して、文化制度間に生きる上での歪みに起因する。それで最近、私はやたらと家族論的視座に惹かれている。
まとめると、結局のところ、私が書きたいと思って楽しいと感じることをやっているということ。これからも精進したい。
(2020/10/15)