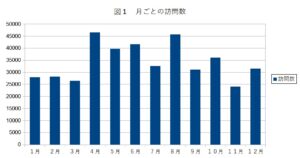私が書く理由|感動の共有は可能か?| 松浦茂長
感動の共有は可能か?
Text & Photos by 松浦茂長 (Shigenaga Matsuura)
テレビ局で働いていたので、テレビニュースのための1-2分の原稿を、30年間書いて来た。新聞社に2年間出向し、ロンドンのBBC海外放送にも出向したから、振り返ってみるとラジオ、テレビ、新聞の3つのメディアに書いて来たわけだ。たかが1分のニュースとはいえ、歴史が大きく動いた瞬間を、1分で伝えるのは不可能では無い。世界地図を書きかえるような出来事だって、そのエッセンスは一言で言えるはずだ。ぐたぐた長い説明を付けたくなるのは、何が起こったかよく分かっていないからに違いない。
1989年マルタでソ連のゴルバチョフ大統領とアメリカのブッシュ大統領が会ったのは、冷戦の幕を閉じる会談として歴史に書き記されているが、その場にいた僕には、恥ずかしいことに、歴史の大きなページが閉じたという感動はなかった。嵐で首脳会談会場の船が揺れ、ブッシュ大統領がひどく船酔いしたとか、東京から来た大物キャスターが「ゴルバチョフは元気が無い」と言い続けたとか、どうでも良いことばかり覚えている。
しかし、あれほど人類を脅かした冷戦がこの日終わったのだ。核戦争の不安、スパイ、亡命、強制収容所……冷戦の半世紀を深く心に刻み込んでいれば、堂々と幕を引いたゴルバチョフの勇気に感動したはずだし、暗い歴史のページが閉じた感動を視聴者に伝える原稿を書けたはずだ。
ソ連崩壊前後、モスクワ支局は応援の記者で賑やかになった。若い女性記者にデモの取材をまかせ、彼女の持ち帰ったレポートを見たら、僕が事前にデモの背景を説明しながら参考までに渡した通信社の記事に書いてある内容しかしゃべっていない。たまたまボンから僕と同世代の特派員が来ていたので、「彼女、自分の見たこと感じたことを全くレポートしてない」とこぼすと、彼いわく「若い連中は感動ってものがないんだ」と切り捨てた。本当に、若い世代は感動する力を失ったのか?それとも感動するのはプロではないと、思い込んでいるのだろうか?感動を表に出すのは子供っぽく見えるのだろうか?
いつ頃からだろうか、テレビに登場する人物が、何か食べると「おいしーい」と叫び、旅番組で美しい風景になると「すっごーい」とつぶやく。感動の常套句を恥ずかしげもなく連発するようになった。誰もが同じ常套句を反芻すると、安心するのだろうか?美術評論家の椹木野依氏に言わせると「感動は、同じ感動を共有することで自分は間違っていないと確認する、ある種の集団的な現象だと思います。」。つまり、感動すると自分を失う。感動とは主体=個喪失の危険な罠というわけだ。(『危うい<共感>? 感情を鍛錬する』 2019年2月)
感動の意味にこだわったのは、僕の書く理由がそこにあるからだ。感動を伝えたい――そのために書くのだと思う。椹木氏が感動の<共有>について語っているのは正しい。ただ、彼が非難するネガティブな共有だけでなく、ポジティブな共有も感動には伴っている。誰でも感動したときは、感動を誰かと分かち合いたい気持に迫られはしないか。感動の独り占めは不健康だ。
いや、もっと正確に言うと、孤独な感動はありえないのでは?音楽に深く感動したとき、その感動の背後に多くの人の存在を感じないだろうか?感動するとは、そんな美の共同体に仲間入りすることかもしれない。感動するとき、主体=個を超え出て、真=美共同体の一員として迎えられる。そこには、落ち着き、静かな喜びがある。本物の感動は、自分を失うのではなく、真=美共同体に守られる自分を発見することだ。
僕がモスクワにいた1988-1994年は、ペレストロイカからソ連崩壊の時期だったので、欧米の新聞社は選り抜きの特派員を送り込んでいた。ニューヨークタイムズのビル・ケラーは、宣教師のような雰囲気。ロシアの民主化を心の底から願う誠意が伝わってきた。後に彼はニューヨークタイムズの名編集長になる。アパートの隣人マルコ・ポリーチは、メサジェーロの特派員。なぜか浴衣を着て原稿を書き、僕が修道院の取材をした話をすると、熱心にメモを取っていた。後に彼はバチカン研究の第一人者になり、フランスのテレビニュースでローマ教皇が話題になると、必ずポリーチ先生が登場する。
彼ら良き仕事仲間の言葉、文章には、歴史の波動に共鳴し、一つ一つの出来事にどれほど感動しているかが読み取れた。忘れられないのはガーディアンのジョナサン・スチールの一言だ。「ゴルバチョフはモーセのようだ。民を約束の地に導いてきたが、彼はモーセ同様、その地に入ることはできない。」ユダヤ人のスチールがモーセにたとえるのは、ゴルバチョフへの愛の告白だし、同時に彼の悲劇的運命を予告している。
ゴルバチョフが別荘に監禁されたクーデター未遂事件の時、ゴルバチョフを迎えに別荘に飛んだ決死隊にただ一人加わったジャーナリストはスチールだった。彼は、僕にトインビーの『歴史の研究』を勧めてくれた。歴史の中で今自分はどこに立っているのかを知らなければ、真実には近づけない。真実に触れないかぎり、感動はない。
でも、書く行為には、どこか後ろめたい感じが伴わないだろうか。何かを偽っているような、人をだましているような後ろめたさだ。嘘とは言わないまでも、本当に大切なことは文字では伝わらないように思う。学生時代、丸山真男の講義を覗いたら「政治は料理と同じで、本を読んでも身につかない。」と、意外な忠告をした。政治の分かる人に、いわば弟子入りし、以心伝心で教えて貰うしかないらしい。道元は「正師を得ざれば学せざるに如かず。」と言う。しかるべき先生が見つからなければ仏道を学ばない方がまし……とすると、本を読んで仏道を学ぶなんて問題外と言うことになる。
有名な映画評論家の講演会を聞きに行ったら、ものの分かった人間は世界中に自分しかいないと信じているような、軽薄な男だった。その後、この大評論家と同じ大学で教える友人に会ったので、講演の話をすると、その時の印象を裏付ける呆れたエピソードをたくさん聞かせてくれた。映画通の友人に聞くと、その男の評論はなかなかのものだそうだ。三流の人格から一流の文章が生まれる?書くとはやっぱり嘘をつくことかも知れない。
自分の知らなかった世界に目を開かせてくれるのは、文字ではなく人との出会いではないか?料理や政治は人から直接手ほどきして貰う必要があるとすれば、美や宗教や哲学はなおさらだ。運命的出会いの相手は必ずしも大先生とは限らない。ジャンクリストフは、風来坊のような叔父と野原を散歩しながら、大自然の歌を啓示される。音楽会で偶然隣り合った愛好家の一言が、一生忘れられない音楽への熱い思いを吹き込んでくれるかも知れない。
上智大学でリーゼンフーバー先生が、土曜の朝、一般人に哲学・宗教を教える講座があった。アリストテレスやヘーゲルの難解なテキストを2時間半ぶっ通しで解読するハードな授業。周りを見廻すと、先生が説明している箇所と全然違うページを開いていたり、黙想に専念したり、それぞれ自己流の学び方だった。それでも、暖房なしの教室(先生は暖房の騒音が耐えられない)の寒さにもめげず、毎週大勢が通ってくる。リーゼンフーバー先生が何を話すかは、そんなに大事ではない。大事なのは、先生と一緒にいられること。話の中身が頭に入らなくても気にしない。もっと大切な何か――本からは決して得られない何かが、先生から豊かに流れ出て来るのを、感じているから。
どんな人に巡り会うかで人生の豊かさが決まってしまう。せっかく美の感性を持って生まれながら、良い出会いに恵まれず、音楽を聴く喜びを知らずに人生を終える人がどれほどいることだろう。書くことによって、その人達の感性を開かせることが出来るならば!いや、文字にその力はない。生身の人間から発する目に見えないそよ風(霊力)だけが、人の魂を変容させるのだ。ただ、それは意識下の出来事であり、本人は変容に気づかないかも知れない。しかし、変容によって今まで見えなかったものが見え、聞こえなかったものが聞こえてくるのに気づく。その後が文字の出番だ。新しく生まれた感動にフォルムを与え、ハッキリと把握し伝えられるものにする――それが、書くこと、読むことの仕事なのだろう。
(2020/10/15)