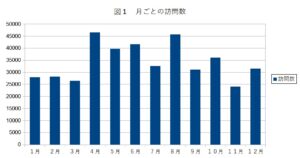私が書く理由|「書く」ことの苦と楽|大河内文恵
「書く」ことの苦と楽
Text by 大河内文恵(Fumie Okouchi)
「SWITCHインタビュー 達人達」というTV番組をご存じだろうか。Eテレで土曜の夜に放送されている番組で、異なる世界で活躍している2人の達人がお互いの本拠を訪ね、インタビューをし合うという趣向で、前半と後半とで攻守を交代(switch)する。先月放送された「藤原聡×古沢良太」の回で面白い遣り取りがあった。
コンフィデンスマンJPなどの人気ドラマや映画の脚本家である古沢が、人気急上昇中のバンド、Official髭男dismのボーカルおよび作詞作曲者である藤原に、歌詞が先かメッセージか先か?と問うたとき、藤原は「メッセージ先行」はないとはっきり否定したのだ。藤原いわく、バンドたるもの、メッセージ性がなければならない思い込み、メッセージやテーマを打ち出すことに懸命になった時期もあったが、テーマが先行して作ったものは面白くならなかったという。
この答えに、古沢がここぞとばかりに自分も同じだと語り始めた。古沢の描くドラマは社会派を標榜してはいないものの、エンターテインメントの奥に何らかのメッセージが見え隠れするものが多い。だから意外だった。彼いわく、脚本を書くということは、何もないところから方向性も何もないまま、こっちだろうかと進み、いや違ったと別の方向を探しと、まさに暗中模索の連続なのだという。
彼らのような才気溢れる人々は、天啓に導かれるように作品をつくっていくイメージを勝手に抱いていたが、凡人である筆者と同じようなことをやっていたのかと救われたような気がした。もっとも、彼らはその作業は「産みの苦しみ」ではなく「楽しい時間」と称していたのがやはり凡人とは違うところなのだが。
彼らのようなクリエーターとは違い、何かを書くときにゼロから書くことはあまりない。レビューなら対象となる演奏会なりがあるし、楽曲解説なら曲はすでに決まっている。それでも、どう書こうかとか最終的にどこに落としどころをもっていくのかというのは、最初から見えていることはほとんどなく、書く前や書く作業と並行して方向性を探っていき、のたうち回りながら見つけることが多い。
考えてみれば、漠然とではあるが、レビューを書くにしても、書きやすい演奏会と書きにくい演奏会とが存在する。それは演奏の上手い下手とはまったく関係がなく、おそらく演奏者や主催者がどれだけ考えてその場を組み立てているかによる。つまり、よく考えられた演奏会は、聴いているこちらがそれをどれだけ汲み取り、そのメッセージをどう再構成すればうまく読み手に伝わるかを考えれば良いだけであるのに対し、そうでない場合には、こちらがプログラムや演奏から、本人が気づいていないであろうメッセージを読み取る作業が必要になる。
だったら、最初からメッセージ性の高い演奏会を選べばいいのではないかと思われるかもしれないが、事はそう単純ではない。一見、無秩序に見えるプログラムに大きなメッセージが隠されていることも少なくないからだ。
もちろん、演奏会の良さはメッセージ性の有無だけで決まるわけではない。だから、どの演奏会を選ぶのかは毎回賭けである。メッセージのありそうな演奏会からも、なさそうな演奏会からも、演奏者の意図とも関係なく、「何か」を受け取ってしまうことはある。受け取ってしまったら、それを自分の中だけにおさめておくのは手に余るので、言葉という形で外に発信する。それが私の「書く」ことの原点かもしれない。
「書く」ときに、たまに頭によぎることがある。自分はどういう立場でこれを書くのか?ということである。筆者は(それで生計を立てているかという基準に照らせば)プロの音楽批評家ではないし、音楽ライターでもない。研究という立ち位置ではあるものの、広くいえば音楽の業界の片隅に存在しているので、素人(=一般人)でもない。プロでもアマチュアでもない人ってナニモノだ?
ある新聞コラムに目が留まった。「人道写真家」という言葉から始まるそのコラムは、毎日新聞の夕刊に日替わりの書き手によって綴られるコラムで、「人道写真家」を肩書にした名刺を受け取った著者(小国綾子氏)の疑問から始まる。その名刺の差し出し主である清水匡氏は認定NPO法人「国境なき子どもたち」(KnK)の広報担当者で、プロの写真家ではないものの、写真展をおこなっているという。この肩書の真意として小国氏に語ったところでは、「(自分は)写真家でもなければ、ジャーナリストでもない。写真技術は特段優れているわけではないと思う。ただ、KnKの職員として、子どもたちの厳しい環境を何とかしたい(後略)」のだという。
これを受けて、小国氏は「つまり『撮りたい』でも『記録したい』でもなく、何としてでも子どもたちを『支えたい』のだ」とパラフレーズする。そうか、「書く(=撮る)」のに、世間を納得させる肩書が必要だと思うのは、書き手(=撮り手)の勝手な奢りなのかもしれない。
たしかに私たちは何かの文章を読んだり、写真を見たりするときに、それをどのような人が書いたのか(撮ったのか)が気になることがある(気にならない人もいるかもしれない)。だけれども、本当に重要なのは書き手の属性ではなく、そこに何が書かれているか、書く対象に対して、どのような眼差しを向けているのかということなのではないだろうか。ついついレッテルを貼ってしまう、この情報化社会において、「書く」ことは書き手にコネやツテがなくても誰でも書けるという自由を与えると同時に、そのレッテルに書き手自身が縛られてしまう危険性を孕むという、一見正反対な作用がありはしないか。それはまさに、「書く」ことそのものに、苦しみと楽しみという相反する感情が伴うことと、どこかでつながっているような気がするのだ。
(2020/10/15)