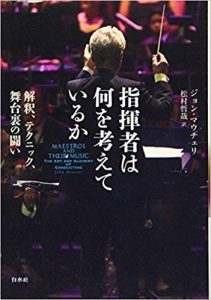Books | 指揮者は何を考えているか|谷口昭弘
ジョン・マウチェリ著、松村哲哉訳
白水社
2019年7月出版 3000円
Text by 谷口昭弘 (Akihiro Taniguchi)
ジョン・マウチェリというと、ハリウッド・ボウル管弦楽団というレコーディング用オーケストラを指揮し、フィリップス・レーベルからCDを多数リリースし、来日した折りにはそれなりに話題になった音楽家だと記憶している(当時のCDの表記は「モーセリ」ではなかったか)。その後の彼については、ミュージカルをはじめ、近年は映画音楽のコンサートなど、どちらかというと「軽め」の演目を指揮しているイメージがある。そんなマウチェリが初めて書いた本が『指揮者は何を考えているか』(現題はMaestros and Their Music)で、その内容も楽しく読めるものだったので、今回はこの一冊を取り上げてみたい。
マウチェリは本書を「専業指揮者」が必要とされるようになった歴史的経緯から解きほぐしていく(第1章「指揮をめぐるちょっとした歴史」)。19世紀半ばになり音楽の書き方が複雑になり、コンサートホールやオペラハウスなどの専門の演奏空間が誕生する。そんな中で、かつては作曲家が担っていた演奏者の取りまとめは、音楽作り全体を俯瞰する専門家が行うようになるということ。
そして第2章「指揮のテクニック」は、プロになりたい人が必要な技術的問題というよりは、例えば指揮者は演奏者よりも一拍先で、どんな準備動作をするのか、あるいは指揮棒の役割は何かといった、基本的な事柄に焦点を当てる。
この本の冒頭の二章は、そのような基礎的な内容も含め、ディズニー映画『ファンタジア』に登場したレオポルド・ストコフスキー、そしてカラヤン、バーンスタイン(後者とマウチェリは18年の親交を持っていた)が成し遂げたことなど、指揮者が日々関わっている諸問題を分かりやすいエピソードを数多く交え、一般の音楽愛好家に語りかけてくる。ポップス・オーケストラの指揮者としてマウチェリが多くの「大衆」と出会ってきたことも、その語り口に影響しているのだろう。
本書はさらに「オーケストラスコアの読み方」と題された第3章となる。ここでは《春の祭典》など演奏に使われた楽譜の実例も交え、出版譜など、与えられた楽譜を指揮者がどのように扱い(例えば書き込みなど)、実際の演奏用楽譜に練り上げて行く過程を、料理のレシピづくりを垣間見るような感覚で述べていく。また指揮者に必要なのは「リーダーシップを持ち、正直であること」だと、指揮者の人心掌握術の実際について書かれている。
次の「指揮者になるための勉強法」と題された第4章になると、指揮者には音楽史・音楽理論が役立つとしつつも、ページの大半は有名指揮者の仕事術(暗譜の意味やリハーサルの方法など)、キャリア形成の様々なあり方に割かれている。この章も第5章(「指揮者によって演奏が違うのはなぜか」)も、タイトルに見られるテーマに対する明確な答えは示されていない。しかし現場の生の声、そしてそれが音楽作りにどのように影響しているかをダイレクトに感じ、そこから読者が考えをさまざまに巡らせるような刺激には富んでいる。
第6章は指揮者と関わり合いをもつさまざまな要素について書かれた長めの章「さまざまな関係」で、音楽作品への向かい方、音楽家との付き合い方、聴衆や評論家、オーナーおよびマネジメントとの諸関係が遡上にあげられる。この中で最も痛烈な批判の対象となっているのが評論家である。指揮者ほど音楽を知らない評論家(攻撃対象になっている人物には音楽学者としても高名なポール・ヘンリー・ラングもいる)が演奏を品評すること、そしてその執筆が演奏家のキャリアを左右する影響力を持っていることについて、マウチェリは理不尽を感じているようだ。
アメリカの音楽評論の社会的な役割は日本よりもずっと大きいということもあるし、ハロルド・C・ショーンバーグのように辛辣な批評も確かに多く書かれているということもあろう。ややうがった見方をすると、この部分に関しては、マウチェリがサイモン・ラトルやマイケル・ティルソン=トーマスほどの「名指揮者」になれなかったことへの自己弁護な側面もあるのではないだろうか(後者に対する「傲慢さ」についてもチクリと一言がある。他の章ではロリン・マゼールに対する批判が強い)。
評論家は聴衆の一人として音楽に接するものだと誰からともなく私は教わったので、マウチェリの評論家攻撃は結局、聴衆の攻撃になってしまうようにも思えたりもするが、とはいえ、それも評論家の傲慢であり、聴衆の方はおそらく評論家よりも音楽家の方に共感を持つことになるのかもしれない。評論家というのも因果な商売をしているということになるのだろう。
さて第7章「仕切っているのは誰か」は、最終的な演奏・上演ができるまでの指揮者の真の影響力について述べるもので、この中では「演出家の時代」のオペラにおける演出そのものへの批判(音楽との関係性が希薄になったことも含め)と、それによって指揮者の役割がオペラにおいて弱まったこと(そもそもバレエでは「仕切る」ことさえ不可能だそうだ)などに嘆き節が見られる。
次の第8章「長距離指揮者の孤独」では、彼のように世界的な指揮者でも「旅芸人」的な側面があり、労働環境から見た指揮者が世間が考えるほど華やかではないことを自身の境遇から述べている。次の第9章「録音対生演奏(対ライブ録音)」では、歴史的録音のCDの時間比較をするなど、あまり演奏家がやらない録音に対する記述が興味深い。
最後の第10章「指揮をめぐるミステリー」では、再び指揮者が楽譜から考えることについて、マーラーの第4交響曲の鈴のテンポの扱い方が詳細に書かれている。ただ一方で、ここまで本書を最初の方からずっと読んでくると、内容が時に(クラシックのファンではなく)一般の愛好家にとって、どれだけ興味のあるものなのか、不安な箇所も多くある。この章にあるような楽譜の微細な問題は、そもそも第2章で述べるような「スコアの一番上がフルートで…」(第3章)ということは既に知っている読者だろう。
マルチェリの想定している読者はどのようなものなのだろう。また全編を通して紹介される幾多のエピソードは最後までとても面白いのだが、それぞれが各章の内容に対してどういう意味があるのか、あるいはこの本全体において、マルチェリは何を伝えたいのかについては最終章に至っても明確でないという問題がある。
ただ改めて全体を見渡してみると、マウチェリの『指揮者は何を考えているか』は、マウチェリの回想録でもあり、一指揮者による音楽論でもある。いきいきとした筆致で現場の息吹きが伝わってくる。訳も読みやすい。丁々発止のやり取りで成功した体験も、うまくいかなかったことも正直に、潔く書かれている。多くのエピソードには(かなりネガティブなものも含めて)実名(指揮者だけでなく作曲家や演出家、歌手なども)が挙げられているが、彼が世界的超一流とまでされていないからこそ、しがらみなく名前を挙げて逸話を多く書けたということなのだろうか。
この読み応えのある本を読むと、マウチェリに対する(正直言ってあまり高くはない)世間の評価が果たして正当なものなのかどうなのかについて問いたくもなるし、指揮者の生き様について、あるいは音楽が立ち起こる現場について、読者がますます興味を持つことは間違いないだろう。一度手にとってご覧になることをお勧めしたい一冊だ。
(2019/11/15)