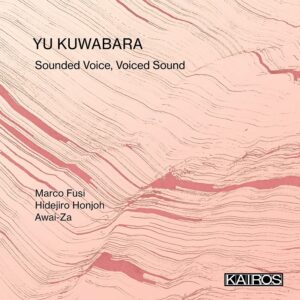Books|三栖一明|西村紗知
 三栖一明
三栖一明
向井秀徳 著
ギャンビット
2017年8月 ISBN 978-4907462314
Text by 西村紗知 (Sachi Nishimura)
ナンバーガールが再結成したことを知ったのは、今年の6月のことだった。新宿の喫茶店でコーヒーを飲んでいたときに、隣の席にいた若い男女の会話から。
そうか、ナンバーガールが帰ってくるのか。再結成の知らせが世間に知れ渡ったのは今年の2月のことだったらしい。まもなくツアーが始まって、当然チケットなんか取れるはずもないのだという。ま、あんまり知らないんだけど、だってリアルタイムで聞いてなかったんだものね、と若い男女。そりゃあ私だってリアルタイムじゃ知らんけど、とコーヒーに再び口をつけたとき一緒に居た友人にどうかしたのかと言われて、あわてて取り繕う。
ナンバーガール。「1995年、福岡にて結成されたロックバンド。メンバーはアヒト・イナザワ(Drum)、向井秀徳(Gt, Vo)、中尾憲太郎 45才(Bass)、田渕ひさ子(Gt)。地元福岡でのイベント開催や、カセットテープの自主制作などの活動を経て、1997年11月に1stアルバム『SCHOOL GIRL BYE BYE』をリリース。1999年5月、東芝EMIよりシングル『透明少女』をリリースしメジャーデビュー。以後3枚のオリジナルアルバムと2枚のライブアルバムを発表し、2002年11月30日に行った札幌PENNY LANE 24でのライブをもって解散。2019年2月15日、再結成しライブ活動を行うことをオフィシャルサイトにて発表」(註1)。
――なるほど、そうだ。筆者とてナンバーガールをリアルタイムでは聞いていない。なのに、「帰ってくる」という感慨でそのとき胸がいっぱいになったのである。この思い入れは一体何に由来するものなのか。そういえばなぜ、毎年夏になったらナンバーガールの「透明少女」を聞くようにしているんだったっけ。
『三栖一明』という本を手に取ってみる。ナンバーガールのフロントマンである向井秀徳の自伝と言うべきこの本のタイトルには、向井の同級生であり、長らくナンバーガールをはじめとする向井の作品のアートディレクションをつとめてきた、グラフィックデザイナーの名前がそのまま付されている。向井が三栖との関係を語りながら自身の創作史を振り返る内容となっていて、もちろんナンバーガールのことを知るにはうってつけの一冊だ。アマチュア時代からのフライヤーやアルバムジャケットなどが順番に掲載されており、それらの制作にまつわるエピソード、その時々のコンセプトを向井自身が説明している。他にも、楽曲誕生秘話とも言える向井の個人的な色恋沙汰のエピソードも。
リアルタイムで聞いていない分、初めて知るような内容がほとんどだ。ナンバーガールのロゴに使われている特徴的なギザ文字は、三栖が手ずから何度もコピー機でそのロゴを複写することにより出来上がったものなのだ、とか、向井がパフォーマンス中に多用する「くりかえされる諸行無常… よみがえる性的衝動」に通ずる、語句の繰り返しという手法はアートディレクションにおいても早くから採用されていたなど、興味深い話がたくさん。しかし、リアルタイムで聞いていないにも関わらずナンバーガールと出会ってしまった、あの感覚を説明する要素は特に含まれていない。もちろんそんなことは自伝の感知したことではないのだ。それでも、三栖のデザインが「切なさ」を基軸としている、ということが確認できたのはよかった。切なさという契機は、そのまま向井の作品のインスピレーションにも該当するように思う。冷たい殺風景の中に一瞬現われては消えるようなもののこと。
筆者にはロックンロールの経験がない。狭くて暗くて人が多くて大きな音のする場所には行けない性質なのと、なによりギターをやる友人がいなかった。ロックンロールを経験するには、これに精通した友人が必要だ。それに加えて都市生活も。仮にあの頃の筆者の故郷のCD屋に、オルタナ系の邦楽ロックを扱うコーナーがあったとしても、それを薦める友人がいなければ話は始まらない。
そんななか、あれは2004年くらいだったろうか。ケーブルテレビが筆者の自宅に実装されたのである。当時のスペースシャワーTVは、いわゆるロキノン系の盛りであった。もちろん邦楽ロックをチャート化する際に、このロキノン系というカテゴリーがどれほど適切なのかは疑わしいけれども、筆者はこのころのロキノン系を、切なさの盛りとして記憶している。あるいは、「世界観」の提示の数々。切なさと世界観の両立となると、単調な音楽は敬遠されて当然だったろう。洗練化の要請。その分当時のロキノン系は、日本のポップミュージックを地上波のヒットチャートの範囲でしか知らないような人間を感化させる力をもっていた。それがロックンロールを知らない人間だとすれば、効果はいかばかりであったか。
ナンバーガールを聞いたのは、それからだいぶ後のこと。聞いた瞬間興ざめした。自分が2004年以降関心を持って聞いていたもの、切なさ、気の利いたコード進行、メロディ、歌詞――これらのものの多くを、違って聞こえても実際にはもっとラディカルなかたちで、すでにナンバーガールがやっていたと直観し、なんとなく傷ついた。あのプールの中から急に巨大なザリガニが出てくるMVも、陽炎が揺れていることにやたら執心するのも、粉雪にあらゆる心情をすべて負わせようとするのも――結局はナンバーガール以降という括りを拒絶するための装置だったのか、と思ったりして、この考えが自分の中で馬鹿にならない説得力を持ってしまったので、あまり考えないようにしたくらいである。
ナンバーガールの方が切ないのだ。しばしば不穏、狂気、あの90年代末期の空気感など形容されるであろう彼らの音楽は、型通りの切なさを生み出す語法を棄却しているけれども。クロマティックな振る舞いはもちろんなく、メロディーラインも歌詞も、直接訴えかけるなどということはない。切なさが虚偽の語りと隣り合わせにあるという事情を暴露しつつ、彼らの音楽もまたそれらの間で揺れている。他人の音楽の切なさを嘘と名指しする彼らの身振りもまた別の方向性で嘘っぽさを保って、少なくとも他人の側には入っていかないようにしているようだ。それに、ナンバーガールの切なさは、模倣や再生を拒絶する。模倣されえないもの、それはギターのひずみなのか、向井のときたま道化じみたあの個性なのか、はたまた風俗嬢にフラれたときの哀痛の情(本書を参照されたい)なのか。むしろ、模倣や再生が均質にくりかえされる都市生活においてさえも、一瞬立ち現われる何かを、必死に掴み取ろうとすることで彼ら独自の切なさが生まれている。筆者がナンバーガールに思い入れを感じたのは、この辺りの緊張関係によるのだと思い出した。
筆者のパソコンには、ナンバーガールのアルバム『OMOIDE IN MY HEAD』が取り込まれている。それにしても、なんて頃合いが良いのだろう。今しがたファッション業界に牽引される90年代リバイバルブームの最中、また再び「赤い髪の少女」が街中を彷徨う時代になって(昔は今ほどきれいに染髪する技術はなかった。ついでに言うと、タピオカだって今ほどおいしくなかった)、本当にあの頃を走り抜けた、ナンバーガールが帰ってきた。
註1:https://numbergirl.com/biography より。
(2019/10/15)