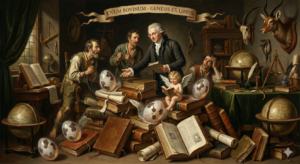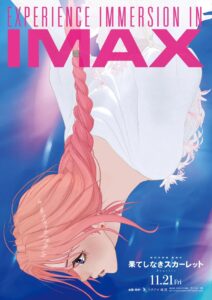五線紙のパンセ|カンドンブレとショーロ|今堀拓也
Text by 今堀拓也(Takuya Imahori) :Guest
カンドンブレ
カンドンブレはブラジルの特にバイーア州の黒人に伝わる伝統宗教である。
バイーア州は16世紀にポルトガル人がブラジルに初めて入植した場所であり、サルヴァドール(救世主つまりイエス・キリストの意味)はその際に最初に拠点とした街である。バイーアとは湾の意味であり、波のほとんど立たない静かな海は大西洋航行の帆船を停泊させるのに都合が良かったのである。最初はイタパリカ島に要塞を築き、ここを捕鯨の拠点とした。鯨の脂は多様な目的で使われており、建築のセメント代わりや、特に大西洋横断の際の重要な燃料となった。捕鯨が軌道に乗ると、今度は湾の周辺にサトウキビ畑を作り、原住民を奴隷として捕縛し働かせた。当時の砂糖は重さあたり金と同じ価値があったので、この新大陸でのサトウキビ畑はポルトガル王国に巨万の富をもたらした。原住民が枯渇すると、今度はアフリカ西海岸で黒人を捕縛し、奴隷船に乗せて連れてきてサトウキビ畑の労働力とした。この歴史ゆえに、バイーア州はブラジルの中でも特に黒人の割合が非常に高く、州都サルヴァドールでは住民の9割が黒人である。イタパリカ島内を歩いても、場合によっては先住民族(インディオ)の血が濃そうな人も見かけるが、街ですれ違うのはほぼ99%黒人である。たまに白人とすれ違うと、おそらくブラジルの他の地域から来たのだろうと推察される。ちなみにアジア人は一人もいない。ブラジルにはサンパウロに日系移民が多いせいか、よく日本人と言われる。他の国ですれ違うたびに中国人と言われるのとは大きな違いである。
歴史的に彼ら黒人の先祖はカトリックに強制改宗させられたが、アフリカの土着宗教も秘匿しながら守り伝えられた。これがカンドンブレである。
カトリックの影響を受けているとされ、祈る時に眉間の辺りで指を揉むなど、カトリックのミサの福音書(新約聖書のうちの特にイエスの伝記部分)朗読で額、唇、胸に指で十字を切るのとよく似た仕草も見られる。礼拝行為はポルトガル語がベースになっているらしいが、シャーマンをオリシャと呼ぶなど独自の単語が多く、もはや全く別の言語に聞こえる。
オリシャは多神教の神々が降臨してくるが、一神教であるキリスト教、特にカトリックの聖人とも密接に結びついているということである。そもそも聖人でたとえばペテロが漁師だったので漁師の守護聖人というような認識はカトリックや正教会(オーソドックス)でいう概念であり、多神教を取り込んだものと考えられる。
少し話がそれてプロテスタントについて書くが、プロテスタントでもカトリックに近い聖公会(アングリカン、英国国教会)や北欧諸国の国教会はいざ知らず、プロテスタントの概念を生み出したルター派は特に、イエスの母マリア(これを聖母と呼ぶのはカトリックや正教会である)、十二使徒などは尊敬の対象でありこそすれ聖人崇拝には至らない。もっとも、イタパリカ島にはあらゆる場所に様々な宗派のプロテスタント教会があった。ごく一部は立派な現代建築だったが、その他の多くはイタパリカ島全体の一般的な建物と同じく、素焼きの穴あきブロックの中におそらく鉄筋も入れずにセメントを入れて積み上げただけのいかにも脆そうな掘立小屋にペンキを塗って体裁を整えたしろもので、「我らのイエスは決して裏切らない」などのスローガンが書かれている。キリスト教そのものは信仰しつつも、歴史的な支配者であるカトリックからは距離を置こうとする態度が少なからず見てとれた。
あるものらはそうして新興宗教系プロテスタントに活路を見出す一方で、別の集団はアフリカ由来のカンドンブレに宗教のルーツを見出そうとする。カンドンブレが多神教でありつつ支配者の白人の宗教であるカトリック側にお目溢しをもらいながら存続するためには、多神教の概念をぼやかしつつカトリックの聖人に対応させる必要があったわけである。
カンドンブレの儀式で使われる楽器はコンガに似たアタバキと呼ばれる小中大の3つの太鼓が中心で、これは白いレース布で飾られ聖なるものとして崇められており、信者たちは楽器の前を通る時にお辞儀する。これに鉄鍬が加わり、竿はなく鉄器の部分だけを持って叩く。鍬を叩くという行為は黒人奴隷たちが身近なものを楽器の代用とした歴史を感じさせ、さらには彼らが元々いたアフリカに鉄器や青銅器が伝来した数万年前の原始文明時代からの伝統を思わせる。アゴゴで代用する場合もあるらしいが(これは見学した2グループのうちの2つ目がそうしていた)、その場合アゴゴは普通は大小2つのベルが組になっているが、儀式ではそのうちのどちらかしか使わない。たまに叩く人が交代する時に大小がひっくり返るが、基本的に一つのベルだけを叩き続ける。楽器を演奏するのは基本的に男性である。だんだんテンポが速くなったところで次のセクションに移行するというのを繰り返す。
まずはレッスンを受けたパーカッショニストのルイス(連載第1回参照)が演奏するグループの儀式を見に行った。
このグループの儀式の会場はタクシーで15分程度、約7km先の隣村ミゼリコルヂアにある。この村の名前は慈悲という意味でカトリック的である。
この日は途中でぶっ倒れて仮死状態を演じた女性がいて、うつ伏せのまま5,6人で担いで奥に引っ込めた。その最中も踊りと音楽は止まないから、皆慣れているのだろう。後で話を聞くと、その女性はそれから2週間家族と乖離されて、その掘立小屋の寺の中で過ごすらしい。いわゆる宗教的なイニシエーションである。
2つ目のグループは、レジデンスから歩いて3分の近所にある礼拝所で行われた。虹の神を崇める団体で(あるいはその日の儀式がそうだったのかもしれない)、途中から虹の7色をまとったおばちゃんが出てきて踊り始めた。
前半
後半
2つの団体とも、王冠を被った王と、明らかに中心的な神がいて、さらに藁や真珠のすだれで顔を隠した女性陣が後半に現れる。これがこの世のものならぬ神聖な存在が降りてきたということらしい。王はマラカスを2つ掲げ持ち、滅多に鳴らさないが、いざ鳴らし始めると会場全体を素早く踊り廻る。それとは別に金属製のカシシと呼ばれるマラカス風の持ち手のついたシェイカーを1つずつ持ち鳴らす一般女性が複数いる。
中心的な神と王が退場すると、最後に楽器隊が今までで一番速いテンポで演奏し、それが終わると同時に別の女性陣がアタバキにさっと白布をかけて、一連の儀式は終了する。そのあとはビュッフェ式の食事が振る舞われ、我々見学者もご馳走になった。
ショーロ
たまにWhatsapp(日本ではLINEが主流だが世界的に主流のメッセージ交換SNSアプリ)のレジデント共通のグループにコンサート情報が流れてくるのだが、それを流すレジデント自身はそれに行きたいわけではなく、興味のある人がいればという目的で流しているらしい。そのうちの一つに、バイーア州立大学の医学部の図書館の中のオーディトリウムでレクチャーコンサートがあるという情報が流れてきて、しかし実際にレジデントで他に行くという人はおらず、一人で対岸の街サルヴァドールまで行ってみることにした。
船で渡った後、タクシーで現地周辺について、医学部らしく白衣のお姉さんに道を聞いてようやく辿り着いたその図書館のオーディトリウムというのは、いわゆる大学の中教室といった感じで、聴衆も10人足らずで期待の薄い印象だったが、いざ始まってみるとこれがなかなか面白かった。何も予備知識がなかったので、ショーロChoroというスペルからコーラスを想像していたのだが全く異なり、19世紀末あたりから始まったブラジルのポピュラー系の室内楽で、フルートやクラリネットなどの旋律管楽器を中心に、7弦ヴィウエラ(ギター属の楽器)やパンデイロ(薄型タンブリン)の伴奏がつく。サンバやボサノヴァの先祖にあたるジャンルということで、雰囲気としてはよく似ていた。
演奏のあとでレクチャーが始まったのだが、ポルトガル語だし聞いていてもよくわからないから退出しようかと思いきや、いざ始まるとこれが非常によくわかる内容だった。ショーロの歴史、歴史的なプレーヤー、主な楽器、主なリズムなどを解説するもので、2時間ほどの解説でショーロの概観がとてもよく理解できた。
ショーロの歴史的録音をまとめたものがYouTubeにあるので貼付しておく。
教室に入って始まる前に最初にここで良いかと確認しに私が拙いポルトガル語で声をかけた年上の男性があとで英語で話しかけてきて、19時から別のコンサートもあるから聴いていってくれと言う。吹奏楽がベースで、その昼のレクチャーコンサートで演奏した室内楽のショーロのメンバーも出るらしい。ホールの建物をここだと指さしてかすめながら大学の敷地を一度出て、近くの学生向けハンバーガー屋で奢ってくれた。私がサカタールのレジデントで現代音楽をやっていて交響曲を作曲しているというと、リゲティ、ペンデレツキ、武満の名前を出してきて、さらに話は弾んだ。どうもその男性は吹奏楽部の指導者の先生だったらしい。
その19時からのコンサートは、吹奏楽の出し物に関しては、まあ普通という印象であった。いかにショーロとして面白くても、吹奏楽に編曲してしまうと、よくある学校吹奏楽コンサートの後半以降にありがちな一昔前のポップスの編曲ものという感じで、ブラジルもので言えば『イパネマの娘』『コパカバーナ』(この2つはリオデジャネイロにあるビーチの名前で、お互い隣接している)などの吹奏楽編曲を聴くのとあまり変わらない。ショーロの1920年代つまり100年前の名曲で原曲はテナーサクソフォンが主旋律を担うSPレコード録音が有名な曲があるらしいが、ホルン協奏曲に編曲しており、それがフェルマータになる3ヶ所でそれぞれリヒャルト・シュトラウス『ホルン協奏曲第1番』『英雄の生涯』『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯』を引用したのには参った。失笑したのが私一人で、まわりの他の観客は誰もわかっていなさそうなのがまた救いようがない。
コンサートの途中から昼間のショーロの室内楽団体が出てきて、彼らのソロだけになったのはさすがにうまかった。独特のグルーヴがあり、これが他の何にもたとえようのない味を出している。最後は吹奏楽伴奏と彼らの共演ということで、ショーロの過去の名曲の何かを演奏していたが、やはりソロの部分だけに独特のグルーヴがあり、うしろの吹奏楽はそのノリが消えていた。
とはいえ、ショーロとは何ものであるかということに全く知識ゼロの状態から半日でここまで興味を持たせたのは素晴らしく、カンドンブレと並んでこの滞在中の最も得難い経験の一つとなった。
ちょうどピアノ曲の委嘱を受けていたので、これらの経験をピアノ曲として纏めた。『交響曲第1番』は2022年5月から書き始めたので、2年以上かけて作曲している。前回書いた通り、7割できている状態で残りの3割をブラジルで仕上げるように持ってきており、例えば打楽器をブラジル風にするなど何か装飾的にブラジルの印象を付け足すことはできても、作曲の根本的な部分でブラジルの文化を基に作り上げていくという段階ではない。ブラジルの、特にイタパリカの印象を元に今から『交響曲第2番』を書くとしても、出来上がるのは年単位かそれ以上先だろう。
まずは小編成の小品を素早く書いて、印象を焼き付けておくのも大事である。大カンヴァスの大作絵画をいきなり描く前のいわば鉛筆の素描であり、このピアノ曲は第一段階の荒削りなものである。今後また室内楽などいくつかの試作を経て、大きな作品へと結実させていこうと考えている。
(2024/6/15)
——————————
今堀拓也 Takuya Imahori
プロフィール
玉川大学文学部芸術学科卒業、パリ・エコール・ノルマル音楽院修了、フランス国立音響音楽研究所IRCAM作曲研修課程修了、スイス・ジュネーヴ州立高等音楽院修士課程修了。2017年イタリア国立ローマ・アカデミア・サンタチェチーリア研究科課程を満点賞賛付き最高位評価で修了。ならびにミラノ市立クラウディオ・アバド音楽学校指揮予備科修了。土居克行、三界正実、平義久、ジャン=リュック・エルヴェ、フィリップ・ルルー、ミカエル・ジャレル、ルイス・ナオン、イヴァン・フェデーレに作曲を師事、ローラン・ゲイ、杉山洋一に指揮を師事。2001年ガウデアムス賞(オランダ)受賞。ドナウエッシンゲン音楽祭(ドイツ)、ラジオフランス・プレザンス音楽祭などで作品が演奏。2018年4月より6月までオーストリア共和国文化庁ウィーン芸術レジデンス招聘作曲家に選出。2019年バーゼル作曲コンクール(スイス)第3位受賞。同年、イタリア共和国マッタレッラ大統領よりゴッフレード・ペトラッシ賞奨学金を受賞。2020年、KLANG!国際作曲コンクール(フランス)で第1位およびモンペリエ国立オペラ管弦楽団特別賞を受賞。2024年3月より5月までブラジル・イタパリカ島の芸術レジデンス・サカタールに選出され滞在。
植物や山河の自然に着想を得た作品が多く、単に詩的な感動だけでなくそれらに潜む数学的なフォームなどを作曲システムに活かしている。
今後の予定
イアン・ペイス ピアノ リサイタル 2024 ~ 現代ピアニズムの此岸I(両国公演)
2024年6月26日 19時開演(18時〜プレトーク)
両国門天ホール
今堀拓也 『イタパリカ奇想曲 Capriccio itaparicano』 新作初演
https://justmusic6.peatix.com/?utm_medium=web&utm_source=results&utm_medium=イアン・ペイス ピアノ リサイタル:35.6837,139.6805:::3946196&utm_campaign=search
オーケストラ・プロジェクト2024
2024年11月27日 19時開演(18時30分〜プレトーク)
東京オペラシティ コンサートホール
大井剛史 指揮、東京フィルハーモニー交響楽団
今堀拓也 『交響曲第1番 Prima Sinfonia』 新作初演
http://www.orch-proj.net/
今堀拓也 ウェブサイト
https://takuyaimahori.mystrikingly.com