小人閑居為不善日記 |アメリカを彷徨い続けて――ロビー・ロバートソン|noirse
アメリカを彷徨い続けて――ロビー・ロバートソン
Continuing to Wander America――Robbie Robertson
Text by noirse :Guest
1
8月9日、ロビー・ロバートソンが世を去った。ザ・バンドのギタリストで、卓越したテクニックもさることながら、そのほとんどの曲を手掛けたことで後進に多大な影響を与えた、ロックの巨人だ。
 わたしも学生のころ、ザ・バンドの《ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク 》(1968)と《ザ・バンド 》(1969)の二大名盤を手に入れ、舐めるように聞いたものだ。ザ・バンドと彼らの盟友ボブ・ディランの作品はカントリー、ブルース、フォーク、R&Bなど膨大なアメリカ音楽の蓄積に裏打ちされている。わたしは彼らの仕事を道標にこれらの音楽に触れ、それが今の嗜好に直結している。そういうファンは、世界中に無数にいるはずだ。
わたしも学生のころ、ザ・バンドの《ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク 》(1968)と《ザ・バンド 》(1969)の二大名盤を手に入れ、舐めるように聞いたものだ。ザ・バンドと彼らの盟友ボブ・ディランの作品はカントリー、ブルース、フォーク、R&Bなど膨大なアメリカ音楽の蓄積に裏打ちされている。わたしは彼らの仕事を道標にこれらの音楽に触れ、それが今の嗜好に直結している。そういうファンは、世界中に無数にいるはずだ。
しかしザ・バンドは、華々しい成功を得ながらも、必ずしも幸福な道を歩んだとは言えない。ロビーとガース・ハドソン以外のメンバー3人はドラッグとアルコールでボロボロになり、ステージをこなすのも難しくなっていく。そこにさらにリーダーのリヴォン・ヘルムとロビーの不和が重なってしまう。
ロビーにはマネージングの才能があったらしく、次第にバンドの采配を取るようになる。さらに作曲は彼が手掛けていたため印税がメンバーに行き渡っていないとして、これらを理由にリヴォンはロビーに不信感を抱いていく。ロビーはそれは誤解で、ドラッグがリヴォンの猜疑心を増幅させたと言うが、真相は藪の中だ。ザ・バンドは限界を迎え、1976年に解散する。
解散後、ロビーと他のメンバーが歩んだ道は大きく異なっていく。ロビーは映画界に進出しマーティン・スコセッシと意気投合、彼の作品の音楽監督などを務め、強い信頼関係で結ばれるようになる。2000年にはドリームワークス・レコードのクリエイティブ・エグゼクティブに招聘され、新人発掘の仕事を任されるなど、ビジネスマンとしても活躍していく。
一方他のメンバーの活動はというと、やや地味なものだったと言わざるを得ない。ザ・バンドの再結成を試みるもロビーは参加せず、解散前ほどの成功は得られなかった。リチャード・マニュエルは酒とドラッグから抜け出せず自殺。もともと隠遁者の癖があったガース・ハドソンは、表舞台から引っ込んでしまう。リック・ダンコとリヴォンはライブやレコーディングを続け、一定の評価は得たが、ふたりとも10年ほど前に相次いで世を去った。
リックとガースはロビーとの友人関係を続けたが、リヴォンとロビーが和解することはなかった。5人はもともとわずか十代でロニー・ホーキンスというシンガーのバックバンドとして集まったグループで、中でもロビーとリヴォンは一番付き合いの長い親友同士だった。しかしその関係は、ザ・バンドの解散と共に砕け散ったのだ。
2
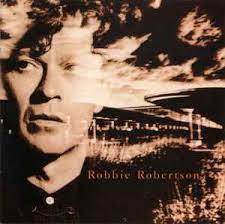 1987年にリリースされたロビーのソロアルバム《Robbie Robertson》は豪華なゲストや流行を意識したサウンドで、往年のファンからは反発の声も少なくなかった。その後の順風満帆の活動も、時勢にうまく乗ることができた、要領のいい人物というふうに見えなくもない。しかしあらためてロビーの足跡を追うと、角度を変えてみれば、ある意味一貫していたのではとも思える。
1987年にリリースされたロビーのソロアルバム《Robbie Robertson》は豪華なゲストや流行を意識したサウンドで、往年のファンからは反発の声も少なくなかった。その後の順風満帆の活動も、時勢にうまく乗ることができた、要領のいい人物というふうに見えなくもない。しかしあらためてロビーの足跡を追うと、角度を変えてみれば、ある意味一貫していたのではとも思える。
それはスコセッシとの仕事を通して確認できる。スコセッシはシチリアからの移民三世で、幼少から青春時代までをニューヨークのリトル・イタリーで過ごした。そのため彼はニューヨークにこだわり、特にキャリアの初期はほとんどの作品が同地を舞台とした。
しかし《タクシードライバー》(1976)や《レイジング・ブル》(1980)で認められたのもあって、次第に仕事の幅を広げていく。ポール・ニューマンの代表作の続編《ハスラー2》(1986)、ラスベガスを舞台にした《カジノ》(1995)、19世紀のギャングの抗争を描いた《ギャング・オブ・ニューヨーク》(2002)、香港映画のリメイク《ディパーテッド》(2006)、ニューロティックスリラー《シャッター アイランド》(2010)、実在するブローカーの回想記を元にした《ウルフ・オブ・ウォールストリート》(2013)、アイリッシュ系ギャングを取り上げた《アイリッシュマン》(2019)……。
ロビーは音楽監督やスーパーバイザーなど、何らかのかたちでこれらすべての作品に関わっている。ただしスコセッシの作品は、ザ・バンドがトラディショナルな音楽を通してアメリカの古層を掘り下げていくようなものではなく、そのせいかロビーとスコセッシの共通点についてはあまり指摘されることはなかった。
けれども作風がまったくの無縁ということもないだろう。リトル・イタリーはマフィアの本拠で、スコセッシの友人にも若きギャングの卵が大勢いた。一方ロビーだが、彼の父親はヤクザのような男だったらしく、事故死したとされているが、何かのトラブルで殺されたという話もある。残された母親はモホーク族の血を引いていて、貧しい少年時代を過ごした。十代にして家を飛び出し音楽業界に身を投じたが、要はドサ回りで、アル中や娼婦がたむろするバーを渡り歩き、時には万引きで糊口をしのぐこともあった。
またリヴォン以外のザ・バンドのメンバーは全員カナダ人で、非アメリカ人がアメリカのルーツ音楽を捉え直すという視点が、彼らの音楽にマジックを宿したと評されている。つまりスコセッシもロビーも貧困や暴力、犯罪と隣り合わせの環境で育ち、イタリア系アメリカ人やカナダ人という外部の視点から作品に向き合ってきたと言えよう。
スコセッシとロビーがタッグを組んだ作品も、多かれ少なかれ犯罪や裏社会と関わりを持つ映画ばかりだ。スコセッシは19世紀のニューヨーク、戦後のフィラデルフィア、1970~80年代のラスベガス、90年代のウォール街などの裏側を、嘗め尽くすように暴いていく。ロビーはそうした映画の的確な同行者だったはずだ。
これはザ・バンドがホーボーや労働者たちの心を代弁していたのと近い。ロビーはザ・バンドという仲間たちとは遠ざかってしまったものの、スコセッシという盟友を通して、ふたたびアメリカの裏面のサウンドトラックを奏でてきたのだ。
3
親父みたいに土地を耕して生きよう
兄貴と同じように反逆者でいよう
彼はまだ18歳で、誇り高く勇敢だった
けれどヤンキーの手にかかって、いまは墓の下で眠ってる
足元に広がるおれたちの土地に誓うぜ
ケイン家の一族はやられっぱなしじゃないってことを
南部が落ちたあの晩、鐘の音が鳴り響いていた
南部の旗が破れ落ちて、鐘の音がずっと鳴り続けていた
ザ・バンド初期の代表曲〈The Night They Drove Old Dixie Down〉(1969)。北軍に敗れた南軍へのシンパシーを歌っているが、もちろん封建的だった南部への礼賛ということではなく、歴史という旗の下で犠牲になっていった敗者への挽歌と言えよう。
スコセッシよりひと回り上の深作欣二はやはりヤクザの実態を緻密に描いたことで知られているが、彼の《仁義なき戦い》シリーズ(1973~)などの作品は、一種の戦後史だったとも見做されている。焼け野原だった広島が次第に復興していき、その過程で流れる裏金に喰いつくヤクザたち。だが結局はヤクザ同士がつぶし合うことになり、生き延びるのは結局政治家や企業だ。
戦後史の裏側には好ましからぬ者も多くいたが、彼らは葬り去られ忘れられて、残ったのは罪のないような顔をした連中ばかりだ。たしかに法を犯した者は然るべき罰を受けるべきなのだろうが、かといって彼らが集めた富を搾取して成長した社会に罪はないのか。そうした歴史を深作は虚飾だと名指しし、闇の中へと消えていった男たちにレクイエムを捧げた。
スコセッシにも同じことが言えよう。アメリカ発展の影には、必ずマフィアやギャングの存在がある。彼らが罪に問われたとしても、そこまで追いやったのは誰なのか。アメリカも潔白だと言えるのか。〈The Night They Drove Old Dixie Down〉などの曲を聞くと、こうした視点はザ・バンドの歌にも流れていたことが分かる。
4
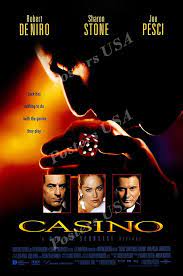 スコセッシ映画の看板俳優といえばデ・ニーロやハーヴェイ・カイテルだが、もうひとり忘れられない存在として、ジョー・ペシという男がいる。《グッドフェローズ》(1990)や《カジノ》のペシは主人公の悪友を演じていて、短気で向こう見ずな性格が周囲を巻き込み、破滅の渦へ引きずり込んでいく。それが分かっていても親友だから、主人公は縁を切ることができない。
スコセッシ映画の看板俳優といえばデ・ニーロやハーヴェイ・カイテルだが、もうひとり忘れられない存在として、ジョー・ペシという男がいる。《グッドフェローズ》(1990)や《カジノ》のペシは主人公の悪友を演じていて、短気で向こう見ずな性格が周囲を巻き込み、破滅の渦へ引きずり込んでいく。それが分かっていても親友だから、主人公は縁を切ることができない。
リヴォンがそういった悪友だと言いたいわけではない。そうではなく、人は一度なんらかの決定的な関係を持ったものとは、一生関係を断つことはできないと言いたいのだ。
ああ、いまわかったよ
遠くの赤いネオンが熱気で震えてる
おれは見知らぬ土地を彷徨う異邦人で
夜になると狂ったようにゲームに興じるこの場所じゃあ
暑すぎて眠れないんだ、神さま
ブルートレインに飛び乗って
誰も知らない街で、おれを探してくれ
荒ぶる河を下って
そのブルートレインに乗って
はるかココモまで来てくれれば
おれをきっと見つけることができる
暴れまわる河の向こうで
ロビー・ロバートソンの〈Somewhere Down The Crazy River〉(1987)。南部アーカンソー州の出身だったリヴォンは、カナダ人のロビーが南部の歌を作ることを快く思っていなかったらしい。カナダ人にはアメリカのことは分からない。親友リヴォンからもそう思われていたロビーは、どこまでも異邦人だったろう。
しかしリヴォンと共にザ・バンドという列車に乗り込み走り抜いた以上、「アメリカのサウンドトラック」を鳴らすのを断つこともできなかったのだろう。《グッドフェローズ》や《カジノ》を見返していると、デ・ニーロとペシの向こうに、アメリカ中をツアーして回った、かつてのロビーとリヴォンたちの姿が重なるのだ。
(2023/10/15)
————————————————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中


