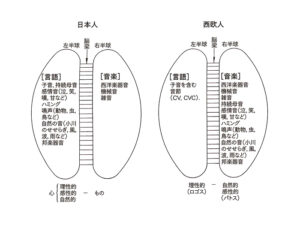カデンツァ|批評の夢|丘山万里子
批評の夢
Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)
創刊9年を迎え、毎年恒例の批評考。
改めて、メルキュール・デザールって何なの、と考える昨今。
 最近、話題となった『レコード芸術』休刊の報に、批評文化が失われる、と懸念の声が上がった。
最近、話題となった『レコード芸術』休刊の報に、批評文化が失われる、と懸念の声が上がった。
商業メディアは広告収入で成り立つものだから、企業に撤退されれば消える他ない。読者数の減少や経費高騰という時代の流れに抗うのは難しい。
かつて『音楽芸術』誌が終わった時もやはり、批評の消滅が騒がれたが、消滅はしなかったと思う。どこかにそれは、存在する。べつだん、多くの目を引かないところであっても。
そもそも、日本には批評がない、と昔も今もよく言われる。
不勉強ではあるが、私はそうは思わない。
例えば、平安前期に編纂の仏教説話集『日本霊異記』(787~822頃)は、前代までの神祇(じんぎ)信仰を仏教に引き寄せるための民間説話が並ぶが、説話のそこここにのぞく当時の人々の批評眼はクスリと笑える鋭いもので、それは『枕草子』(清少納言)『徒然草』(兼好法師)『方丈記』(鴨長明)の日本三大古典随筆にも明らかに見える。『枕草子』の「枕」の意がいまだ判然としないらしいこと一つとっても、これぞまさに批評、ではないか。
ん? 何が、これぞまさに批評なのか?
昔、遠山一行氏が私の母校桐朋学園大学で「批評実習」という講座を開講、私はとっくに卒業し2歳の子供もいたが、これに2年間密かに潜入受講した。まずは近代批評の父と呼ばれるらしいシャルル=オーギュスタン・サント=ブーヴの何だか(忘れた)、ついでポール・ヴァレリーを数冊読むように言われただけで(批評史的解説も講義もなかった)、あとは延々と氏の西欧生活あれこれを聞くばかり。全くもって徒然草であった。親に幼子を預けての貴重な時間ゆえ、私はそれがかなり不満で、1年目はへえへえと新鮮に聞いたが、2年目にはやや飽きてしまい、もう少し批評美学みたいなガッツリ体系的勉強がしたいなあ、などと思った。今となって、それが氏の「批評」そのものであったと気づき、頭を垂れるのである。ただたまに、演奏会にゆき批評を書いてこい、という課題があり(これが実習らしい)、それが嬉しくて続けた。氏はもちろん持ち帰って読むのだが、何か言われた記憶もないし、それについて受講生(3人)と話を交わすこともなかったと思う。書き方教室なんぞ、なんのことか、である。
パリ留学足かけ6年の徒然草を私は「批評」と言ったが、氏は29歳で彼の地に出立直前に『純粋批評という夢』(「音楽芸術」1951年9月号)と題した文章を書いている。それからほぼ40年後、70歳を記念してまとめられた私家版『私の音楽批評』(1993年、小沢書店)*で、この『純粋批評という夢』をふりかえり、批評にかけた自身の変わらぬ夢を語っている。「批評の消滅」についても一言しているのでご紹介する。
まず『純粋批評という夢』で、若き遠山は。
批評の客観性とか、批評の価値とか限界とか、色々の言葉を人は発明して、懐疑するのだが、しかしそんな事で、批評というものが消滅した事実は、一遍だってありはしない。創作家も演奏家も、自分の行為の中に批評精神というものが、どの様に働いているかはよく知っている筈である。美の鑑賞家にとっても、何も違った所はありはしない。
これは平凡な、しかし何よりも生き生きとした体験なのだろう。こうした一人々々の体験を別にして、批評というものを外から眺めようというのは、やっぱり大変不健康な事なのだと私はいつでも考える。
さらに、
私の仕事について、その価値やら限界やらという様な事は、むしろ他人の語るにまかせたいと思う。私は私の心の中に何が起こるかを率直に言って見れば足りる。
先日、私は若いメンバーが似たようなことを言うのを聞き、笑ってしまった。
批評を書きたい人が居なくなれば、批評は無くなるほかない。でも、そういうことは決して起こらないだろう、と彼は言ったのだ。
私もそう思う。
敷衍するなら、批評の「場」が、なんらかの状況で失われても、「人」は居なくならない。
誰も居なくなったら、それは仕方のないことだし、嘆くことでもない。
けれど、必ず誰かがどこかにいる。
いや、少なくともここに自分が居る(と思うひとが居る)。
全てはそれに尽きるのではないか。
批評は、「場」があるから存続しているわけではなく、「人」がいるから自ずと出来てきたものにすぎない。
どんなメディアであれ、誌面には「もの・こと・ひと」(物販・イベント・アーティスト)が読者の興味をそそるべく彩り豊かに並んでいる。
さて、「情報誌ではなく批評誌」と声高に謳う本誌はどうだろう。
そこに批評文化はあるのだろうか。
以前、メンバーたちと誌面構成についての論議の折に、読まれるのは「こと」だ、という話になった。
読者は、誰が書いているか、ではなく、何が扱われているか、レビュー対象となる公演なりイベントなりという「こと」に興味があるのであって、「誰」にはさして意識が向かない、というのである。
「こと」に検索をかけて本誌に飛んでくるのは、アクセス状況を見ればわかる。
でも私は、「誰」つまり「ひと」であってこそ批評誌と思う。
「誰が、何を、どう書いているか」が私の中での順番なのである。自己中と言われようがなんだろうが、物書きの欲動とはそういうものだ。この誌面は、広告もないしパトロンもいないし、自分たちの会費で維持しているんだから、どこに気兼ねなく、まずは書く人間を主体としよう、と傲岸不遜な編集長(私)は考えるわけだ。
したがって、執筆者全員の顔を見せましょうと《プロムナード》という枠をつくって、自由に思うこと、考えることを書いてもらうことにしたのである。いずれ《カデンツァ》(編集長コラム)だってフェイドアウト、巻頭に毎号メンバーが入れ替わり立ち替わり顔を見せるのは、楽しいではないか。
私は何も、「こと」では「ひと」は見えないと言っているわけではない。「こと」から「ひと」が見えてこその批評だし、みんなそういう批評を書いている。けれども、例えば誌面のレイアウトとして「こと」がずらりとショウケース的に並べば、「こと」だけがサクッと読まれ、消費される危惧は大いにあるのだ。一期一会の唯一無二体験と、それを語る人間の持続的存在の両方を響かせ合うような仕掛けは、執筆者にとっても読者にとっても楽しいのではないか。
「ひと」が見えるのが批評、については異論があろう。
本誌メンバーが全員そう思っているとか、賛同している、とかではない。
あくまで私個人の考えだ。
でも8年間、全ての記事(ゲストコラムも含む)を熱心に読んできた私は、そのどれにも「ひと」が見えてしまい(という言い方は変だが)、歌声が聞こえてしまい、それを嬉しく楽しく眺めまわしてきたのである。
例えば、その明快な分析力に脱帽し、自分もこんな評を書いてみたいものだ、と思い、コンサートに行っては「分析」してみようと試みるのだが、そんな意識は数分も持たず、自分の享受(私はそれが実に妄想物語であることを自覚する)にどっぷりはまってしまう。
だからよけい、自分が持たざるものへの畏敬を抱く(ようになった)。
歴史的考察に長けたもの。社会的洞察に優れたもの。哲学的思惟を促すもの。無駄の一切ないエキスだけのもの。グサっと一刺しするもの。などなど。
私は全ての記事に、それぞれの「目、耳、心の働き=そのひと」を感じ、深く感じ入るのである。
結局、書く、読む、とはそういうことで、ひたすらその喜び、ひと(他者)との遭遇なのではなかろうか。
読者にしたって同じだろう。
妄想物語に付き合うのは御免、という人もいようし(たぶん大勢)、この評の学的考察がたまらん、という人もいようし(たぶんかなり)、読み手だって好きに読めばいいわけで、何かを教わろうとか、知識を増やそうなどという作業は他でいくらでもできるのだから。
この8年で私が学んだのはそれ。
私は全ての記事に、うーむと腕組みして考え込んだり、きゃっきゃと笑ったり、そうだそうだ!と大きく頷いたり、上手い!お見事!と手を叩いたり、go! go! と叫んだり、実に忙しい。おまけにそれを書き手に伝えたいという衝動も持つのでさらに忙しい。私は自分が書いたものに絶大な自信を持つが、感想は聞きたい。きっと書き手はみなそうだろうと思うから、口がむずむずするのである。もっとも自分については、特に昨今、こんな妄想、書いて平気か?と思うことが多く、本誌校正者の瀬戸井厚子さん(実は腕っこきの編集者でもある)に「なんか変なこと言ってない?」と聞き「いいんじゃない?」と言われほっとする。これは書き手には大事で、だから必ず優れた読み手が必要なのである。
そんなこんなで、本誌で一番育てられたのは私ではなかろうか。ははは。
「好きなことを好きに書きたいなら、一人でブログでも書いてれば?」という声も聞く。
本来単独者であることを好む自分が、ともかく集団的な場で何か書き続けているのは、結局、そこで刺激をうんと受け、常に、自分を振り返ることを教えられるからだと思う。
つまり、どこまでも自己本位なのだ。
何が批評か、とか批評文化のあるなし、などどうでも良い。
何かを書きたい人がいる。
いる限り、それは無くならない。
前述の「批評実習」ではないが、若手育成講座みたいなことは各地の創造現場もしくは教育現場で大なり小なり行われており、それは批評必要論からくるものなのだろうが、誰が必要とするか、といえば、最終的には他の誰でもない、書きたい人でしかない。
 先述したが、遠山氏には「批評の消滅」という文章がある。
先述したが、遠山氏には「批評の消滅」という文章がある。
その一節はこうだ。
現在の批評は、一人ひとりの芸術家に対してではなく、グローバルな形での「芸術」をめぐって回転しているのでしょう。そうでなければ———特に音楽では———個々の作品のなかの「音楽」に対する純粋で専門的な、つまりマニエリスティックな分析があるだけです。自由な聴衆の発言としての批評の場は失われています。そういう聴衆そのものがいなくなってしまったのだから、これは当然なことでしょう。(『遠山一行著作集』第3巻 「批評の消滅」238頁 新潮社)
さらにその批評人生を振り返っての言。
戦後になって新しい大衆文化の状況が開けてきた。音楽的意識の成熟よりも新しい啓蒙の時代に戻ったんです。音楽を聴く人の意識はこういう時代には音楽についてたくさんのことを知りたい。そして音楽を理解したいということになるんでしょう。これは音楽的体験の深まりとは少し違ったことで、批評にとっては必ずしも幸福な時代ではないかもしれないんですよ。
(『私の音楽批評』61~62頁)
氏も憂えてはいるものの、『私の音楽批評』のあとがきを、こう結ぶ。
この十年ほどは楽壇の「公務」でとびまわることが多い日々ですが、私はあくまで批評家という自覚をもちつづけているつもりで、その批評家のささやかな経歴書として見ていただければ幸いです。
批評にとって幸福な時代であろうが、なかろうが、「あくまで批評家という自覚を持ち続けている」こと。
要は、そこではなかろうか。
とここまで勢いで書いてきたが、古き良き時代の話でしかない。
なにしろ昨今は AIが論文から ART作品から、なんだって造形・造型してゆく時代に突入した。
昨年だかに、私の評文をいくつかデータとして打ち込み、AIに「丘山風評文」を書かせたものがweb上に公開されていることを教えられ、へえ、と読んでみたが、なるほど、こうなるわけね、と思ったものの、だからなんなんだ、の話である。
誰それさんのフェイク本や作品が出回り、喧伝され、それでお金が動こうと動くまいと、そういう回路とは別のところに、ひとはやっぱり生きてゆくだろう。
少なくとも私は、そうとしか生きられない(と思うひとは私だけではないはず)。
言語の萌芽はおよそ7万年前と言われる。
意思疎通(対人とは限らない)という振る舞いに含まれるひとの表現衝動は、そんなにたやすく手放されるものではなかろう。
これ以上の未来図は、化石のような私には無理。
ただ「もの・こと」は、便利に使い回されて消えてゆくだろうが、「ひと」はどうあっても「ひと」であるところに踏みとどまるに違いない。
と、そこは楽観している(ひとも充分搾取、消費されているでしょ、という現実はあるにしても)。
で、本誌も「こと」でなく、やっぱ「ひと」でしょう、とか思うものの、ぜんぜん具体形が浮かばない。バブルに沸いた時代の子であるこの頭の因習的貧弱と限界。どんどん変化するツールにもついてゆけない。
であるから、涼しい顔でノートパソコンで会議のメモをとってくれ、編集の円滑を図るべくなんとかいうツールを使おうとかの提案をしてくれ、その枠は私にやらせてください、とか言ってくれちゃう頼もしい限りの今後世代の面々が、明るく楽しく伸びやかに「ひと」がわさわさ言い合う誌面を創っていってくれたらなあ、と勝手に思う次第である。
いや、はたしてやっぱ「ひと」なのか? からわいわい語らってくれれば、そこから新しい何かが生まれてくるのでは。
と、これが今の私の「批評の夢」。
(2023/10/15)