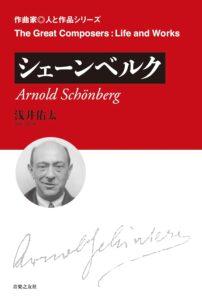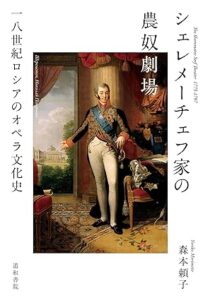Books|『シェーンベルク』 |佐野旭司
浅井佑太 著
音楽之友社
2023年5月出版
ISBN 9784276221987
2300円(税別)
Text by 佐野旭司(Akitsugu Sano)
2004年から刊行が始まった、音楽之友社による作曲家の伝記「作曲家◎人と作品シリーズ」。これまでに、バッハやヘンデルからショスタコーヴィチや武満徹まで、20人以上もの作曲家が取り上げられている。そして今年の3月、ついに同シリーズから新ウィーン楽派の作曲家の伝記が出版された。
同出版社でシェーンベルクの伝記が刊行されるのは、おそらく1998年に出た「大作曲家」シリーズ(エーベルハルト・フライターク著/宮川尚理訳)以来ではないだろうか。ただこちらは翻訳書であるのに対し、今回新しく刊行されたものは、日本人の研究者による伝記である。私自身もシェーンベルクの研究をしている者の1人として、これは是非とも目を通さなければならない1冊である。そのようなこともあり、今回本誌で取り上げさせていただくこととなった。
個人的な話をすれば、私はシェーンベルクの研究といっても、とりわけ1900年代(ゼロ年代)およびその前後の時期を中心としている。この時期は彼が《浄夜》で一躍注目を浴びてから、次第に調性やそれを支える機能和声が弱化し、いわゆる「無調」へと至った期間に当たる。これは当然ながら、音楽史的に見ても重要な様式の変化であり、私自身も、当時そのような時代様式の変化がどのようにして起こったか、という問題に関心を持っている。ところが、私がシェーンベルクの研究をしているという話を周囲の人々にすれば、必ずといっていいほど12音技法の話題となる。たしかに12音技法はシェーンベルクが考案した斬新な作曲技法であり、それが20世紀の音楽に多大な影響を及ぼしていることもまた事実であるから、無理もない話ではある。しかし「シェーンベルク=12音技法」というイメージがいかに強く定着しているかという事実を、私自身の経験から感じさせられることが多い。
本書の前書き(「はじめに」の項)は、まさにそうした一般的なイメージを逆手に取ったものといえよう。ここでは唐突に1921年の話から始まる。シェーンベルクがトラウンキルヒェンの街を散歩していた時に弟子のヨーゼフ・ルーファーに「私は今日、ドイツ音楽の次の100年の優位を保証するものを見つけました」と語り、その直後に12音技法を用いた《ピアノのための組曲》Op.25の第1曲を完成させたというエピソードである。しかし読み進めていくと、12音技法だけがシェーンベルクを語るうえで全てではない、という著者の主張が見えてくる。本書は作曲家の幼年期から12音技法に至る過程、およびその後の経歴を重視したものである。
同シリーズの他の著書と同様に生涯篇、作品篇、資料篇(巻末資料)からなるが、まず生涯篇ではシェーンベルクを取り巻く環境や様々な出来事について、絶妙な筆致によって客観的かつ劇的に描かれている点は大いに感服させられる。私のように、論文だけでなく本誌のような文章まで堅苦しい文体で執筆してしまっている者には、いかにして読み手を惹きつける文章を書くべきか、ということを考えさせられるばかりである。そのような例を逐一紹介していくと枚挙にいとまがないが、一例を挙げれば1933年のアメリカ亡命の描写(125および132~4ページ)からは、作曲家のおかれた境遇や心境が手に取るように伝わってくる。
また作品篇では、主要な作品の様式について丁寧に説明がなされているが、和声や形式、音列などの専門的な分析も、非常に簡潔で分かりやすく説明されている(個人的には《4つの歌曲》Op.2の和声分析は目から鱗であった)。
最後に、これは本書に限ったことではなく同シリーズに共通していえることだが、文章に脚注がないのは残念なところである。このシリーズは刊行時点での、作曲家の最新の研究成果をまとめた一冊であり、研究書としての価値も大きい。もちろん本書も例外ではない。とりわけシェーンベルクは、手紙やエッセイなど多くの言説を残しており、本書にもそれらの引用が多い。そのような部分には出典(引用文献やそのページ数)を明記すべきだろう。もちろんそのような脚注が多ければ、一般の読者にはとっつきにくいという印象も与えかねない。そのためこのシリーズのように、学術書でもあり読み物でもある著書においてはその加減が難しいところではあるのだが。
今後はそのあたりの折り合いをうまくつけた編集方針が望まれよう。
(2023/10/15)