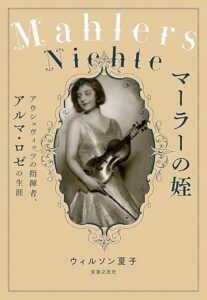Back Stage|その「場」は開かれ続けるのか―音楽ホールが朽ちる時|井上はるか
その「場」は開かれ続けるのか―音楽ホールが朽ちる時。
Will the ‘space’ continue to be opened up?: When a music hall is falling into decay
Text by 井上はるか (Haruka Inoue):Guest
思い出話から始めることをお許しください。
昨年10月7日、私たち公益財団法人神奈川芸術文化財団の芸術総監督だった作曲家・ピアニスト、一柳慧が亡くなった。財団が運営する3つの施設のうち主として神奈川県立音楽堂と神奈川県民ホールの、音楽、舞踊、美術全般にわたるプログラムを監督し、もう1つの施設であるKAAT神奈川芸術劇場の芸術監督(現在は演出家の長塚圭史)と時に2人で対話しつつ、神奈川の文化振興や、神奈川から広く発信していく劇場、音楽堂のあり方をスーパーバイズする役割を担っていただいた。
2021年春、就任20周年を祝い音楽堂と県民ホールが合同で行ったプロジェクト「Toshi伝説」の最終公演、「エクストリームLOVE」で、成田達輝(Vn)とペルト『鏡の中の鏡』を弾き、有馬純寿のサウンドテクニクスによる『エレクトロニクス卓球台』で元気にプレイする姿を見せて以来、ついぞ横浜に来ることがなくなってしまっていたから「ついに」という気持ちと「こんなに急に」という気持ちが複雑にからみあった。思い出せば大きな喪失感に襲われる一方で、生前楽しかった瞬間が思い出され、幸福感が湧き上がってくる。スタイリッシュでありつつ、独特の間合いを持ち、人物を知る人同士が集まると、ユーモラスなエピソードを披露しあっていつのまにか笑顔を共有する。そんな不思議な魅力の人だった。
芸術総監督のポストは当面2025年度までの現指定管理期間いっぱい空席で、私たちは支柱を失ったように見えるが、不安はあまりない。何故なら、一柳監督が私たちに指し示した道、というよりスピリットは、極めて明快なものだったからだ。
それはひとつには「芸術が開かれ、社会と切り結ぶ」リアルな力を意識する、ということと、もうひとつには「自由であれ。(精神も感覚も)若くあれ。」ということだった。
私は、神奈川県立音楽堂の企画を担当している。1954年、このホールが日本初の本格的な公立音楽ホールとして開館するまで、主な音楽会は日比谷の「公会堂」などで行なわれていたから、東京藝大の奏楽堂は別として、音響反射板を持つ「公立の音楽堂」は、戦後初めてできたのだ。かねて県内の文化人から「戦争で荒廃した人々の心を豊かにし、新しい社会を創るには文化施設が必要だ。わが国には本格的な音楽ホールもない」という声が高まっていた。折しも景気回復で税収が向上し、1952年には戦後日本の主権回復を定めたサンフランシスコ講和条約が発効。外交官出身の県知事、内山岩太郎が「条約発効記念事業として県立図書館と付属設備・県立音楽堂を建設する」ことを決断した。
「もはや戦後ではない」と経済白書が謳ったのは数年後だ。街なかにはバラックも残り「音楽どころじゃない」と県議会でも反対の嵐が吹き荒れた。一方、戦前の反省から「市民の集会の権利を保障する公会堂」「国民の知る権利を保障する図書館」の建設には誰も反対できない、という時代でもあった。様々な政策的駆け引きなどもあり、一転「音楽堂建設」が議会で可決される。このあたりの劇的な経緯は、当時の神奈川新聞が連日報じている。
前川國男が設計を担った。明るい社会の建設というビジョンを象徴する如く、ホワイエは全面を覆うガラス窓からの外光に溢れている。前川はロンドンのロイヤルフェスティバルホールを参考にした。今の感覚では少し不思議に思うが、当時最新鋭の音響を誇ると評判だったのだという。モダニズム建築の世界三大巨匠のひとり、ル・コルビュジエに師事した前川が参考にするならムジクフェラインやコンセルトヘボウではなくサウスバンクだったのか。テムズ川に映るその姿と音楽堂は面影が似ているので、比べてみてください。
音響は石井聖光。当時弱冠20代、東大の大学院生だった。「音響設計」という概念自体がまだ一般にない頃。前川が若い力を求めたという。石井は湾曲した波型の天井、舞台や客席の壁表面だけでなく、それらを支える芯材も木材で組み上げた「木のホール」を造った。舞台天井裏に上がると、コンクリート建築の中にすっぽりと木造建築が収まる構造が、客席のどこにでも舞台上の微細な音を伝える響きを支えていることがわかる。
横浜生まれ・育ちの私だが、1980年代後半、音楽堂には「地元の古いホール」の印象しかなかった。サントリーホールやカザルスホールなど、都内に続々と機能もアメニティも充実したホールがオープンしていた。1994年に現財団プロパー一期生として入職してしばらくも印象は変わらなかった。急な階段。毎回お客様からお叱りをいただく小さい椅子。豪雨の際天井から漏ってホワイエに降り注ぐ雨をバケツで掻い出した経験を持つホール職員などあまりいないだろう。さらには細部を見ると、「どうしてここにこれ?」と首をひねる箇所が結構ある。楽屋の真ん中に鎮座した柱、天井に頭がぶつかる楽器庫、なぜ作ったのか(未だに)わからない扉…。
ところが、数年音楽堂に「棲んで」いるうち、ハッと気づくのだ。目の前にあるのは、「日本初」の試行錯誤を重ねた設計と、消防法改正に合わせて客席数を減らして設けた通路、楽屋不足のため増築を繰り返したバックヤードなど、時代の変化に応じた苦肉の策の集積だと。純粋な音楽ホールにあるまじき「緞帳」は「色々な目的で使える公会堂」として建設計画を可決に導いた経緯を思い起こさせる。「奇妙な細部」を一つ一つ脳内で取り除くと、全体の構造の美しさが浮かび上がる。人々の挑戦の歴史が、時代を超えて建物からオーラを放つようだ。そしてそれが、故・一柳監督の「社会とかかわる芸術」「実験せよ。自由であれ」との声にも通じているようにも、個人的には感じられるのだ。
音楽堂にはもうひとつ貴重な「歴史」が眠る。開館初日、1954年11月4日から本日に至るまで、一日も欠かさず一部ずつ製本し、保管されたプログラムだ。記録を整理し、保存することを旨とする図書館の付属施設たる出自がここに生きている。ポスター、チケット、写真、サイン、新聞記事…。アルゲリッチが日本デビューし、若き小澤征爾が齋藤秀雄の副指揮者として幼少の潮田益子らのオーケストラを指揮し…。戦後日本の音楽演奏史の鏡。いつか整理し公開する手立てと助力はないか。ご助言乞います。音楽会に限らず、ファッションショーから理髪コンテスト、「ネズミ2匹を持参すれば粗品進呈」という、時代を反映した「衛生推進の会」まであらゆる催しがある。そして、オペラも。
今、音楽堂は毎年室内オペラを主催上演しているが、かつては違った。着想は2000年代初頭。2004年の開館50周年の記念企画を悩む中「音楽堂で昔オペラ公演があった」という声を、ベテランの舞台スタッフさんから耳にした。「何たってオケピがあるからなあ」。何ですと⁉ 勤続8年、誰も教えてくれなかった(というより多分知らなかった)!「地下の倉庫に、まだオケピの柵があるだろ」…転がっていた。コンクリの床に、数十年分、何センチもの埃に埋もれたステンレスの支柱、紅い繻子のロープが。そして私たちが「謎の境目がある」と思っていた床板を開けると、演奏者の肩くらいの深さ、小型のオーケストラが入れるサイズの「ピット」が出現した。
調べると、開館翌月からオペラ公演が行われていた。近衛秀麿指揮、二期会による『コシ・ファン・トゥッテ』。竣工直後に視察した近衛閣下が「本格的なオペラ上演には小さすぎる」とご不満を述べた、という新聞記事もある。今なら、いや音楽堂にそこまでのご期待は…という笑い話にも思えるが、「日本初の音楽ホール」に音楽人の悲願がかかっていたのだろう。以後、1961年に東京文化会館が同じ前川國男の設計によりオープンするまで、数々のオペラやバレエの公演が音楽堂で開催されることになる。
「音楽堂オペラ」は、神奈川県民ホールが制作するオペラをフラグシップに予算も人員体制も最適化していた当時の財団内部では、当初過大な発想として大反対された。が同時に内外から応援の声も頂いた。横浜にもみなとみらいホールが開館し、首都圏の音楽ホールに群雄割拠状態が生まれていた。放っておいたらただ不便なものとして朽ちていくだけの古い音楽ホールが、新しさ、便利さが追求される社会で生き残れるか? それにはホールの個性を徹底的に見つめ直し、発信するしかない。神奈川県立音楽堂にしかない個性。それが、建築、音響、歴史の物語なのだ。
「オケピ発掘」の物語は、半信半疑だったおじさん役人達(失礼!)も含め、関係者をワクワクさせた。ある館長は、新聞のスクラップを作り、政治が動く瞬間を読み解いてくださった。歴史に埋もれた名曲を現代に蘇らせ、音楽との新しい出会いを創るバロックオペラがピタリとはまった。当時バロックオペラを継続的に上演するホールはほとんどなかった。候補を探すうち、ファビオ・ビオンディがヴィヴァルディ『バヤゼット』の蘇演を長年希求しているという情報が入った。「ヴィヴァルディのオペラなんて、日本では研究者ですら存在は知っていても誰も観ていない。日本の音楽演奏史に残る。やりなさい」と背中を押してくださったのは関根敏子先生だ。音楽堂の「ルネサンス」と名付けた。
しかし実は当初からバロックオペラだけを想定していたのではない。1994年、ポクロフスキー主宰モスクワ・シアターオペラが訪れショスタコーヴィチ「鼻」を上演した。簡素な装置、当意即妙な音楽で、突如出現する「場」…。これだ。不足だらけの音楽堂の舞台を逆手にとり、「サイズ」だけに着目し、「室内オペラ」をシリーズ化したら? 人員も予算も限られた中でも、ルネサンスから現代までオペラの多様性を楽しんで頂けるのでは?2人でも30人でも成立する、自由度の高い「室内楽」に着目することで、音楽の自由な可能性を感じて頂けるのでは? シンフォニーには不向きな音楽堂ならではの室内楽ラインナップの軸にできるのでは?
コロナ禍による2020年の中止を経て昨秋実現したビオンディらとのヘンデル『シッラ』、コロナ禍真っ最中の2021年、過酷な隔離策をクリアして実現したジネール『シャルリー~茶色の朝』。『バヤゼット』、遠くは『コシ』から続く流れはこうして一線上に並ぶ。
前者は中止で積立金を使い果たし、予算の目途が立たない中「必ず上演を」という音楽関係者の皆さまの声や「金の事は後で考えろ。鉄の熱いうちだ」という当時の館長の叱咤激励、後者は第二次安倍政権下の日本で「時期尚早か」と尻込みする中「やるなら今だろ」という沼野雄司・芸術参与の助言に背中を押されて踏みだすことができた。
そして『バヤゼット』から『シッラ』、『シャルリー』にいたるまで、一柳監督は常に「実に刺激的で面白い。やりなさい」と応援してくれたのだ。現代音楽に限らず、挑戦する試み、社会に刺激を与える芸術活動について自由にフラットに評価する姿勢は一貫していた。この場を借り改めて深い感謝と敬意を表したい。
神奈川県立音楽堂は2024年11月4日、開館70周年を迎える。2024年も、2025年も室内オペラのプロジェクトは既にスタートしている。しかしその先は?「日本初」ということは、その辿る道は全国の公立音楽ホールの行く末を占うものにもなるということだ。
建物はいつか朽ちる。だが、多くの芸術家や支援者、名もなきスタッフ~役人も民間人も~が拓き、支えてきた「場」は、これからも開かれていくと信じている。自分もまたその歴史の一端を担っているという緊張感に震えながら。
(2023/8/15)
井上はるか
神奈川県立音楽堂プロデューサー
(公益財団法人神奈川芸術文化財団)
Haruka Inoue,
Producer, Kanagawa Prefectural Music Hall
(Kanagawa Arts Foundation)