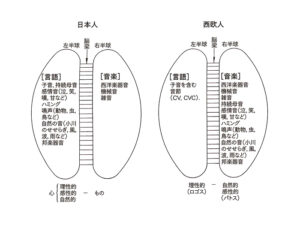小人閑居為不善日記|日陰をゆく――岡田徹、バビロン、エンパイア・オブ・ライト、フェイブルマンズ|noirse
日陰をゆく――岡田徹、バビロン、エンパイア・オブ・ライト、フェイブルマンズ
Walk in the Shade
Text by noirse
※《バビロン》、《エンパイア・オブ・ライト》、《フェイブルマンズ》、《チャンス》の内容に触れています
1
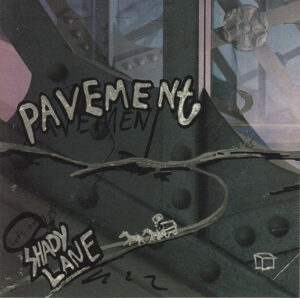 2月初旬。ペイブメントの来日公演に行ってきた。1990年代初頭、グランジブームをよそ眼に、シニカルな歌詞とひねくれたポップセンスで大きな支持を得たバンドだ。
2月初旬。ペイブメントの来日公演に行ってきた。1990年代初頭、グランジブームをよそ眼に、シニカルな歌詞とひねくれたポップセンスで大きな支持を得たバンドだ。
止まれ、動くな
きみは、きみの伝記映画の、
エキストラに選ばれたんだから
彼らの代表曲、〈Shady Lane〉(1997)からの一節。売れ線のバンドをからかい、あえてヘタに演奏してみせ、最後までロックの王道から距離を置き、高評価を得たにもかかわらず10年程度で解散したペイブメントの、あえて脇道を歩んでいった姿が重なる。
ロックスター、アイドル、俳優、スポーツ選手、マンガ家。誰にもひとつくらいは憧れた夢があったろう。そうでなくとも、こんな人生を歩みたいという未来像が、おぼろげにでも存在したはずだ。けれどその道を進むことができるのは、ほんのひと握りの少数に過ぎない。ほとんどが人生のShady Lane――日陰の小径――を歩んでいく、そういうものだろう。
 ここ1ヶ月、映画製作や映画関係の仕事に携わる人々を描く作品が次々と公開された。まずはサイレントからトーキー移行期のハリウッドを描いた《バビロン》(2022)。映画に憧れ、下っ端として雇われたマニーは、次第に才覚を発揮し、プロデューサーにまで上り詰める。しかしギャング絡みのトラブルに巻き込まれ、地位も財産も捨て、身ひとつでハリウッドから逃げ出す羽目になる。
ここ1ヶ月、映画製作や映画関係の仕事に携わる人々を描く作品が次々と公開された。まずはサイレントからトーキー移行期のハリウッドを描いた《バビロン》(2022)。映画に憧れ、下っ端として雇われたマニーは、次第に才覚を発揮し、プロデューサーにまで上り詰める。しかしギャング絡みのトラブルに巻き込まれ、地位も財産も捨て、身ひとつでハリウッドから逃げ出す羽目になる。
20年近い月日が流れ、マニーは妻と幼い娘を連れ、ハリウッド観光に訪れる。ニューヨークでラジオ店を営んでいるらしいが、スタジオで辣腕をふるっていた頃と比べると羽振りもよくなく、毎日の苦労が疲れた表情から伝わってくる。
若きマニーの口癖は、「I always wanted to be part of something bigger」というものだ。「何か大きなものの一部になりたかった」。マニーは「大きなもの」の端を掴みかけたが、それは残酷にもその手を離れ、今では日陰の小径をトボトボと歩むしかない。
最後、映画史上に残る作品のフッテージが次々とモンタージュされていく場面がある。マイブリッジ、リュミエール、メリエス、《イントレランス》、《アンダルシアの犬》……。輝かしい映画史へのオマージュであると共に、そこに《バビロン》も加わりたいという、監督デイミアン・チャゼルの思いも込められているのだろう。厚かましさも感じるが、最年少32歳でアカデミー監督賞を受賞しつつもなお「何か大きなものの一部になりたい」と願うチャゼルから漂う人間くささに、若干の親近感を覚えてしまう。
2
 《エンパイア・オブ・ライト》(2022)は1980年代、イギリスの海辺の映画館、エンパイア劇場でマネージャーとして働く中年女性ヒラリーが主人公。少女時代のトラウマで家族はおらず、精神の病を抱えている。若いスティーヴンと恋仲になるも、彼が去っていくことに耐えられず、病を再発し、周囲に迷惑をかけてしまう。しかし最後は、スティーヴンが大学に進学するため街を去っていくことに耐え、孤独な人生を受け入れていく。
《エンパイア・オブ・ライト》(2022)は1980年代、イギリスの海辺の映画館、エンパイア劇場でマネージャーとして働く中年女性ヒラリーが主人公。少女時代のトラウマで家族はおらず、精神の病を抱えている。若いスティーヴンと恋仲になるも、彼が去っていくことに耐えられず、病を再発し、周囲に迷惑をかけてしまう。しかし最後は、スティーヴンが大学に進学するため街を去っていくことに耐え、孤独な人生を受け入れていく。
ヒラリーは映画館で働いていても、上映されている映画を見たことがない。自分の人生で手一杯な彼女には、フィクションを楽しむ余裕がないのだろう。だが最後にヒラリーは、初めてエンパイア劇場で映画を見て、心を動かす。
彼女が見た映画《チャンス》(1979)は、知的障害を持つ初老の庭師が、誤解が誤解を呼ぶことで大統領候補にまで上り詰めていくという皮肉な作品。誰から見ても「エキストラ」だった人物が、世界の中心へと歩んでいくという内容とも言えよう。これはヒラリーが、自分が世界の中心にいるのではなく、他者も彼らの人生では主人公であり、彼らの世界では自分は脇役に過ぎないということを理解した、そういう意味合いもあるに違いない。
 《フェイブルマンズ》(2023)はスピルバーグの自伝的映画という触れ込みだ。「日陰の小径」から彼ほどかけ離れた人物もいないが、それでもはじめて映画業界の「助手の助手の助手」の仕事を射止めて喜んだり、ジョン・フォードからアドバイスをもらって舞い上がる姿を見ていると、スピルバーグでさえチャゼルのように、自分が「自伝映画のエキストラ」だったと思っていたことが窺える。想像するよりも、「わたしはわたしの人生のエキストラ」と感じている人は多いのかもしれない。
《フェイブルマンズ》(2023)はスピルバーグの自伝的映画という触れ込みだ。「日陰の小径」から彼ほどかけ離れた人物もいないが、それでもはじめて映画業界の「助手の助手の助手」の仕事を射止めて喜んだり、ジョン・フォードからアドバイスをもらって舞い上がる姿を見ていると、スピルバーグでさえチャゼルのように、自分が「自伝映画のエキストラ」だったと思っていたことが窺える。想像するよりも、「わたしはわたしの人生のエキストラ」と感じている人は多いのかもしれない。
3
3月になっても音楽界に残念なニュースが続いている。2月には大作曲家バート・バカラックと、ヒップホップにおいて多大な影響力を持ったデ・ラ・ソウルのトゥルゴイが、3月にはジャズの巨人ウェイン・ショーターと、スライドをはじめとした弦楽器の名手デヴィッド・リンドレーが、次々と鬼籍に入った。それぞれ長年聞いてきた音楽家たちだが、一番こたえたのはムーンライダーズの鍵盤奏者、岡田徹の訃報だった。
ムーンライダーズは1976年《火の玉ボーイ》でデビュー、1977年以降は不動のメンバーで長く活動を続け、いつしかロック界のゴッドファーザーなどと目されてきた。2011年に無期限活動休止を宣言、その後ドラマーのかしぶち哲郎が逝去したが、2016年に活動を再開、今年も新作のリリースやフェスへの参加が控えていた。
ライダーズには、6人いたメンバー全員が、作詞作曲はもちろん、リードボーカルやプロデュースまでこなせるオールラウンダー揃いという特徴がある。とは言え岡田徹が作詞やボーカルを担当することは少ない。それでも彼の存在感が大きかったのは、岡田の作曲能力の高さからだ。〈さよならは夜明けの夢に〉、〈いとこ同士〉、〈Kのトランク〉など、ライダースのディスコグラフィに彼の存在は欠かせない。特に《9月の海はクラゲの海》は、筆頭に上がる代表曲だ。
君のことなにも知らないよ
君のことすべて感じてる
(中略)
君のこといつも見つめてて
君のことなにも見ていない
作詞はメンバーではなく、岡田と親交の深いサエキけんぞう。流行には敏感だがおもねることはなく、活動期間は長いのにヒット曲はなし、日本ロックの中央に君臨しているはずなのにシーンからは常に離れている、そうした彼らの二重性をよく捉えている。
4
 《9月の海はクラゲの海》が収録された《Don’t Trust Over Thirty》(1986)は結成10周年目にあたる記念すべきアルバムだった。ライダーズの名曲や代表作と言うと、大抵はこれ以前の作品が並べられる。しかしわたしは、この後のほうが思い入れのある曲が多い。
《9月の海はクラゲの海》が収録された《Don’t Trust Over Thirty》(1986)は結成10周年目にあたる記念すべきアルバムだった。ライダーズの名曲や代表作と言うと、大抵はこれ以前の作品が並べられる。しかしわたしは、この後のほうが思い入れのある曲が多い。
本作発表の時点でライダーズはメンバー全員が30歳を越え、精神的にも身体的にも限界に達していたらしく、一旦活動を停止する。5年後に活動を再開するが、以後はそれまでと少し様相が異なっていく。
彼らは初期から、世の中を醒めた視点で見つめており、若くして老成していたのが特徴だった。けれど活動再開後の楽曲は、妻や家族とのすれ違いや不和を、以前の彼らからすれば意外なほど直截に歌っていく。けれどそこで真に歌われているのは、ひとつの時代が終わったこと、そしてその喪失感を抱えたまま生きることについてであり、わたしはその点に惹かれていった。
カメラ二人並んで
海をバックにして 旅の
記念写真にと
君の姿写らない
昨日眠る前に そっと
君にキスをしたら 何とも
感じないって言ったね 愛の
果てに辿りついたよ
(中略)
ダイナマイト クールガイ 僕たち
言われてた頃に
帰れない 忘れない お互い
愛を返す季節じゃない
岡田作曲、鈴木慶一作詞《ダイナマイトとクールガイ》(1993)。タイトルはもちろん皮肉で、(おそらく)妻とのあいだの心の距離を綴っていると同時に、ひとつの「季節」が過ぎ去り、もう戻ってはこないことについて歌っている。
 この曲には続きがある。アルバム《MOONOVER the ROSEBUD》(2006)の冒頭を飾るナンバーで、同じく岡田/鈴木コンビによる〈Cool Dynamo, Right on〉。《ダイナマイトとクールガイ》では「砂の天使」や「虹」が、「愛の果て」にいる彼らの最後の希望のように言及されるのだが、この続編では「ダイナマイト残ってたら/天使たちを 集めて 吹き飛ばそう」「虹なわけがない 飛び散った 過去の鬼火だ」と、かすかに残った希望すらもなくなったと歌われる。
この曲には続きがある。アルバム《MOONOVER the ROSEBUD》(2006)の冒頭を飾るナンバーで、同じく岡田/鈴木コンビによる〈Cool Dynamo, Right on〉。《ダイナマイトとクールガイ》では「砂の天使」や「虹」が、「愛の果て」にいる彼らの最後の希望のように言及されるのだが、この続編では「ダイナマイト残ってたら/天使たちを 集めて 吹き飛ばそう」「虹なわけがない 飛び散った 過去の鬼火だ」と、かすかに残った希望すらもなくなったと歌われる。
このアルバムには、同じコンビによる〈Vintage Wine Spirits, and Roses〉という曲もある。表向きは(おそらく)かつての恋人に久々にバーで再会したという歌なのだが、「76年来/仕草は 変わらない」と、1976年にデビューしたライダーズ自体をなぞらえたりと、あきらかに自己言及的な内容になっている。
不幸は ずっと 続いてもいいんだ
心の 傷は 塞がらなくてもいいんだ
小さな 幸せ なら手にしなくてもいいんだ
相手に(つまり過去に)心の一部を残したままのようなのだが、「小さな幸せ」なんてなくてもいいし、「心の傷」も塞がなくてもいい、そうした生きかたをそれでも肯定できるのだと歌われるこの曲を、わたしは忘れることができない。
どれも岡田は作曲のみで、歌詞には携わっていないのだが、おかしみとせつなさを同期させた彼のメロディが、これらの歌詞を引き寄せていった点もあるのではないか。
岡田が演奏する姿を見たのは昨年の春の野音が最後となってしまった。だがわたしはもちろん、これからもライダーズを聞いていくだろう。「日陰の小径」を歩んでいく際のサウンドトラックに、ムーンライダーズほど似合う音楽を、わたしは知らない。
(2023/3/15)
—————————————————-
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中