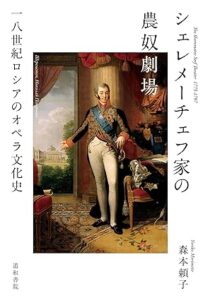Back Stage| オーケストラとホールが手を組むこと|竹内淳
オーケストラとホールが手を組むこと
Text by 竹内淳 (Jun Takeuchi)
写真提供:ミューザ川崎シンフォニーホール
わたしは、昨年4月より公益社団法人日本オーケストラ連盟に在籍しているが、その前は神奈川県川崎市にあるミューザ川崎シンフォニーホールに2004年のオープンから18年間勤めていた。
日本オーケストラ連盟は、国内の38団体(正会員25、準会員13)のプロフェッショナルなオーケストラが加盟している公益社団法人で、わが国の音楽文化の発展に寄与することをその目的としている。
連盟の業務は細々と多岐にわたるが、大きな役割のひとつに国とオーケストラをつなぐ調整や交渉があげられる。国の助成金をどのような活動に活用するのがより効果的か、どのような形態の支援が芸術団体による日本の文化振興に役立つのか、時には加盟団体に国の考えを伝達し、時には国に対して申し入れを行う、そんな役割だ。
私はこの連盟に来てまだ1年とたたない新米だが、ホール側からオーケストラを見ていたこれまでの視点に加え、反対側のオーケストラからホールを見るという視点を得ることができた。そこからオーケストラにとってのホールの役割が、演奏する「場」というだけでなく、ホールのあらゆる活動に「食い込む」ことがいかに重要かを感じ取ることができた。
「オーケストラとホールの関係」について、オーケストラの統括団体としての現在の立場、そして行政が建てたホールの職員として勤務した立場、この2つの立場の「目」を通して紹介したいと思う。
◆ミューザ川崎シンフォニーホール
ミューザ川崎シンフォニーホールは、川崎市が建設した約2000人の客席とパイプオルガンをもつコンサートホールで、客席が舞台を円形に取り囲む形状から、クラシック音楽の演奏に向いている、というよりはむしろそれ以外の用途では少々使いにくいホールとなっているので、音楽専用ホールと思って差支えないだろう。
JR川崎駅とはペデストリアンデッキで繋がっており、川崎駅西口再開発計画の一環として、「街のシンボル」としての役割を担う存在でもあった。
川崎市は京浜工業地帯の中核を担う、わが国有数の工業の街だった。
現在のミューザ川崎が立地する川崎駅西口地区は、以前は大手電機メーカーの事業所があり、わが国の電子技術の最先端を行く街でもあった。また、川崎市の海沿いには石油産業や鉄鋼業の工場が立ち並び、工場を三交代制で支える多くの人々が昼夜を問わず街を行き来し、街全体が工業の街として機能していた。
そして、高度経済成長の副産物でもある大気汚染や水質汚濁が進み、川崎市は「公害の街」のレッテルを張られてしまった。
ちなみに「川崎病」という名は、川崎の公害による病気と思っている方が多いが、公害の病気でもなければ川崎市とはまったく無関係な病気で、発見した川崎医師の名前が付けられただけである。アンデスメロンがアンデス山脈で栽培しているメロンでないのと同じなのだ。
その川崎も、やがて工場の市外移転が進み、跡地は学校や住宅となり、街の景色も変わっていった。
そんな中で、川崎市の玄関口であるJR川崎駅西口にある工場が撤退し、その跡地を中心とした川崎駅西口地域の再開発に取り組むことになる。再開発の目玉であったかどうか私は知らないが、ホールを中心とした複合商業施設がミューザ川崎、そのなかにあるホールがミューザ川崎シンフォニーホールである。
そしてホールのオープンに合わせて「音楽のまち」構想を立ち上げ、東京交響楽団とフランチャイズ提携を結ぶという、「オーケストラの住むホール」「オーケストラのいる街」を目指した政策を打ち出した。
私は川崎市に隣接する東京・大田区に住んでおり、その当時は音楽業界からは離れた仕事をしていたが、隣町川崎がコンサートホールを建設中と聞いて、「川崎の街にコンサートホールは本当に必要なのだろうか?」と首をかしげていた。隣町に本格的なコンサートホールができてうれしい・・・とは思わなかったが、ひょんなことからオープン直前にそのホールの職員となってしまったのである。
川崎市とフランチャイズ提携を結んだ東京交響楽団は、言わずと知れた我が国を代表するオーケストラだ。フランチャイズ提携の詳細は省くが、東京交響楽団はミューザ川崎シンフォニーホールを本拠地として、そこでリハーサルや演奏会を行うというもので、現在、同楽団のリハーサルの大半をミューザ川崎で行っている。
そしてオーケストラが自主公演としての定期演奏会を開催するほかに、ホール主催による東京交響楽団のオーケストラ公演は年間20回に上る。
私がミューザ川崎の職員になったときには、東京交響楽団による年間の公演数の枠組みやそれに費やす予算はほぼ固まっており、さらにそれはオープン時の一過性のものではなく、将来にわたって続くものという基本的な方針だった。私はミューザに入る10年以上前は新日本フィルハーモニー交響楽団で働いていたこともあり、日本の自主運営オーケストラの置かれた状況は理解していたつもりである。
少々大げさかもしれないが、いま振り返ると、ホールと東京交響楽団の2つが充実した関係を構築するよう奮闘することが、私に課された役割と当時は思っていた。
◆東京交響楽団
そんな川崎市に、東京交響楽団は乗り込んできた。
ある記者会見の場で、新聞社の川崎支局の記者から「川崎市のフランチャイズということは、いずれは東京交響楽団の〝東京〟を〝川崎〟に変えるのですか?」と半ば冗談めかして質問してきた。その時の川崎市長は「浦安にあって東京ディズニーランド、成田にあって新東京国際空港と言うのだから、それと同じに考えればいいのでは?〝東京〟というのは行政区画の名前ではなくて、もはやエリアの名前になっているのですよ。」と返した。さらにその場に居合わせた音楽記者が「オーケストラが〝川崎〟を名乗りたくなるようになるといいですね。」と付け加えた。
東京交響楽団(東響)は、オケ主催の定期演奏会を川崎で5公演、ホール主催のシリーズ公演を年10回、東響による小編成のオーケストラ公演としてはじまったマチネシリーズが年4回、そのほかジルベスターなど「季節もの」のオケ公演を含めるとオケ主催、ホール主催を合わせると30回近い公演をミューザで行っている。
そして話はホールの15周年記念公演にまで一気に進む。
ホールのオープニング、ホール5周年、ホール10周年と節目の年には東京交響楽団によるマーラー作曲の交響曲第8番「千人の交響曲」が取り上げられてきた。当初は、15周年記念も同じ曲でよいのでは?という話があり、東響もおおむねその方向で受け止めていた。
ただ、「またまたマーラーの8番は少々安直すぎるのでは?」と思われたのと同時に、「東響の現在の音楽監督ジョナサン・ノット氏にとって、もっとふさわしいプログラムがあるのではないか?」と考え、後期ロマン派最後の傑作と言われるシェーンベルクの「グレの歌」はどうだろうか?と東響に話を持って行った。
監督はやはりマーラーをやりたがるかもしれないし、もしかしたら「それだったらこっちの曲がいい」ともっと奇抜な(チケットが売れない)レパートリーを提案してくるかもしれない。また、グレの歌は歌手の負担も大きく、監督のお眼鏡にかなう歌手が見つかるとも限らない。
あるリハーサル終了後、ホテルに帰るタクシーの中で東響の事務局長が「ミューザがホールの15周年に〝グレの歌〟をやりたいと言っているがどう思うか?」と問いかけたら、監督は〝It’s crazy!〟を連発して大興奮でOKしたそうだ。ホテルに着くまで興奮しっぱなしで、「おかげで帰りのタクシーの中で話そうと思っていた別の相談は全くできなくなったよ。」と後からから聞かされた。
東京交響楽団とミューザ川崎シンフォニーホールの共同企画は、このほかにも3年間かけてモーツァルトのダ・ポンテ3部作を毎年取り上げる企画や、現在進行中のリヒャルト・シュトラウスのオペラに取り組む企画など、年々充実してきている。2022年にミューザ川崎とサントリーホールの2つの会場で行われた、リヒャルト・シュトラウスの「サロメ」は高い評価を得ている。
◆ホールとオーケストラ
このように意欲的な企画を、次々とオーケストラが本拠地で取り組むことができるのは、ホールとオーケストラが確固たる信頼関係を築いてきたからにほかならない。
冒頭に述べた川崎市の歴史は、高度経済成長の日本を支える工業の街の姿だったが、いまの川崎市はスポーツ、文化、産業、商業など多面的な魅力を備えた街に変貌した。そのなかで「音楽のまち」構想は、東京交響楽団をその中心に据え、市民による活発な音楽活動やこどもたちへの鑑賞教育の提供など、大きな実を結ぶものとなった。
東京交響楽団はここに書いたような活動を一朝一夕に築き上げたわけではない、ホールとがっちりと手を組み、そして川崎市とも手を組んでオーケストラの公演以外にも室内楽公演や市内の学校訪問なども積極的に行っている。
また、記憶に新しいところでは新型コロナウイルス感染症が爆発的に拡大した時、ホールのYouTubeチャンネルでは楽員による教育的な番組「おうちでミューザ」を流したり、観客を呼ぶことができないホールを使ってCD制作を行ったり、さらにはコロナ禍においていちはやく動画配信を行ったりと、常にホールの要求に応える形、ホールと手を組む形で音楽を提供してきた。
音楽業界人と行政マンは言ってみれば「水と油」かもしれない。お互いにしゃべる言語は異なるし、目指すところが違うので、それぞれが主張を曲げなければ「水と油」のまま交わらず終わってしまう。
しかしその「水と油」は、ミューザ川崎シンフォニーホールのような公共ホールが媒介となり、混ざり合って化学変化を起こしたときに、あらたな音楽文化の姿が生まれると思うのだ。
竹内 淳(公益社団法人日本オーケストラ連盟 常務理事・事務局長)
(2023/3/15)