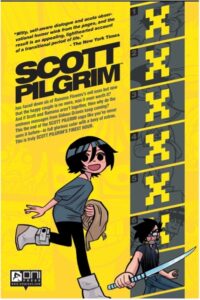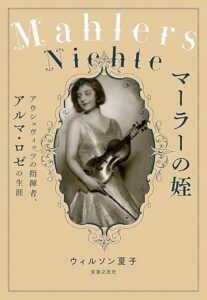Books |『スコット・ピルグリム』シリーズ|秋元陽平
『スコット・ピルグリム』カラー・ハードカバー版 全6巻
Scott Pilgrim Color Hardcover 6 vol.
ブライアン・リー・オマリー(Bryan Lee O’malley)著
Oni Press, US, Portland
2012-2015 (2004-2010)
Text by 秋元陽平 (Yohei Akimoto)
それにしてもなぜ2023年にスコット・ピルグリムなのか? 昨年の初めに、Netflixが本作品のアニメ化を計画中だというニュースを目にして、そのことがずっと頭の片隅にあったのだが、その後どうなったのか、音沙汰がない。だが今年何らかの動きがあるかもしれないということを、すでに北米コミックの古典と見做されるこの作品を今更取り上げる口実としよう。このシリーズは日本では「邪悪な元カレ軍団」というどことなく昭和じみたサブタイトルの付いた実写版によってよく知られているが、真骨頂はもちろんこの原作コミックである。作者のブライアン・オマリーが日本のレトロゲーム、高橋留美子作品の影響を受け、相原コージと竹熊健太郎による『サルでも描ける漫画教室』に触発されてこの作品を執筆した、といった諸々の伝記的事実はすでによく知られているのでその詳細は省く。前回書評で取り上げたベルンハルトの『推敲』とはまったく違った意味で、本作のあらすじの詳細を喋々することにはあまり意味がない。天然系バンドマンのスコットが予知夢で出会ったアマゾンの配達員のヒロイン、ラモーナ・フラワーズと現実で奇跡の「再会」を果たし、彼女と付き合うために七人の元彼を倒さないといけないと知る、と書いたところで何になろう。トロントの寒い冬、シェアハウスに転がり込んで馬鹿話をして、クラブで酔い潰れ、アルバイトに辟易し、バンドを組んで、冴えないレコーディングをして、勢いで一線を越えて気まずくなる、などといったエピソードの集積もそれ自体たわいない。
だが、それらを修飾する荒唐無稽なレトロゲームの文法(スコットと元彼たちの「対戦」は基本的に格闘ゲームとRPGの混合形式で表現される)はむしろ、目的に向かった進行—つまりモラトリアムの終わりという宿命—が重力を持ちすぎることを防ぎ、ただそれに軽快な律動を与える。
この点で、たしかにこの作品は自己充足的な「青春ポルノ」であることを好ましい形で免れている。キャラクターはしばしばゲーム内のアイコンのように小さく表示され、さまざまな「パラメータ」が書き込まれるが、こうしたデフォルメはバンドデシネ的カリカチュアがもたらす「愛嬌」というよりは、端的に、描き手によるキャラクターへの「敬愛」の仕草だ。話の成り行きで身体改造され、ビームを出し、空間移動し、果ては「1UP」できる彼らキャラクターたちはしかし、同時に「トロント若者界隈」の実在感を持っている。彼らは有色人種、同性愛者、あるいはヴィーガンといったさまざまな属性をもって生きる現実のひとびとであり、二十歳のころ欧州に住んだときにわたしが一緒に過ごした彼らと同じように話し、悩み、憤慨し、からかい合う、西欧世界のごく一般的な若者たちのリアリズムのコードに則って描かれているのだ。
結果として、こうした複数の現実性の公準の雑居が、こうした「キャラ化」のステレオタイプ化作用としばしば危うい緊張関係を作り出していることも見逃せない(とくに中国系カナダ人女子高生のナイヴズ・チャウ)。
この作品がどこか強い印象を残すのは、高橋留美子作品に見られるキャラクターたちが「逗留可能な」フィクション空間を作り出すその仕方、そしてその空間が持っている懐かしさ、あるいは穏やかなメランコリーが、作風の明らかな違いにもかかわらず、そして全く異なる文化的コンテクストの中でみごとに成立しているからかもしれない。フィクション、それもコミックのさまざまな美学的機能のうちには、いつでもそこに自身の居場所を見出すように読者を促す、というものが確かに存在するように思う。トロントでの青春を経験したことがなくても、読者はその世界に歓迎されている。
その空間は「あらかじめ失われる」ようなドラマチックなものでもなく、またただの空想的ユートピアでもない。原則としてテンポのよいギャグ漫画のナラティヴが間断なく披露されるのだが、例えばふと登場人物の誰かがまごついて、言うべきことをうまくいえないまま時間が経過する、そんな生々しい時間(コマ)がしばしば差し挟まれる。そこにはフィクションの断層があって、読者は戸惑いとともにシンパシーを覚える。ここに永遠に循環するユートピアはないが、長引いたアドレセンスの漸進的解体がゲーム的な単線進行形式によって柔らかくユーモラスに表現され、そのなかにこそ、確実に失われていく時間の手触りがある。
(2023/3/15)